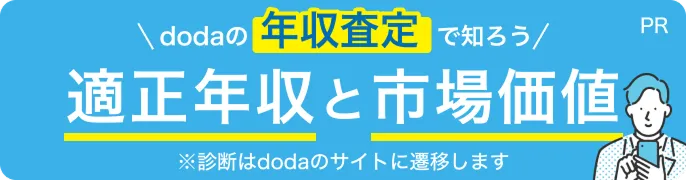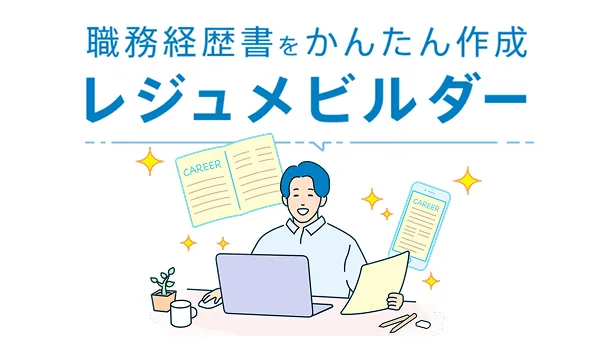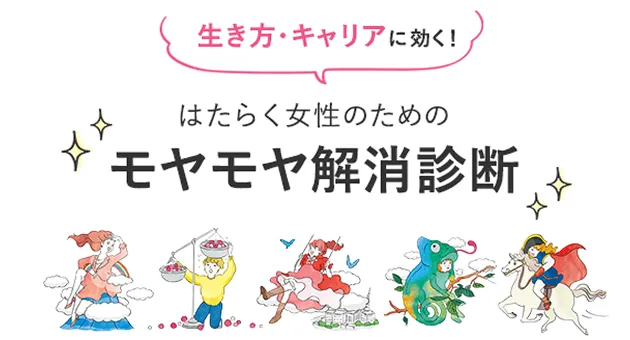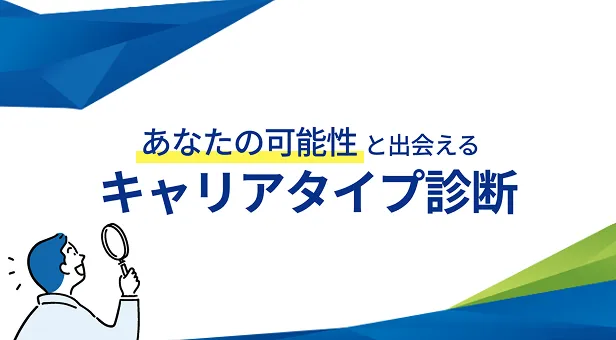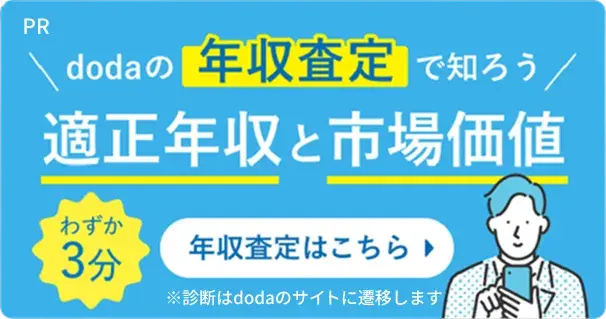コンピテンシーとは?意味を簡単にわかりやすくまとめ
コンピテンシーの意味とは?簡単にわかりやすくまとめ。コンピテンシーという言葉が生まれた背景、コンピテンシーのモデルを紹介。コンピテンシーとの意味の違い、よく似た言葉との比較も解説します。
コンピテンシーの意味とは?簡単にわかりやすくまとめ
コンピテンシーの意味とは|パフォーマンスが高い人に共通する行動特性
コンピテンシー(competency)とは、仕事上に置いて業務や職務といった優れた成果を出す人材に共通する行動特性を指します。優れた行動特性については、人材評価に活用されています。
コンピテンシーでは、一流の大学や大学院を卒業したから優秀で自社でも活躍してくれるだろうという曖昧な基準ではありません。自社の社風や方向性、周りとのコミュニケーションが問題なく取れているかなどを評価する制度になります。
コンピテンシーは、学歴(履歴書・職務経歴書)や面接だけでは判断できないため数値としての可視化が難しい評価制度になります。
コンピテンシーという言葉が生まれた背景とは?
コンピテンシーは、1950年代に心理学用語として誕生しました。人事用語として用いられるようになったのは、1970年代にハーバード大学のマクレランド教授が行った調査結果からになります。
マクレランド教授らは、コンピテンシーの調査で「知能や学歴は、仕事をする上で業績の高さと比例しない」と公表しており、仕事で高い業績を上げる人物には、共通した行動特性があると結論をづけています。
日本では高度経済成長期時代から最近まで、年功序列を基本とした考え方で人事評価を行ってきました。しかし近年では、年功序列の考えよりも成果主義の考えに移行してきており、人事評価におけるコンピテンシーが採用されてきています。
コンピテンシーのモデルとは?3つの種類まとめ
実在型モデル
実在型のモデルでは、社内で成果を上げている(営業などで数値を出している人)に向けてヒアリングして作られるモデルになります。実在する人物を対象にコンピテンシーのモデルを作成すると、次のようなメリットが挙げられます。
- 成果を上げるための行動特性を把握することが可能
- 評価を受ける社員が納得した人事評価が可能
- 現実に即したモデルの構築が可能
上記のようなモデルを構築することができますが、モデルとなった社員の再現が難しい場合もあります。例えば、モデル社員の経験や知識などすぐには習得できないこともあります。実在型のモデルを構築する場合は、一般社員が再現が可能かどうかも検討する必要があるでしょう。
理想型モデル
理想型のモデルでは、企業が求める人材を基本として作成するモデルになります。
事業の戦略や経営理念からモデルケースの人材を構築します。実在型では、実際にハイパフォーマンスが出せる社員をモデルケースにしますが、理想型では自社にモデルになる人材がいない場合に有効なケースになります。
しかし実在しないモデルなため、理想と現実のギャップが出てしまう可能性があります。理想型のモデルが高すぎると、採用や人事評価をする際に合格点に達する人がいなくなります。そのため理想型のモデルを構築する場合は、現実とのギャップが生まれすぎないように調整する必要があります。
ハイブリッド型モデル
ハイブリッド型のモデルは、実在型モデルと理想型モデルの要素を組み合わせて作成するモデルになります。実在型モデルや理想型モデルよりも優れたモデル構築となっており、さらに上の状態に持っていくことができます。
理由としては、実在型のモデルの場合は既に実践している項目だけを取り入れているので学びが少ないからです。また理想型では、現実とのギャップを埋めるのは難しく年度などで調整が必要になります。
そのため既にハイパフォーマンスを出している社員にとっては、さらに上を目指せる人事評価を構築することができます。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。