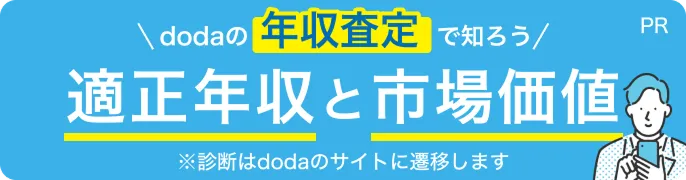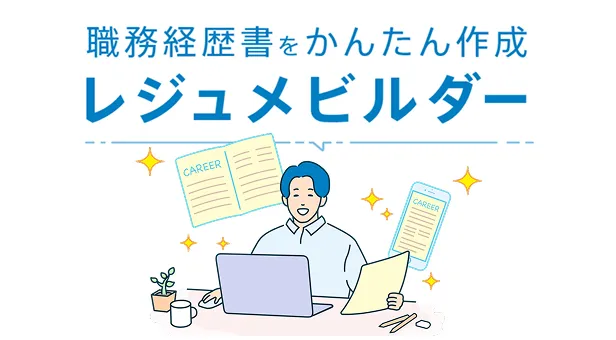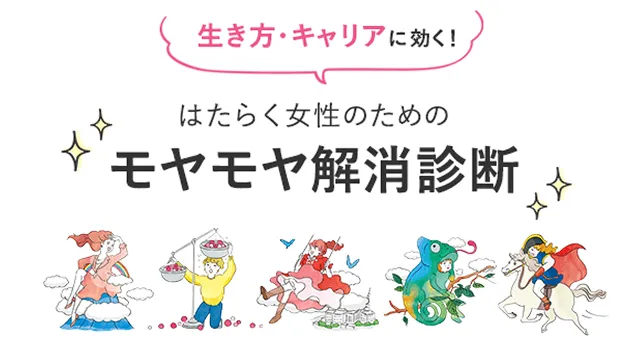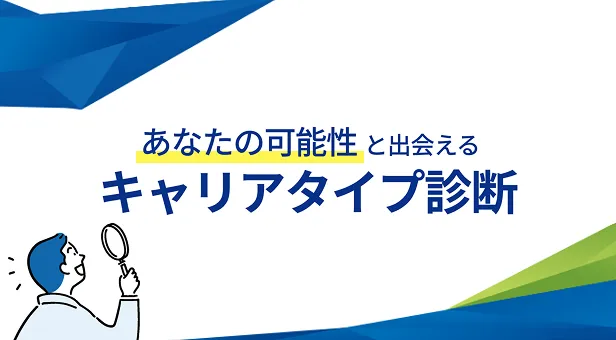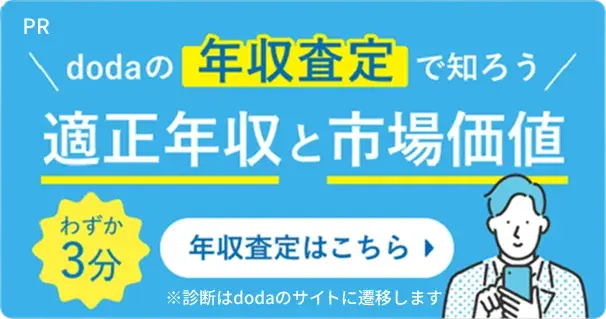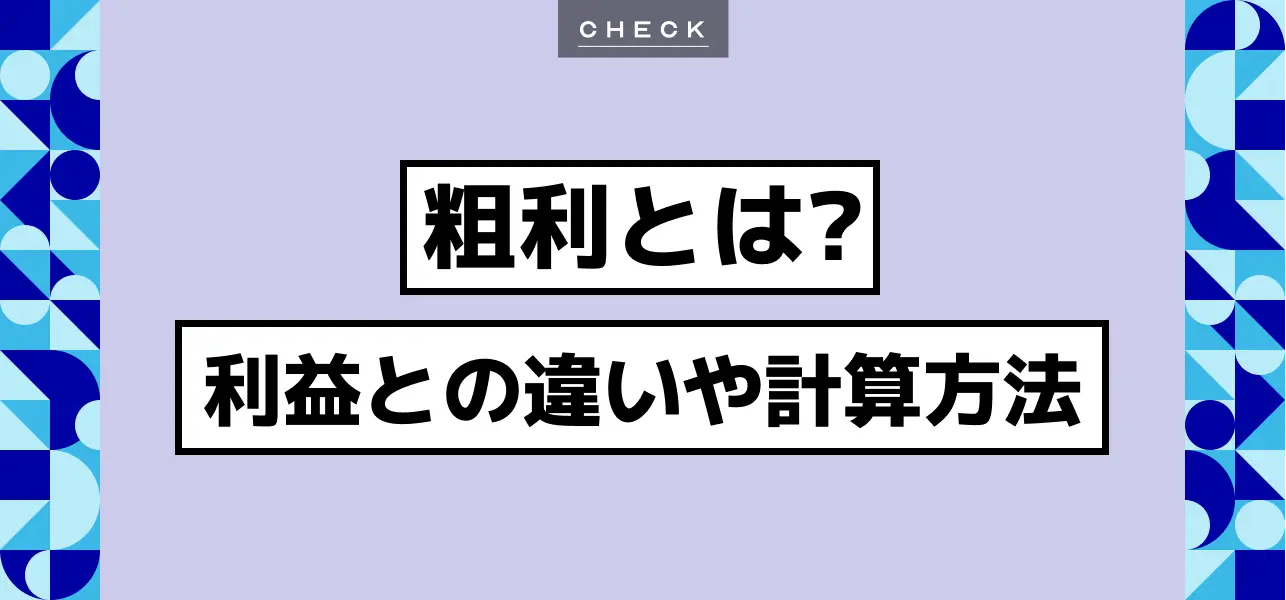
粗利とは?意味も簡単にわかりやすくまとめ
粗利は売上総利益と呼ばれることもあります。粗利額の出し方、粗利率の計算方法、業種別粗利率の目安を紹介。粗利が重要と言われる理由、粗利の注意すべきポイントも解説します。
粗利の意味とは?簡単にわかりやすくまとめ
粗利とは?損益計算書上の5つの利益から解説
損益計算上は以下の5つの利益が存在します。
【損益計算書上の5つの利益】
- 粗利(売上総利益)
- 営業利益
- 経常利益
- 税引前当期利益
- 当期純利益
粗利について理解したいならば、損益計算書における5つの利益について知っておくことが大切です。それぞれの利益の計算方法や違いについて把握しておきましょう。
ビジネスを進める上でどの利益についても正確に理解することが求められます。
それでは、損益計算書上の5つの利益について詳しく解説しましょう。
粗利(売上総利益)とは
粗利は売上総利益と呼ばれることもあります。
粗利はあくまでも俗語であり、正式名称は売上総利益です。粗利は「売上高-売上原価」で求められます。
粗利の計算式には、人件費などの費用は含まれていません。大雑把に計算した利益という意味で粗利と呼ばれるのです。
粗利の計算に用いる売上高とは本業で得た収益であり、売上原価には仕入れにかかった費用や製造にかかった費用などが含まれます。粗利は本業で得た利益を大まかに示したものです。
営業利益とは
営業利益とは粗利から販売費及び一般管理費を差し引いたものです。粗利の計算式は「粗利-販売費及び一般管理費」と表せます。
営業利益は企業が営業活動で得た利益であり、本業の利益のみを示します。営業外収益は計上されていません。
販売費及び一般管理費とは人件費や交際費、通信費など営業活動に伴い発生するコストです。
経常利益とは
経常利益とは営業利益に営業外収益を足して営業外費用を差し引いたものです。経常利益の計算式は「営業利益+営業外収益-営業外費用」で表せます。
「営業外収益-営業外費用」とは本業以外で得た利益から費用を差し引いたものです。
したがって、経常利益は本業以外の利益も含めた会社の儲けを表しています。経常利益は会社が事業活動で得た利益を合計したものといえるのです。
税引前当期利益とは
税引前当期利益とは経常利益に特別利益を加えて特別損益を差し引いたものです。税引前当期利益の計算式は「経常利益+特別利益-特別損益」となります。
税引前当期利益は税金を支払う前の会社の利益のことです。
特別利益とは営業活動以外の臨時の出来事で得られた利益であり、臨時の出来事による費用として特別損益を差し引きます。たとえば、不動産の売却は特別利益に該当するのです。
当期純利益とは
当期純利益とは税引前当期純利益から法人税などを差し引いたもので、計算式は「税引前当期純利益-法人税等」です。
サラリーマンにとっての手取り収入と同じ意味だと考えましょう。
会社が1年で得たすべての利益から経費などを差し引き、支払った税金を差し引くことで当期純利益が求められます。
注意点として当期純利益の計算で用いる税額は前年の所得により生じたものです。
当期純利益から株主への利益還元などを差し引くと会社の内部留保となります。内部留保は会社の将来の設備投資などの原資です。
粗利額の出し方とは?計算する方法
粗利を考える際には粗利額の正確な計算方法を理解することが大切です。粗利額の計算にどんな要素が考慮されて、どんな要素が考慮されないのか正確に理解しましょう。
そうしないと正確な粗利額を把握することができず、経営判断に影響を与えます。
粗利額における売上高や売上原価の意味を正しく理解しましょう。
以下の見出しでは粗利の計算式・求め方と粗利で考慮されない要素について説明します。
粗利の計算式・求め方とは
粗利の計算式は「売上高-売上原価」です。仕入れの代金や製造の過程で生じた費用などは売上原価に含まれます。
売上原価の計算式を詳しく表記すると「期首商品棚卸高+当期商品仕入れ高-期末商品棚卸高」です。
期首商品棚卸高とは前年度に売れ残った在庫の金額を示します。
前年度に売れ残った在庫金額に当該年度の仕入れ金額を足して、年度末に在庫として残った分の金額を差し引けば売上原価を求められるのです。
粗利で考慮されない要素とは
粗利の計算では考慮しない要素があります。
たとえば、経費や金融活動による損失、税金などは粗利の計算に含めません。粗利の計算ではあくまでも売上原価だけを売上高から差し引くのです。
たとえば、飲食店の粗利を計算する場合は、費用として食材費のみに着目します。
粗利の計算ではテナントの家賃やスタッフの人件費などは差し引かないのです。売上に直接影響する要素のみに着目します。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。