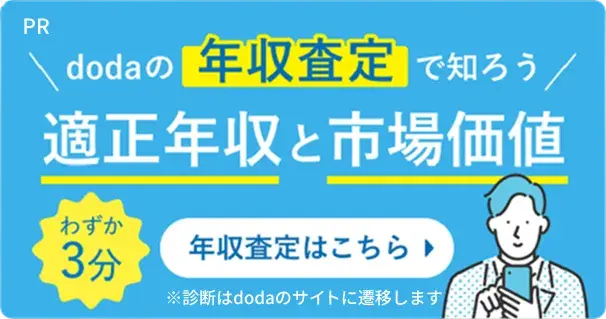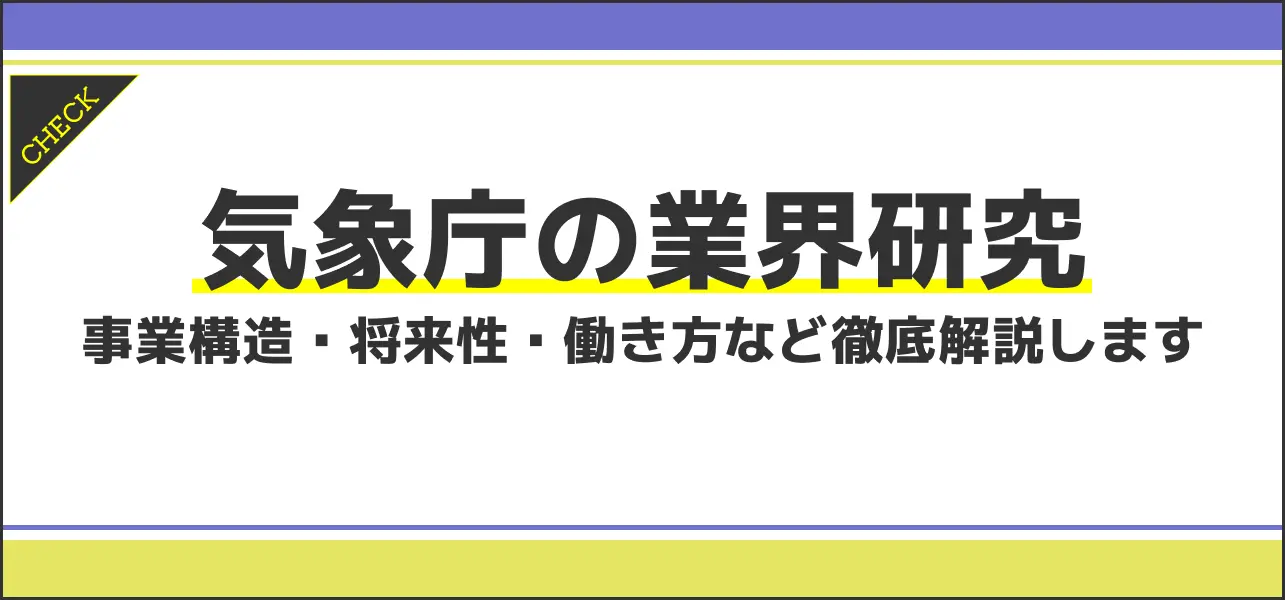
気象庁の業界研究|就活に役立つ事業構造・将来性・働き方など徹底解説します
東日本大震災の際の津波の速報などで気象庁は国民の注目を集めました。気象庁の歴史は古く1875年の明治時代から日本の気象行政を担っています。人気省庁と比べると若干人気には劣りますが、気象庁の的確な情報提供などで多くの国民の命が守られています。日常生活で国民の命を守りたいと考える学生にぴったりの省庁です。この記事では気象庁を志す学生に向けて、気象庁の採用ホームページや気象庁が公表している白書、気象庁が所管している法令を参考にして、気象庁の省庁研究を行っています。気象庁の官庁訪問のポイントについても解説していますのでぜひ最後まで読んで参考にしてください。
気象庁とは
気象庁は、明治8年(1875年)の発足以来、1世紀以上にわたって、自然を監視・予測し、国民の生命財産を災害から守るため、適切な情報提供に努めています。
気象庁は気象・海洋や地震・火山などの自然災害を常に監視・予測し、的確な気象情報を提供することによって自然災害の軽減、国民生活の向上、交通安全の確保、産業の発展などを実現することを任務としています。
気象庁ではこれらの自然現象に関する防災気象情報を防災関係機関にオンラインで迅速に伝達すると同時にテレビ・ラジオやインターネットなどを通じて広く国民に発表しています。
気象庁の任務については国土交通省設置法第四十六条に「気象庁は、気象業務の健全な発達を図ることを任務とする。」と規定されています。
気象業務は、気象や気候、海洋、地震、津波、火山等の自然現象の観察・観測、観測データの取得・収集、スーパーコンピュータ等をはじめとする各種システムを活用した解析・予測、情報の作成・提供、それらに必要な調査・研究などの業務をいいます。
この気象業務は気象庁のみならず、自治体、民間事業者等、様々な主体によって実施されています。
また、気象業務の遂行には世界各国とのデータの交換や技術協力等が不可欠であり、これらが国際的な協力により実施されています。
この気象業務は災害予防、交通安全、産業の興隆等に寄与することを目的としています。
そのために気象業務を担う機関、関係者により気象情報・データが的確に提供され、これらが防災対応や一般社会・産業分野等において利活用されるようにすること、すなわち、「気象業務の健全な発達を図ること」が必要となります。
気象庁は最先端の技術開発やその成果を導入し、自ら観測・予測を行い気象情報・データを作成・提供するとともに、自治体や報道機関、民間事業者等における気象情報・データの作成・提供や様々な社会経済活動における利活用を促進することにより、気象業務の健全な発達に向け、その役割と機能を十全に発揮できるよう取り組んでいます。
気象庁の役割
気象データの収集
全国に配置したネットワークで大気の状態を24時間を観測しています。
気象衛星やアメダスなど様々な装置で観測データを収集しています。
具体的には衛生観測で地球規模の気象状況を把握、レーダーで降水の強さや上空の風の分布を観測しています。
また、ラジオゾンデで気圧・気温・湿気・風向・風速などを観測、さらに全国1,300箇所のアメダスで地上の観測を行っています。
このように地上から上空までの大気の状態を正確に把握するため、全国に設置した観測装置や気象衛星などで構成されたネットワークを敷いて、24時間体制で観測しています。
気象データの解析
観測データをもとにスーパーコンピュータを用いて未来の大気状態や気象状況を予測しています。
その他にも防災の解析や警報・予報につながる最先端のシステムを導入しています。
また、気象庁は世界の中でも先進的な気象観測や予報を行う起床機関としてアジアにおける人材育成など指導的な役割を果たしています。
国際的な取組と連携して観測データの効率的な共有を推進するとともに数値予報を使って世界の気象状況を解析して予測した結果を示し、世界中の各専門家と議論しています。
また、気象業務に活用する先進的な研究開発や観測・予報システムの改善や高度化を図っています。
気象情報の提供
日本は災害大国としてこれまで様々な自然災害にみまわれてきました。
気象庁では地震や津波、台風や火山噴火による被害を軽減し、国民の生命や財産を守るために様々な防災情報を発表しています。
提供する情報は幅広く、航空機・船舶等の交通安全に資する情報、地球温暖化対策に資する情報、生活や社会経済活動に資する情報などがあります。
気象庁の仕事内容
観測及び提供
大気海洋部では防災、交通安全、気候変動適応、産業の振興に寄与することを目的としてます。
気象・海洋・地球環境に関する様々な時間・空間スケールの現象に対して観測や短期の予報から季節予報、気候変動の予測に至るまでの情報を適時提供しています。
提供する情報は観測・予測など専門的な技術の上に成り立っており、改善には技術の進歩が必要です。
したがって、最新の科学技術の成果を取り入れ、社会との対話を行いながら、よりよい情報の提供ができるように改善を続けることが必要です。
情報基盤
情報基盤部では安全・強靭で活力ある社会の実現を目的としています。
国民の生命・財産を守る気象防災情報や国民の生活、経済活動など様々な場面で活用される気象情報の基盤となる数値予報の予測家家の提供とスーパーコンピュータ、気象衛星ひまわり、庁全体の情報基盤を支える重要なシステム、および国内の基幹通信網などの安定的な整備・保守を担っています。
また、気象情報の利用を促進するための知識の普及や環境整備も重要です。
地震・火山対策
日本は世界でも有数の地震・火山国であり、これまでに地震・津波や火山活動により大きな被害を受けてきました。
このような被害を防止・軽減し、国民の生命や財産を守るために地震や火山のリアルタイムデータを24時間体制で監視し、最新の科学技術を駆使して、緊急地震速報や津波警報、噴火警報など様々な防災情報を発表しています。
また、緊急時に発表する情報を国民の防災行動などに役立てるために平時から周知広報活動や訓練などに取り組んでいます。
さらに監視や情報発信のためのシステムの構築、情報の練度を向上させるための技術改善も重要な業務です。
最新のトレンド
防災気象情報の伝え方改善
近年の豪雨の中でも2018年7月の豪雨は全国で死者が200名を超えており、その甚大な被害から「平成最悪の豪雨災害」と報道されました。
この記録的な災害を受けて、気象庁では学識者に加えて、報道関係社、自治体関係者、関係省庁による「防災気象情報の伝え方に関する検討化」を開催し、災害における防災気象情報の伝え方について課題を整理しています。
主に挙げられた課題は①気象庁が伝えたい危機感が住民に十分感じてもらえていない
②防災気象情報を活用しようとしても使いにくい
③気象庁の発表情報のほかにも防災情報が数多くあり、関連がわかりにくい
④大雨特別刑法の情報の意味が住民に理解されていない、の4点でした。
①に関しては気象庁から災害時に気象防災対応支援チームを都道府県や市町村の災害対策本部に派遣し、気象概説を行うこととしています。
また、報道機関や気象キャスターと連携して、情報利用の訓練を行うワークショップも実施しています。
②に関しては土砂災害の「危険度分布」の危険度が高まったときにメールやスマホアプリで通知がくるサービスを開始。
また、危険度分布と各種ハザードマップを気象庁のホームページに重ねて表示するようにしています。
③に関しては防災気象情報について防災気象情報を発表する際にどの警戒レベルに相当するかがわかるように明示して提供することで住民の自主的な避難行動の判断を支援しています。
④に関しては大雨特別警報についてその位置づけや役割について周知を強化し、局地的な大雨に対しても大雨特別警報を精度よく発表できるように危険度分布の技術を活用した土砂災害の新たな基準値を導入し、すでに伊豆諸島において先行的な運用を開始しています。
世界気象機関(WMO)を通じた世界への貢献
大気に国境はなく、台風等の気象現象は国境を超えて各国に影響を与えます。
このため、精度の良い天気予報とそれに基づく的確な警報・注意報の発表のためには国際的な気象観測データの交換や技術協力が不可欠です。
WMOは世界の気象業務の調和的発展を目標として設立された国際連合の専門機関です。
世界気象会議を4年ごとに開催し、向こう4年間の予算や事業計画を審議する他、執行理事会を毎年開催し、事業計画実施の調整・管理に関する検討を行っています。
日本は1953年に加盟し、アジア地区における気象情報サービスの要として中心的な役割を果たしており、歴代気象庁長官は執行理事としてWMOの運営に参画しています。
2019年6月3日から14日まで第18回総会がスイスのジュネーブで開催され、総会では2020年から2023年の事業計画や予算を決定し、
①社会ニーズに対応したより良いサービス、
②地球システムの観測・予測、
③ターゲット研究の推進、
④サービス能力の向上、
⑤WMO組織の戦略的再編成、の5つの長期目標が設定されました。
この総会には日本から関田気象庁長官を主席代表とする政府代表団が派遣され、会期中には日本政府代表部がレセプションを開催し、防災先進国としての貢献及び先進性をアピールしました。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。