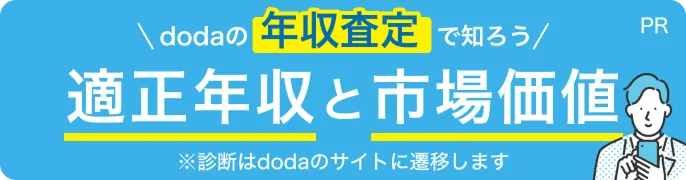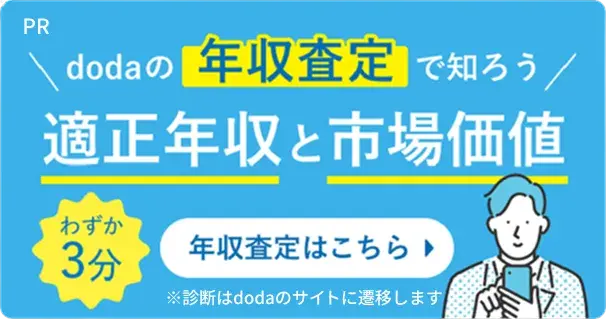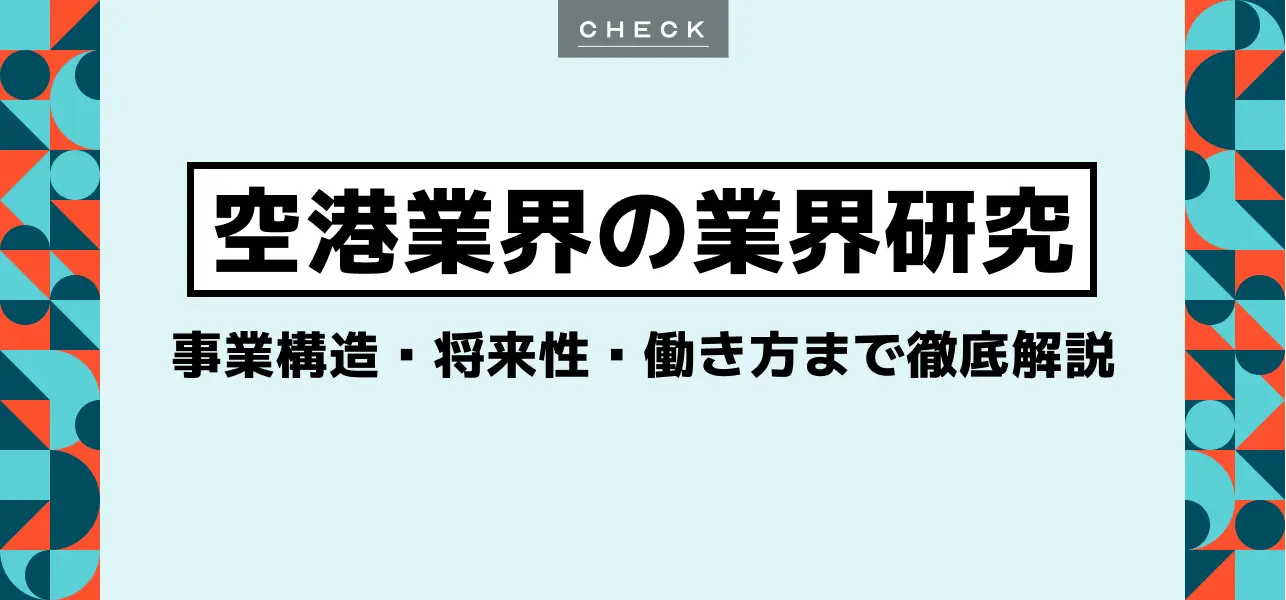
空港業界の業界研究|就活に役立つ事業構造・将来性・働き方など徹底解説します
航空業界と並んで学生から圧倒的な人気を誇るのが空港業界です。日本の玄関口としての役割を担い、日本の最も重要なインフラである空港業界は文理問わず学生から根強い人気があります。就活対策を行うにあたって業界のビジネスモデルや業界のトレンド、各社の動向を丁寧に理解することが大切です。この記事では各社の有価証券報告書や政府関係機関のレポートなどを参考にして、業界研究を行っています。ぜひ最後まで読んで就活対策を万全にしてください。
空港業界とは
この章では空港業界の
- 業界構造
- 将来性
- 業界分類
- 最新トレンドについて
解説していきます。
業界構造
航空系収入と非航空系収入
空港の収益源は主に航空系収入と非航空系収入に大別されます。
三井物産戦略研究所が世界の空港のうち 653 空港 (年間旅客取扱数の 合計で世界の 70%に相当) を対象として行った 2013 年の調査によれば、収入の内訳は、 航空系収入が 56.7%、 非航空系収入が 43.3%となっています。
航空系収入
航空系収入とは航空会社からの着陸料(滑走路、誘導路の使用料)、旅客からの旅客サービス施設使用料(旅客ターミナル、搭乗用施設等の使用料)、石油会社などからの給油施設使用料、貨物取扱料、 収入駐機料、地上支援業務料(機体の誘導、牽引、手荷物・貨物の搭降載、ケータリング、給油・給排水、 機内清掃、機体整備補助などの作業料)などで構成されています。
これら航空系収入を構成している各種料金は政府による価格規制が行われているのが一般的です。
料金は政府と空港事業者がプライスキャップと呼ばれる将来の料金の改定幅の上限を事前に合意によって決定する「プライスキャップ制」によって設定されています。
プライスキャップ制においては空港の運営にかかるコストをプライスキャップより低く抑制することで差額が空港事業者の利益となる仕組みです。
この仕組みではコスト削減や効率化など生産性向上に取り組むことで利益を最大化することができます。
航空系収入を増やすためには航空機の発着回数を増加させ、着陸料やその他空港施設の使用料を徴収すること及び搭乗客を増やして、旅客サービス施設使用料を受け取ることがポイントになります。
空港事業者は国内のみならず海外の航空会社に対して新規就航路線の誘致を行ったり、魅力ある空港づくりを通じて、旅客者数を増やすなどの取組を行っています。
また、新規就航路線及び旅客者の収容能力を引き上げるために設備投資を行って、空港の拡充などの投資を行う必要もあります。
しかし、航空系収入は非航空系収入と比較して利益幅が限られるという特徴があります。
そもそも価格は政府との合意によって決定されるため、収入の上限はプライスキャップとなります。
また、成田空港の場合は着陸料は騒音と重量に比例するように設定されていますが、近年の航空機の低燃費化及び軽量化に伴って、大型機よりも中・小型機の運航回数が増え、平均単価は低下傾向にあります。
さらに空港事業者は乗客の中継拠点である「国際ハブ空港」になることで収益の拡大を目指していますが、価格を高く設定すると低価格志向の強い新興国の空港に航空会社や乗客が流れてしまうという構造があります。
非航空系収入
非航空系収入には航空会社や商業店舗から徴収するターミナルビル使用料(航空会社のカウンター、商業店舗スペースの賃貸料)、施設貸付事業(駐車場、事務所)、免税店収入、物販・飲食収入収入、鉄道事業(スカイアクセスなどの鉄道施設使用料)などがあります。
ブランド品などの免税品は単価も高いことから、リテール事業を中心とする非航空系収入の利益率は、航空系収入の利益率よりはるかに高いという特徴があります。
従来、空港で出国手続きを終えると、搭乗口まで小規模の売店程度しか整備されていませんでした。
しかし、国際線の場合は搭乗手続きから出発までの間隔が2時間程度あり、その時間を有効に使いたいとう乗客のニーズに応える形で免税店や飲食店などが出店しました。
さらに2001年のアメリカ同時多発テロ以降は空港のセキュリティチェックがより厳重になり、出国手続きにかかる時間も長時間化しました。
乗客は時間に余裕を持って空港に到着するようになり、出国手続き後の時間の有効活用のニーズがより高まりました。
航空系収入にはプライスキャップという規制があり、利益幅が決まっていますが、非航空系収入にはプライスキャップのような規制はありません。
空港の事業者は乗客が搭乗手続きを終わらせてから、出国するまでの時間及びスペースを過ごす飲食店やその他のショッピングモールを独占的に提供することができます。
設備投資を行って、快適なターミナルビルや人気やブランド力のある店舗を提供することで、乗降客や送迎者空港での滞在時間を延ばし、そこでの消費を喚起する努力を行っています。
非航空系収入は航空系収入と切り離して考えることはできず、両者は車の両輪のような役割を果たしています。
空港事業者の創意工夫によって非航空系収入を確保し、その収益基盤をもとに航空系収入を低減することで、競争力を強化して、より多くの航空会社や乗客を誘致することができます。
空港の利用者が増えれば、非航空系収入が増大するという良い循環に向かうことができます。
実際に成田空港では、経営基盤強化策の一つとして商業施設の再整備 ・ 充実を積極的に進めてきており、近年では売上高で一般のショッピングモールを凌ぐ規模となり注目を浴びています。
市場規模・将来性
市場規模
空港の主要事業者7社の売上高の合計は2020-2021年ベースで2,649億円となっています。
矢野経済研究所によれば、道路や鉄道、空港、港湾、河川、ダム関連、上下水道/浄水場などの水関連、防災・消防・警察関連の計8分野の社会インフラの市場規模は以下のように推移しています。
(単位:億円)
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| 6,186 | 6,005 | 6,080 | 6,140 | 6,040 | 6,020 |
日本経済新聞社によれば、2020年の国内の主要空港の旅客者数は以下のようになっています。
| 国内線 | 国際線 | |
| 東京国際(羽田)空港 | 1,929万人(前年比76%減) | 41万人(前年比97%減) |
| 成田国際空港 | 198万人(前年比73%減) | 106万人(前年比96%減) |
| 中部国際空港 | 199万人(前年比69%減) | 1万7,300人(前年比99%減) |
空港の市場規模や旅客者数は海外旅行者数や国内旅行者数に比例します。
2020年は新型コロナウイルス感染症の影響に因る移動自粛・渡航制限によって国内の主要空港の旅客者数は軒並み落ち込んでいます。
JTB総合研究所によれば、日本人の海外旅行者数は以下のように推移しています。
(単位:万人)
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| 1699 | 1849 | 1747 | 1690 | 1612 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1712 | 1789 | 1895 | 2008 | 317 |
国土交通省航空局の「国際空港旅客動態調査」によれば、大手7社の出国空港別日本人・外国人・トランジット別旅客数は以下のとおりです。
| 出国日本人 | 出国外国人 | トランジット |
合計人数 |
|
| 成田 | 6,748,167 | 7,589,428 | 1,996,800 | 16,334,395 |
| 羽田 | 4,613,547 | 3,731,543 | 162,698 | 8,507,788 |
| 関西 | 3,296,876 | 7,097,780 | 97,441 | 10,492,097 |
| 中部 | 1,428,656 | 1,255,858 | - | 2,684,514 |
| 新千歳 | 161,677 | 1,461,679 | - |
1,623,356 |
将来性
近い将来は新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けると予想されます。
日本国内のみならず、世界の旅行需要が著しく減退しているなかで市場の縮小は避けられません。
国連世界観光機関(UNWTO)によれば、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、世界中で渡航が制限されるなかで、14億5800万人を受け入れた2019年レベルに回復するのは最大で4年後の2024年になると予測しています。
成田空港や羽田空港など国内の主要空港は軒並み経営不振に陥っており、国内外の旅行需要が回復するまでは空港事業者にとって厳しい収益環境は続きそうです。
また、新型コロナウイルス感染症以前から空港事業者の収益環境は厳しい状態が続いています。
アジアでは旅行需要やトランジット需要、物流需要の獲得競争が加熱しており、アジアや中東の空港は成長著しいアジアの需要を取り込んで急成長を続けています。
特にアジアの空港においては2017年から2019年にかけて、大規模な整備に多額の投資が行われていることから今後、アジアにおける路線獲得競争はさらに激しさを増すと考えられています。
日本国内においては羽田空港の一人勝ち状態となっています。
東京オリンピック・パラリンピックを前に羽田空港は国際線を一日あたり50便を増便させており、豊富な国内線に加えて、「日本の表玄関」としての機能が強化されることで、利便性や国際競争力が向上しています。
一方で、成田空港は主要路線の多くは羽田空港に奪われており、シェアが低下しているほか、地方空港でも慢性的な赤字が続いています。
業界の分類
大手7社
年間の利用者が100万人を超える空港は日本では成田(1,633万人)、関西(1,049万人)、羽田(850万人)、福岡(307万人)、中部(268万人)、那覇(172万人)、新千歳(162万人)の7つです。
民間管理空港
航空行政上「会社管理空港」と呼ばれている空港を指します。
成田空港など民間の事業者が運営している空港です。
国管理空港
国が運営に責任を持ち、国が設置・管理する空港を指します。
東京国際空港(羽田空港)や政令で定める空港が該当します。
最新のトレンド
新型コロナウイルス感染症の影響
国内の主要空港の売上高の推移を見ると、2012年以降、国内景気の拡大及びインバウンド需要の拡大に伴って市場が拡大傾向にありました。
しかし、2020年以降は新型コロナウイルス感染症の影響による渡航制限及び移動自粛によって国内及び海外観光客者数が減少しています。
空港の収益源である航空系収入及び非航空系収入は航空会社の路線数及び利用者の数に比例しますので、相当な減収となっています。
例えば、関西、大阪(伊丹)、神戸の3空港を運営する関西エアポートが3日発表した2021年3月期決算によれば、最終的なもうけを示す純損益が345億円の赤字(前年は335億円の黒字)となっています。
また、成田空港が運営する成田国際空港会社が2021年5月27日に発表した2021年3月期決算によれば、2004年の成田空港民営化以来初めて、通気の純利益が赤字(△714億円)となりました。
ここ数年、上昇を続けてきた空港業界ですが、新型コロナウイルスの影響で業績が急減する事態となりました。
世界の空港市場は拡大見込み
日本国内の空港の市場はアジア各国の空港の路線拡大などを受けて、縮小傾向にありますが、世界の空港市場は拡大が見込まれています。
2021年4月に調査会社REPORT OCEANが発表した調査結果によれば、世界のスマート空港市場は2020年から2030年までに年率9.35で成長し、2030年までに347億ドル(約3兆5,000億円)に達すると予測されています。
空港市場の拡大の背景には空港の近代化・ハイテク化への投資の増加や5Gなどのテクノロジーの進化があります。
さらに調査会社である株式会社グローバルインフォメーションが発表した市場調査レポート「新型コロナウィルス(COVID-19)が空港運用市場に及ぼす影響 - 技術および地域別:2025年までの世界市場予測」 (MarketsandMarkets)によれば、新型コロナウイルス感染症鎮静後の空港市場は2020年の85億ドルから2025年には145億ドルと年率11%で成長すると予測されています。
新型コロナウイルス感染症の影響によって世界的に観光需要が低迷しており、今回の調査では低めに見積もりがされていますが、空港運営に対する政府の資金援助や貨物輸送の増加によって、堅調に拡大すると予測されています。
一方で、IATA(国際航空運送協会)によれば、新型コロナウイルス感染症の影響によって世界の100ヶ国以上の国が渡航制限を実施しており、世界中で空港の運営収益が95%減少していると言われています。
したがって、世界の空港市場の拡大幅は変動する可能性があることに留意が必要です。
また、三井物産戦略研究所によれば、世界の653の空港全体では収支は黒字ですが、空港全体のうち69%は赤字となっており、各国政府による損失補填によって運営されています。
また、653の空港のうち、年間旅客取扱数が 100 万人を下回る小規模空港が 8 割以上を占めており、赤字空港の大半はこれら小規模空港かつ官営空港であると予測されます。