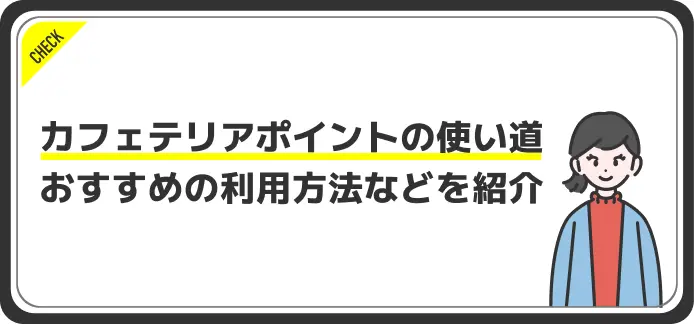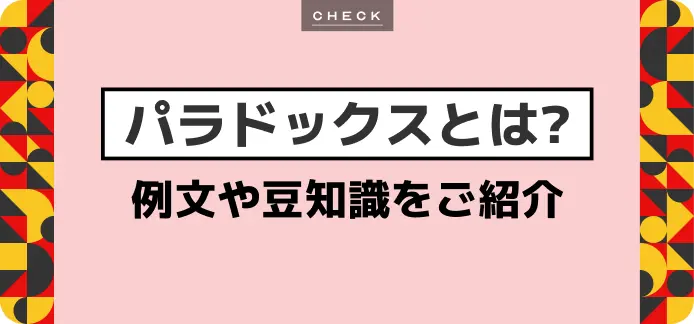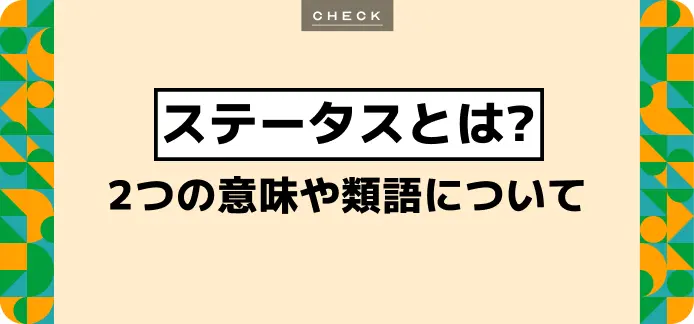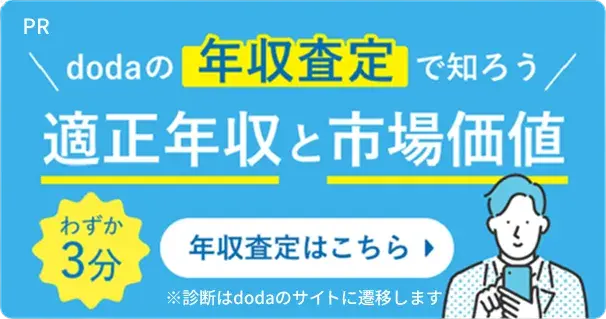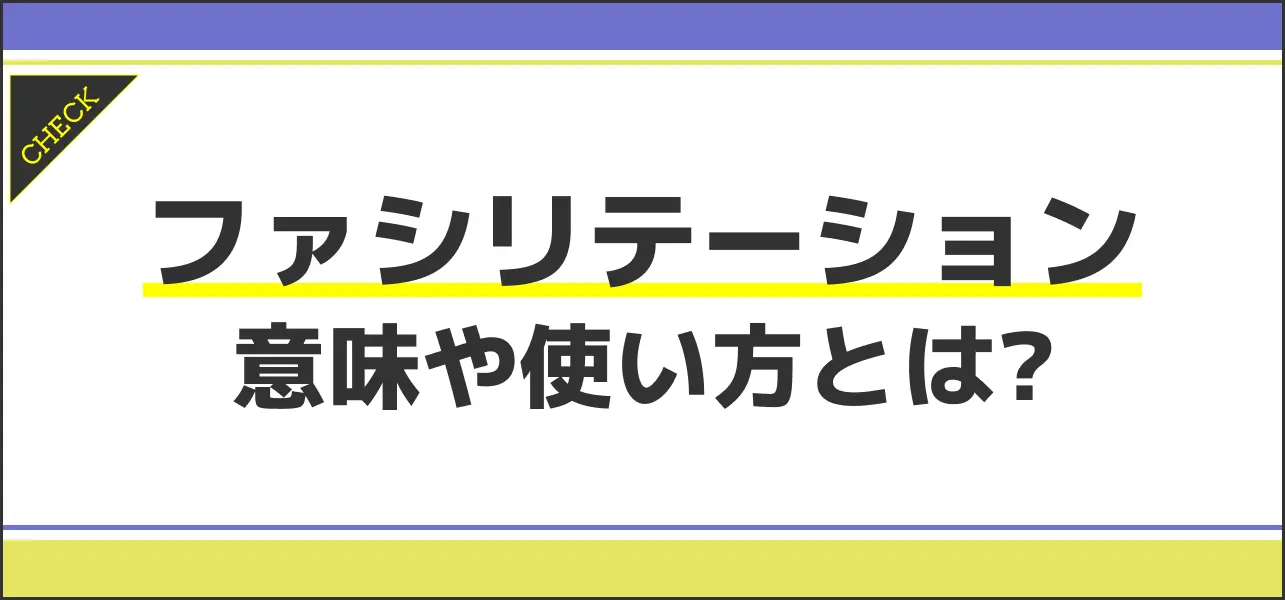
ファシリテーションの意味とは何か簡単に解説|使い方もわかりやすくまとめ
ファシリテーションを一言でいうと「会議を円滑かつ迅速に進める方法」のことです。会議や研修、ミーティングなどの活動の場において、円滑に進行するように活動を支援する役割を果たします。ファシリテーションの意味とは何かを、簡単に解説していきます。
ファシリテーションの意味とは?簡単にわかりやすくまとめ
ファシリテーションの意味や使用目的について、下記の通りまとめます。
- ファシリテーションの意味とは
- ファシリテーションの目的とは
ファシリテーションの意味とは
ファシリテーションとは|円滑に進行するように、活動を支援すること
ファシリテーションとは、一言でいうと「会議を円滑かつ迅速に進める方法」のことです。
ファシリテーションは、会議や研修、ミーティングなどの活動の場において、円滑に進行するように活動を支援する役割を果たします。
司会を担当する人が進行すると考えている方も多いですが、それはファシリテーションの一部でしかありません。
たくさんの人が集って問題を解決するために話し合いの場を持ったりする際には、参加者がそれぞれの意見を出し合うのが重要です。
認識の一致を確認すること、相互理解を深めたりするためのサポートを行い良い結論に導くという成果を生み出す手法が、ファシリテーションです。
ファシリテーターとは|会議や研修などで、舵取りをする役目を担う人
ファシリテータ―とは、会議が始まってから終了するまでの進行を管理して、参加者が納得できる結果を導くために働きかける役割を果たします。
一言でいうと、会議における進行役がファシリテーターです。
しかし、ただ会議を進行するだけでなく、さまざまなスキルを必要とします。
会議の目的や意味をはっきりさせることやどのような進行になるのかの情報共有をすることで、進捗を促進させます。
また全員が意見を発言できるようにしたり、全員の意見を存分に聞いたところで意見をまとめて結論に導けるように手助けをすることも重要です。
会議の結果に不満などが出ないように、フォローするという流れをファシリテータ―は担うということになります。
そのため、「どのように会議を進行する」、「自由な雰囲気で意見を出せる空間を作り出す」などのスキルが重要となります。
「リーダー」と「ファシリテーター」の違いとは
それぞれの違いを解説します。
リーダーはそのチームの中でのトップを務める責任のある立場にある人を指します。
チーム内で行われる会議内で、個々の発言や流れに問題がないかどうかを考えることが必要です。
しかし、ファシリテータ―は、会議の結果に責任を持ちません。
ファシリテータ―はあくまでも参加者の中立的な立場で、参加者の意見を引き出した後にまとめていく役割になります。
ファシリテーションの目的とは
会議やミーティングなどのビジネスでの利用目的だけでなく、地域活動や生涯学習、グループ学習などの人が集まる活動すべてに活用できる手法です。
性別や年齢などが違うさまざまな人が集う場では、目的や目標を1つに絞って進めることはとても困難だと言えます。
そのような時には、ファシリテーションによって、参加者の意見を募り、多くの意見をまとめることにより、達成や完了といったゴールに導くことが可能になります。
ファシリテーションのメリットとは
ファシリテーションのメリットは、次の通りです。
- 有意義な意見の交換ができる
- 様々なアイデアが出やすくなる
有意義な意見の交換ができる
会議中には、話が逸れてしまうことや、論点がずれてしまうことはよくあることです。
ファシリテーションでは、話がそれてしまったり論点がずれてしまっている場合には、話を戻したりします。
また、論点を再確認して進行する役割をファシリテーターが果たすことで、時間中でも有意義な話し合いができます。
限られた時間の中で有意義な意見を出すことができ、それに対しての意見などを引き出せることにもなるため、結果として参加者の納得のいく結論を出すということにも繋がります。
様々なアイデアが出やすくなる
参加者全員が意見を出せるような雰囲気を作るということも、会議などの話し合いの場では大切になってきます。
ファシリテーションは、全員がまんべんなく意見が出せるように進行します。
そのため、たくさんの意見を引き出すことができ、新しいアイデアなどの様々なアイデアを引き出すことができます。
ファシリテーションをする人のやり方・役割とは?
ファシリテーションのメリットは、次の通りです。
- 開始地点と着地点を明確に示す
- 参加者全員が共通の保有情報を持っていることや立場であることを確認
- 参加者全員が自身の意見を発言できる空間作り
- 論点がずれていないのかを確認しながら進める
- タイムキーパーとして時間の管理を行う
- 結論付けと合憲形成を行う
開始地点と着地点を明確に示す
ファシリテーションでは今回の会議がどこから話を始めるのか、そして最後の着地点をどこにもっていくのかということをしっかりと示すことが必要です。
議論の着地点は、参加者が不満がないように結論を出すことです。
議論の最終的なゴールは参加者同士の「合憲形成」です。
合憲形成のプロセスは、以下のプロセスになります。
- この場で何をするのかの共有
- 意見の理由を共有
- 結論の選択と合意
- 実行プランの認識の一致の確認共有
例えば、今回の会議では、1と2の議論は終わっているため、3と4についての議論を行うという場合には、開始地点が3で着地点が4となります。
会議を始める際に参加者にその旨を共有しておくことで円滑に議論を進めることができます。
参加者全員が共通の保有情報を持っていることや立場であることを確認
ファシリテーションを行う場合は、同じチームや部署のメンバーとの会議の場合に、共通の認識や共通の言語ができていることがほとんどです。
しかし、他部署などいつも行っているメンバーではない場合には、保有情報が異なっていたり、話し合いの目的なども異なる場合もあります。
そのため、会議を円滑に進行するために、保有情報の差がどれくらいあるのか予測します。
またどのようなミッションや目的を持っているのかの把握して、相互関係の把握が必要です。
参加者全員が自身の意見を発言できる空間作り
参加者の意見をまんべんなく聞き出すためには、参加者が発言しやすい話題などを出すなどの空間作りが必要です。
発言ができないという人の中には、本当は意見を持っているのに、発言しないという場合もあります。
自分の発言が特に必要ではないと思っていたり、発言をすることに自信がない場合が多く挙げられます。
ファシリテーションでは、そういった参加者の気持ちも汲み取りながら、個々の発言には十分に意義があるということを伝えて意見を出しやすい空間作りをすることが大切です。
論点がずれていないのかを確認しながら進める
円滑に進めていくためには、話が逸れてしまうことや、論点がずれてしまうことに注意をすることが大切です。
ファシリテーションでは論点がずれてきた場合に、ファシリテーターが、軌道修正をしたり、再度参加者の認識を再確認することが必要です。
話が盛り上がっていくとなかなか起動酒精できないということもおこりかねません。
しかし、参加者の気持ちに配慮しながら議論をまとめるということも求められるのがファシリテーターの役割と言えます。
タイムキーパーとして時間の管理を行う
ファシリテーションではあらかじめ決めておいたゴールに到着するためには、会議の時間管理を行うことも必要です。
ある程度の時間の予測をたてておくことで、時間だけがかかってしまって結論が出なかったということになってしまう可能性があります。
会議の目的の共有やまとめなど、それぞれの大体の所要時間の配分を決めておくことで、実際の会議の進捗などを考慮しつつ、時間の管理を行いながら進行していきましょう。
結論付けと合憲形成を行う
ファシリテーションでは最後に今後の活動に向けて「誰が」「いつまでに」「何をするのか」ということを明確に提示することが必要です。
参加者全員の意見や認識を再確認することで、会議を締めくくるための結論付けを行います。
今後のアクションまでが未決定の場合には、今回の議論で決定したこと、決定していないことを明確に示します。
次回の会議で話し合うことを共有してから会議を締めくくりましょう。
ファシリテーションの実践事例|円滑に進めるコツとは
ファシリテーションの実践事例は、次の通りです。
- 事例1. ミーティングをファシリテーションするコツ
- 事例2. 研修・ワークショップをファシリテーションするコツ
事例1. ミーティングをファシリテーションするコツ
ファシリテーションの実践例として、事前準備から当日の進行、会議後の対応までの流れは以下のとおりです。
| 会議前 | ・会議を行う目的、目標を決める ・会議に参加する人を確認する ・会議の目的や参加者情報をふまえた、進行方法の決定 ・会議に使う資料や会場の準備 |
| 会議中 | ・会議を行う目的、目標を共有する ・参加者の発言をうながしたり深めたりする ・タイムキーパーとして時間を管理する ・会議の結果をまとめ、合意を得る |
| 会議後 |
・議事録の作成、回覧 |
ファシリテーションは事前準備から始まっています。
スムーズな会議進行のために、あらかじめ情報を集めたりある程度の進行方向を決めておくことが大切です。
当日は事前準備のもと、円滑かつ活発な会議進行のためにファシリテーションスキルを発揮します。
会議後は速やかに議事録を作成し、今回の会議についてふりかえって次回の目標や議題を確認するとよいでしょう。
事例2. 研修・ワークショップをファシリテーションするコツ
ワークショップとは参加者の主体性を重視した体験型講座のこと。
参加者同士が話し合いを通して課題解決や合意形成、学習などを行います。
会議と比較して研修やワークショップの場合、参加者が能動的に参加するためのしかけづくりやワークタイムのシミュレーションが重要になります。
研修・ワークショップ中は参加者の体験が促進されるよう、ファシリテーションスキルを生かしながら柔軟に対応しましょう。
大切なのはワークショップが議論や討論の場にならないこと。
参加者同士がお互いを尊重し、体験を深める存在としてワークに取り組めるよううながします。
ワークショップ後は成果を確認し、参加者からもフィードバックを得ると次回に生かされるでしょう。
ファシリテーションスキルの具体例とは
ファシリテーションの実践事例は、次の通りです。
- 場のデザインスキル
- 質問するスキル
- 話を聞くスキル
- 構造化スキル
- 合意形成のためのスキル
場のデザインスキル
会議や研修、ワークショップなどの成功は、場のデザインが左右します。
参加者や議題を考慮して、活発な意見交換が行われるよう働きかけることが大切です。
たとえば会場の配置を考えたり、当日の活動が促進されるような資料を作成したりして事前準備を行います。
当日は参加者の雰囲気や話し合いの進み具合にあわせて柔軟に対応するとよいでしょう。
空間のデザインはもちろん、意見交換の時間や参加者同士の関係性をデザインすることで、より活発な会議・研修・ワークショップになります。
場のデザインスキルは、場の空気感を察知して対応し、コントロールするスキルといえるでしょう。
質問するスキル
話し合いの目的を達成するためには、ファシリテーターの質問力が重要です。
たとえば「つまりこういうことですね?」と参加者が言いたいことを要約して確認したり、「具体的に言うとどういうことでしょう?」と発言をうながしたりすると、場の理解が深まります。
ファシリテーターが積極的に介入することで、会議・研修・ワークショップは活発になります。
ただし場の主役はあくまで参加者個人。
目的達成のための補助として、個人の想いや考えをしっかりと受けとめ、引き出す能力が必要です。
話を聞くスキル
ファシリテーターの聞く力が活発な意見交換をうながします。
たとえば発言者に顔や体を向けてしっかりと目を見たりうなづいたり、相づちを打ったりすると発言者も聞いてもらっている自覚が得られ安心するでしょう。
発言を聞くことで、それまでの発言を加味してまとめたり、さらなる発言をうながすために質問したりできます。
ファシリテーターも場を構成する一員として、まずはしっかりと聞く力が求められます。
話しやすい場づくりは聞く姿勢から。
話を聞くことは場のデザインスキルや質問するスキルにも通じる、重要な能力です。
構造化スキル
交わされたさまざまな意見を集約し、整理して共有する力が求められます。
たとえば議論の全体像を把握して軌道修正を行ったり、最終目的を意識しながら話しあわれる議題ごとに論点を整理したりするのはファシリテーターの役目です。
ファシリテーターは全体を俯瞰で見る立場として、意見交換の骨組みとなって機能する必要があります。
そのためには物事を体系的に理解し、筋道を立てて考え、整理する論理的思考力が重要です。
物事の枠組みを整理するフレームワークもあるので、効率的に活用しながら話し合いを進めましょう。
合意形成のためのスキル
会議や研修、ワークショップの終結には、対立をポジティブにとらえ問題解決につなげるスキルが求められます。
たとえば条件や認知、感情などなにが対立を生んでいるのかを確認したり、活動の目的を改めてふりかえって認識を共有したりすると合意形成が促進されるでしょう。
交わされた意見のなかには、対立するものもあります。
それらを目的にそって整理し、合意形成をうながすことが大切です。
どちらか一方に偏るのではなく、お互いにとってwin-winになるように調整します。
また結論やアクションプランについて参加者一人ひとりが納得することで、ネクションアクションがスムーズになるでしょう。
ファシリテーションでよくある質問とは
ファシリテーションでよくある質問は、次の通りです。
- ファシリテーションとはどういう意味・手法ですか?
- ファシリテーションの4つのスキルとは?
- ファシリテーターは何をする?
- ファシリテーターのメリットは?
- ファシリテーターの重要性は?
- 「ファシリテーションする」という言葉の意味・使い方とは?
- ファシリテーション能力を向上させるには?資格や研修・本はある?
ファシリテーションとはどういう意味・手法ですか?
会議や研修、ワークショップをスムーズに進行するのに求められるのがファシリテーションです。
いわば話し合いを円滑に進めるための技法のこと。
たとえば参加者の発言をうながしながら、多様な意見を整理したり深めたりして目的にそった結論を導きます。
ファシリテーションは実際に話し合いをまとめるほか、事前準備や事後のまとめも重要です。
多様な価値観が集まる集団を目的に向かってまとめ上げ、参加者が納得するかたちで終結させるためにはさまざまなスキルを要します。
このファシリテーションの役割を担うのがファシリテーターです。
ファシリテーションの4つのスキルとは?
ファシリテーション場面で重視されるスキルとして、以下の4つがあります。
- 場のデザインのスキル ~場をつくり、つなげる~
- 対人関係のスキル ~受け止め、引き出す~
- 構造化のスキル ~かみ合わせ、整理する~
- 合意形成のスキル ~まとめて、分かち合う~
目的をもって行われる話し合い場面で、ファシリテーターの役割は重要です。
場を先導したりまとめたり、ときにはグループの一員として話し合いに加わったりして、活発な場づくりを心がけます。
また目的にそって出された意見を構成したり合意形成を得たりして、話し合いを意義あるものにするのも重要。
ファシリテーターの働きかけを支えるのが、上記4つのスキルです。
ファシリテーターは何をする?
話し合いをスムーズに進行するファシリテーター。
以下の2つがファシリテーターの役割としてあげられます。
- 外面的なプロセス
活動の目的を達成するために必要な段取りや進行、プログラムといった過程のこと - 内面的なプロセス
参加者一人ひとりの想いや考えに基づいた思考的プロセスや関係性上の心理的プロセスのこと
会議や研修、ワークショップを円滑に進めるためには外面的なプロセスが求められます。
一方、参加者が会議に対して成果・満足感を感じるのは内面的プロセスの充実です。
これら双方に働きかけ、チーム活動のダイナミズムを生むことがファシリテーターに求められる役割といえるでしょう。
ファシリテーターのメリットは?
話し合いにファシリテーションを取り入れることで以下のようなメリットがあります。
- 生産性の向上
- 話し合いにかかる時間の短縮
- アクションプランの立案と実行
- 参加者のモチベーション向上
- 参加者同士のチームワーク向上
ファシリテーションによって話し合いが促進されると、アイディアが出やすくなったり新しい発想が生まれたりします。
これらが深められれば、適切なアウトプットによってネクストアクションにつながったり、他分野との連携が進んだりするでしょう。
話し合いが結果につながることで参加者のモチベーションやチームワークの向上が期待できます。
組織や社会によい変化をもたらす効率的な話し合いには、ファシリテーションが重要です。
ファシリテーターの重要性は?
環境や価値観の変化から、ファシリテーターの重要性は高まりつつあります。
ファシリテーションは1960~70年代頃にアメリカのビジネスシーンで使われはじめました。
会議の参加者がアイディアを出しあって意思決定を行う過程は、トップダウンの問題解決法を打破し、生産性の向上やチームの結束を強めます。
それはグローバル化によってさまざまな価値観を有する人々とともにひとつの目的に向かう現代に即した技法ともいえるでしょう。
このような背景から、ビジネスの組織構造が縦社会から縦横無尽なネットワーク型に変化しつつある日本でも、ファシリテーターへの注目が集まっています。
「ファシリテーションする」という言葉の意味・使い方とは?
ファシリテーションとは会議や研修、ワークショップをスムーズに進行するための技法のこと。
たとえば以下のように使われます。
- ワークショップをファシリテーションする
- 今度の会議からファシリテーションが導入される
事前・事後準備を含めてスムーズな話し合いを支えるファシリテーション。
司会としての役割ばかりでなく、多様な意見を整理したり話しやすい場づくりを行ったりする能力が求められます。
それらを総合的に行う意味で用いられるのが「ファシリテーションする」という言葉です。
ファシリテーション能力を向上させるには?資格や研修・本はある?
ファシリテーションは注目されるスキルのひとつです。
話し合い場面での進行役ばかりでなく、仕事上や対人関係においても生かされる能力といえるでしょう。
近年ではファシリテーションスキルを習得するための研修やセミナーが開催されています。
また書籍で勉強することも可能です。
ファシリテーションの技法を身につければ、資格試験によってそのスキルを証明できます。
事前・事後準備から話し合い場面での構造化や合意形成、コミュニケーションスキルまでファシリテーションにはさまざまな技術・能力を要します。
しっかりと学習し実践的な経験を積むことが大切です。
ファシリテーションの意味まとめ
ファシリテーションの意味は、以下のとおりです。
- 一言でいうと「会議を円滑かつ迅速に進める方法」のこと
- 認識の一致を確認すること、相互理解を深めたりするためのサポートを行い良い結論に導くという成果を生み出す手法
なお、司会としての役割ばかりでなく、多様な意見を整理したり話しやすい場づくりを行ったりする能力が求められます。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。