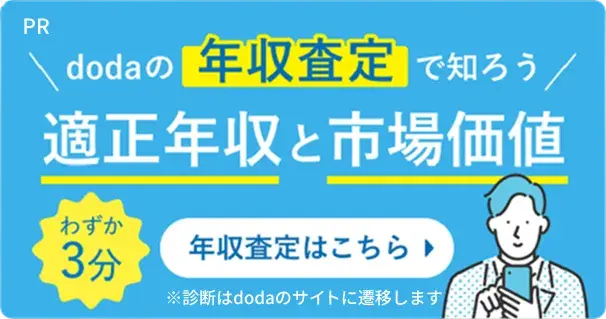【個人事業主の社会保険】加入条件やメリットなどを詳しくご紹介
本記事では、個人事業主の社会保険についてご紹介します。個人事業主が加入できる社会保険、個人事業主の社会保険の任意加入とは何か、個人事業主が社会保険へ加入するメリットは何か、個人事業主は社会保険の扶養に入れるのか、個人事業主の社会保険は経費で落とせるのかということについてご紹介します。
個人事業主が加入できる社会保険を解説
一般的に個人事業主が加入する保険は、国民年金保険と国民健康保険です。
会社員の社会保険と異なるのは、自分で全額支払わなければならない点です。
個人事業主が加入できる社会保険は残念ながらありません。
個人事業主は国民年金保険
個人事業主が加入する年金は一般的に国民年金保険で、国が運用している年金です。
加入は住まいの市区町村になり、保険料は一律です。配偶者がいる場合は夫婦二人分の保険料を支払らう必要があります。
年払い(一年分一括払い)だと保険料が若干割引になり、クレジットカード払いもあります。
個人事業主が加入する国民健康保険
個人事業主の加入が必要な健康保険は、一般的に国民健康保険になります。
国民健康保険は前年の所得に応じて保険料負担が変わりますので、前年度にの所得が高いと保険料が高くなり、支払いの負担が大きくなるのが特徴です。
さらに40歳の誕生月(1日が誕生日の場合はその前月)から、介護保険料を健康保険料とは別に納める必要があります。
該当月に介護分保険料を追加した国民健康保険料変更通知書兼納入通知書が送られてきますので、追加で支払います。
国民健康保険も住まいがある市区町村で加入します。家族も自分の国民健康保険に加入する場合は、家族それぞれに対し保険料が徴収されるようになります。
国民健康保険料も、市区町村によっては、まとめて支払うと割引になる場合があります。
個人事業主が従業員を雇った場合
正社員が常時5人以上の個人事業所(個人事業主)は、事業所として従業員の社会保険の加入が義務となります。
5人未満の場合には、通常従業員が個人で国民健康保険に加入し、個人事業所として社会保険は任意加入になります。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。