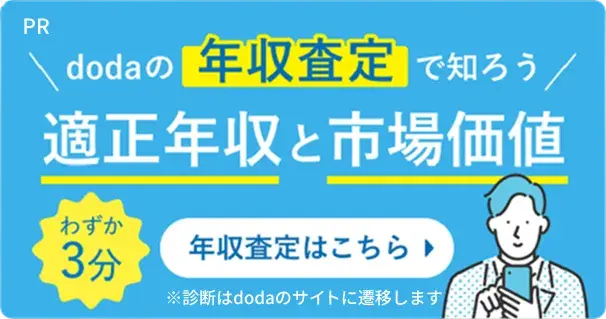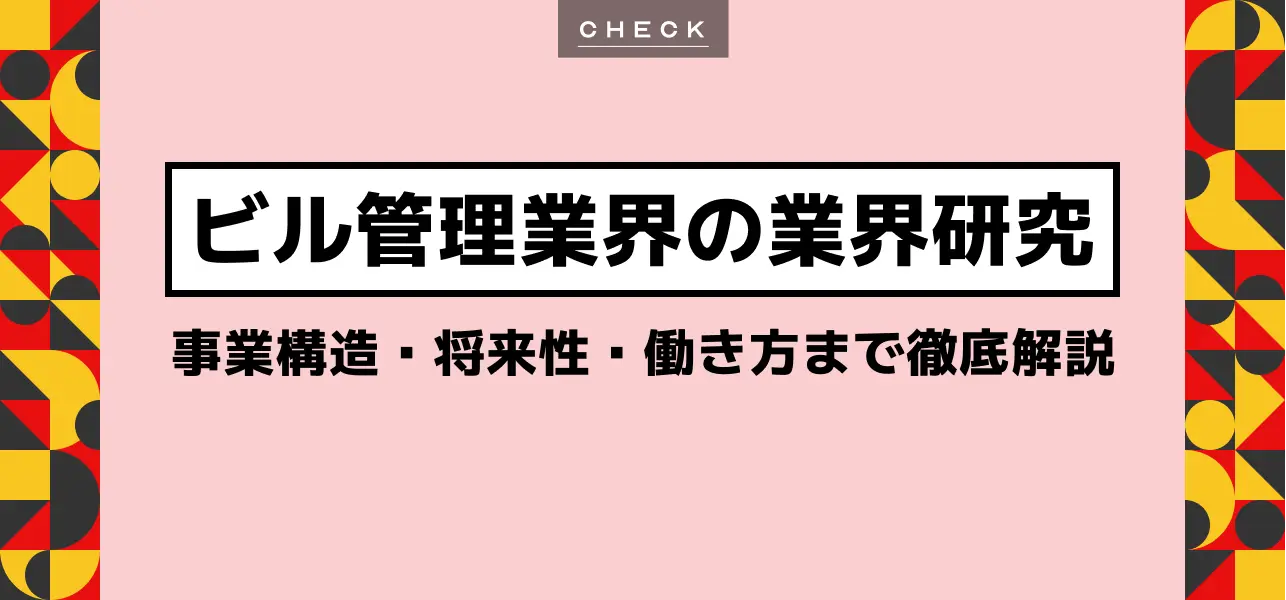
ビル管理業界の業界研究|就活に役立つ事業構造・将来性・働き方など徹底解説します
ビル業界は比較的ニッチな業界ですが、建設やインフラに関心のある学生から根強い人気を誇っています。大手企業も多く、安定志向の学生が多く志望しています。人気のある業界ですので、しっかりと就活対策を行うことが大切です。この記事では各社の有価証券報告書、シンクタンクや公的機関のレポートを参考にしてビル業界のビジネスモデルや業界のトレンド、各社の動向などを解説しています。業界研究をしっかり行ったうえで自分の強みや経験をどのように活かせるのかを面接官に伝えることが大切です。ぜひ最後まで読んでビル業界の就活対策を万全にしてください。
ビル管理業界とは
この章ではビル管理業界の
- 業界構造
- 将来性
- 業界分類
- 最新トレンド
について解説していきます。
業界構造(Tier1・2や商流やメインビジネス(稼ぎ方))
建物の保守・修繕・運営
ビル管理業はビルメンテナンス業とも呼ばれます。
身近な企業ではセコムやALSOK、アズビル、イオンディライトなどがイメージしやすいかもしれません。
ビル管理業の対象となる施設はオフィスビルに限定されず、商業用施設、倉庫、学校、病院、ホテル、飲食店、マンションなど幅広く、顧客はそれらの施設を保有する法人や学校、医療法人となります。
事業内容はそれら施設の清掃、維持管理、施設及び内部の施設の修繕、リフォーム、防犯監視システムなどの設置・保守・修理、点検整備、保安警備、ビルマネジメント、建物に侵入する不審者の監視など多岐に渡っています。
主な分類は以下のとおりです。
- ビルメンテナンス
清掃、設備管理、警備
- 建物管理・工事
点検・調査、緊急修繕、定期修繕、長期修繕、防災工事
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事業別の売上構成比として一般清掃業務が約6割、設備管理業務が2割弱、警備業務が1割弱となっており、この3業務で約9割を占めています。
施設の設計段階からビルメンテナンス事業に携わる事業者や完成後の施設に対して施設の保守や運営などを行う事業者など建物の完成前後によって関与するタイミングがあります。
また、建物の保守や修繕・運営などすべての事業に携わる事業者もいれば、特定の事業に限定して事業を行っている事業者もいます。
大手企業はすべての事業に携わることが多いですが、小規模事業者は特定の事業に絞っている場合が多く、特に一般清掃事業の割合が多いようです。
規模が大きくなるほど設備管理や警備の占める割合が高い傾向にあります。
清掃業務は単にビルの衛生環境の維持だけではなく、ビルの老朽化の防止及び資産価値向上という意味を持ちます。
清掃事業は顧客の施設の利用者に快適な環境を提供することが重要であり、高頻度で業務を行う必要があります。
ビルの管理及び運営においては空調や電気、給排水設備、エレベーターの安全運転など24時間365日体制で管理・運営する必要があります。
これらの設備は対象となる施設や設備によってはメンテナンス事業者に技術や知識、関連資格が必要となります。
特に近年ではビルや商業施設の設備がICT技術の進展などによってハイテク化しています。
例えば、エレベーターの設備の遠隔監視やタブレット端末を活用して施設の運営・保守などです。
したがって、メンテナンス事業者にはより高度かつ専門的な知識やスキルが求められます。
また、エレベータなどの設備の遠隔監視も同様に設備集約型です。
これらの業務は監視拠点を集約しながらICTの進化にあわせて機能を高度化してきています。
設備管理でもタブレット端末を活用して生産性を高める動きがあります。
労働集約的なビジネス
ビル管理業のビジネスモデルの特徴として事業活動を営む上で、事業活動の労働力に対する依存度が高い労働集約型産業であることが挙げられます。
農業や製造業、サービス業にも共通しますが、サービス原価に占める人件費の割合は高く、実に総費用の8割を人件費が占めていると言われています。
ビル管理業では法人や学校、病院などの顧客から施設の保守や管理の業務を受託し、サービスの対価として報酬を受け取ります。
労働集約型産業であり、人件費の動向が会社の業績に直結することから各社はコスト削減のためにパートやアルバイトといった非正規雇用を中心に採用を行っており、従事者の多数を高齢者や女性が占めています。
しかし、ビル管理業は参入企業が多く、競争が激しいことから人材の獲得競争が続いています。
また、3K(「きつい」「きたない」「危険」)というイメージが強く、労働の待遇が必ずしも良くないことから人材採用は難しくなっています。
例えば、最も一般的な事業である清掃事業ではビル管理業全体で9万人の労働者が不足していると言われています。
しかし、上記の通り、人件費が業績に密接に関連しており、人材獲得のために賃金を上げることが容易ではないというジレンマを抱えています。
さらに人件費を受注単価に転嫁させることは受注獲得の観点から難しく、ビル管理業界は受注にあたって多くの困難に直面します。
サービス面での差別化が難しく、価格競争の激しい業界である一方で、ハイテク化に対応している企業や高い技術や専門性の有する一部の企業は業務の差別化によって受注単価を上げることに成功しており、企業によって明暗が分かれる業界でもあります。
また、ビル管理業の構造として元請業者が下請けや二次下請けに外注するケースが多いです。
ピラミッドの下に行くほど収益性は下がりますので、顧客を獲得する力のある元請業者でないと収益性の低い業界であることも特徴です。
市場規模・将来性(シンクタンクのレポート)
市場規模
ビル管理業の事業内容は多岐に渡ります。
ビル管理業に関する業務を全般的に行っている企業もされば、特定の事業に限定して行っている企業もあります。
また、ビル管理関連の事業のほかに様々な事業を経営している事業者も多いため、業界全体の市場規模をまとめにくいという特徴がありますが、代表的な関連企業に注目したうえで、ビル管理業の各社の有価証券報告書によれば、主要対象企業10社の売上高の合計は2020-2021年時点で9,403億円となっています。
少し古いレポートになりますが、2014年にシンクタンクNTTファシリティーズ総研が発表した「ビルメンテナンス業界の動向」によれば、ビル管理業界の市場規模(清掃+設備管理+警備)は3兆6,000億円となっています。
| 清掃・衛生管理業務 | 設備管理業務 | 警備保障業務 | 修繕・その他 |
| 33% | 38% | 15% | 14% |
ビル管理業はオフィスビルや商業施設など建築物の新設と業況が比例します。
高度経済成長期、その後のバブル期までは業界全体の市場規模は数%程度で成長していましたが、バブル経済の崩壊後に成長は著しく鈍化しました。
2000年代に入ると行政セクターの公共事業費の増加や景気拡大期に入ったことから市場は成長基調に転じています。
しかし、アメリカ初のサブプライムローン問題やリーマンショックによって世界的に景気後退期に入って、民間の建設投資が低迷し、市場環境は悪化します。
しかし、その後2011年の東日本大震災の影響で新規の建設需要が増加したことや省エネ対応需要が増えて、微増傾向にあります。
矢野経済研究所によれば、2015年以降の市場規模の推移は以下のようになっています。
(単位:億円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上記の通り、ビル管理業界の市場規模は微増で推移していましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大で市場環境が一変しました。
リモートワークの普及や企業の収益環境の悪化によってオフィスビルを閉鎖・縮小する企業が増えたことで、ビル管理業の主な顧客であるオフィスビルのメンテナンス需要は減少しています。
また、緊急事態宣言や外出自粛要請によって商業施設や宿泊施設は客足が遠のいており、市場は縮小しています。
将来性
ビル管理業界はバブル経済崩壊以降の新設の公共施設や商業施設の建設の低迷によって顧客層が縮小しています。
また、ビル管理業界の業界慣習として顧客から建物の保守や管理を受注すると、半永久的に受注していた場合が多くありましたが、近年では不動産の証券化や官公庁物件における随意契約の減少などを背景として、ビル業界側から顧客に対して提案型の競争入札を行う建物が増加しており、安定的な収益が見込めなくなっています。
また、バブル経済崩壊以降に企業は設備投資を抑制したり、経費削減策を打ち出して、内部留保を蓄積する傾向にあり、オフィスビルの保守・管理・運営などのビルメンテナンスコストは真っ先に削減対象となります。
したがって、受注単価が低下傾向に有り、ビル業界の収益性を圧迫しています。
また、ビル管理業界を悩ませる課題の一つに人材不足があります。
ビル管理業は参入企業が多く、競争が激しいことから人材の獲得競争が続いています。
また、3K(「きつい」「きたない」「危険」)というイメージが強く、労働の待遇が必ずしも良くないことから人材採用は難しくなっています。
また、現場で働く作業員のみならずマネジメント層の確保・育成も難しい状況にあります。
ただし、一方でオフィスビルや商業施設は決して世の中からなくなるものではないため、ビル管理の業務自体は消滅せず、今後も一定の需要があると予測されます。
受注単価の低下に対してはICT技術を活用することで高度な技術や専門性を武器に契約の見直しや単価の上昇などの交渉を行う企業もあります。
一番の課題である人材不足に対しても清掃ロボットや警備ロボットの活用などによって、省人化による人材不足の解消が試みられています。
今後はビル管理業界の構造的課題である労働集約型産業の効率化やコストバランスを追求した新たな業務運用の形式を確立していくことが課題となると考えられています。
業界の分類
全国ビルメンテナンス協会によれば、ビル管理業界の主な分類は以下のとおりです。
独立系
清掃会社が起点であり、設備管理、警備と複合化しています。
大手企業系
自社保有施設の管理が主体です。
例としてイオンディライト、共立メンテナンス、日本ハウズイングなどがあります。
不動産・生保系
賃貸ビルが対象です。
例として東急不動産HDと日本管財などがあります。
建設会社系
自社施工物件の保守が主体です。
商業施設系
大型小売店舗が起点となっています。
住宅系
マンション管理が主体です。
外資系
不動産サービスが主体です。
警備保安サービス系・設備保守サービス系
エレベータ・空調機の保守が主体です。
例としてセコムやALSOK、アズビル、イオンディライトなどがあります。
最新のトレンド
投資家からのコスト低減圧力
近年、ビルメンテナンス業界には受注単価の低下圧力がかかっています。
その背景には2000年以降に進んだ不動産の証券化があります。
不動産の証券化とは不動産を管理する合同会社や特的目的会社などの事業体を設立し、土地や建物などの不動産から得られる賃料や売却益を管理します。
賃料や売却益は社債や株式などに証券化され、市場で売買されます。
これは不動産投資信託(REIT)と呼ばれますが、REITを保有する投資家は投資額に応じて、家賃収入や運用益を受け取ります。
もともとREITはアメリカで1960年代に誕生しましたが、日本では流通していませんでした。
しかし、2000年に投信法が改正されると、手軽にできる不動産投資としてREITが注目され、市場が急激に拡大しました。
2008年までに法人の所有する不動産490兆円のうち45兆円が証券化されたと言われています。
不動産の証券化がビルメンテナンス業界に与えた影響は一体なんでしょうか?
従来はビルメンテナンス業務の発注者はオフィスビルや商業施設のオーナーでした。
ビルメンテナンス業務は一度受注したら、慣習的に特定の事業者に発注されるため、収益が安定しているという特徴がありました。
しかし、不動産の証券化によって、ビルメンテナンス業務の発注者がREITを運用するアセットマネージャーとなりました。
アセットマネジャーがプロパティマネジメント会社を通じてビルメンテナンス会社に業務を発注するようになったのです。
REITの投資家としては不動産の収益性を上げるために不動産を運用するコストが最大限削減してほしいというニーズがあります。
このように不動産の投資効率や収益性が重視される中でビルメン テナンス業界には厳しいコスト低減圧力がかかることになりました。
新型コロナウイルスの影響
新型コロナウイルス感染症の影響はビルメンテナンス業界にも及びんでいます。
全国ビルメンテナンス協会がビルメンテナンス事業者に対して行ったアンケートによれば、新型コロナウイルス感染症が経営に悪い影響があったと回答する経営者や管理者は全体の81.6%に上りました。
具体的な影響としては売上の減少が74.1%、業務の縮小・延期・中止要請が63.7%を占めています。
当初、新型コロナウイルス感染症の影響が与える影響は軽微だと見られていました。
政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が2020年に発表した「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」によれば、ビルメンテナンス事業者は「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」とされていました。
オフィスビルや商業施設が存在する限り、ビルメンテナンスの業務は存在しますし、新型コロナウイルス感染症に伴って感染症予防のための追加的な清掃・消毒需要も見られます。
しかし、新型コロナウイルス感染症が長引くにつれて、企業でリモートワークが普及したほか、顧客である企業の収益環境が悪化しました。
これによってオフィスビルを閉鎖したり、緊急事態宣言や外出自粛要請によって商業施設や宿泊施設は客足が遠のいています。
これによって顧客のビルメンテナンスにかける経費の削減圧力がかかっています。
したがって、今後の不透明感が強くなっており、市場規模の縮小は避けられないものと考えられています。