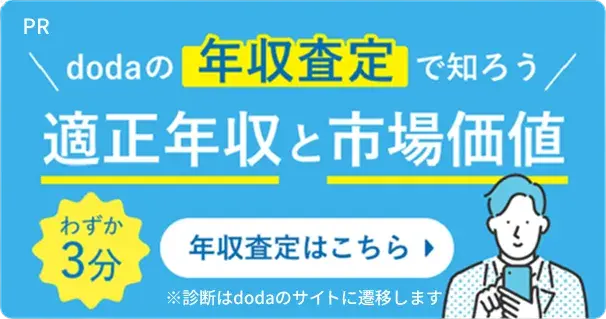【ボーナスにかかる税金は高い?低い?】計算方法や手取り額まで解説
ボーナスを貰えると気になるのは、その中から税金はどれほど引かれるのかということでしょう。実際に、ボーナス額は何十万、何百万単位でもらえることが多いため、税金が掛かるとかなりの額が差し引かれることになります。今回は、ボーナスと税金について調査しましたので、確認しましょう。
ボーナスから引かれる税金は4つ

ボーナスから引かれるものは何か
ボーナスからは、税金や保険料が引かれます。引かれるものは以下の4つとなります。
- 源泉所得税
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
以上のように、各種保険料と源泉所得税のみがボーナスから引かれる対象となります。ですので、前年1年間の所得を基に年間の納税額が決まる住民税はボーナスから引かれず、毎月の給与から引かれます。
また社会保険関連に関しては、一定の割合で引かれる額が決まっております。
- 健康保険料:4.1%
- 厚生年金保険料:7.144%
- 雇用保険料:0.6%
以上の割合がボーナスの額面に対してかかる割合になります。
住民税はボーナスから引かれない
住民税は、前年1年間の所得を参考にして、納税額が決まります。
ですので、住民税はボーナスに関係なく、毎月同じ額が引かれるという仕組みになっています。
ただしボーナスが貰える月に税金が多く引かれてる場合、その月の支給額を常に貰っているとして一時的に計算するために引かれます。
ですが、年末調整に税金が多く引かれていることが分かれば、しっかりと年末調整で戻ってきます。
また、保険の支払いをボーナスが貰える月と合わせて半年払いにしている会社もあります。
ボーナスと税金の関係については知っておこう
その中でも税金は少し特殊な位置にあり、源泉所得税だけが差し引かれる所得です。
一般的には「ボーナスから税金がどのくらい差し引かれるか?」という表現をしますが、源泉所得税は前月分の前月の給与のうち社会保険料を控除した後の金額を基準とし、税率が決定されます。
また、扶養親族の数によっても変動があり、扶養親族が以内場合には6万8000円未満、扶養親族が3人いる場合では17万1000円までは所得税は課されません。
この基準を超えると、前月の給与と扶養家族の人数に応じて、2.042%〜45.945%の税率が賞与へ課されるというシステムです。
そのため、前月いくらの給与を手にしているかがボーナスの金額に大きく影響していることになります。
社会保険料や厚生年金保険料などの税金以外の部分でも差し引かれる項目があります。
あらかじめ計算方法を含めた確認をしておくとよいでしょう
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。