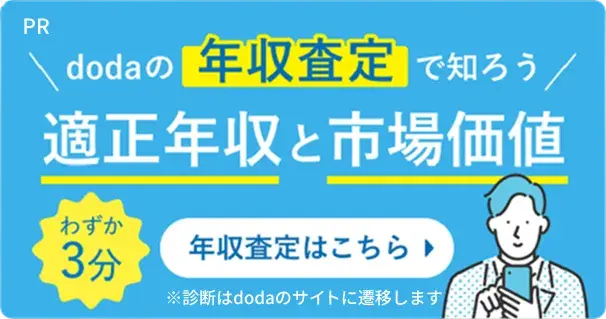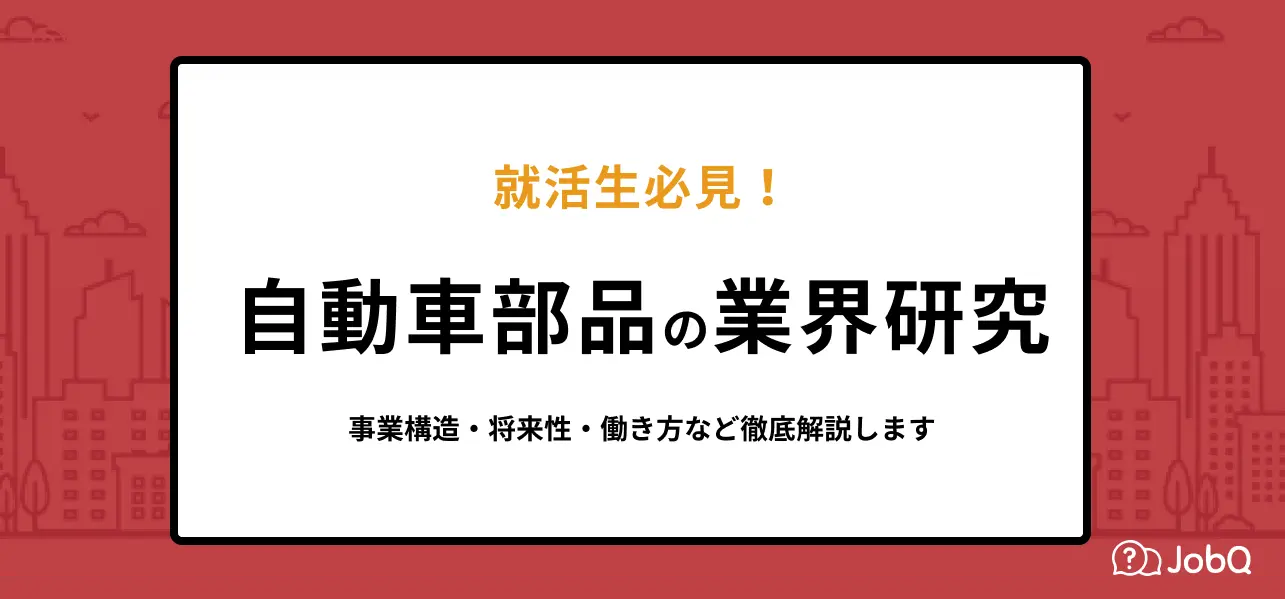
【就活生必見!】自動車部品業界の業界研究|事業構造・将来性・働き方など徹底解説します
自動車ぶ業界は学生から根強い人気を誇っています。最も人気があるのは完成車メーカーですが、陰ながら自動車開発を支えているのが自動車部品業界です。完成車メーカーを志望する多くの学生が部品業界を併願します。多くの学生が志望するため部品業界の倍率は高くなりがちです。激しい競争を勝ち抜いて内定を獲得するためには自動車業界全体の商流やビジネスモデルを理解して、その中の部品業界の立ち入りを明確にすることが必要です。この記事では自動車部品業界の業界研究を有価証券報告書やシンクタンクのレポートをもとに、詳しくわかりやすく説明しております。この記事を読めば、自動車部品業界の業界研究は完了するでしょう。
自動車部品業界とは
この章では自動車部品業界について、
- 業界構造
- 将来性
- 業界分類
- 最新トレンド
以上の4点から解説していきます。
業界構造
自動車部品の製造業界は自動車業界に属しています。
自動車業界は自動車の生産及び自動車の生産に必要な部品の供給、自動車の販売・整備など自動車関連産業全体を指します。
各メーカーによって差異はありますが、自動車の部品やパーツが約4,000種類、2万から3万の部品から構成されています。
1つの自動車の生産に上場企業から中小企業、小規模零細企業など全部で数百社以上の企業が関わっています。
これら自動車製造業のほかにも自動車を販売する自動車ディーラーや自動車の修理会社、車検会社、金融会社、陸運を行う物流会社など膨大な自動車関連企業によって自動車産業全体が構成されています。
下請けビジネス
自動車部品の製造業のビジネスモデルを考える前にトヨタやホンダなどの自動車完成メーカーから自動車業界を見渡してみましょう。
マーケティングによって得られた情報を分析し、新しい自動車の開発・設計を行います。
自動車の製造に必要な部品を自動車部品メーカーに発注します。
自動車部品メーカーから納品された部品を自社の工場で組み立てて、完成車を完成させます。
完成した自動車はディーラーなどに引き渡され、エンドユーザーに販売されます。
1種類の自動車には約2万〜3万の部品から構成されており、完成車メーカーが自社で製造する場合を除いて、大半を自動車部品メーカーが製造しています。
したがって、自動車部品メーカーにとっては完成車メーカーが顧客、発注者であり、構造としては完成車メーカー→部品メーカーの下請けビジネスです。
部品メーカーはさらに1次部品、2次部品、3次部品と階層構造に分かれており、下請けの部品メーカーの中でも分業構造が構成されています。
完成車→1次部品メーカー→2次部品メーカー→3次部品メーカーと発注されます。
末端の3次部品のメーカーになると、従業員数人の小規模零細企業であることも珍しくありません。
これら部品メーカーは鉄鋼・合成樹脂・アルミニウム・ゴムなどの原材料を仕入れて、自社の工場でプレス、鋳造、鍛造、熱処理、機械加工、鈑金、塗装、組立などを行って必要な部品を製造しています。
原材料の多くはピラミッドの頂点にある完成車メーカーが一括購入し、部品メーカーに有償で支給することによって原材料コストを最低限に抑えています。
また、これら部品メーカーの多くは完成車メーカーの向上の近辺に自社の向上を構えて、企業城下町を形成している場合が多く見受けられます。
自動車の部品は約4,000種類に上ると言われていますが。これらすべてを1つの部品メーカーが総合的に製造しているわけではありません。
自動車部品メーカー最大手のデンソーでも熱機器やエンジン、駆動系の部品を製造していますが、ブレーキや車体は製造していません。
それぞれの部品メーカーが専門分野を持ち、電装に特化したメーカーやブレーキ、エンジンなどに特化して高度な技術を有するメーカーが存在します。
完成車メーカーから見れば、複数のサプライヤーに発注する部品を分散させることでリスクを分散しています。
1つの部品メーカーでトラブルが起きて、大量の部品の供給が滞り、製造過程に大きな支障が生じるのを防ぐためです。
系列完成品メーカーからの発注
自動車部品メーカーは大きく大別すると「系列」と「独立系」に分けられます。
系列とは完成車メーカーの系列となっており、資本関係を含む強い協力体制が敷かれています。
例えば、トヨタ自動車に専門的に部品を供給している自動車部品メーカーはトヨタ系と呼称され、他のトヨタ系の部品メーカーと一緒にトヨタの部品供給協力会社グループを形成しています。
他にも日産系、ホンダ系などそれぞれの完成車メーカーの下にこのような部品供給協力会社が存在しています。
現在では完成車メーカーの海外現地生産シフトに合わせる形で系列の部品メーカーも海外に向上を移す動きが出ています。
有名な系列企業としては以下のような企業があります。
-
トヨタ系
デンソー、アイシン精機、豊田自動織機、日本精高工、ジェイテクト、豊田合成
-
日産系
マレリ、日産車体、ジャトコ
-
ホンダ系
テイ・エステック、エフ・シー・シー、ジーテクト、ユタカ技研、ケーヒン
一方で、完成車メーカーと系列関係になく、複数の完成車メーカーに納品しているのが独立系です。
代表的な独立系部品メーカーとしてはスタンレー電気、曙ブレーキ工業、ニッパツ、矢崎総業などがあります。
しかし、現在では系列系の部品メーカーが複数の完成車メーカーに部品を納品することもあり、系列構造が崩れつつあります。
グローバル化の進展によって、完成車メーカーが海外メーカーとの激しい競争に晒される中で完成車メーカーの部品の調達コストや品質に対する姿勢が厳しくなっています。
そのため、「より良いものをより低価格で」調達するために従来の協力体制を終わらせる動きがあります。
系列の完成車メーカーに依存してきた部品メーカーにとっては厳しい動きとなっています。
しかし、複数の完成車メーカーに部品を供給することでコストダウンやより大きな利益を上げることができるというメリットもあります。
市場規模・将来性
市場規模
業界動向リサーチによれば、2019年-2020年の自動車部品業界の市場規模(主要対象企業87社の売上高の合計)は34兆5,551億円となっています。
部品別の市場について見ていきましょう。
日本自動車部品工業会の出荷動向調査によると、2019年度の出荷額はショックアブソーバーが894億円(前年度比4.4%減)、サスペンション・ストラットが705億円(同4.8%減)、その他の懸架制動装置部品が212億(同32.4%減)となりました。
富士キメラ総研が2021年1月に発表した「自動車部品30品目の世界市場予測」によれば、2020年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、自動車の生産台数が激減しました。
詳しく見てみましょう。
国際自動車工業連合会(OICA)によると、2020年の世界自動車生産台数は前年比16%減の7,762万1,582台と3年連続して減少しました。
最大市場の中国が同2%減の2,522万台と減少し、日本は同17%減の806万台、インドも同225%減の339万台と前年比マイナスとなりました。
一方で、米国は882万台と同19%減少、同28%減のカナダ(137万台)とそれぞれ減少しましたが、米国とカナダ合わせて北米では1,0000万台の大台を保ちました。
これによって自動車部位の世界市場も2019年に比べ21.3%減の見込みとなりました。
もともと自動車部品メーカーは為替変動、原材料の高騰、その他人件費上昇や投資負担によって、苦戦していました。
そこに2021年も新型コロナウイルス感染拡大の影響で自動車メーカーは生産・販売体制で苦戦しており、部品メーカー各社も対応に追われています。
2020年下半期には自動車工場が再稼働しており、2021年以降は部品需要も回復に向かう見通しではありますが2019年の市場規模まで回復するのは、2024年頃になると予測しました。
将来性
富士キメラ総研が2021年1月に発表した「自動車部品30品目の世界市場予測」によれば、2020年の市場規模見込みは27兆6820億円でした。
それに対して、2030年は46兆5,796億円と予測しました。
部品別の市場規模の予測は以下のとおりです。
| 2017年実績 | 2030年予測 | 2017年比 | |
| 自動車部品販売額 | 36兆5,497億円 | 46兆5,797億円 | 127.4% |
| エンジン系部品 (15品目) |
4兆2,113億円 | 4兆7,646億円 | 113.1% |
| 駆動/足回り系部品 (8品目) |
8兆5,147億円 | 8兆9,315億円 | 104.9% |
| 内装系部品 (9品目) |
6兆6,335億円 | 8兆4,086億円 | 126.8% |
| 外装系部品 (8品目) |
17兆1,902億円 | 24兆4,750億円 | 142.4% |
市場規模が最も大きいのは外装系部品であり、その市場構成品目であるボディでは高価なホットスタンプ材などの採用が欧州を中心に進んでいます。
また、ボディと同様に自動車に必ず搭載される部品としてタイヤやヘッドランプがあげられます。
それらは、自動車の低燃費化や乗り心地の向上に対するニーズの増加や、LED照明の採用による高付加価値化が先進国市場を中心に進んでいます。
次いで市場規模が大きいのが駆動/足回り系部品です。
この市場ではトランスミッションやパワーステアリングの構成割合が高いようです。
自動車の走行性能の根幹を担う部品であり、ほぼ全ての自動車に搭載されています。
燃費向上などのために電子制御化が進んでいる部品が多いですが、エンジン系部品と同様に将来EV化や自動運転化により搭載の省略や採用タイプの変更が生じる部品が多くあります。
今後そうしたトレンドの中でいかに価値を提供できるかが問われています。
内装系部品はシートシステムやカーエアコンの市場構成割合が高く、快適性向上のために電子制御化など高付加価値化が進んでいます。
また、乗員の安全を志向する動きが新興国でも高まってきています。
そのため、パッシブセーフティ関連部品であるエアバッグモジュール/インフレーターやシートベルトプリテンショナーの車両1台当たり平均個数が増加しています。
業界の分類
トヨタ系部品メーカー
トヨタの系列となっており、資本関係を含む強い協力体制が敷かれているのはデンソー、アイシン精機、豊田自動織機、日本精高工、ジェイテクト、豊田合成などです。
日産系部品メーカー
日産の系列となっており、資本関係を含む強い協力体制が敷かれているのはマレリ、日産車体、ジャトコなどです。
ホンダ系部品メーカー
ホンダの系列となっており、資本関係を含む強い協力体制が敷かれているのはテイ・エステック、エフ・シー・シー、ジーテクト、ユタカ技研、ケーヒンなどです。
最新のトレンド
世界的に市場は拡大傾向
自動車部品業界の市場規模の過去の推移を見てみましょう。
2007年から2009年にかけて市場は減少し、2009年以降は一転して回復、その後市場が停滞した時期もありました。
しかし、2017年以降は再び拡大、しかし2020年以降は新型コロナウイルスの影響によって市場が縮小に向かっています。
経済産業省の「生産動態統計」によると、2020年の自動車部品の生産金額は、前年比15.3%減の7兆2,023億円となり、2年連続の減少となっています。
これまでは世界的な自動車需要の拡大を受けて、自動車部品業界では拡大路線が取られました。
しかし、2009年のアメリカのサブプライムローン問題やリーマンショックによって世界的な金融恐慌に突入し、自動車の販売台数は大幅に減少します。
自動車部品を供給する部品メーカーもその影響を受けて、2009年には大幅な減少を記録します。
しかし、2009年以降は自動車市場、特に北米や欧州市場で需要が回復してきたことで、海外市場での売上比率が大きく増加しました。
その結果、最近では自動車業界は不況を脱して再び軌道に乗ってきており、東南アジアが新しい生産・販売拠点として注目されています。
一般的に1人当たりのGDPが3,000ドルを超えると自動車が普及し始めるとも言われていますが、インドネシアやフィリピンなどがちょうどこの時期に該当しており、今後の成長が期待されます。
また、東南アジアだけではなく、アメリカや中国市場の伸びも堅調に推移し、世界的に自動車需要は旺盛です。
しかし、2020年に入りその流れが一転しました。2020年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、自動車の生産台数が激減したことを受けて、自動車部品業界も大きな打撃を受けています。
米中貿易摩擦や新型コロナウイルスの影響
2018年から米中の間で外交問題に発展したのが米中貿易摩擦です。
当時のアメリカのトランプ大統領がアメリカの貿易赤字の主要因を中国にあると考えたことでアメリカが中国の工業製品に高関税を課しました。
その後、米中が互いに関税を掛け合う形となり、世界のサプライチェーンが混乱しました。しかし、実は米中貿易摩擦は日本の自動車業界にはマイナスの影響をあまりもたらしませんでした。
日本の自動車完成車メーカーや部品メーカーは工場の一部をアメリカに移転していますが、アメリカで生産して中国に輸出される自動車台数がさほど多くないことから影響は限定的でした。
むしろ、米中が互いの工業製品に高い関税を課したことによって、世界最大の自動車市場である中国でアメリカの自動車よりも日本の自動車の販売が促進されました。
2018年7月には中国における日本の自動車の販売台数が記録的に増加しました。
一方で、マイナスの影響をもたらしのが新型コロナウイルスの影響です。
中国では2020年2月に自動車の生産・販売が前年比80%以上減少しました。
アメリカ・カナダなどの北米ではロックダウンの影響によって99%以上減少し、欧州では93%以上減少しました。
世界全体の販売台数の合計は2020年1~8月累計で4,558万台にとどまり、前年同期から約1,300万台という大幅な落ち込みとなっています。
これは自動車の需要の減少というよりは各社の工場閉鎖や稼働停止により生産台数が販売台数よりも減少したことが要因です。
2020年下半期には自動車工場が再稼働しており、2021年以降は部品需要も回復に向かう見通しではありますが2019年の市場規模まで回復するのは、2024年頃になると見通しです。