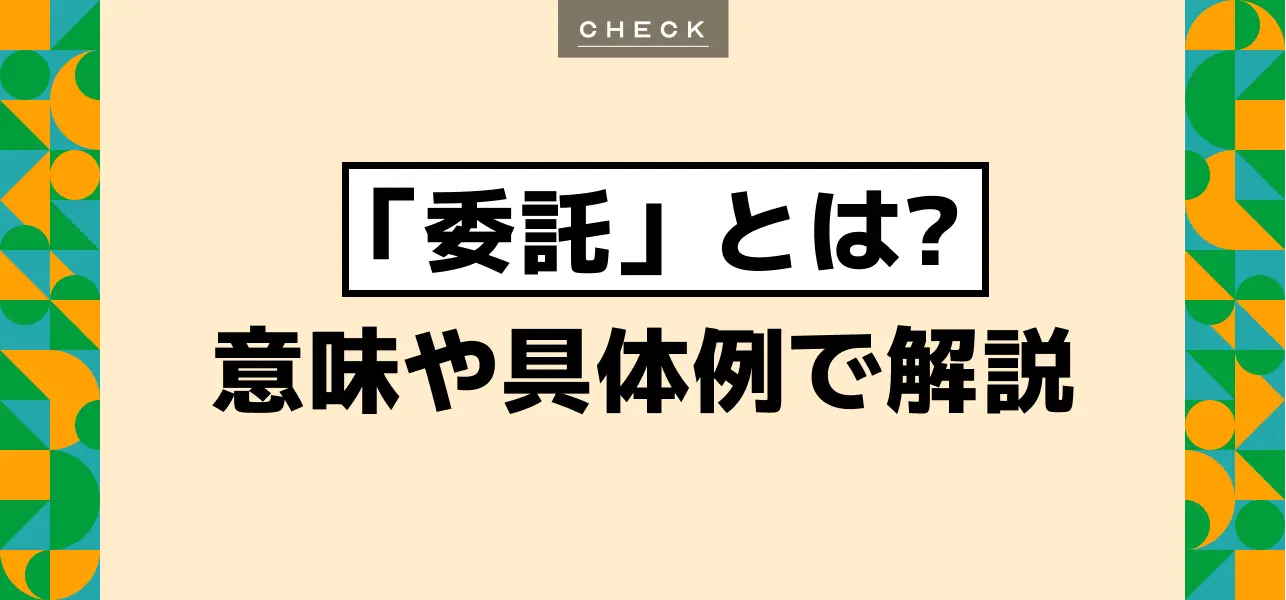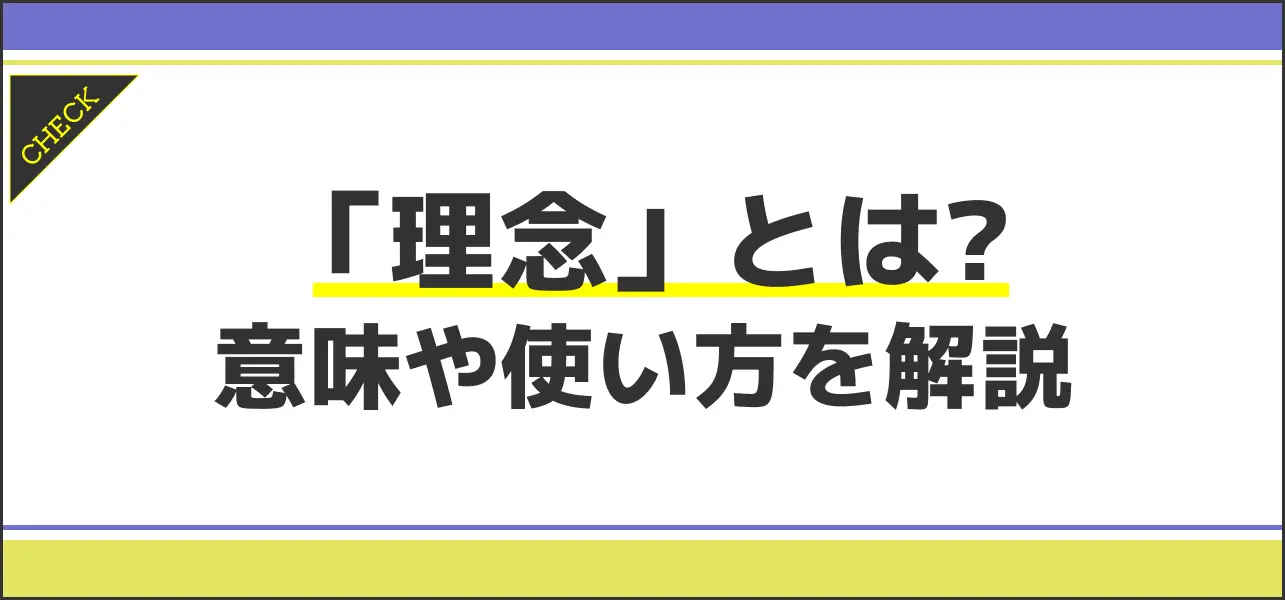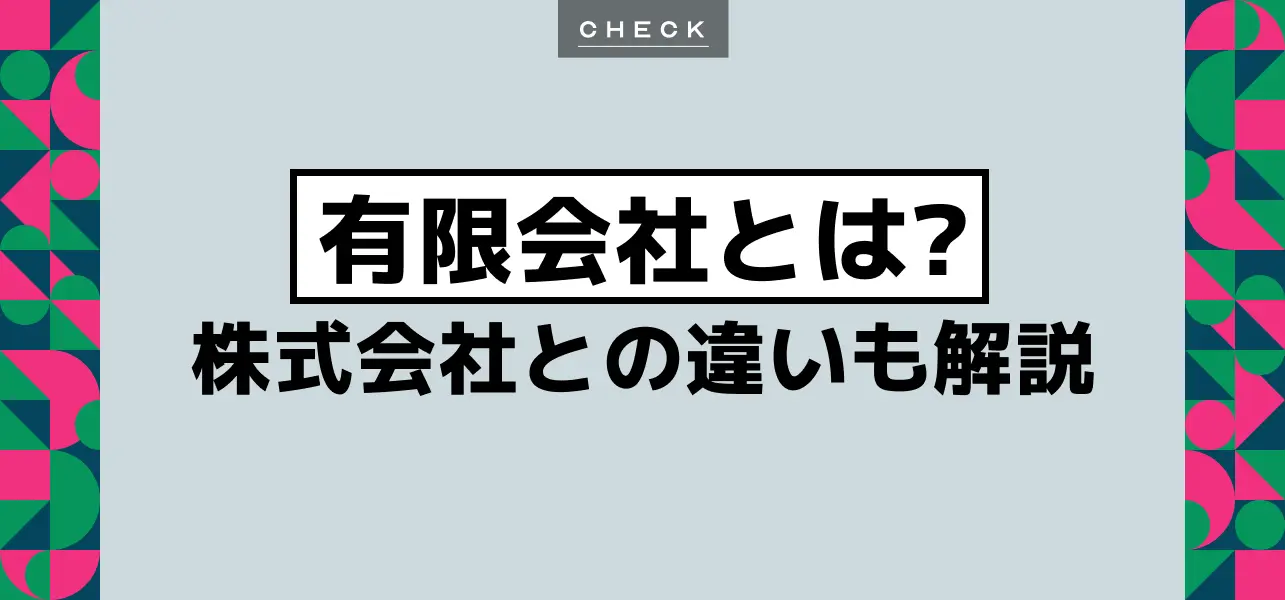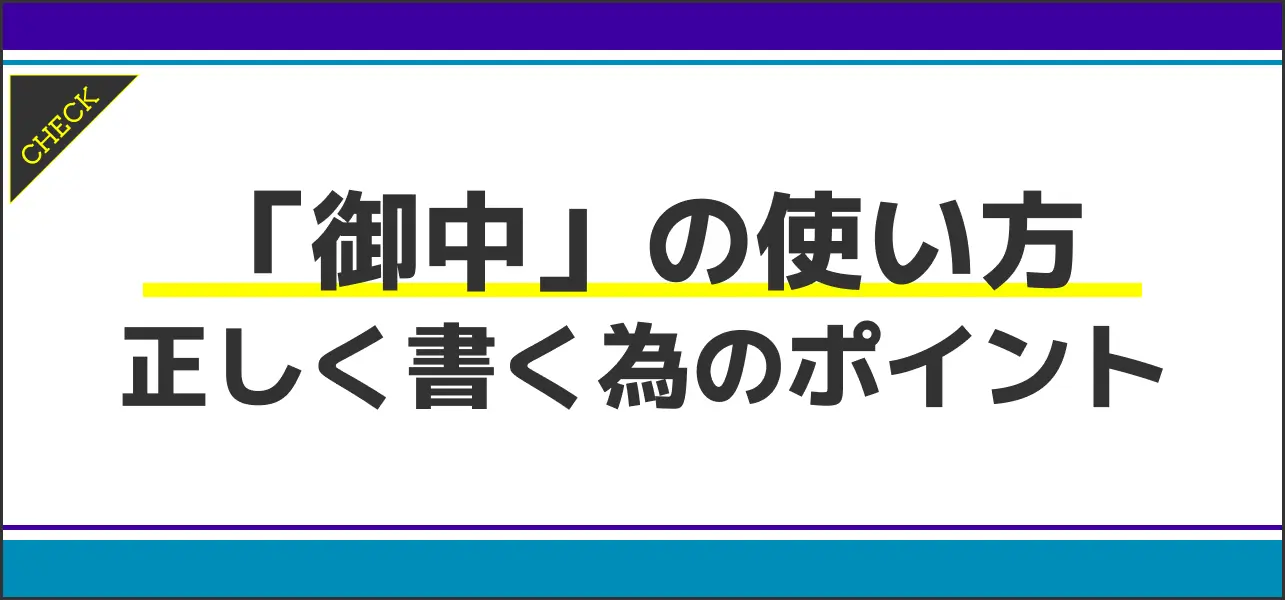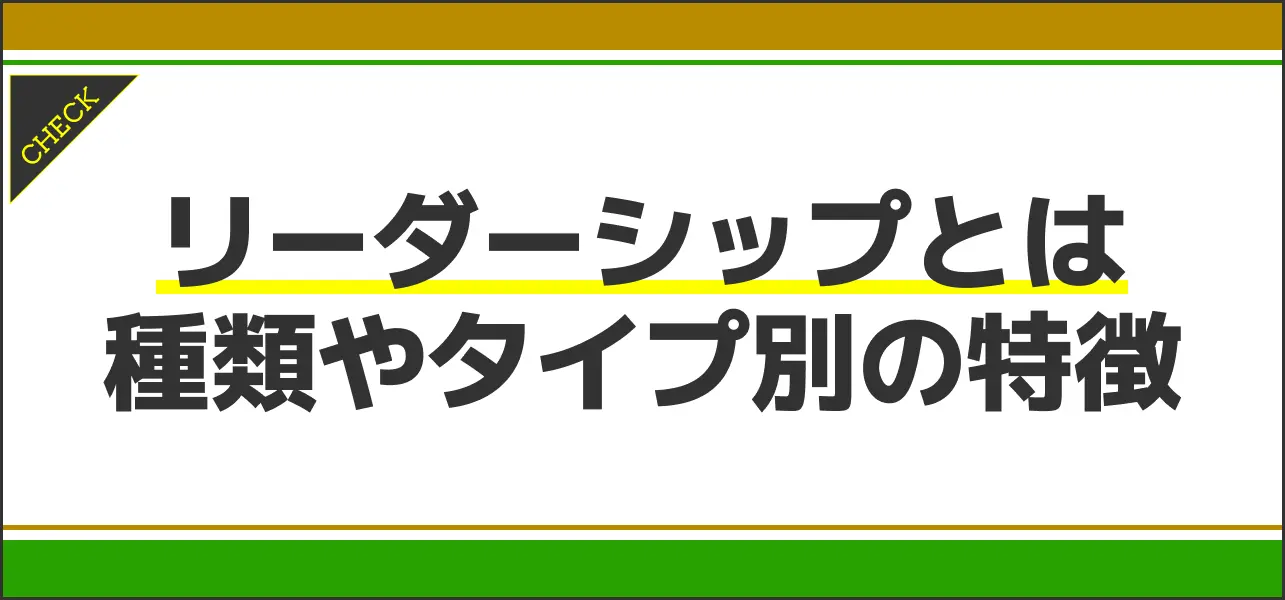フレックスタイム制度とは?具体例、メリット・デメリットまとめ
フレックスタイム制度とは?どのような仕組みか解説。フレックスタイム制度の目的、フレックスタイム制度に向いている業界・職種を紹介。フレックスタイム制で勤務するメリット・デメリットも解説します。
フレックスタイム制度とは?どのような仕組みか解説
フレックスタイム制度とは
フレックスタイムの概要について確認していきましょう。
参照:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省
仕事の「出勤時間」と「退勤時間」を自分で決められる制度
フレックスタイム制度は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、勤労者が毎日の始業・終業時刻、労働時間を⾃ら決めることのできる変形労働時間制の1つでのことです。
通常の労働時間制度の場合、会社の就業規則等により「出勤時間」や「退勤時間」が固定されているため勤労者側が働く時間を選ぶことができません。(例えば、8時30分から始業開始、17時30分に退社など)
一方、フレックスタイム制度を導入している会社であれば、労使間の十分な話し合いにより、あらかじめ働く時間の総量(総労働時間)を決めた上で「出勤時間」と「退勤時間」を自分で決めることができます。
労使協定での注意すべき点として、以下の6つがあります。
- 対象となる勤労者の範囲 (部署単位や個人単位など、労使間の話し合いにより設定可能)
- 標準となる1⽇の労働時間
- 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
- 清算期間
- フレキシブルタイム(任意)
- コアタイム(任意)
清算期間とは、フレックスタイム制度での勤労者が労働すべき時間を定める期間のことです。
これまで上限は1ヶ月でしたが、2019年4月の法改正によって上限が3ヶ月になりました。
また、注意点としては「コアタイムの時間が1⽇の労働時間とほぼ同程度になるような場合や、フレキシブルタイムの時間帯が極端に短い場合」などです。
労働者が始業・終業時刻を自由に決定するという趣旨に反する場合には、フレックスタイム制とはいえなくなるため注意が必要です。
フレックスタイム制度のコアタイムとは
「コアタイム」とは、勤労者が1日のうちでこの時間だけは必ず働かなければならない時間帯のことを指します。
コアタイムは任意であるため必ず設定する必要はありませんが、設ける場合は労使間で「開始時間帯・終了時刻を話し合い(協定)で定める」必要があり、その時間帯については協定で自由に決めることができます。
例えば下記のようなことも可能です。
- コアタイムを決めている日と、決めていない日がある。
- 日によってコアタイムの時間帯が異なる。
ただし、コアタイムを設定せずに出勤日も勤労者が自由に決められる場合でも、あらかじめ所定の休日は決めておく必要があります。
フレックスタイム制度のフレキシブルタイムとは
フレキシブルタイムとは「勤労者が自分で労働時間を決めることができる時間帯」のことで、その時間帯であれば勤務中でも中抜けすることも可能となります。
フレキシブルタイムもコアタイムと同様に任意であるため必ず設定する必要はありませんが、設ける場合は労使間で「開始時間帯・終了時刻を話し合い(協定)で定める」必要があります。
また、フレキシブルタイムの時間帯そのものも話し合いによって自由に決めることができます。
フレックスタイム制度の目的とは
フレックスタイム制度の主な目的は、勤労者に柔軟な働き方の選択肢を与え「ライフワークバランスをより充実させる」ことが目的です。
フレックスタイム制では、労働者が労使間の協定により「日々の勤務時間を自身で決められること」に大きなメリットがあります。
例えば、育児や介護をしながでも働きたい人にとってはとても効果的です。
特定の時間(日中など)に働くことが困難な場合でも、フレックスタイム制を取り入れることで早朝・夜間に働くことができ、よりワークライフバランスの向上を図ることが可能となります。
労使間の協定によって決めることが前提にあるので、一般的な時間が固定された労働よりも柔軟に働くことができます。
さらに政府は2019年4月の法改正によって、フレックスタイム制の上限を1ヶ月から3ヶ月に引き上げ、労働時間の調整を行うことのできる期間を延長しました。
フレックスタイム制度に向いている業界・職種とは
フレックスタイム制度に向いている職種は、「個人で仕事が完結しやすい職業」です。
例えば、デザイナーやフリーライター、プログラマー、設計士などが代表的といえるでしょう。
これらに共通していることは、対面でのコミュニケーションを必要とせず、特定の場所に縛られずに働けたり、個人の裁量で仕事を進めることができたりするところです。
このように「個人の裁量で仕事が完結する仕事」は、フレックスタイム制が非常に向いています。
なお、厚生労働省の「令和3年度就労条件総合調査」によると、フレックスタイム制度を導入している企業の割合は全体の6.5%に留まっています。
企業別では「1,000人以上」が28.7%、「300〜999人」が15.6%と、企業規模が大きいほどフレックスタイム制度を導入している割合が多い傾向にあります。
【具体例】フレックスタイム制度の導入で、働き方はどう変わる?
通常の働き方|決められた就業時間で必ず稼働しないといけない
一般的な働き方の多くは、会社によって決められた時間に出勤・退社をし、決められた就業時間は必ず稼働しなければなりません。
時間が固定されていることで生活リズムが一定になりやすくなる反面、日中の大部分を会社に縛られて過ごすことになるのでなかなか都合をつけにくいのも事実です。
中抜けができないため、勤務中に個人的な急用が発生したとしても対応しにくく、プライベートの時間も会社の勤務形態に合わせなければなりません。
それがフレックスタイム制だと労使間の協定で、勤務時間を自身で決められるのはもちろんのこと中抜けも可能となります。
さらに通勤時間をずらすことで満員電車に乗るストレスは激減し、育児をしている家庭であればゆっくりと子供たちを送迎した後に勤務することができるので、精神的なゆとりを持つことができます。
このように自分で生活と仕事のバランスを調整することができるので、通常の固定された勤務よりも柔軟に働くことができます。
フレックスタイム制度|コアタイムとフレキシブルタイムが混在
フレックスタイム制度は「コアタイム」と「フレキシブルタイム」の2つが混在しています。
繰り返しになりますが、コアタイムは「必ず勤務しなければならない時間」で、フレキシブルタイムは「いつ出退勤してもいい時間」です。
これを組み合わせることで、例えば下記のような働き方が可能となります。
<通常の勤務>
- 「定時での出勤ー休憩ー定時まで勤務」
- →勤務時間は拘束されているため、勤務中は必ず稼働しなければならない。
<フレックスタイム制>
- フレキシブルタイム(いつ出社してもOK)ーコアタイム(必ず勤務しなければならない時間)ー休憩ーコアタイム(必ず勤務しなければならない時間)ーフレキシブルタイム(いつ退社してもOK)
- →フレキシブルタイムの活用で、自分の好きな時間に出退勤ができる。
フレックスタイム制のコアタイムやフレキシブルタイムは、必ず決めなければいけないものではありません。
労使間の協定で決めることができれば、コアタイムを設定せずに勤労者が働く日も時間も決めることが可能であり、フレキシブルタイムの途中で中抜けすることも可能です。
スーパーフレックスタイム制|コアタイムとフレキシブルタイムの区別もなし
スーパーフレックス制度とは、「フレックス制度を基準にした、より自由度の高い働き方が可能な勤務形態」のことです。
会社で定められている月間総労働時間を達成することができれば、出退勤時間も自由に設定することが可能になります。
つまり「フレックスタイム制から、コアタイムが排除されたもの」であり、育児や介護などのライフイベントに対してより柔軟な働き方ができるようになった制度です。
例えば、下記のような働き方がスーパーフレックスタイム制の特徴とも言えます。
<特徴1>
社員が自分で1日の労働時間を決めることができるため、「今日は10時間働いて、明日は4時間だけにしよう」といったことが可能です。
<特徴2>
働く時間を自由に決めることができるため、休日も自由に設定できます。
月の前半に多く働いて後半に休日を設定したり、用事があれば半日を休みにし翌日にその時間分を補って働くことができます。
スーパーフレックス制度を利用するためには、最初に労使協定を結ぶ必要がありますが、協定を結ぶことができれば「総労働時間の範囲内ならどんな働き方でもできる」のが最大の特徴です。
スーパーフレックスタイム制はとても画期的な手法であり、国が推進している「働き方改革」の中でさらにライフワークバランスを重視したものと言えるでしょう。
フレックスタイム制で勤務するメリット
ワークライフバランスが取りやすい
フレックスタイム制は、ワークライフバランスを重視する人にとって大きなメリットがあります。
例えば、資格取得のために働きながら大学に通いたい場合です。
通常の時間が決まった勤務だと、学校のスケジュールにも合わせなければならないため無理が生じる可能性が高くなります。
しかしフレックスタイム制であれば、大学に通う日は仕事量を減らし、通わない日は多く働くことで学業と仕事のバランスを取ることができ、その両立がしやすくなります。
また、出退勤時間も自分で決めることができるので、満員電車に乗って会社に着く前に疲れたり、仕事で疲れた後の帰宅ラッシュも避けることができます。
その他にも、介護と仕事を両立させたい場合にもフレックスタイム制は有効です。
コアタイムの時間は福祉サービスを利用し、フレキシブルタイムの時間を調整することで介護と仕事とのバランスをうまく取ることもできます。
これまで介護のために仕事を辞めざるを得なかった人でも、フレックスタイム制がある会社であれば意欲を持って働くことができます。
このようにワークライフバランスをうまく取ることができれば、精神的にも余裕を持つことができQOLも格段に向上します。
心身ともに余裕があることで、仕事に対しても向上心や熱意を持って取り組むことができるようになり、ワークライフバランスを重視している人にとってフレックスタイム制は大きなメリットとなります。
効率化により生産性の向上が期待できる
仕事を行う上で業務の効率化や生産性の向上は非常に重要です。
フレックスタイム制を使うことで、月末や月初めなど多忙となりやすい時期は仕事量を多くし、逆に書き入れ時が過ぎれば早めに帰るなど業務状況に合った時間の使い方が可能です。
このように業務の効率化を図りながら残業時間を短縮することで、社員への負担も軽減することができます。
また、自分で働く時間を決めることができるため、個人に合った効率の良い時間の使い方でより業務の効率化や生産性の向上が期待できます。
例えば、朝早くから働いた方が作業が捗る人にとっては、時間を固定して働いてもらうよりもその人に合ったスタイルで働いてもらった方がはるかに生産性の向上が期待できます。
その他にも、フレックスタイム制を活用し毎日の通勤・帰宅ラッシュを避けることで、不要なストレスを軽減し従業員が業務に集中しやすい環境を整えることもできるでしょう。
優秀な人材の採用や定着の向上
フレックスタイム制を導入している企業では、それだけでも優秀な人材の採用や社員定着への大きなアドバンテージとなります。
これまでは通常の勤務に育児や介護が重なると、どんなに優秀な人材がいたとしても退職してしまうケースが多くありました。
しかし、フレックスタイム制を採用している会社であれば、育児や介護などのライフイベントが発生したとしても、フレキシブルタイムを十分に活用して働くことができます。
例えば、保育園への送迎時間や日中は介護をする人でもフレキシブルタイムを使うことで働くことが可能となります。
このようにフレックスタイム制を使い仕事が続けられることは、社員の定着率の向上につながります。
また、働きやすさのある会社では人材が多く集まる傾向にあるため、優秀な人材を採用できる確率も上がります。
優秀な人材を採用し定着率の向上を図ることは、会社にとっても社員にとっても大きなメリットになるといえるでしょう。
フレックスタイム制で勤務するデメリット
労働時間の管理が難しい
フレックスタイム制では1日の明確な勤務時間が決まっていないため、従業員個人単位で出勤時間と退勤時間をもとに総稼働時間を算出して残業代を計算しなければなりません。
手作業での集計はかなり大変になっています。従業員が多く、時間がかかりすぎるのであれば勤怠管理システムの導入を検討してみると良いでしょう。
生産性が低下する可能性がある
フレックスタイム制では、勤務時間に関して労働者にある程度裁量ができます。そのため、労働に対するモチベーションが自己管理にゆだねられるため、人によっては労働意欲が低下することに繋がり、生産性が低下する可能性があります。
また、社員が集まる時間が決まっているため、コミュニケーションがコアタイムに集中してしまう傾向にあり、状況によっては重要なコミュニケーションができるようになるまでに時間がかかってしまう可能性もあります。そのため、一つ一つの相談事にかかる時間が伸びてしまい生産性が低下することになります。
クライアントの信頼感低下の懸念がある
自由に勤務時間を制御できるようになると個人で差がありますが、多くが勤務時間が後ろ倒しになってしまいます。そのため、朝一で連絡してくるクライアントとのコミュニケーションが取りにくくなってしまいます。
1回だけなら大きな支障はないですが、何度も繰り返されると「この人は、朝は折り返しになって緊急性の高い相談ができない」とクライアントの信頼感が低下してしまうでしょう。クライアントがついている従業員に対してはクライアントと勤務時間を合わせるなどの制度を導入すると良いでしょう。
フレックスタイム制を導入する際の注意点は?法制度・法律を確認
フレックスタイム制を適用する旨を、就業規則に規定する必要がある
フレックスタイム制の導入には就業規則にフレックスタイム制を採用する旨を記載する必要があります。この時には業務の開始時間及び業務の終了時間を労働者の決定にゆだねる旨を記載するようにしましょう。
注意点としては開始時間及び終了時間の両方を労働者にゆだねることです。始業時間が決められて、終業時間を労働者にゆだねるケースはフレックスタイム制とはみなされません。
フレックスタイム制について、労使協定に記載すべき事柄がある
導入には労使協定を結ばなければなりません。労働組合がない場合には労働者の過半数を超える代表者と締結をしましょう。
フレックスタイム制の稼働時間の清算期間は2019年より最大3ヵ月まで採用できるようになりましたが、1ヵ月を超える場合には労働基準監督署に届け出を出さなければならない点は注意しましょう。また、労使協定では以下の5点を記載しなければなりません。
- 適用する労働者の範囲
- 給与および残業時間の清算期間と起算日
- 清算期間での総稼働時間(例:30日では171時間25分)
- 1日あたりの標準となる労働時間
- コアタイムの開始時間・終了時間、フレキシブルタイムの適応範囲時間(任意)
清算期間の範囲内で、法定労働時間を計算しないといけない
フレックスタイム制を導入した場合には法定労働時間である1日8時間、1週間40時間の規則はなくなります。ただし、清算期間内で平均して1日8時間であることは求められます。
例えば、清算期間を1〜3月とすると1月は平均約6時間、2月、3月は平均して9時間労働するといったことが可能となります。
その一方で、1月は平均約8時間、2月、3月は平均約9時間、4月を平均約6時間では2〜4月の平均は8時間を満たしていますが、清算期間である1~3月では平均8時間を超えてしまい、その分は残業扱いとなるので注意をしましょう。
フレックスタイム制度でよくある質問
そもそも、フレックスという言葉の意味とは?
フレックス(flex)という言葉はもともと「曲げる」という意味でしたが、その意味が転じて、柔軟に対応する、臨機応変に対応すると解釈されています。英語の「flexible」はそのように解釈された形容詞になります。
また、英語でもフレックスタイム制は「flextime」とほぼ同じように表現されますが、「system」はつけません。
フレックスタイム制度を導入すると、労働時間が少なくなる?
フレックスタイム制度を導入しても、労働時間が短くなるわけではありません。
あくまで労働する時間帯を労働者が決定できる制度と考えましょう。しかし、1日6時間程度しか作業がないのに8時間職場にいなければならないというようなケースでは労働者の裁量によっては6時間で帰宅することで労働時間を少なくすることができます。
ただし、労働者の裁量にゆだねられるため、モチベーションが低く6時間の作業が8時間になってしまうようなケースもあり、必ずしも労働時間が少なくなるわけではありません。
フレックスタイム制度において、残業代・残業時間の扱いは?
残業はなくなりませんが、計算方法が変わることになります。通常の8時間労働制では1日8時間以上労働した場合に残業が発生しますが、フレックスタイム制では清算期間内にまとめて残業時間を計算することになります。
清算期間内で決められた労働時間を超えた分が残業時間として計上されることになります。例えば、1ヵ月30日の清算期間で1ヵ月200時間働いた場合には、28時間35分の残業となります。また、清算期間が1ヵ月を超える場合には週50時間を超える労働は残業扱いとなる点も注意しましょう。
フレックスタイム制度において、休憩時間の扱いは?
フレックスタイム制でも休憩は取らなければなりません。法律で準ずる休憩時間を確保させるようにしましょう。
1日6時間以上、8時間未満である場合には45分の休憩時間を、1日8時間以上である場合には60分の休憩時間をとるようにしましょう。
フレックスタイム制度において、有給休暇はどう扱われる?
有給休暇を取得した場合には、就業規則またはそれに準ずるものによって定められている1日の標準労働時間に該当する時間が、有給休暇の消費時間として扱われます。
例えば、標準労働時間を1日あたり8時間で定めている場合には、有給休暇を利用すると8時間分の労働時間として扱われます。
「フレックスタイム制」と「裁量労働制」で違いはある?
フレックスタイム制と裁量労働制の違いは大きく3つあります。
- 裁量労働制は厚生労働省に定められた専門職(例えば、弁護士などの士業など)にしか適用できませんが、フレックスタイム制では対象業種の制限はありません。
- 報酬の計上方法が両者で異なります。裁量労働制ではみなし残業制となるので、いくら働いても給料は変わることはありません。フレックスタイム制の場合では、指定期間内で定められた労働時間を超えた場合には支払われます。
- フレックスタイム制は就業規則に明記して労使協定を締結すれば導入可能ですが、裁量労働制では労使協定を締結したうえで必ず労働基準監督署に届けなければなりません。
「フレックスタイム制」と「時差出勤」で違いはある?
時差出勤は出勤時間を調整できる制度であり、1日必ず法定労働時間分は勤務しないといけません。
また法定労働時間を超えた場合には1日単位で残業扱いになります。一方、フレックスタイム制ではコアタイムを除いては1日の労働時間を労働者の裁量により変動させることができます。
フレックス勤務の出勤時間は?1日何時間働けばいい?
会社によって定められたコアタイムのみ確実に働いていれば、いつ出勤しても、いつ退勤しても問題ありません。また、働く時間も労働者によって自由に調整することができます。ただし、以下2点には留意しましょう。
- 深夜時間(午後10時〜午前5時)に働いた場合には割増賃金が発生します。
- 36協定を結んでいる場合には1日16時間を超過する労働はできません。
フレックスタイム制は違法?
フレックスタイム制は、違法ではありません。しかし、下記3つの手順を踏まずにフレックスタイム制を導入してしまうと違法となります。
- 就業規則またはそれに準ずるものに明記する
- 労使協定を締結する
- 清算期間が1ヵ月を超える場合には労働基準監督署に届け出を行う
フレックスタイム制における「時間外労働」とは?
清算期間を定めて指定した期間にまとめて時間外労働を計算します。
指定した期間内で決められた総労働時間を超えた分が時間外労働として計上されます。清算期間が1ヵ月を超える場合や週50時間を超過した場合にも、労働時間は時間外労働扱いになるので注意しましょう。
また、深夜労働や休日労働をした場合には法律で定められる割増料金分を支払う必要があります。
フレックスタイム制を適用する際、労使協定への記載は不要?
労使協定への記載は必ず必要です。労使協定へ以下の5点を記載して、労働組合、労働組合がない場合には労働者の半数を超えるものの代表者と合意しなければなりません。
- 適用する労働者の範囲
- 給与および残業時間の清算期間と起算日
- 清算期間での総稼働時間(例:30日では171時間25分)
- 1日あたりの標準となる労働時間
- コアタイムの開始時間・終了時間、フレキシブルタイムの適応範囲時間(任意)
まとめ
フレックスの意味は、以下のとおりです。
- フレックスタイム制度とは、仕事の「出勤時間」と「退勤時間」を自分で決められる制度
- 勤労者に柔軟な働き方の選択肢を与え「ライフワークバランスをより充実させる」ことがフレックス制度の目的
デザイナーやフリーライター、プログラマー、設計士などがフレックスに向いている職業です。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。