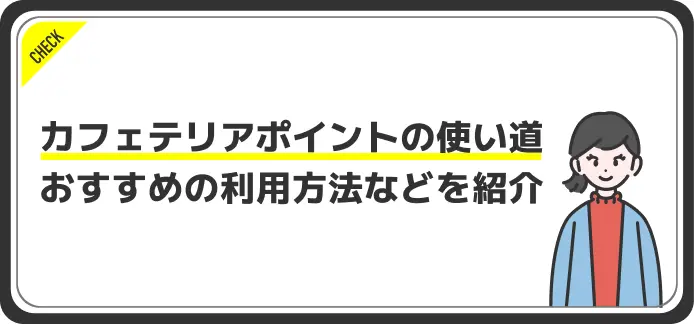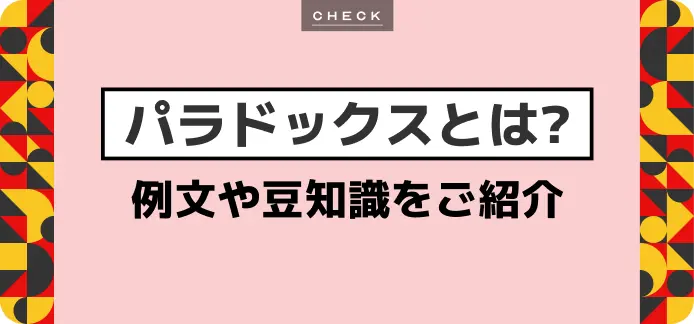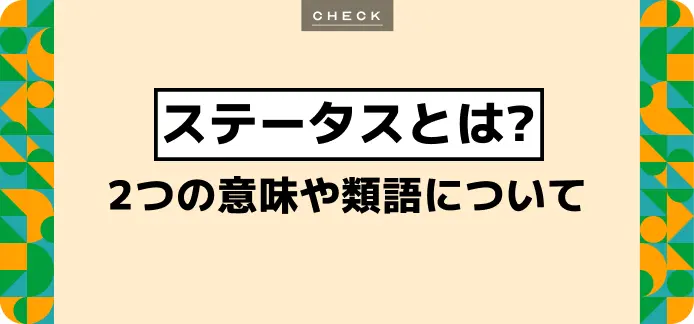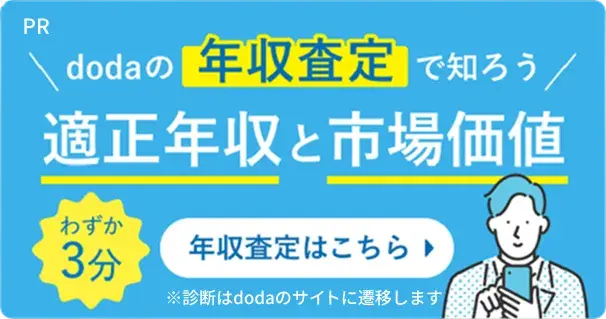【ディーセントワークの意味とは】働き方改革について解説
ここでは、ディーセントワークについて解説しています。ディーセントワークとは、適切なワークライフバランスや家庭と仕事を両立できる働き方のことを意味します。また、日本でのディーセントワークの取り組みなどについても紹介しているので、参考にしてみて下さい。
ディーセントワークについて
ディーセントワークとは?
ディーセントは「社会的にちゃんとした、まともな」という意味を持ち、「decent」と綴ります。ここから、適切なワークライフバランスや、
家庭と仕事を両立できる働き方を意味する「ディーセントワーク」が生まれたのです。元々は1999年に国際労働機関が掲げた概念ですが、
その後、日本では「働きがいのある人間らしい仕事」と訳されて輸入されました。
ディーセントワークが誕生した背景は?
ディーセントワークの誕生には、劣悪な労働環境や所得の格差などが起因しているといわれています。
他にも、男女間の待遇格差や障害を理由にした差別など、指摘される問題は枚挙にいとまがありません。世界中の労働環境からこうした問題を解決するため、ディーセントワークが提唱されたのです。
ディーセントワークとワークバランスの関係について
ディーセントワークにおいては、従業員の権利が保障されていること、収入が十分であること、生産的な仕事であることが重要であるとされています。
「人間らしく働ける生産的な仕事」とも言えるでしょう。中でも、長時間労働の廃止に向けた企業取り組みは従業員のライフワークバランスにおける重要な因子であり、企業に対する世間や株主からのイメージにも影響するのです。
日本のディーセントワークの取り組みについて

日本におけるディーセントワークの捉え方は?
日本の企業では、ディーセントワークは以下のように解釈されています。
・労働の機会が与えられ、最低限必要な収入が支給されること
・労働三権をはじめとした労働者の権利が尊重されること
・家庭と仕事が両立でき、雇用保険や医療・年金制度が整備されていること
・性別や年齢、障害などによる不当な扱いをされないこと
企業によって解釈の違いや実際の実施している内容の差はあるでしょうが、上記のように働く上で大前提となる4項目が大元になっているのです。
ディーセントワークの認知度について
ディーセントワークは働く上で基本的な最低限のことを提唱していますが、世間での認知度はあまり高くないようです。
ある調査結果では、「ディーセントワークという言葉を聞いたことがあり、内容も知っていた」という人は2%ほどしかいませんでした。
「内容どころか、聞いたことすらない」という人たちが調査対象のおよそ88%を占めたそうですので、これから経営陣、従業員ともにいかに浸透させていくかが課題と言えそうです。
さらに、「働きがいのある人間らしい仕事」から連想される仕事内容を調査した結果、以下のような結果となったそうです。
1位 人の役に立てる仕事
2位 好きなことややりたいことができる仕事
2位 自分の能力を生かせる仕事
3位 きちんと能力を評価され、それに応じた報酬を貰える仕事
4位 人から感謝される仕事
この結果からも、仕事におけるやりがいというのは誰かの役に立つことや、個々の能力を生かして働け、さらにそれを評価されることと言えそうです。
日本におけるディーセントワークの取り組みは?
2012年、労働経済白書により「分厚い中間層の復活に向けては、ディーセント・ワークの実現が不可欠」と指摘がありました。
加えて、野田内閣による経済成長戦略である「日本再生戦略」においても、ディーセントワークについて触れられています。
日本では、厚生労働省を中心としてまずはディーセントワークという概念の早急な普及が求められているでしょう。
ディーセントワークと働き方改革について

ディーセントワークと時間について
ディーセントワークの実現において、労働時間の短縮は避けては通れない道です。
過度な時間外労働が原因で従業員が過労死したり、心身の病気を患ったりすることもあるのです。また、時間外労働をしているのにもかかわらず残業代が出ないというケースもあるようです。
過度な労働時間と時間外労働に対する報酬の未払いがまずは解決すべき問題と言えるでしょう。
ディーセントワークと家庭環境について
ディーセントワークの主な目的のひとつとして、家庭と仕事の両立も含まれます。
これは女性に限った話ではなく、今の社会では男性にも当てはまるでしょう。雇用や労働において男女の差はあってはならず、性別に関係なく活躍できる社会を目指すべきです。
その一方で、男女ともに家事・育児に参加できるよう企業側は労働時間の配慮を行うべきとも言えます。
ディーセントワークと人権について
労働時間や報酬、ワークライフバランスをより良いものにしていく根底には、労働者の権利の尊重があります。
労働三権をはじめとした労働者の権利が守られることは、安心して働ける労働環境作りに必要不可欠なのです。加えて、保険関係の整備も重要でしょう。これには、雇用保険や医療保険、年金制度などが含まれます。
障害のある人がたのディーセントワークについて

障害のある人がたのディーセントワークとは?
日本に限らず、世界中で身体的もしくは精神的な障害から労働を諦めざるをえない人たちがいます。ディーセントワークはそういった人がたも活躍できる社会も目指しているのです。
具体的には、「社会から認められる役割があること」「『働けない』ことを『障害の問題』にしないこと」などがディーセントワークの掲げる理念となります。
障害のある人がたのディーセントワークの実践について
例えば知的障害者に向けたディーセントワークの実践では、「B型事業所」などが当てはまるでしょう。
これは知的障害者を雇用し、仕事を与えて報酬も支払うというものですが、働くことの喜びややりがい、労働して報酬を貰う喜びなどを知的障害者に学習させることができます。
ここでは一人ひとりの多様性が認められ、尊重されるのです。さらに、労働を通してキャリアアップの機会を得たり、社会に参加したりすることができます。
障害のある人がたのディーセントワークの課題は?
障害のある人がたのニーズに応じた仕事を提供することがディーセントワークの一番の課題と言えるでしょう。
例えば、障害の度合いに応じて労働時間や労働日数を調整し、「一日に4時間だけ」とか、「週に3日だけ」といった具合です。
他にも、在宅で出来る仕事を割り振ったり、障害のある人がたをグループとして仕事を任せたりといったように、労働の形態も臨機応変に変化させることが重要でしょう。
ディーセントワークの企業事例などについて

ディーセントワークの企業事例について
日立製作所では、基準をグローバルに置き、透明性の高い人事評価を行っています。
さらに、安心かつ安全な労働環境、労働時間の短縮などを通したワークライフバランスの向上も推進しているのです。
オリンパスでは、「多様性と機会均等」という標語の元、ディーセントワークを推進しています。これにより性別や年齢に関係なく雇用の機会を得、能力を発揮できる環境作りを目指しているのです。
企業でのディーセントワークの推進ポイントについて
ディーセントワークは個人個人の取り組みで実現できるものではありません。
国や地方自治体、企業の努力により実現されるのです。さらに、ディーセントワークは労働者だけでなく、企業にもより良い利益をもたらすものです。
ディーセントワークへの取り組みを徹底することで社会からの企業イメージは向上するでしょう。さらに、従業員が良い環境で働くことで生産性の向上が期待でき、結果的に企業全体の業績アップにつながるのです。
まとめ
今回はディーセントワークについて解説いたしました。
いかがでしたでしょうか。まだまだ認知度は低い概念ですが、よりよい社会を実現するために欠かせないといえるでしょう。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。