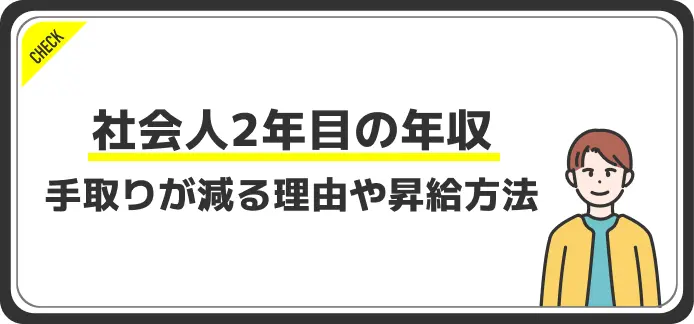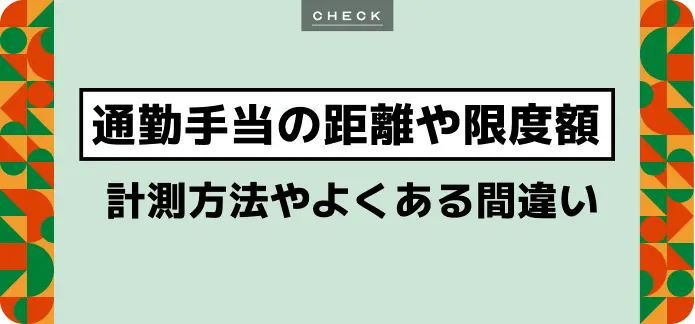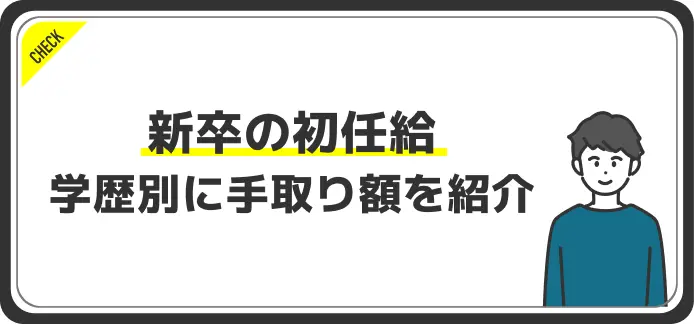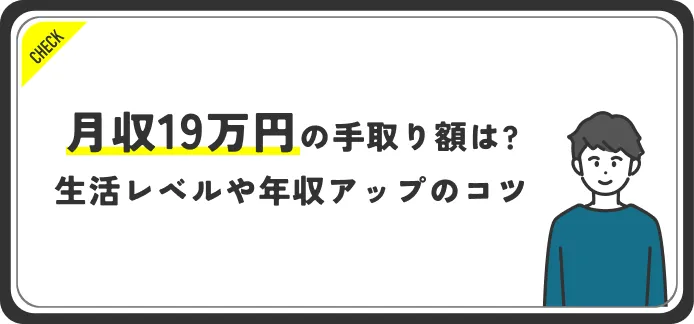【源泉徴収はいくらから】対象になる?103万円の壁についてもご紹介
皆さん、源泉徴収はいくらから対象になるかご存知でしょうか。この記事では、源泉徴収の対象や、よく耳にする103万円の壁について詳しくご紹介致します。また、副業をしている場合の源泉徴収や、確定申告を行うと還付金があるケースなども解説致しますので是非参考にしてみてください。
給与と源泉徴収の関係とは
給与と源泉徴収の関係を紹介します。
給与の源泉徴収計算は、国税庁が定める「給与所得の源泉徴収税額表(月額表および日額表)」に基づき、給与所得・扶養親族の人数に応じた源泉徴収税額を算出します。
「給与所得の源泉徴収税額表(月額表および日額表)」には「甲」欄と「乙」欄があります。
「乙」欄は一般的に1事業所から給与が支給されているケースです。「乙」欄は複数の事業所から給与が支給されているケースです。
源泉徴収額はその月の社会保険料を控除した給与所得を「給与所得の源泉徴収税額表(月額表および日額表)」の「甲」「乙」欄に該当する税額を参照して、源泉徴収額を求めます。
給与から源泉徴収される税金の種類
給与から源泉徴収される税金の種類を紹介します。
給与明細表をみると「所得税」「住民税」の2種の税金があることがわかります。
「所得税」は国税で「住民税」は地方税です。「所得税」は国税ですので税務署が管轄になります。
「住民税」は地方税で、都道府県税が4%・市区町村税が6%の構成になっており地方自治体(市区町村)が管轄になります。
年間の正確な課税対象額は源泉徴収票に記載される
国税である「所得税」と地方税である「住民税」は給与から天引きされて、事業所が税金を納付する源泉徴収の形態をとっています。
源泉徴収は、概算の税額を差し引いて納める方法です。
1年間の収入が決まった時点で正式な税金が再計算して過不足を調整します。
この調整する行為を年末調整と言い、12月分の給与で清算される仕組みになっています。
地方税である「住民税」前年の年収額によって税額がきまります。
住民税は所得税と異なり翌年度に課税されます。そのため新卒新入社員は入社して1年間は住民税の支払いがありません。
住民税の課税額は、その年の所得税が確定したあとに住民税額が算出されます。
この算出された住民税額は翌年の6月から適用される仕組みになっています。
住民税は翌年の6月から給与天引きされることになります。
パートやアルバイトでも源泉徴収の対象になる場合がある

パートタイマー従業員・アルバイト従業員も源泉徴収の対象になる場合があります。
正規雇用従業員・非正規雇用従業員・アルバイト従業員・パートタイマー従業員全員が「給与所得者」です。
給与支給者(事業所)は給与を支給するときに、所得税を天引きして納税する(源泉徴収)義務が法律で定められています。
早朝から深夜までアルバイトに精を出した結果でも、働いた時間×時給額>給与振り込み額のように支給された給与が少ないケースがあるようです。
給与明細書には源泉所得税額欄に金額があり、その分が減算させています。
減算分は所得税として事業所経由で納税されています。
一定基準の月額報酬・年収額を超えると課税対象になり、源泉徴収(給与天引きして納税)するケースがあるようです。
月間の給与額が一定以上になると源泉徴収が行われる
アルバイト従業員の月額給与額が一定以上になると源泉徴収が行われるようです。
アルバイト従業員は月額88,000以上の収入があるときは、国税庁のホームページに掲載されている「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」で源泉徴収する所得税額が天引きされます。
給与天引きを源泉徴収と言います。
よく耳にする103万円の壁とは何か
よく耳にする103万円の壁とは何か?紹介します。
103万円の壁とは、パートタイマー従業員・アルバイト従業員の年収が103万円以内のときは、税金面で優遇されます。
税金面の優遇等は非課税であることです。
パートタイマー従業員・アルバイト従業員の年間の給与合計が103万円以下のときは、所得税が課税されません。
また、学生の場合は、103万円ではなく130万円以下が非課税になります。
非課税枠外に至ったときは、確定申告が必要になります。
交付された源泉徴収票を持参して税務署へ出向き確定申告書を作成しましょう。
最近は簡単な操作で確定申告書の作成が可能になっています。確定申告期間は翌年の2月16日~3月15日です。
関連記事
▶︎業績によって賞与は連動する?メリット・デメリットをご紹介
副業をしている場合の源泉徴収はどうなるのか

副業をしている場合の源泉徴収はどうなるのでしょうか?
アルバイト・副業をしていると「源泉徴収」をするか否かを選択することになるようです。
源泉徴収は、所得税の給与天引きですので、源泉徴収を選択すると本来得る予定の収入から源泉徴収分として収入の数%が差し引かれます。
雇用形態を問わずに給与計算パッケージアプリケーションを導入している事業所では、無条件に源泉徴収されるようです。
副業の収入が給与の場合
副業の収入が給与のケースを紹介します。
本業の収入が給与のときは源泉徴収されます。副業の収入が給与のケースで、月額88,000円を超えると所得税課税対象になるので、源泉徴収されることがあるようです。
源泉徴収は本業の所得税率と副業の所得税率が異なります。本業・副業ともに国税庁が定める「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を基にして算定します。
本業は基にする税額表の「甲欄」、副業は基にする税額表「乙欄」から税率を求めて所得税計算します。
2019年4月に施行された「働き方改革法」で副業を容認する企業が出始めていますが、日本古来の商慣習では「副業」は容認しない企業が多く残っているようです。
本業・副業の企業に所得税計算するための適用列を明確に指示できれば良いですが、個人の都合に合わせた対応をしてくれるか課題が残るようです。
副業の収入が給与以外の場合
副業の収入が給与以外のときの所得の計算方法を紹介します。
給与以外の収入は事業所得・雑所得が該当します。事業所得は週末起業・物販など繰り返し継続して事業を行うケースを示します。
雑所得は前記以外に単発でイベントなどを開催して収益を上げるケースを示します。
事業所得・雑所得と給与所得による所得税計算と比較すると複雑ではないようです。
1年間の収入から1年間の経費・費用を差し引いた金額が所得金額になります。
例えば、1年間の収入が300万円とします。費用・経費が100万円とすると差益が200万円になります。
この200万円が所得金額なります。事業所得・雑所得は源泉徴収が適用されないので、確定申告をして納税します。
源泉徴収の対象にならない所得はあるのか
源泉徴収の対象にならない所得を紹介します。
① 税理士や司法書士等に支払う金額のうち、本来は支払者(業務を依頼した方)が払う印紙代の立替分は、用途が明記されていると源泉徴収の対象外です。
② 旅費・宿泊費は、支払者が直接ホテルや旅行会社へ支払いを行い、料金が通常の範囲内であれば報酬・料金等に含めなくても構いません。
③ 懸賞小説等の入選者への賞金の支払い・新聞・雑誌の投稿の謝礼金は一人1回5万円以下であれば源泉徴収外です。
④ 試験問題の出題料・答案の採点料は、源泉徴収外です。
⑤ 広告宣伝が目的の賞金額が50万円以下なら源泉徴収外です。
源泉徴収で納めすぎた税金は確定申告で還付される

源泉徴収で納めすぎた税金は確定申告で還付されます。
源泉徴収は事業所が一定の概算額で所得税額を計算します。
そのため所得税を過払いしているケースがあるようです。
その過不足の調整をする行為が年末調整・確定申告になります。
確定申告を行うと還付金があるケースとは
還付金とは、所得税の過払いにより納税者へ返還される税額を指します。
源泉徴収した所得税額は予定納税のため、確定した税額ではありません。
その税額を再計算したときに納税した所得税額よりも多いときに、確定申告で過払いの所得税還付を受けることができます。
過払い所得税還付を行う申告のことを還付申告と称します。
還付申告は給与所得者・事業所得・雑所得の方が対象になるようです。
確定申告で勤務先に副業がばれる可能性はあるのか
確定申告をしたことで勤務先に副業していることが知られてしまう可能性があるのでしょうか?
回答は、副業が知られないように操作することは不可能なようです。
住民税の納税方法を普通徴収(納税者が支払い行為をする納付形態)にするに副業を知らないようにするための具体的な対策があるようです。
しかし現状では、あらゆる対策を施しても、副業を100%隠し通す方法はありません。
特にマイナンバー制度導入により、所得税や住民税に関する通知が会社に届く可能性を「0」にすることはできないようです。
まとめ
源泉徴収は月額収入が88,000円以上、または年収103万円を超えると所得税課税対象になります。
年収103万円に至るケースは年末までわかりません。
収入が月額88,000円超えのケースは給与支給時に源泉徴収されるケースがあるようです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。