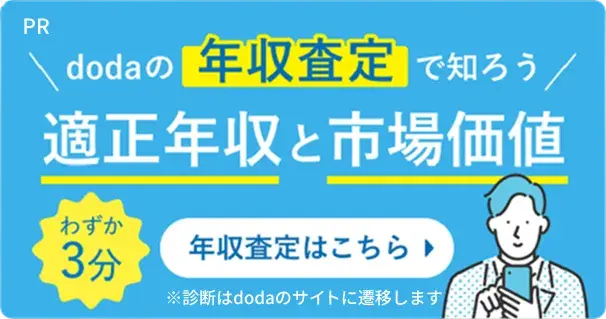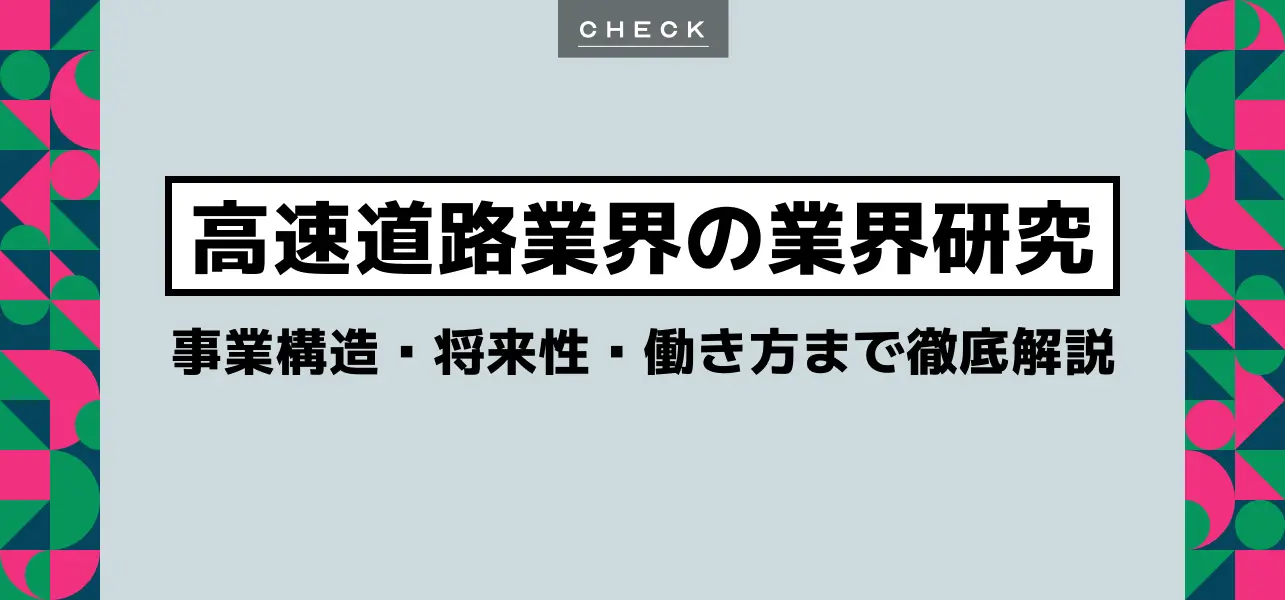
高速道路業界の業界研究|就活に役立つ事業構造・将来性・働き方など徹底解説します
高速道路業界は半民半官で運営されており、安定性は公務員と同等かそれ以上です。待遇や 給与水準も高く、公務員志望の学生の併願先として人気です。一方で知名度はそこまで高くない ので、安定性・高い給与水準を求める学生にとっては最高の選択肢です。高速道路業界の内定を獲得するために業界の歴史や政府との関係、ビジネスモデルなどを正し く理解し、その上で自分の強みや頑張ったことを、入社後にどう活かせるかを具体的にイメージし 面接官に伝えることが重要です。この記事では高速道路について各社の有価証券報告書や政府のレポートなどを参考にして、徹 底した業界研究を行っています。ぜひ最後まで読んで、業界研究を完成させてください。
高速道路業界とは
この章では高速道路業界の
- 業界構造
- 将来性
- 業界分類
- 最新トレンドについて
解説していきます。
業界構造(Tier1・2や商流やメインビジネス(稼ぎ方)など)
高速道路運営収入
高速道路の最も基本的な収入源は高速道路の運営収入です。
高速道路には料金所が設置され ており、利用者(ドライバー)から料金が徴収されます。
しかし、高速道路の料金は高速道路の管 理会社が自由に決定できるものではありません。
料金設定については道路整備特別措置法第 23条に以下のように記載されています。
- 高速道路の維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、料金の徴収 期間内に償うものであること
- 道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、料金 の徴収期間内に償うものであること
- 公正妥当なものであること
- 路の通行又は利用により通常受ける利益の限度を超えないものであること
このように高速道路の通行料金は高速道路の通行料金は、高速道路の新設、改築、維持、修繕 その他の管理に要する費用を、料金収入で償えるように、かつ物価水準や他の公共交通機関の運賃などと比べて社会的に公正妥当と認められる水準に設定されています。
このように高速道路は極めて公共性の高い施設であるため、一般消費財のように需要と供給の関係だけで決まるものではありません。
道路整備特別措置法第23条の規定にしたがって、国土交通大臣の許可を受けて通行料金を設定することになっています。
それでは通行料金はどのように設定されているのでしょうか?
一般的には区間ごとの走行距離によって決められると考えられがちですが、実際はそうではありません。
高速道路における普通乗用車の料金の計算は以下のようになっています。
(24.6円/km×利用距離+150円)×1.1
上記の計算式で算出した数字を四捨五入により10円単位の端数処理をします。
このように算出される通行料金ですが、実際には高速道路管理会社にとって十分な収入源にはなっていません。
運営会社は利用者から幅広く徴収した利用料金を原資として、日常的な点検や清掃、補修、事故復旧作業、計画的な補修工事に充当しています。
したがって、これらの経費を差し引くと手元に残るキャッシュはそこまで多くはないと言われています。
高速道路会社も民営化されていますが、極めて公共性の高い事業ですので、利益を追求するというよりは国民が快適かつ安心・安全に高速道路を利用できることに重点を置いています。
サービスエリア・パーキングエリア
高速道路運営会社にとって大きな収入源となっているのがサービスエリア事業及びパーキング エリア事業です。
これらはそれぞれ、SA・PAとも呼ばれ、「道ナカ」事業と言われています。
高速道路は一般道路のように休憩することができないため、長時間運転しているとドライバーに疲れがたまります。
運転で疲労したドライバーに疲れや緊張をとって休憩する施設が必要だということで設置されたのがサービスエリア及びパーキングエリアです。
サービスエリアは基本的に50km、 パーキングエリアは15km間隔に設置されています。
サービスエリア及びパーキングエリアには 駐車場やトイレなど最低限の施設のほかに比較的長時間滞在できるようにレストランや売店、ガ ソリンスタンドなどが設置されています。
また、サービスエリアによって設置されている施設は異なりますが、コインシャワー、コインランドリー、入浴施設、ホテル、コンビニ、ドラッグストアなどを展開しているサービスエリアもあります。
高速道路の管理会社はこれらの施設を直接運営しているわけではなく、出店者からテナント料金を徴収しています。
一般的にサービスエリア、パーキングエリアへの出店料は高額であると言わ れ、売上高の20%が目安となります。
一般的な商業施設では20%という料金設定はかなり高額ですが、サービスエリアを利用する利用客を独占的に集客できるという利点があり、テナント出店の希望者も多くいます。
高いテナント料を賄うため、また利用者を独占できるためサービスエリア やパーキングエリアの施設の料金は通常よりも高めに設定されています。
関連事業
高速道路の利用料金やサービスエリア事業がメインな事業ですが、高速道路に関連した事業も行っています。
例えば、高速道路が発行するクレジットカード事業、地域の良質な観光資源やインフラを活かした旅行商品を販売する旅行事業、産地直送の名品などを取り扱うECの運営、そのほか駐車場、駐輪場、高架下駐車場、ホテル、トラックターミナルなど、経営資源を活用した多様な事業を展開しています。
市場規模・将来性(シンクタンクのレポートなど)
市場規模
高速道路業界の主要企業6社(東日本高速道路、西日本高速道路、中日本高速道路、首都高速 道路、阪神高速道路、東京湾横断道路)の有価証券報告書によれば、これら6社の売上高の合計は2020年時点で3兆5,605億円となっています。
東日本高速道路によれば、平成29年度の1日当たりの高速道路別の収入は以下のようになっています。
| 道央自動車道 | 116,404 | 八戸自動車道 | 11,288 | 日本海東北自動車道 | 13,339 |
| 札樽自動車道 | 21,851 | 釜石自動車道 | 974 | 東北中央自動車道 | 2,226 |
| 道東自動車道 | 28,643 | 秋田自動車道 | 22,176 | 関越自動車道 | 254,692 |
| 東北自動車道 | 507,080 | 山形自動車道 | 21,880 | 上信越自動車道 | 103,742 |
| 青森自動車道 | 1,498 | 磐越自動車道 | 44,570 | 常磐自動車道 | 224,021 |
| 館山自動車道 | 36,080 | 東関東自動車道 | 126,218 | 新空港自動車道 | 1,471 |
| 東京外環自動車 道 | 70,465 | 北関東自動車道 | 78,718 | 合計 1,800,981 | |
| 北陸自動車道 | 89,366 | 長野自動車道 | 24,279 |
また、日本の高速道路管理会社の事業領域ではありませんが、Mckinsey & Coによれば、世界のインフラ投資市場は、2013年から2030年までの間で累積 で約57兆ドルの規模に達すると予測しています。
特に大きいのが道路系、電力系、水道系などと なっていて、2011年までの累積の実績でみると、中国が最も多額のインフラ投資を行ってきており、今後も同国をはじめとする新興国におけるインフラ投資が加速すると予想されます。
将来性
高速道路の主要な収入源は高速道路の利用料金ですので、自動車産業の影響を強く受けます。
これまで高速道路は自動車保有者の増加とともに発展を続けてきました。
一般財団法人自動車検査登録情報協会によれば、乗用車に限定した自動車保有台数の推移は以下のとおりです。
| 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 |
| 727万台 | 2,275万台 | 3,293万台 | 5,122万台 | 5,790万台 |
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 6,083万台 | 6,125万台 | 6,158万台 | 6,177万台 | 6,180万台 |
このように自動車の保有台数はこれまで順調に伸びてきており、高速道路はその恩恵を十分に享受してきました。
しかし、今後は一転して縮小が見込まれており、東京都主税局によれば、乗用車の保有台数は2020 年 6,180万台から 2050年 5,554 万台と減少(▲10.6%)、新車販売台数は 2020年 383万台から2050年 302 万台と減少(▲21.1%)すると予測されています。
高速道路の需要は自動車の台数に比例するので、今後は利用料金収入源の減少が予想されます。
また、「若者のクルマ離れ」と言われるように首都圏など公共交通機関が発達しているエリアでは、駐車場など維持費が高いなどの理由で、若い世代でクルマを所有している人は少なくなっ ています。
さらに少子高齢化社会によって単身・夫婦のみ世帯が増加し、特に親と同居している独身者層の新車購入率の極端な低下が目立っています。
自動車産業が衰退する可能性がある 中で高速道路の事業としての将来性は明るいとは言えないかもしれません。
ただし、高速道路の管理会社の事業環境が悪化するからといって高速道路業界が完全に悲観的であるわけではありません。
高速道路は国民生活に欠かせない存在です。
需要は減少してい くかもしれませんが、自動車を使って移動する人がいる限り、高速道路がなくなることはありません。
また、高速道路の運営は政府の事業の一環として行われています。
政府も高速道路の運営は政策の一つに位置づけており、民営化されているといっても政府が株主となっています。
そのため、事業自体は安定しており、倒産の心配はないと言えるでしょう。
また、各高速道路は完全 に棲み分けが行われており、民間の事業者が勝手に高速道路を建設することもできないので、 競合他社は全く存在しません。
競争にさらされる心配はないので、業績が急激に悪化することも ありません。
業界の分類
高速道路管理会社
日本には高速道路管理会社は6社しか存在しません。
その6社とは東日本高速道路、西日本高速道路、中日本高速道路、首都高速道路、阪神高速道路、東京湾横断道路です。
高速道路管理会社の株主は政府であり、高速道路事業は国の政策で決定されるので、新規参入は一切なく、競合となる事業者は存在しません。
最新のトレンド
高速道路の民営化
高速道路会社は東日本高速道路、西日本高速道路、中日本高速道路、首都高速道路、阪神高 速道路、東京湾横断道路の6社ですが、このうち東日本高速道路、西日本高速道路、中日本高 速道路はNEXCOによって運営されています。
NEXCOは高速道路株式会社法で規定された特殊会社のうち、2005年10月1日に日本道路公団(JH)の民営化により発足した3社の総称であり、主に道路施設の管理運営を行っています。
NEXCO東日本は関東から北海道までを、 NEXCO中日本は中部地方を、NEXCO西日本はおおむね近畿以西を管轄としています。
民営化以前は日本道路公団(JH)と首都高速道路、阪神高速道路、東京湾横断道路の4社合わせて40兆円にのぼる有利子負債がありましたが、確実な返済を図ることと民間のノウハウによっ て多様で弾力的な料金設定を行い、多様なサービスを提供することを目的に民営化が実施されました。
高速道路の開通進む
高速道路主要6社の売上高の推移について見ると、2000年代は緩やかな減少傾向にありましたが、2012年4月に新東名高速道路が開通したことで同高速道路を管轄するNEXCO中日本の通行料金収入、サービスエリア店舗収入が大幅に増加したことで市場が拡大しました。
一方で、 2013年には第二京阪道路の開通やサービスエリア事業の好調によってNEXCO西日本の売上 高が大幅に増加しました。
2014年にはNEXCO東日本による常磐自動車道、圏央道の開通、 NEXCO西日本による東九州自動車道、徳島自動車道の開通などによってNEXCO社の売上高 が大幅に増加しました。
さらに2017年には東京外環自動車道(外環道)の三郷南-高谷間が開通し、業績がさらに拡大しました。
新型コロナウイルスの影響
2019年まで高速道路の利用料金収入は堅調に推移していましたが、2020年以降は新型コロナウイルスの影響を受けます。
緊急事態宣言による外出自粛によって観光需要がほとんど消滅しました。
これによって高速道路の利用者が減少し、高速道路の利用料金やサービスエリアの利 用客も減少しました。
また、国土交通省は料金所の職員が感染したことを受け、2020年7月、高 速道路料金所の完全ETC化の検討を発表しています。