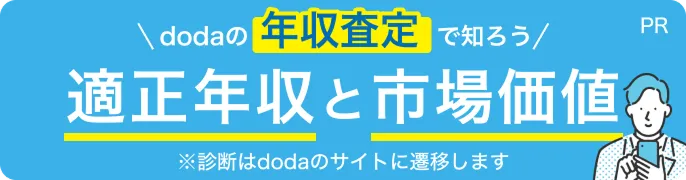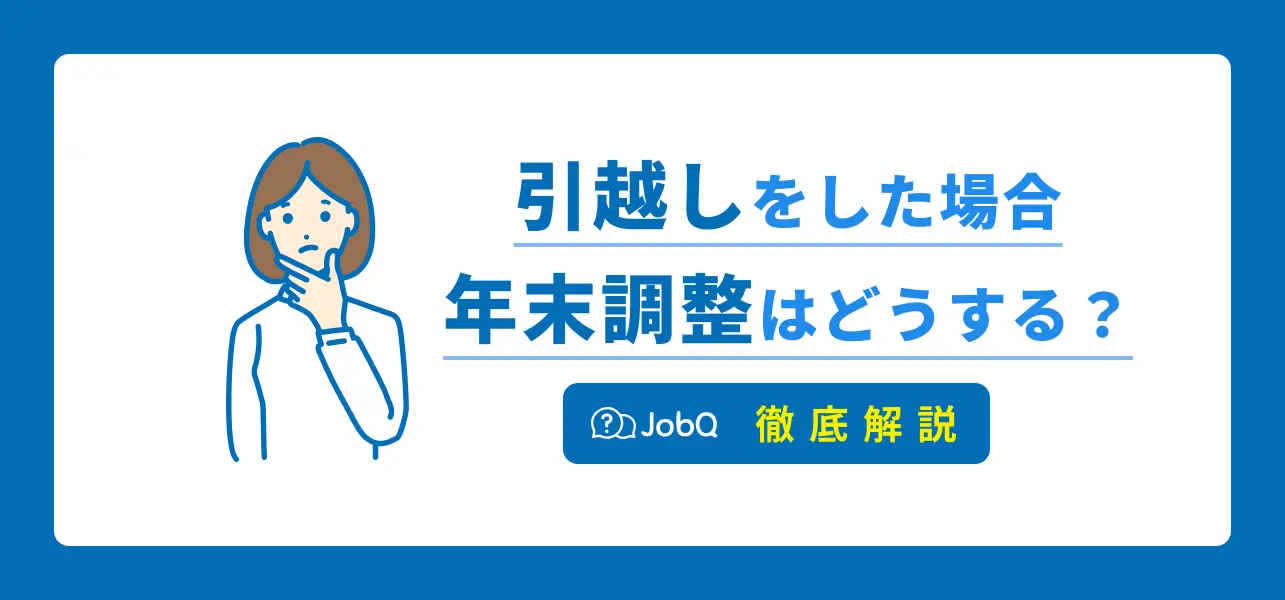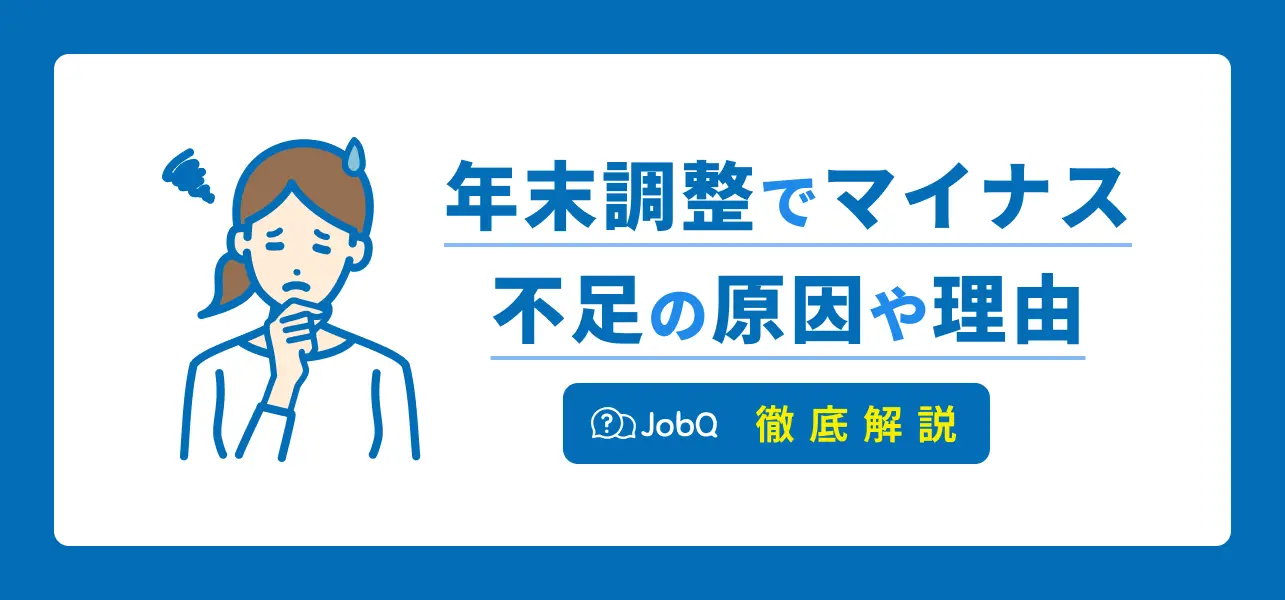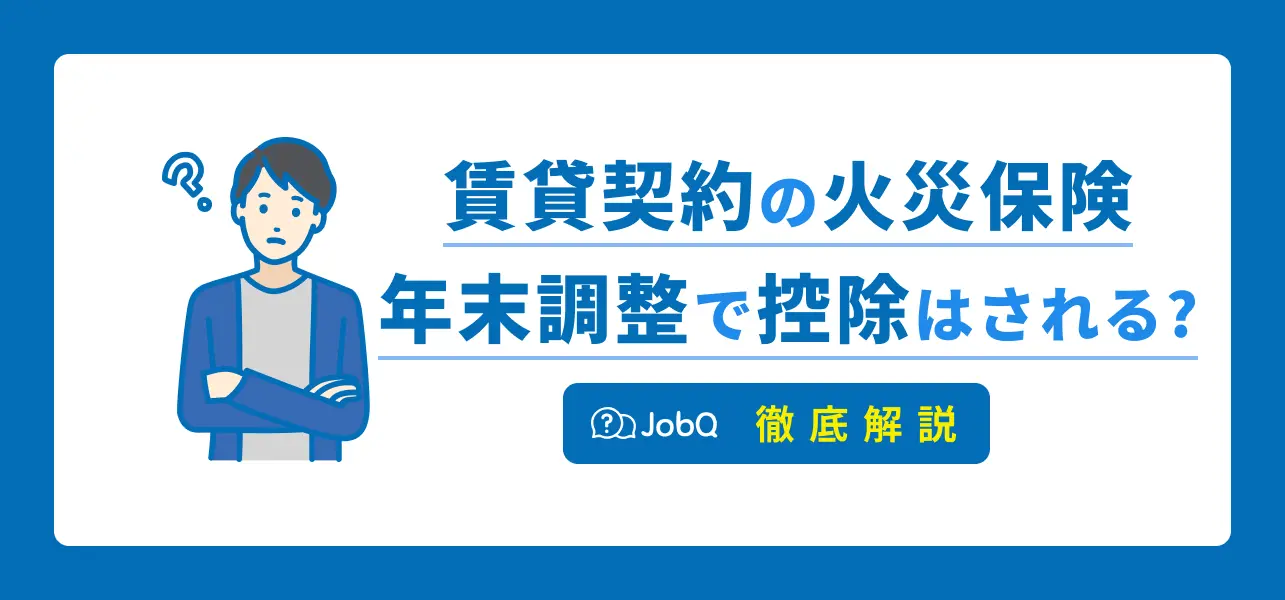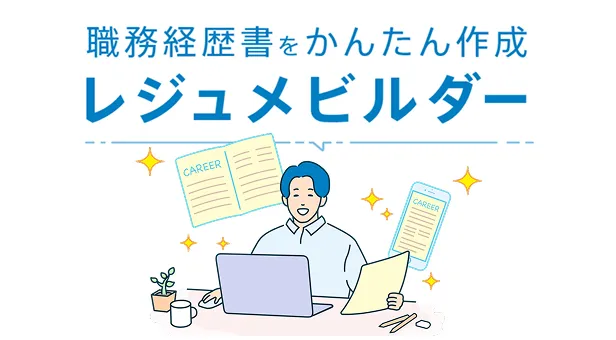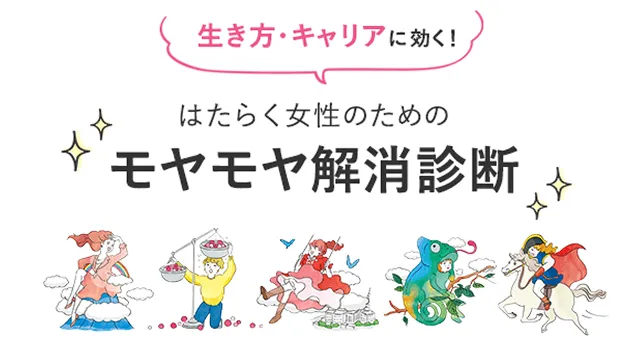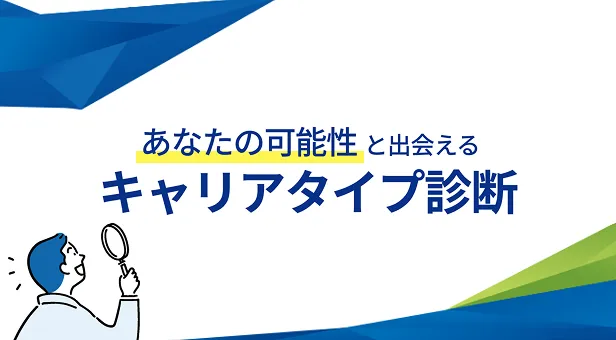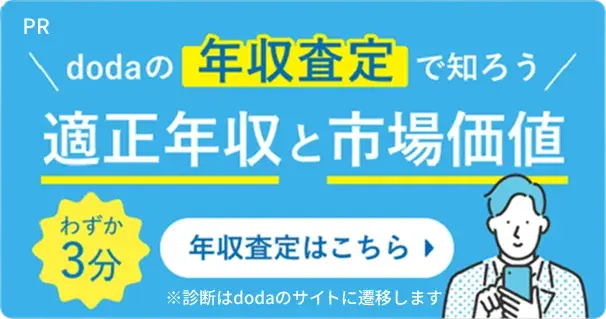【年末調整の振込】1月の給料に上乗せ?行われないこともあるって本当?
皆さん、年末調整の振込について詳しくご存知でしょうか。この記事では、年末調整の還付金の振込み時期や、年末調整で徴収になる場合や還付金が少ない場合の理由など具体的にご紹介致します。また、年末調整と還付金に関する仕組みについても解説致しますので是非参考にしてみてください。
年末調整について
会社員の皆さんは毎年、年末調整をされていますね。
バイトをしている学生の皆さんも、年末調整を行ったことがある方もいらっしゃると思います。
そんな皆さんは年末調整について正しく理解していますか?
この記事では、年末調整の基本について紹介した後に、還付金やその振り込みについて詳しく説明します。
年末調整とは
そもそも年末調整とは、1年間(その年の1月から12月まで)に支払われた給与から差し引かれた所得税を精算する手続きのことです。
所得税は1年間の所得に対して税額が決まりますが、従業員は毎月の給料を受け取る際、あらかじめ所得税を差し引かれているのです。
これを源泉徴収と呼びます。
源泉徴収額はあくまで概算であるため、各人の生活事情に応じた所得控除は控除されていません。
そのため、本来その人が納めるべき所得税を再計算する必要があるのです。
源泉徴収額と正しい所得税額を比較し、給与を受け取った人が税金を多く払っていた場合は差額を返金し、不足している場合はその分を徴収することになります。
年末調整と確定申告の違い
さて、年末調整と確定申告の違いをご存知ですか。
年末調整と確定申告は、どちらのその年の所得を計算し、所得税を納めるという意味で目的は同じです。
違いは、誰が申告や納税を行うかという所にあります。
年末調整は、先ほども説明したように、会社があらかじめ従業員の1年間の給与所得を確定し、大まかに天引きしていた税金を年末に計算し直して還付または徴収することです。
一方、確定申告とは、様々な種類の所得について、自分で申告や納税をすることです。
よって、基本的には給与所得者は年末調整を行いますが、給与所得者であっても以下の条件に当てはまる人は確定申告が必要となります。
- その年の給与収入が2000万円を超えている
- 災害減免法で、その年の給与に対する所得税の徴収について猶予や還付を受けている
その他、年末調整をしていても確定申告が必要になる場合もあるので、注意が必要です。
年末調整の還付金について

さて、年末調整という言葉を知っていても、詳しい仕組みまでは理解していない方も多いのではないでしょうか。
そこでこの章では年末調整と還付金に関する仕組みについて紹介します。
年末調整の仕組み
これまでに説明したことのまとめとなりますが、年末調整とは、1年間に支払った税金の中から、支払額が多かったり少なかったりした場合に差額を調整する作業です。
すなわち、毎月の給与やボーナスから差し引かれている源泉徴収による税金と、実際に支払わなくてはならない税金の差額を調整します。
そして、年末調整と確定申告の違いとしては、前者は所属する企業や団体を通して行う一方で、確定申告は個人で行うということが挙げられます。
還付金がもらえる人
そして、還付金を受けることができるのは、勤務先で把握できない所得控除がある人です。
主な対象者としては以下のものが挙げられます。
- 生命保険料などの支払額に応じた控除
- 配偶者や扶養家族に対する控除
- 本人や家族の障害控除
- 住宅ローンの控除
逆に、扶養家族の人数が減った人や、解約や満期などの理由で保険料や住宅ローンの支払いがなくなった人は、控除額が減るため還付金額が少なくなります。
年末調整の還付金の振込みについて

それでは、還付金について詳しく説明していきます。
基本的には1月の給料に上乗せされる
説明してきたように、年末調整の還付金は1年間に支払った給料の総額と、税金の金額を照らし合わせて再計算して決定されます。
また、それに加えて扶養家族や配偶者、生命保険などの控除も考慮して正確な税金額を算出する必要があります。
差額の還付金は、それらの計算を終えてから振り込まれるため、基本的には1月の給料に上乗せされて振り込まれます。
ただし、会社の忙しさなどによっては1月に間に合わない場合もあるようです。
還付金が振り込まれないこともある
また、税金が所得に対して相違がない場合は還付金は振り込まれません。
再計算された税金のうち、余った分は還付し、足りなかった分は改めて徴収するため、還付金を楽しみにしている方もいらっしゃるかもしれませんが、還付金がない場合または再徴収される可能性もあることを念頭に置いておきましょう。
年末調整で徴収になる場合や還付金が少ない場合の理由

それでは最後に、年末調整で還付金が少ない場合あるいは徴収されてしまう理由を3つ紹介します。
年の途中で扶養人数が減った
まずは、年の途中で扶養人数が減ったという理由が考えられます。
例えば、途中で妻(または夫)が働き始め、年収が103万円を超えた場合、元々の天引き額より多くの税金を徴収されることになります。
妻の年収が一定の場合には配偶者特別控除がありますが、配偶者控除に比べれば控除額は下がるため、追加天引きとなるのです。
処理間違い
また、こちらは単なるミスですが、扶養から外れた旨を会社に届けたのに未処理だったなどのミスが考えられます。
こちらも、年末調整の頃に追加徴収をされる可能性があるでしょう。
子供の年収が103万円を超えていた
また、親の管轄外で働く子供の年収が103万円を超えていたということも考えられます。
親は扶養に子供を入れて申請をしていたのにも関わらず、子供が103万円以上稼いでしまった場合、控除の対象外となり、結果的に年末調整で徴収または還付金の減少が考えられます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
以上、年末調整の基本と、還付金の振り込みなどについて詳しく説明しました。
年末調整について疑問を抱いていた方は解決できたでしょうか。
また、還付金が少なくなったり、中には追加徴収をされてしまうケースもありますので、注意が必要ですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。