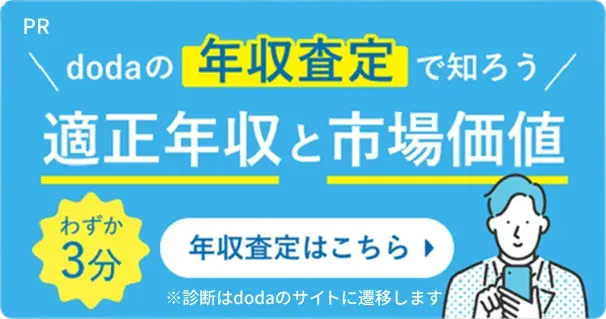【退職後の住民税はいくらになるの?】確定申告などの手続き方法を解説
退職すると住民税を自分で払わなければなりません。今までは会社があなたの代わりに住民税を給料から天引きしていましたが、これからは自分でやらなければならないのです。そこで今回は住民税の支払いが個人になった時に役立つ基礎知識をご紹介します。ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
そもそも退職金に住民税はかかるものなの?

退職金には税金がかかるのか
退職金には住民税と所得税の両方がかかります。
ですので、退職金はこれらの税金を差し引いた分が手元に残ります。
ですが、退職金には長年働いてきたご褒美と老後の生活を支えるための意味が込められているため、差し引かれる額は優遇されています。
また退職金の税金は、「退職所得控除」と「2分の1課税」を行うことで、支払う金額が決まります。
ただし、これらの優遇措置を受けるためには、「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要があり、もし提出しなかった場合、20%以上の所得税がかかってしまいます。
「退職所得控除」と「2分の1課税」の計算方法は以下の通りになります。
(退職金の総額 − 退職所得控除額) × 2分の1
= 退職所得金額(住民税・所得税がかかる金額)
以上のように「退職所得控除」と「2分の1課税」を行うことで、税金がかかる金額が少なくなります。
ただし、申告書を出し忘れた場合は、確定申告をする際に退職金について申告し、払い過ぎた分を還付してもらうことができます。
基本的に退職金に関する税金は、自分で手続きを行う必要があり、支払う前にしっかりとした知識を身につけておきましょう。
住民税はどのくらいかかるのか
住民税は、住んでいる都道府県と区や市町村に支払う必要があります。
つまり、都道府県と市町村の2つの税金を合計した金額が支払うべき住民税となります。
また住民税は税率が決まっており、以下のようになっております。
都道府県の住民税4% + 区市町村の住民税6%
= 住民税の税率10%
以上が、住民税の税率になります。
また計算する際は、1000円以下の数値は切り捨て、1800円だった場合、1000円となります。
また住民税の出し方は以下の通りになります。ただし、住民税を出す場合は、100円以下の金額は切り捨てとなり、1180円だった場合、1100円となります。
退職所得額 × 10% = 控除前の住民税の額
控除前の住民税の額 × 10% = 住民税の控除額
控除前の住民税の額 − 住民税の控除額 = 住民税の額
住民税は滞納して何年か経つと時効になるって本当でしょうか?
住民税をもう、3~4年払っていません。
会社を退職してから、すでに3~4年たち、住民税の支払い等を自分でしなくては行けなくなった時から、払えていない状態です。
あるサイトを見た所、住民税は5年ほど経てば、時効になり消滅するということを聞きました。これって本当なのでしょうか?
また、時効になった場合のデメリットとは何でしょうか?お詳しい方いましたら、ご回答お願いします。
確か民法にあったと思います。
うろ覚えですが「払ってください」旨の通知が来て5年で時効ですが、金額が30万円を超えるとかなりの確率で…続きを見る