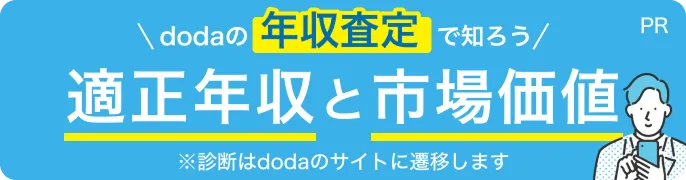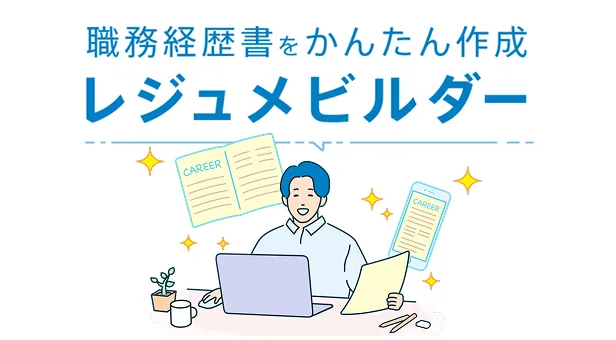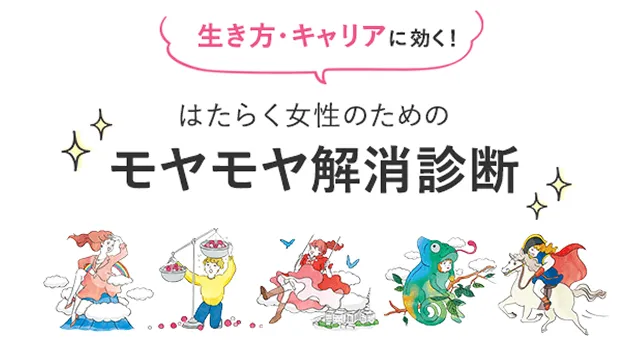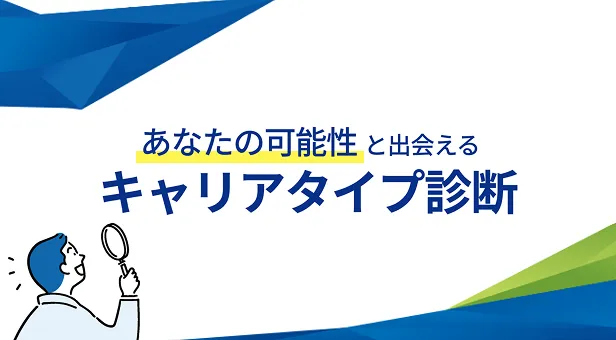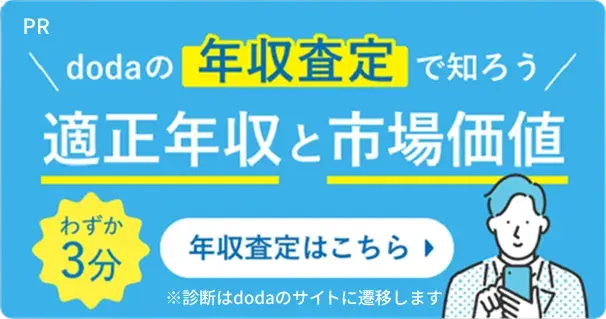【起業の成功率は高い?低い?】知りたい情報を公開いたします
今回は、起業の成功率について詳しくご紹介いたします。起業の成功率は高いのか、低いのか、また起業して失敗しやすい業界など様々な情報についてお伝えいたします。これから、起業することを考えている方は、是非、参考にしてみてください。
起業の成功率についての通説
日々のニュースを見ていても景気のいい話はあまり聞きません。
それは、日本の情勢が決して良い方向に進んではいないからかもしれません。
年功序列はすでに破綻していると言っても過言ではない状態です。
そのため、同じ会社で働いていたとしても、給料が上がることが少なくなっています。
または、長時間労働で残業代も出ないブラック企業問題などが頻繁に色々なメディアに取り上げられています。
そのような状態で、起業を考えている人が増えていっています。
起業を行えば、様々な束縛から解放されて、劣悪な環境から抜け出し高収入やライフワークバランスが理想のものになるかもしれません。
その中、起業の成功率などは本当に通説通りなのでしょうか。
起業の成功率とは何か
世間には「企業の生存率」という数字もあります。
企業がなくなるということは、起業失敗ということになるので、転じて「起業の成功率」として使われる言葉になっています。
実際に残り続けていればどんな状況でも成功に入るのかもしれません。
実際の起業の成功率という数字は出されていません。
まことしやかに言われている数字になっています。
起業を行うことは、難しいと言いたいために誰かが言い出したのかもしれません。
そもそも何を基準に「成功」としているかによっても変わってきますし、起業する業界によっても変わってきます。
ですので、世間に出回っている噂の成功率は自分の気持ちを戒めるため程度に覚えておくことがいいかもしれません。
起業後5年と10年と20年等の生存率
起業後の生存率は、1年で40%、5年で15%、10年で6%、20年で0.3%、30年だと0.02%になっています。
これだけ、起業を行うということは、生存競争が激しい世界で生き抜いて行くことが厳しすぎると言わざるをえません。
起業をすると、たった1年で過半数である60%の企業が倒産していることになります。
確か100人起業したら、1年で残るのは40人になってしまうわけですから、末恐ろしくなり起業を諦めた人もいるかもしれません。
身近な成功している人ではなく、大成功しているビル・ゲイツなどを思い浮かべてしまうとさらに、意欲がなくなってしまうかもしれません。
いわゆる起業の成功率は6%の意味は?
起業を起こして10年の成功率6%の意味とは、何を指しているのでしょうか。
起業を考えているわけでもない人にしたら、「起業するって難しいことなんですね」と思うくらいでしょう。
この成功率や生存率を見て、逃げ出してしまったり色々なことの挑戦する意欲を失ってしまった人は、何に対しても成しえなくなってしまう可能性があります。最初から成功する人はいないでしょう。
起業に対してももちろんそうです。
そのため、起業に対する10年後の成功率6%の意味は、実質的な意味より、これから起業を興すことができるかという、最初のふるい落としになるのではないのでしょうか。
意外に高い中小企業白書に基づく起業の成功率
サイトを見て起業の成功率に踊らされてしまった人も大勢いるかもしれません。
ですが、その段階で諦めた人は、逆に良かったのかもしれません。
それは、起業をしても長続きしない可能性が高いからです。
では、どのようなものを起業して成功しているのか、参考にするものはないのか、みていきましょう。
あるサイトだけを見て諦めるのではなく、公式の情報を参考にして違った方面からでも情報をみたい人もいることでしょう。
その情報の中に、毎年5月に中小企業庁から発表される、中小企業の動向を詳細に調査・分析した白書に基づいた内容から確認してみましょう。
中小企業白書に基づく起業後5年と10年と20年等の成功率
中小企業白書が作成している企業の生存率という表を参考にして5年・10年・20年の成功率をみてみましょう。
5年では82%、10年では70%、20年では52%と企業してから生存=成功しています。
1年で言えば実に企業してから97%が生存しています。
このようにあるサイトの成功率とは、大幅に成功率が変わってきます。
ちゃんと起業プランがしっかりしているのなら、生存していないことはないのです。
成功の範囲を狭めてみてしまえば、確かに成功率は変わってしまうかもしれませんが、そのようなデータは存在していません。
起業する目的は何が多いか
起業する目的としてどのように考えていることが多いのでしょうか。
成功と考えている人は、漠然とお金持ちになりたいと考えているかもしれません。
しっかりとした道筋を考えているのであれば問題はないでしょう。
そして、中小企業白書では起業をする目的として3つの成長タイプに分けられています。
成長タイプは「高成長型」「安定成長型」「持続成長型」としています。3つのタイプと起業する目的で思うことをあてはめてみたものが以下のものになります。
- 高成長型:「自分の裁量で自由に仕事がしたい」「アイディアを事業化したい」等
- 安定成長型:「収入を多く得たい」「社会貢献したい」等
- 持続成長型:「仕事の経験・技術・知識・資格等を活かしたい」「生計を維持したい」等
主にこのように分けられています。
特に多く見受けられるのが、「自分の裁量で自由に仕事がしたい」と考えて人が多いことを中小企業白書では記載されています。
起業する人の年齢別構成を男女別に見ると
中小企業白書より年齢別構成を男女別に分けているグラフがあり確認を行うことができます。
2007年から2017年にかけて男女ともに26~39歳で約35%~40%、40~49歳代で約23%~29%となっています。
59歳までに企業を起こす割合が全体で約70%を占めています。
若くて行動に移せる体力もあり、アイディアもあるうちに実行したい人が多くいると見られます。
実際にメディアでも取り上げられる起業家は若い人を多く見受けます。
また、60歳以上でも会社を退職した後、今までの経験や知識・技術などを活かしてセカンドキャリとして起業を選択している人も男女問わずいます。
起業の成功率は6%という説について
前述でも少しお話しましたが、起業後10年での成功率はあるサイトでは6%と言われています。
それが拡散されたためか、起業しても成功するわけないと信じている人が増えた可能性はおおいに考えられます。
では、今回は違った目線をもって企業の成功率を紹介していきます。実際はどのようになっているのでしょうか。
起業の成功率は6%を裏付ける統計のデータはない
起業後の成功率を調べて、10年後や20年後に成功できるような人は、それこそビル・ゲイツみたいな人だと思って諦めた人が多くいるかもしれません。
ですが、その裏付けできる統計のデータは存在していません。
1年で60%の企業がなくなるなどというデータは、どこにも存在していないのです。
中には「国税庁の調査結果」などと書かれたものまであります。
そのため、このような情報を信じて起業を諦めた人は正解だったのかもしれません。
上記だけの情報を信じ、目の前にある情報を鵜呑みにしてしまっているようでは、確かに起業しても存続させることが難しいでしょう。
起業の成功率は高くも低くもない
実際の起業をおこなった際の成功率は、高くも低くもないのが現実です。
他のサイト等で成功率が著しく低くしているのは誤りです。
成功の定義によって変わってはきますが、およそ5~8割くらいは成功しています。
根拠としてあげられる理由が、「中小企業白書」で中小企業の動向を調査したレポートがあるからです。
中小企業白書は、中小企業庁が毎年発表している、中小企業の動向を詳細に調査・分析したものになり、ホームページ上で公開しています。
日本は起業5年後の生存率が高いというデータ
中小企業庁が発表しているデータでは、5年後の生存率が81.7%となっています。
他のサイトでは5年後に15%と言っているので、実際のデータとは逆になっています。
このようにしっかり元になるデータをみれば一目瞭然です。
根拠がなく起業成功率が低いと、言われているものを信じるより、しっかりと調査されたデータを信じることが大切です。
もし、周囲で起業し5年以内に辞めた人が多いから、起業成功率が低い内容のサイト等を信じるではいけません。
どうして廃業したかの理由を探ったほうが賢明でしょう。起業したいのであれば、原因を探ることもときには必要です。
起業して失敗しやすい業種とは
起業するからには誰でも成功したいと思っています。
それは、間違いありません。
ですが、起業した全ての人が成功するわけではありません。
その場合は、負債があるため早く安定した収入が欲しいため、仕事探しから始めるかもしれません。
これは、起業する前や起業後よりもはるかにきつく、大変なことでしょう。
ではこのような、大変なことにならないためには、どうすればよいのでしょうか。
起業だけではなく、独立・開業について安易に考えてはいけません。
安易に考えて失敗しない方法を考えずに、自分はしっかり経験したから大丈夫とだけで起業してはいけません。
では、失敗しないようにするにはどうすればいいのでしょうか。
飲食業など店舗を必要とする業種
失敗しやすいものの代表例としてよく上げられる業種が、飲食業になります。
見たことある人も多いのではないでしょうか。
新しくオープンした飲食店が、最初こそお客さんが多かったものが、気がついたら潰れていたということ。
このように、元手の必要とするビジネスの起業を避けることが賢明です。
但し、潤沢な手元資金があれば問題ない可能性もあります。
飲食店だけではなく、店舗を構える場合にはかなりの費用が必須です。
敷金、礼金、保証金等や月々の賃料は毎月発生します。安定した売り上げを出すことは、並大抵のことではないため軽く考えてはいけません。
建設業など多くの人手を必要とする業種
物流業、建設業、土木業、イベント運営サービスなど、「人手が必要」とされるビジネスで起業する場合も、今の時代相当のリスクを覚悟する必要があります。
単純明快な理由ですが、簡単に人が集まらないからです。
ニュースなどで色々情報が流れていると思いますが、多くの職業で人材が集まらないと言われています。
特に建設業などは、キツイ・汚い・危険と思われているからに他なりません。
そのため、おススメできるビジネスとは言いにくいです。
OA機器販売業など在庫を抱えなければならない業種
商売を行うビジネスもあまりおススメできません。
なぜなら、商品を販売するには、在庫を抱える必要があります。
多くの商品を入れてしまうと、その分多くの仕入れ原価が発生するため資金がかなり必要となります。
ですが、一つの商品で販売等のビジネスは成り立たないため、過剰な在庫を抱えてしまうことがよく見受けられます。
在庫を抱えすぎてしまうと、原価割れで販売をしてしまい、悪循環に陥ることがあるためです。
起業と成功率に関するいろいろな問題
起業をしようとするときに、一番多い割合は中小企業白書上では、30代付近の人が最も多いです。それは、サラリーマンから独立をしていることになります。起業を思い立ったときは、「やる気」が溢れんばかりでしょう。
ですが、やる気だけで起業は成功しません。ですが、やる気がない人はもっと成功しないかもしれません。熱意が溢れに溢れまくっている場合は、一旦、冷静になって考えることが必要でしょう。
他にもサラリーマンだけではなく、学生起業家も最近では増えてきています。サラリーマンからの起業とは何が違うのでしょうか。起業と成功率に関わるいろいろな問題を説明していきます。
脱サラ起業の成功率は選ぶ事業のタイプによって変わる
脱サラをして、起業を行う場合はかなり覚悟を持っていることでしょう。特に家族がいる場合は尚更です。起業と言っても様々な種類がありますが、「消費者向け」「企業向け」の事業2つをメインに考えます。
消費者向けの事業とは、主に販売業やサービス業が該当します。前述で、販売業は成功することが難しいことを説明しました。店舗を構えることや商品の仕入れなどでしっかりした資金がないとおススメできません。
企業向け事業とは、特定分野の外注請負や代行が該当します。IT分野などサラリーマン時代に獲得した技術を活かせます。ですが、経営者になることは、仕事を作ることになるので、業務は優秀だったとしても仕事を得ることができないと難しい場合があります。
学生起業のメリットとデメリットは?
現在は学生で起業する人も増えています。それは、この情報社会の中で学生でも起業できると知った人が多くなったことも一因としてあるかもしれません。その学生起業のメリット・デメリットとはどのようなものがあるのでしょうか。
メリットは、失敗しても学生で家族などを養っていくことは稀でしょう。そのため背負っているものも少なく再チャレンジが行いやすいでしょう。また、若い才能を見つけるための支援環境が整っていることがあげられます。
デメリットは、経験不足によって防げる失敗を犯す可能性があります。また、友人と起業することで友達感覚が悪い意味で働き、思わぬ亀裂を生むこともあります。若いから失敗しても大丈夫と思うことが失敗に繋がってしまうこともあるので注意して下さい。
起業の成功率の基準に関わる起業の成功と失敗の定義は?
起業が成功したと言える定義はあるのでしょうか。考えだしたらキリがありませんが、成功の定義を「学術」と「実務」の2つから紹介します。
学術の世界では、世界中の研究者が起業の成功要因を研究しています。現在、明確な統一的な定義は存在せず、学者によってバラバラですが、売上高・利益率・成長率などの指標を使て一定水準を超えたものを成功としています。
実務の世界では、一定水準を超えなかったからといって、必ずしも失敗ではありません。売上高・利益率・成長率が一定ライン以下でも事業を大きくするつもりがないのであれば失敗ではなく成功と言えるのです。
まとめ
起業する上で、成功することに越したことはありませんが、成功に固執ばかりするのは良いことではないかもしれません。そもそも、10年後の成功率などが6%などということを信じるようでは、成功はないかもしれません。
成功も人それぞれの考え方があります。普通に生活できれば成功。世界有数の富豪になって、初めて成功と言う人もいるかもしれません。このように、自身の信念で成功の基準を図ることは決して悪いわけではありません。
情報に惑わされることなく、様々な不確定情報をもとに決断していかなければならないため、起業する場合には、これからも自身の信念を曲げずに進んでいきましょう。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。