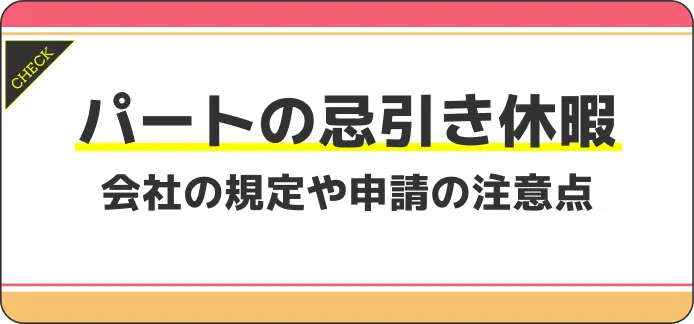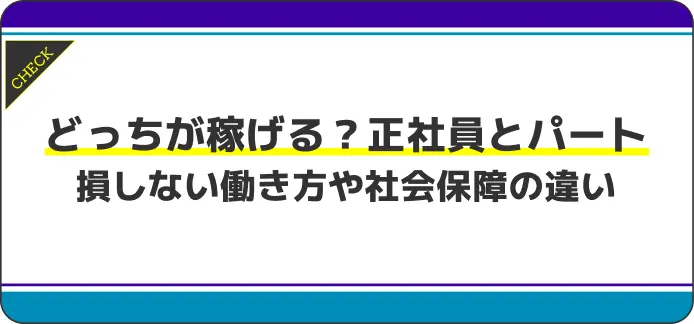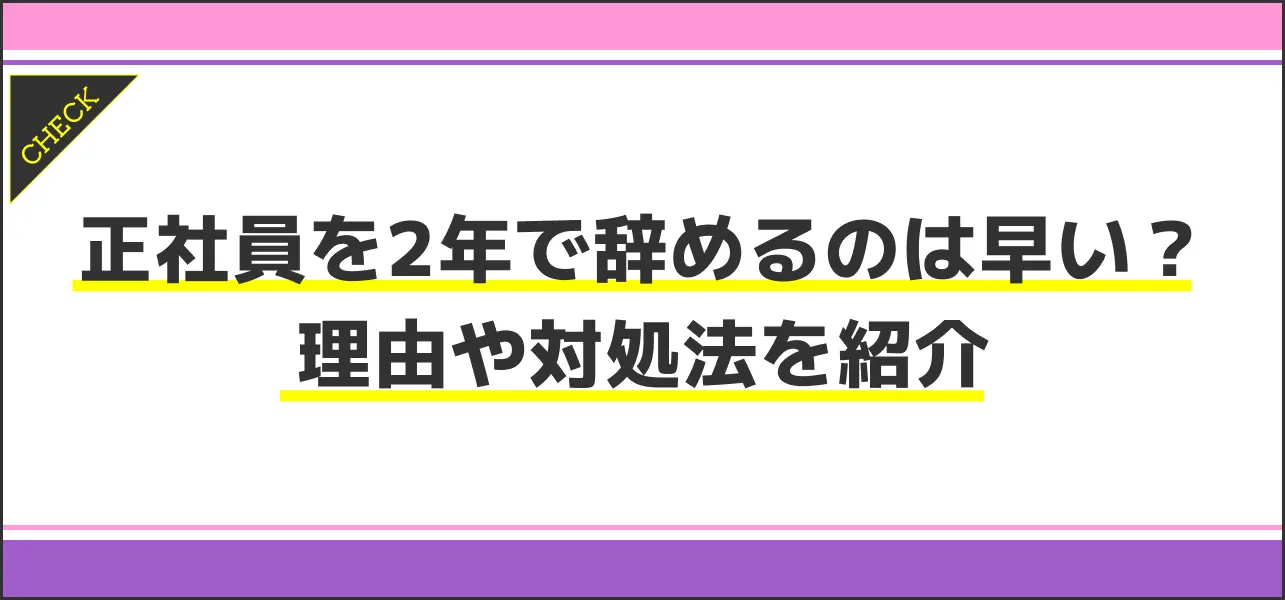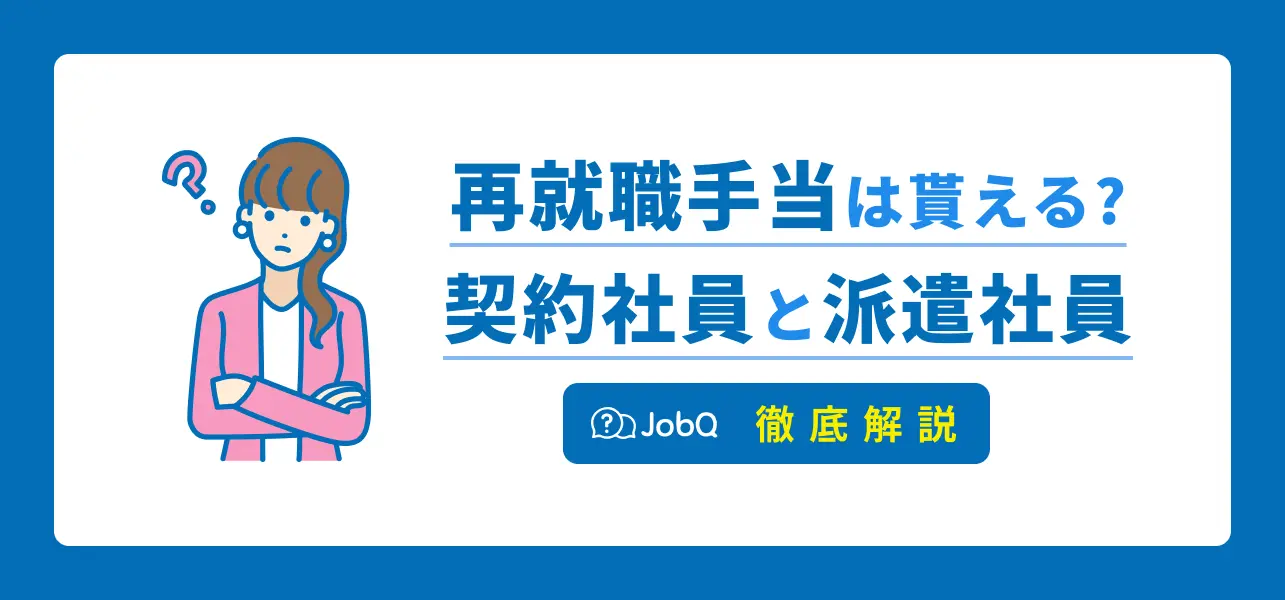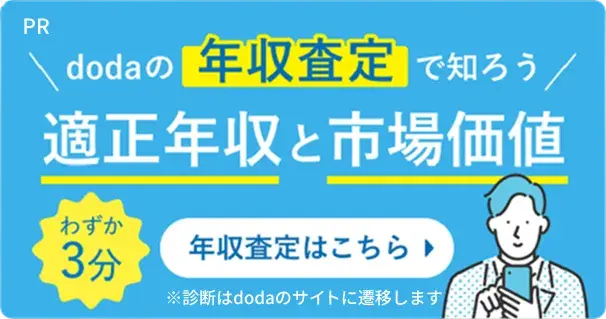【二重派遣のデメリットとは】疑いがある際にとるべき行動とは
二重派遣は法的に問題があるだけでなく、派遣労働者にとって不当な労働管理や賃金の搾取など、さまざまなデメリットがあることはご存知でしょうか?もしかしてと疑いがある場合はまずどうしたらいいのでしょうか。今回はそのことについて触れていきますので、是非参考にしてみてください。
法律で禁止されている二重派遣とは?
非正規雇用の増加により、派遣労働者として働く方も増えています。
派遣労働者の権利や安全は、正規雇用労働者と同じように法律によって守られていますが、法の目をかいくぐって行われる「二重派遣」をご存知でしょうか。
そもそも労働者派遣とは、労働者派遣事業の許可を受けた派遣会社に雇用された労働者が、派遣先企業で勤務する雇用形態です。
派遣先企業と派遣労働者との間には雇用関係が存在せず、派遣労働者は派遣先からの業務上の指示にのみ従います。
これを指揮命令関係と呼びます。
今回取り上げる二重派遣とは、一言で表すと「派遣の派遣」を行う行為です。
ここでは、派遣元となる派遣会社をA社、A社の派遣先かつ二重派遣の仲介企業をB社、B社の派遣先をC社として、二重派遣の構造について詳しく解説します。
- 労働者は、派遣元A社と雇用契約を結ぶ。
- 派遣元A社は、労働者を仲介企業B社へ派遣する。
- 仲介企業B社は、A社から派遣された労働者を自社の業務に就かせず、C社に派遣する。
- 労働者は、B社とC社双方の指揮を受け、C社の業務に従事する。
ここで問題となるのは、B社が自社と雇用契約のない派遣労働者を、第三者であるC社の指揮命令下に置き、C社の業務に従事させることです。
これは職業安定法第44条で禁止されている「労働者供給事業」に該当し、違法行為に当たります。
二重派遣によるデメリットは労働者の負担に

二重派遣される労働者には、さまざまなデメリットやリスクが伴います。
ここからは、先ほど例に挙げたA・B・C社を用いて、二重派遣によって労働者にかかる負担を詳しくご紹介します。
中間搾取によって労働報酬が低下してしまう
二重派遣によって発生する中間搾取は、派遣労働者の賃金低下をもたらすことがあります。
中間搾取とは、A・B・C社間の二重派遣において、仲介役となるB社が、C社から派遣料金や派遣手数料などの名目で、不正に報酬を受け取る行為です。
中間搾取は、他人の就業に不正に介入することで生じる利益を受け取る行為で、労働基準法に違反しています。
二重派遣における中間搾取の代表例は、A社とB社の間で労働者派遣を仲介するB社が、派遣労働者の賃金をピンハネして自社の利益とすることです。
このピンハネによって、派遣労働者の賃金が不正に下げられるケースもあります。
また、ピンハネが行われていない場合でも、二重派遣は派遣労働者の賃金低下をもたらしかねません。
そもそも、派遣元から派遣先に請求される派遣料金は、下記の計算式で算出されます。
派遣料金=派遣労働者の賃金+中間マージン(派遣労働者にかかる各種費用を含む)
上記のマージンは派遣元の取り分で、マージンから派遣労働者の福利厚生費など、派遣労働者にかかるさまざまな費用を差し引いた金額が、派遣元の利益となります。
二重派遣の場合、派遣元A社と仲介企業B社の2社で中間マージンが発生します。
2社分の中間マージンが生じることで、派遣労働者が受け取れる賃金の低下を招くこともあるのです。
契約内容が不透明になってしまう
二重派遣は、派遣元A社や仲介企業B社と、派遣労働者の間に交わされるの契約内容が不透明であることが多く、労働者が不当な労働を強いられやすい傾向にあります。
また、A社と雇用契約を結んだ労働者が、B社を介してC社へ派遣された場合、それが二重派遣なのか、それとも「偽装請負」と呼ばれる行為なのか、曖昧になりがちです。
ここでご紹介した「偽装請負」とは、見かけ上は請負でありながら、実際は労働者を派遣する違法行為です。
そもそも二重派遣が違法行為であるため、法の網をすり抜けるべく、偽装請負を行うケースが多く見られます。
本来の適正な請負であれば、派遣労働者はまず、派遣元A社からB社へ派遣されます。
そしてB社の指示のもとで、B社の請負元であるC社の業務に従事します。
ここでポイントとなるのは、B社と労働者の間には指揮命令関係が成立するものの、請負元C社と派遣労働者の間には、一切の指揮命令関係が存在しない点です。
では、偽装請負の場合はどうなるのかを見ていきましょう。
派遣労働者が派遣元A社からB社へ派遣されるところまでは、先ほど解説した請負の形態と同じです。
先ほどとは異なるのは、B社と請負元C社の間の契約は業務請負であるにもかかわらず、派遣労働者が請負元のC社の業務に携わる際に、C社の指示に従う点です。
つまり、請負では存在し得ないはずの指揮命令関係が、派遣労働者とC社との間に成立しているのです。
また、B社と請負元C社の間の契約は請負ですので、C社がB社に支払うのは、成果物に対する報酬のみとなります。
B社の派遣労働者が、C社の請負業務を遂行するために残業・深夜労働・休日出勤が必要になったとしても、C社はそれらの時間外・深夜手当等を支払う必要がないのです。
このように、二重契約や二重契約を請負に見せかける偽装請負では、契約内容の不透明さから労働者の負担が増え、適正な賃金が支払われないなどのデメリットがあります。
不当解雇される危険を伴う
二重派遣の3つ目のデメリットは、派遣労働者の不当解雇リスクです。
派遣法に基づく適切な労働者派遣の形態であれば、派遣労働者の解雇時に誰が解雇保証金を支払うかなど、雇用主および指揮命令者の責任の所在は明らかです。
派遣先企業は派遣法に基づき、派遣労働者の労働管理や安全管理に対する責務を負う義務があります。
ところが二重派遣の形態においては、派遣労働者を不当解雇しても、C社は責任を問われることがありません。
このため、二重派遣では不当解雇や不当な契約解除など、いわゆる派遣切りが行われるケースも多いと言われています。
IT業界では二重派遣が当たり前に行われている

IT業界は先進的なイメージが先行しがちですが、慢性的な人材不足により、過酷な労働環境が問題視されることが多い業種です。
そして二重派遣は、技術者不足に悩むIT業界では当然のように行われていると言われています。
IT業界では自社エンジニアをクライアント先に常駐させることが多く、その際に派遣の形態を取ることは珍しくありません。
エンジニア派遣の形態は大きく分けて下記の2種類に分かれます。
- 派遣業の認可を受けたIT企業(ここではE社とする)が、自社エンジニアをクライアントのF社に派遣。
- 派遣会社D社から自社(E社)に派遣されたエンジニアを、クライアントF社に派遣。
①は派遣法に基づいた労働者派遣であり、合法です。
ところが、②は二重派遣に該当し、違法行為になります。
IT業界における二重派遣は、技術者に不当な労働を求める構造になっており、労働環境の悪化やさまざまな不利益を招いているのです。
二重派遣の疑いがある時に取るべき行動は?

派遣労働者が就労先企業からさらに別企業へ派遣される場合、二重派遣が疑われます。
自身の派遣形態が二重派遣に該当する可能性がある場合、派遣労働者が取るべき対応をご紹介します。
告発または相談窓口へ届け出る
派遣形態が不適切であったり、二重派遣のように違法性が疑われたりする場合、まずは登録先の派遣会社に相談してみましょう。
派遣会社に相談しても解決しない場合は、(社)日本人材派遣協会が提供する電話相談(相談料無料)で、専門家のアドバイスを受けることもできます。
日本人材派遣協会の労働者派遣事業アドバイザーを通して、適切な届け出先あるいは相談機関を紹介してもらうことも可能です。
【一般社団法人 日本人材派遣協会】
また、派遣労働者にかかわる相談窓口や専門機関には、次のものがあります。
【ハローワーク】
【各都道府県の労務局】
【派遣ユニオン(派遣労働者の労働組合)】
【社会保険事務所(厚生年金や健康保険に関する相談)】
まとめ
二重派遣は法的に問題があるだけでなく、派遣労働者にとって不当な労働管理や賃金の搾取など、さまざまなデメリットがあることは、おわかりいただけたでしょうか。
派遣労働者は派遣先に直接雇用されているわけではないため、派遣先の社内立場が弱いことも多いでしょう。
そのため、二重派遣を疑いながらも派遣先の指示・命令を拒否するのが難しく、二重派遣で搾取されるケースが後を絶ちません。
二重派遣を回避して自身の立場を守るためには、派遣労働者にもできることがあります。
- 大手派遣会社に登録する。
- 雇用契約時に契約書をきちんと確認する。
これらを行っても二重派遣を避けられない場合は、今回ご紹介した相談窓口を利用してみてください。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。