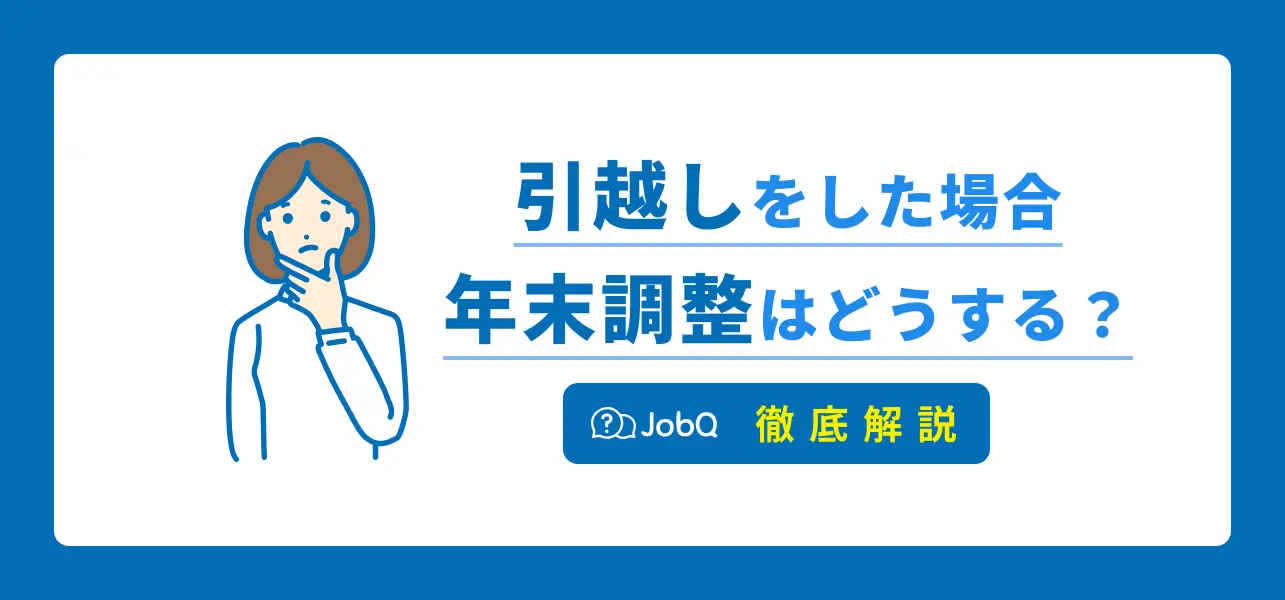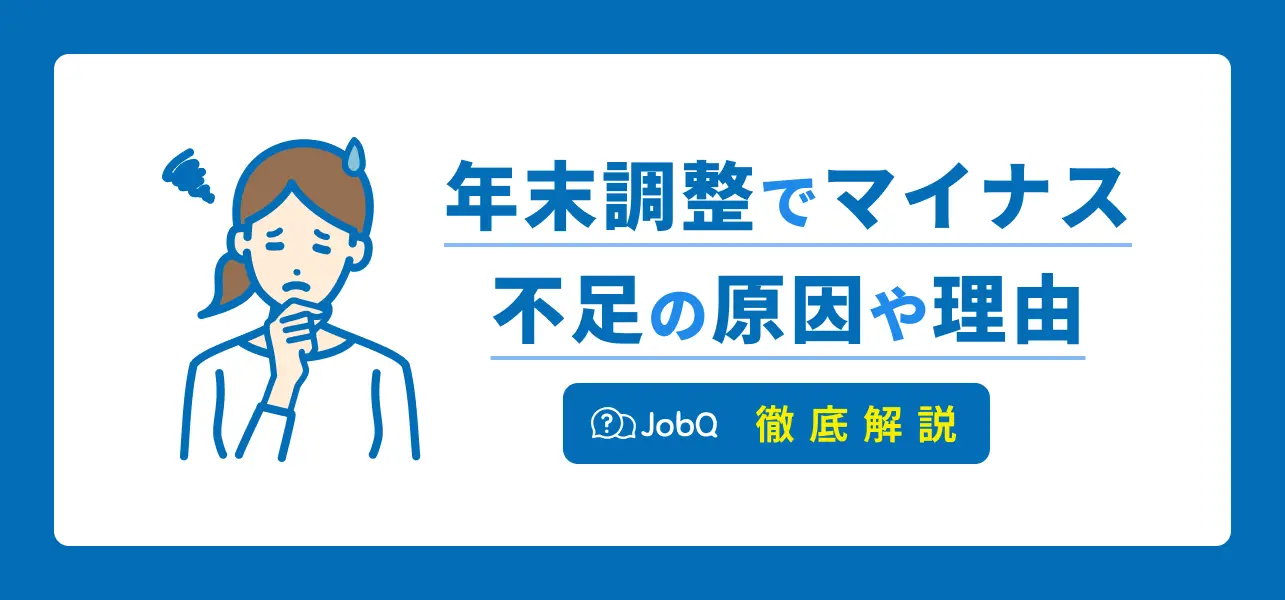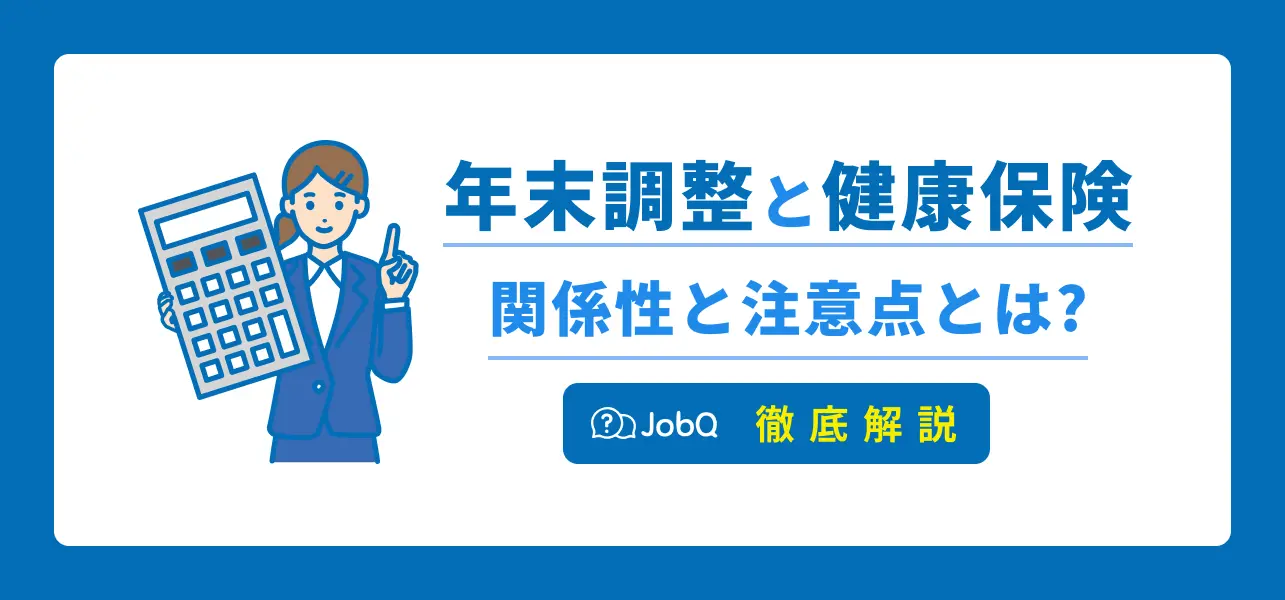
年末調整と健康保険の関係とは?注意すべき点や不明点を解消!
みなさんは年末調整と健康保険の関係をご存知ですか?年末調整とは、毎月給与から天引きされている所得税について過不足額を算出し、その精算を行う手続きのことで、健康保険料などによる控除があることもあり、追加徴収となるよりも、払いすぎによる還付となることが多いです。今回は年末調整と健康保険の関係や控除について、注意点や不明点を解説していきます。ぜひ参考にしてみてください!
年末調整と保険との関係
毎月の給与や賞与が支払われる時に、そこから所得税や健康保険料などの社会保険料が差し引かれているのを給与明細で見たことがあるかと思います。
年末調整と保険との間にはどのような関係があるのか、解説していきます。
年末調整とは
年末調整とは、毎月給与から天引きされている所得税について過不足額を算出し、その精算を行う手続きとなります。
なぜこのような手続きを行うかというと、毎月給与から天引きされている所得税額は国が定める源泉徴収税額表を基に決められているのですが、この表は給与が毎月一定額である想定で作られていることや、年の途中で扶養親族の人数に増減があってもその増減があった月からしか徴収税額が変わらないこと、健康保険料などによる所得控除は年末調整で行うことになっていることなどの理由から、源泉徴収税額表上での年間所得税額と、実際の年間所得税額に差額が生じ、納めるべき所得税額に過不足が発生してしまうため、これを年間所得金額が確定する年末に調整を行う必要があるからです。
なお、健康保険料などによる控除があることもあり、追加徴収となるよりも、払いすぎによる還付となることが多いです。
年末調整のできる人とできない人
年末調整ができる人は、原則として会社などに年末まで雇用され、給与の支払いを受けている人となります。
また、例外的に年末以前に退職した人でも、以下の場合は年末調整を行うことができます。
・死亡退職した人
・心身障害で退職後において再就職することができない人
・12月の給与の支払い後に退職した人
・パートやアルバイトで、退職後に再就職をしない人で給与総額が103万円以下の人
・年の中途で海外勤務になり、国内に住所または居所がなくなった人(非居住者)
これらの場合は、退職などの時点で年内の給与総額が確定しますので、その時点で年末調整を行うことができるのです。
年末調整ができない人は、1年以上非居住者である人や、同一の勤務先を持たない日雇い労働者などとなります。
なお、年末調整ができる人でも、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を行わないと年末調整ができません。
また、給与収入が2000万円を超える人は年末調整ができず、確定申告を行わなければなりません。
年末調整の保険料の控除について

年末調整において、所得から社会保険料などの保険料は控除することができます。
この項では、そのことについていくつか解説をしていきたいと思います。
年末調整で控除を受けるための提出書類
年末調整で保険料の控除を受けるためには、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を勤務先に提出しなければなりません。
これは、配偶者や子などの扶養の状況を記載する書類となります。
また、勤務先が社会保険に加入していない・離職していた期間があるなどの理由で会社ではなく本人が直接社会保険料を支払っていた場合、保険料控除申請書に支払金額を記載し、社会保険料控除証明書を添付して勤務先に提出しなければなりません。
年金で引かれている介護保険料の控除
生計を一にする、すなわち生活費などを負担し家計を共にしている親族で、その親族の公的年金から引かれている介護保険料について、家計を共にしていて扶養親族であることから、自分が負担し支払っているという見方もできます。
しかし、実際には公的年金から控除された時点で介護保険料は年金受給者が負担していると判断されているため、社会保険料の控除対象とはなりません。
健康保険の年末調整での注意点

では、実際に健康保険の年末調整を行う時の注意点としてはどのような点が挙げられるのでしょうか。
具体的に、実際によくある注意点を解説していきます。
転職した場合の注意点
転職した場合は、前の勤務先から源泉徴収票をもらって、それを現在勤めている勤務先に提出すれば、会社で年末調整の時にすべて合算して調整してもらえます。
ただし、転職するまでに自分で直接支払ったものがある場合は、保険料控除申請書に支払い金額を記載して勤務先に提出しなければなりません。
添付書類の社会保険料控除証明書を紛失した時
国民年金・国民年金基金を支払っている人は、保険料控除申請書に、年金機構から送られてくる社会保険料控除証明書を添付する必要があります。
しかし、これを紛失した時は、年金機構に連絡すれば再発行してもらえます。
最寄りの年金機構の事務所に連絡すれば、2、3日後には郵送されてくるでしょう。
もし、急ぎで再発行してもらいたい場合は、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を持参して最寄りの年金機構の事務所へ直接取りに行けば、即日再発行してもらうこともできます。
年末調整と健康保険についての不明点

年末調整と健康保険について、実際に手続きを行うとよく分からないことが出てくるかと思います。
そこで、よく聞かれる不明点について解説していきます。
健康保険料を世帯主と世帯員で分けたい
健康保険料は、納付済額を上限にそれぞれの負担分に応じて控除を分けて申告できます。
しかし、納付額証明は、健康保険料の計算を世帯ごとに行っているため、発行してもらうことはできません。
そのため、控除額は自分で計算する必要があります。
12月までの支払金額を含めて申告できるか
健康保険料については、支払予定金額を含めて1月から12月までの支払金額で申告することができます。
しかし、実際に予定通り支払いができなかった場合、確定申告で確定した支払金額に修正しなければなりません。
まとめ
年末調整において、健康保険などの社会保険料は全額所得控除の対象となるため、正しく手続きを行えば所得税の納付額を減らすことができます。
基本的には会社がほとんどの手続きを行ってくれますが、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書や保険料控除申請書など、私たちが提出しなければならない書類もあります。
それらの書類と必要な添付書類を適切に準備・提出し、適正な所得税を納めることが、納税義務者たる私たちの責任といえるでしょう。
以上、年末調整と健康保険などの社会保険料との関係などについてひととおり解説させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。
少しでも皆様の年末調整への理解の一助となれたなら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。