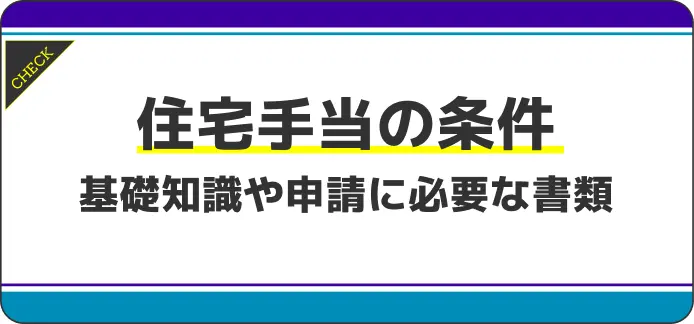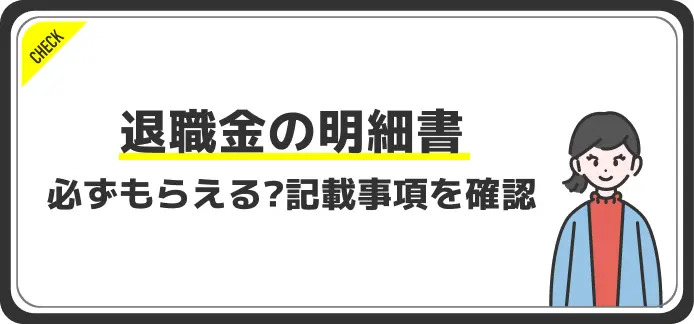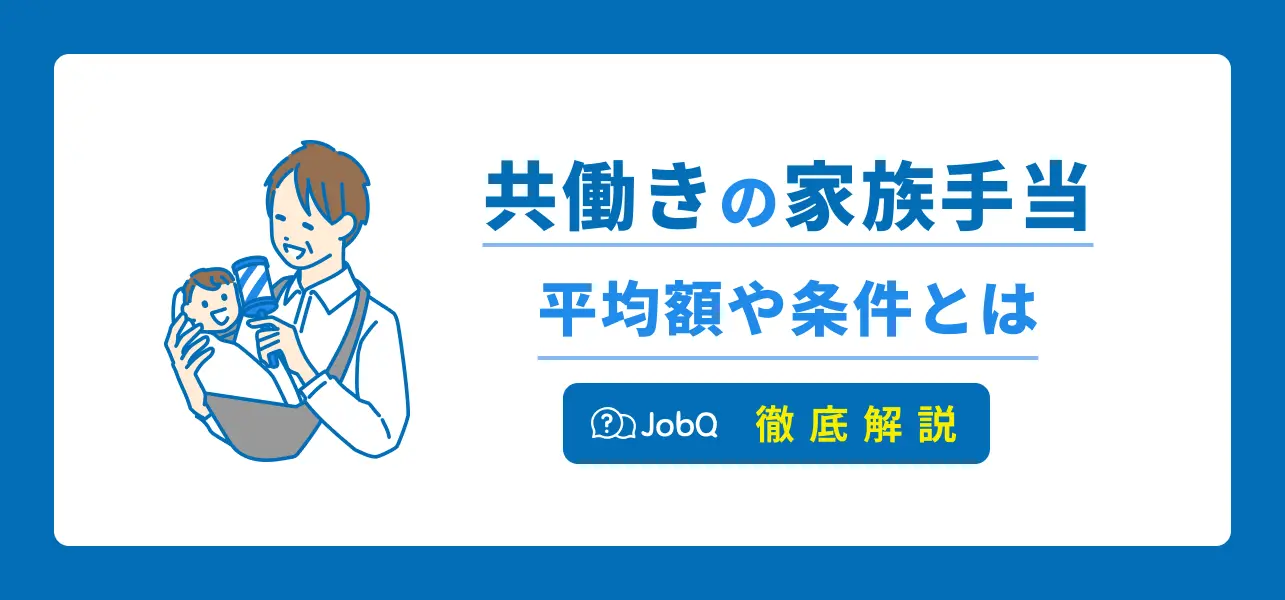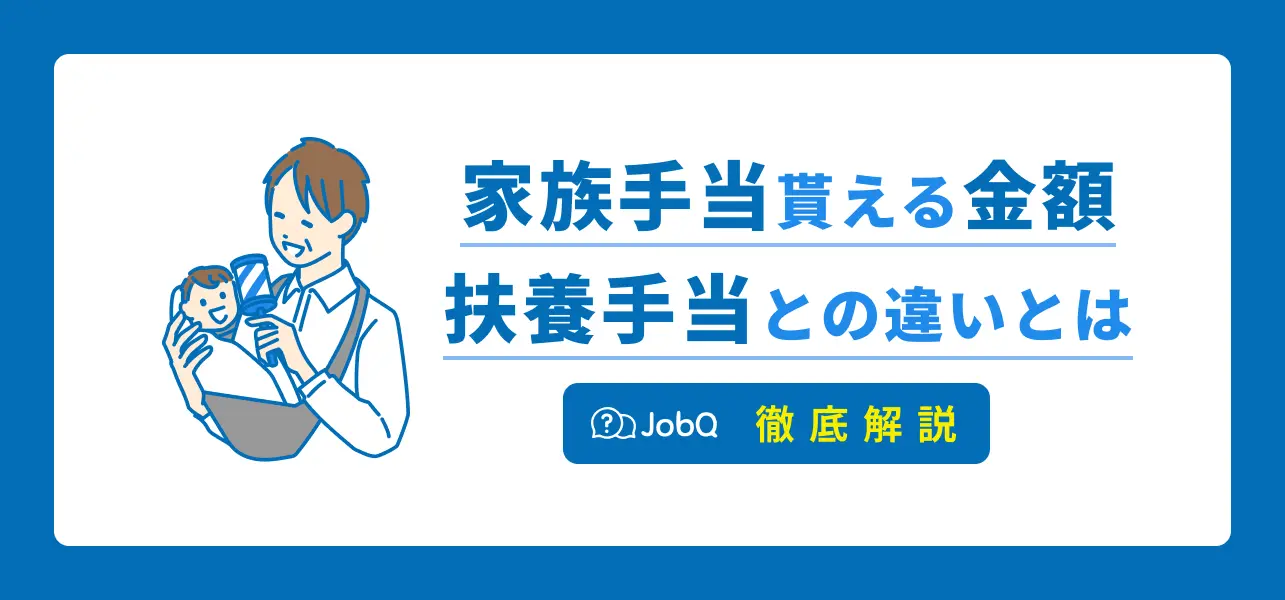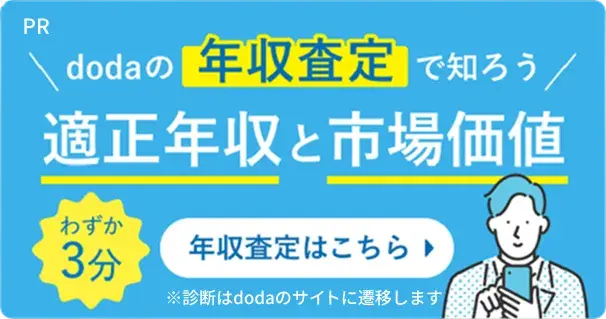【財形貯蓄とは?】確定申告や解約においての注意点などご紹介します
皆さん、「財形貯蓄」という制度があることをご存知でしょうか?財形貯蓄がどのような仕組みのものなのかという事を、詳しくご存知の方は少ないと思います。今回は一般財形貯蓄の解約についてや財形住宅貯蓄の解約についてなど、詳しくご紹介します。是非、ご参考にしてみてはいかがでしょうか?
財形貯蓄とは
財形貯蓄という制度があることをご存知の方は多いのではないかと思いますが、どのような仕組みのものなのか、という事を詳しくご存知ではない、という人もいらっしゃるのではないかと思います。
そもそも財形制度とは厚生労働省の所管である「勤労者財産形成促進法」の基づいて作られた制度で、簡単に言うと給料から一定の金額を天引きして、それを企業が契約している銀行に貯金するというものです。
なお公務員の場合は「共催組合貯金」という財形貯蓄と似た制度を利用することができます。
この財形貯蓄には貯めたお金をどのように使うかによって、3つの種類に分かれます。
ここではどのような貯蓄方法があり、どのような制度があるのかをご紹介します
一般財形貯蓄
お金の使用目的が特に定めの無い財形貯蓄です。
原則3年以上の積み立てをする必要がありますが、貯蓄が始まって1年経過していれば自由に出す事が可能です。
しかし、このように目的を定めずに自由に出す事が出来る反面、税金上での優遇処置が無く、利子に約20%の課税がされます。
財形住宅貯蓄
文字の表す通り、住宅の購入や建築、リフォームに必要な資金を貯める為の貯蓄です。
満55歳未満の労働者であれば利用する事が可能です。
一般財形貯蓄と大きく違うのは、財形年金とあわせた元本が550万円までは利息に税金がかかりません。
また、貯蓄期間は5年以上となっていますが、住宅のための使用であれば5年以内であっても貯蓄額を使用する事ができます。
ただし、住宅関連以外で貯蓄額を使用する場合は利息が課税対象となります。
財形年金貯蓄
こちらも文字の表す通り、老後の資金を作るための貯蓄となっています。
財形住宅貯蓄同様、満55歳未満の労働者であれば利用する事が可能です。
積み立て期間が5年以上ですが、満60歳以降で5年以上20年以内の受け取りとなっています。
こちらも年金目的以外の使用をすると利息が課税対象になります。
しかし、大きな病気の治療費など理由によっては非課税になることもあります。
一般財形貯蓄の解約について

転職や環境が変わることで一般財務貯蓄を解約しなければならない事も出てきますよね。
その場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか?
解約方法
解約の方法は2つあります。
1つは会社を通じて解約手続きを行う方法、もう1つは直接財形貯蓄を行っている金融機関で解約手続きを行う方法です。
どちらの方法を行うにしても、手続きに3日から5日程度の時間がかかってしまうことを理解しておきましょう。
解約するときには、銀行印、財形貯蓄の証書、運転免許証など顔写真つきの本人確認書類、貯蓄した金額を振り込んでもらう口座のわかるもの、などが必要です。
また、銀行によっては上記以外の書類が必要になる事もあるので、事前に確認をするようにしましょう。
解約にかかる税金
一般財務貯蓄に関してはもともと税に対して優遇はされていませんし、解約するからとそれ以上の税金がかかることもありません。
そのため、約20%の税金が利息に対してかかってきます。
解約の要件
解約の要件に対しては企業によって異なるのですが、積み立て期間が3年以上あり1年以上引き落とししていない事、などがあるようです。
解約前に会社に事前に確認しておくとよいでしょう。
財形住宅貯蓄の解約について

財形住宅貯蓄は一般財形貯蓄とは少し異なるものです。
では、解約するにはどのようにすればよいのでしょうか?
解約方法
解約方法は一般財形貯蓄と同じです。
書類等必要になるものがありますので、事前に確認をしておきましょう。
解約にかかる税金
財形住宅貯蓄は税金が優遇されています。
しかし、先に説明したように「目的外」の使用であれば税金がかかります。
これは解約でも同じ事です。
財形住宅貯蓄を解約する場合、直近5年間の利息に対して約20%の税金がかかります。
解約の要件
住宅関連以外の払い出しは全て財務住宅貯蓄払い出しの要件外になります。
積み立て期間などは企業によって条件が異なるので、確認するようにしましょう。
財形年金貯蓄の解約について

財形年金貯蓄は年金用ですから、人によっては受け取る前に解約する人も多いかもしれません。
ではどのように解約すればよいのでしょうか?
解約方法
解約方法は上記2つの財形貯蓄と同じです。
必要書類を事前に会社に確認するようにしましょう。
解約にかかる税金
財形年金貯蓄を年金以外で解約する場合、解約利子の課税だけでなく過去5年間の利息に対して約20%の税金がかかります。
しかし、大きな病気にかかった場合の治療費、災害にあったときの治療費や住宅の修繕費などやむを得ない事情がある場合は非課税になる場合もありますので、解約時に解約理由と共に確認をするようにしましょう。
解約の要件
先に記載をしましたが、年金目的以外でも非課税の範囲が広がっているので、解約時に会社や銀行に確認をするとよいでしょう。
また、財形年金貯蓄は他の財形貯蓄よりも解約に日数がかかる事がありますので、事前に確認する事が大切です。
財形貯蓄の解約においての注意点

では財形貯蓄を解約するときに注意しなくてはいけないことはどのようなものはあるのでしょうか?
確定申告は必要か
給料以外の所得があると確定申告をする必要があることが多いですよね。
しかし、財形貯蓄については所得税が引かれたあとの給料からの貯蓄のため、確定申告をする必要はありません。
財形の引き継ぎ
転職するから財形貯蓄を解約しなければいけないのか、と思われる方が多いのではないか、と思いますが、転職先の会社で財形貯蓄を引き継ぐ事はできます。
しかし、2年以内の転職であること、転職先でも財形貯蓄を行っている事、といった条件をクリアしていなければなりません。
会社を辞めた後転職するまでに2年以上たってしまうと解約手続きが複雑になってしまうので、転職先に財務貯蓄がないのであれば早いうちに解約手続きを行うほうがよいでしょう。
利息に対しての税金
先にもご説明しましたが、一般財形貯蓄以外の財形住宅貯蓄や財形年金貯蓄は解約すると利息に約20%の税金がかかってしまいます。
しかし、100万円の元本に対して200円程度の税金がかかる程度なので、それほど帰任する必要はないのではないかと言えます。
まとめ
いかがでしたか?
財形貯蓄は解約するのに書類手続きやお金を受け取るまでに日数はかかりますが、利息にかかる税金は大きくありません。
もしもどうしてもお金が必要になった場合には、財形貯蓄を解約したり引き出すことを検討してもよいのではないでしょうか?
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。