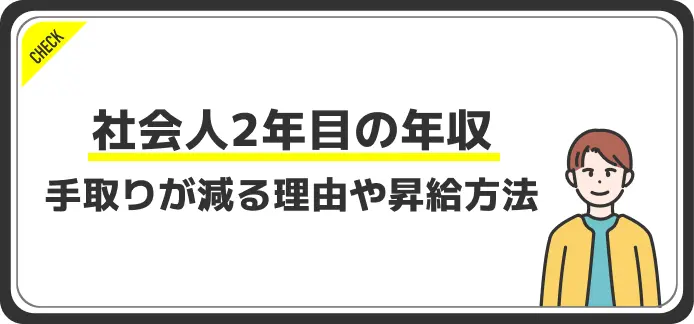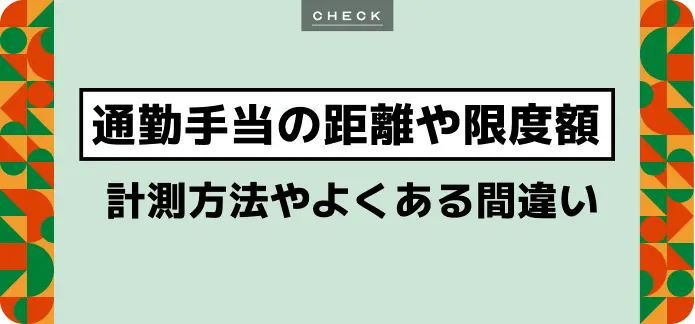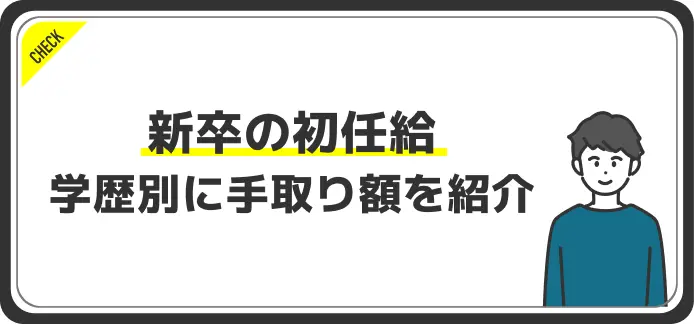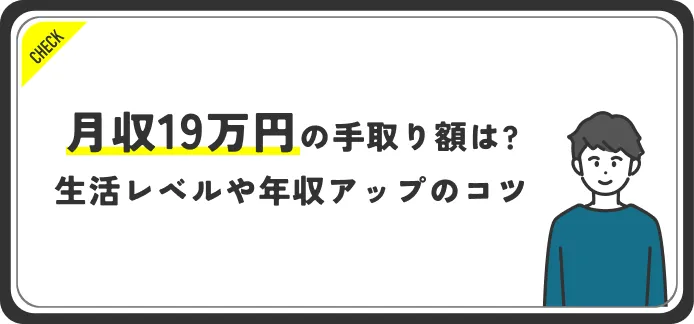【通勤手当の規定について】細則や決め方、見直しや注意点などをご紹介
通勤手当の支給は企業の任意ですが、通勤手当を支給する際には規定を定めておくと、トラブルの回避や不正受給の防止に役立ちます。この記事では、通勤手当の規定について説明し、通勤手当規定の決め方や見直しの方法についても解説します。ぜひご一読ください。
通勤手当の規定と細則
通勤手当の規定や細則とはどういったものなのでしょうか。また、企業は通勤手当の規定や細則を絶対に定めなければいけないのでしょうか。ここでは、通勤手当の規定と細則について解説します。
通勤手当の規定とは
通勤手当の規定は企業が自由に定めることができ、企業が定めた通勤手当の規定は就業規則や賃金規程に記載して、従業員に周知させることが必要です。従業員は企業が定めた通勤手当の規定に則って通勤手当の申請をすると、通勤手当が支給されます。
通勤手当の規定を定めなくても法的には全く問題はありませんが、通勤手当の規定を定めておくと労務管理や経理処理が楽になるため、多くの企業では通勤手当の規定を定めています。
通勤手当の細則とは
通勤手当の細則とは、通勤手当の規定をより細かく明記したもので、主に、公務員の通勤手当を決める際の基準になります。民間企業では通勤手当の規定を定めても、細則までは定めないケースが多いですが、通勤手当の細則を定めておくと、トラブルの回避や通勤手当の不正受給の防止にもつながります。
通勤手当の細則の様式などは特に決まりはなく、どのような様式であっても細則として認められます。
通勤手当規定の決め方と見直し

通勤手当の規定は企業が自由に決めることができます。通勤手当を支給する際には必ずしも規定が必要ではありませんが、規定を策定しておくことが望ましいです。ここでは、通勤手当規定の決め方と通勤手当規定の見直しについて解説します。
通勤手当規定の決め方
通勤手当の規定は労働基準法などの法律によって規制されておらず、通勤手当の規定は企業が自由に定めることができます。よって、通勤手当の規定の決め方は企業によって違いがありますが、通勤手当の支給は通勤手当規定に基づいて行われます。
通勤手当規定を決めると、規定の内容を就業規則に記載することが必要です。従業員は就業規則を確認すると、通勤手当がどのような方法で支給されるのかがわかりますので、過失による通勤手当の不正受給を防げます。
通勤手当規定の見直し
税制改正が行われた時などは、通勤手当の規定を見直すことが必要になります。平成28年度の税制改正で通勤手当の非課税限度額が引き上げられましたので、もし、通勤手当の規定を見直していない場合は、早急に規定を見直すことが必要です。
従業員に対する福利厚生を改善する場合も、通勤手当の規定の見直しが行われることがあります。通勤手当の規定を見直した場合は、就業規則に記載して従業員に周知させるようにします。
アルバイトに対する通勤手当規定

アルバイトに対する通勤手当規定はどのようにして決めるのでしょうか。ここでは、アルバイトの通勤手当の決め方を解説し、アルバイトの通勤手当で大きな問題になる勤務日数に対する考え方についても言及します。
アルバイトの通勤手当の決め方
アルバイトの通勤手当の決め方は、働き方改革関連法案の施行により、「同一労働同一賃金」で正規社員との格差是正を考慮することが大事になってきます。通勤手当は賃金に含まれますので、「同一労働同一賃金」になるようにアルバイトの通勤手当を決め、就業規則に規定を記載するようにします。
ただし、アルバイトに対して通勤手当を必ず支給しなくてはならないという決まりはなく、アルバイトに通勤手当を支給しなくても違法ではありません。しかし、有能な人材を確保するために、多くの企業ではアルバイトに対しても通勤手当の支給を行っています。
アルバイトの勤務日数に対する考え方
正規社員と同じようにフルタイムに近い勤務をしているアルバイトに対しては、正規社員と同じ方法で通勤手当の支給額を決めるようにします。なお、勤務日数が正規社員よりも大幅に少ないアルバイトに対しては、勤務日数に応じて通勤手当の支給額を決めても問題ありません。
なお、アルバイトに通勤手当を支給する場合には、正規社員と同じ基準で非課税限度額が決定します。電車通勤やバス通勤の場合は1ヶ月あたり15万円が非課税限度額になるため、通勤手当の金額が1ヶ月あたり15万円以下の場合だと、通勤手当は全額非課税になります。
通勤手当規定の注意点

企業が通勤手当規定を定める際には、いくつかの注意点があります。ここでは、通勤手当の規定を定める際の注意点と、通勤手当と労災との関係について説明します。
通勤手当申請内容決め方の注意点
通勤手当の支給は労働基準法などの法律では規定されておらず、通勤手当を支給するかどうかは企業が自由に決められます。通勤手当の規定の内容も企業が自由に決められますが、労働者が極めて不利になるような事項を規定するのは禁止です。
通勤手当の規定を定める場合は、マイカー通勤を許可するかどうかを決めることが大切であり、非課税の限度額を考慮して支給額を決めるようにします。
通勤手当の規定はできる限り細かく定めることが望ましく、規定を細かく定めておくと労使紛争や通勤手当の不正受給を未然に防げるようになります。
通勤手当規定と労災との関係の明確化
マイカー通勤やバイク通勤、自転車通勤は、通勤中に交通事故に遭うリスクがあるため、通勤手当の規定には労災との関係を明確にしておくことが必要です。
企業にとっては、電車やバスなどの公共交通機関を使って通勤することが望ましいですが、交通利便性が悪い地域だと、マイカー通勤を許可しないと通勤に支障が出ることがあります。マイカー通勤を認める場合は、できるだけ細かく通勤手当の規定を決めておくと、通勤中のケガなどにも迅速に対応できるようになります。
まとめ
企業が通勤手当の支給を行う際には、通勤手当の規定を定めておき、規定に基づいて支給額などを決定します。
規定の内容は就業規則に記載して、従業員に対して周知させることが必要です。細則は規定をさらに細かくしたもので、細則を策定しておくと、労使間のトラブルの回避や通勤手当の不正受給の防止などに役立ちます。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。