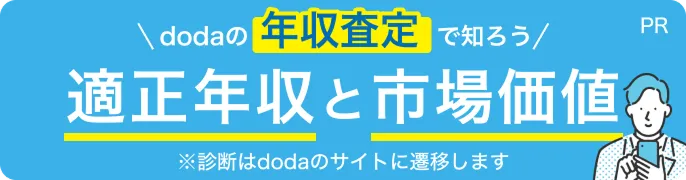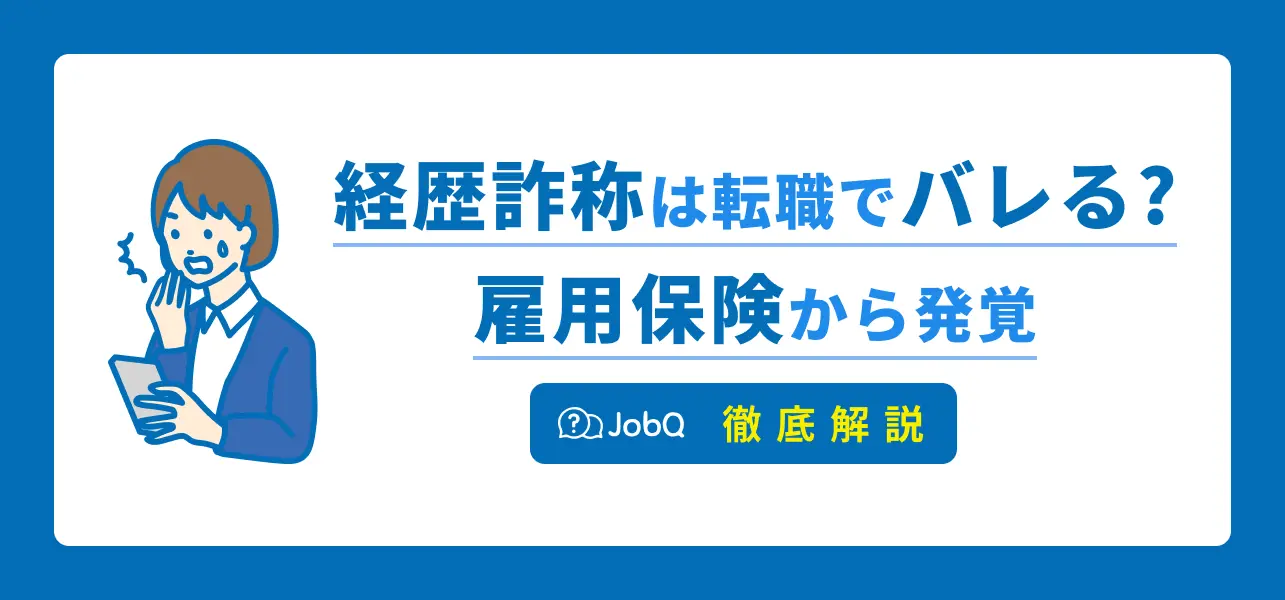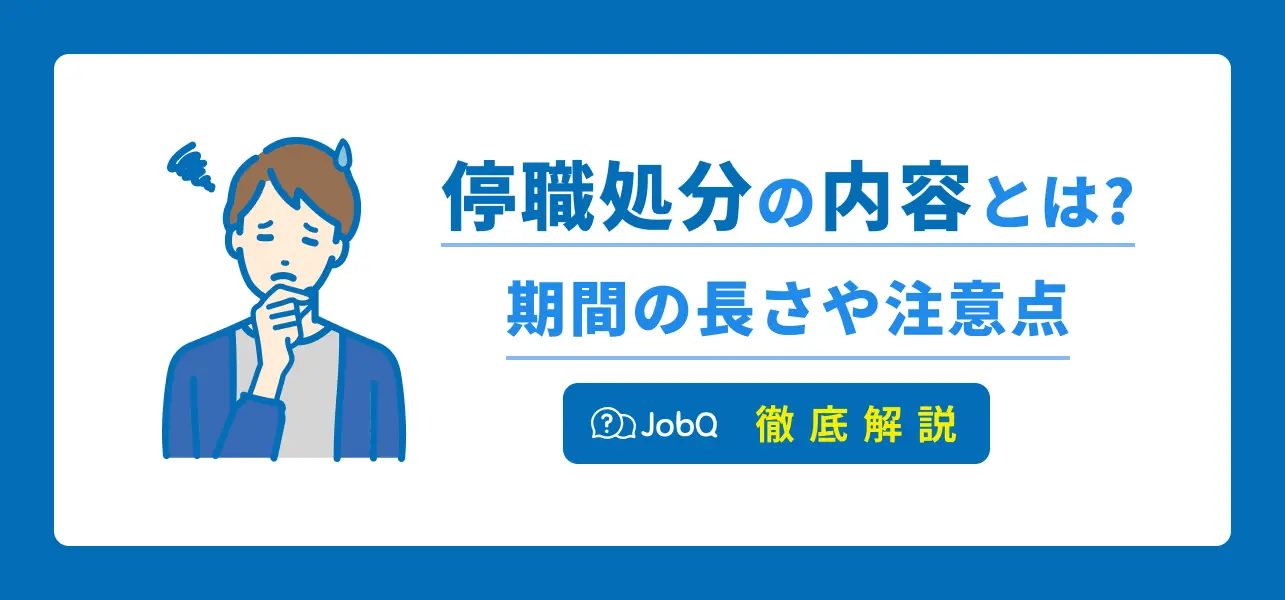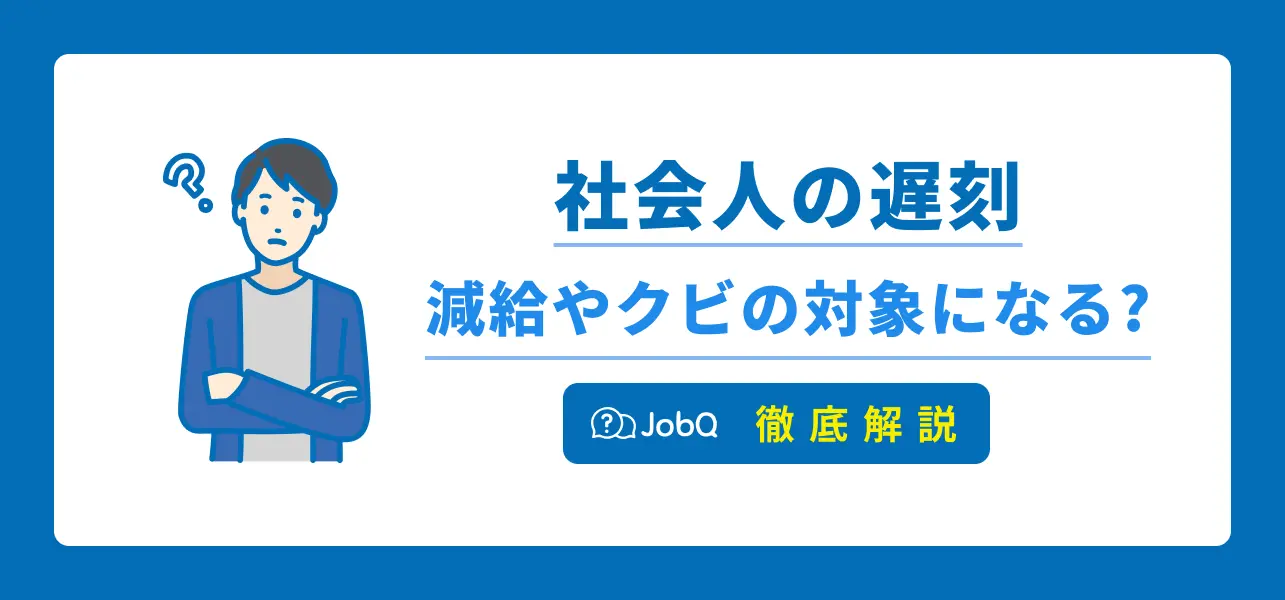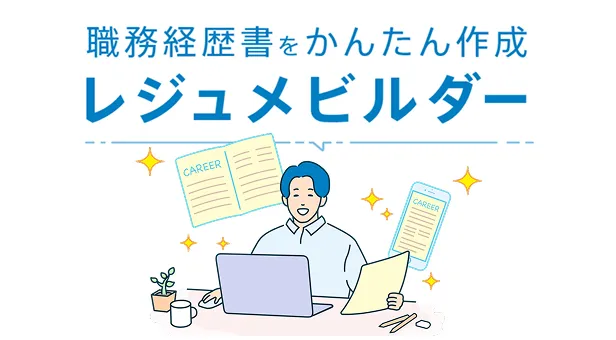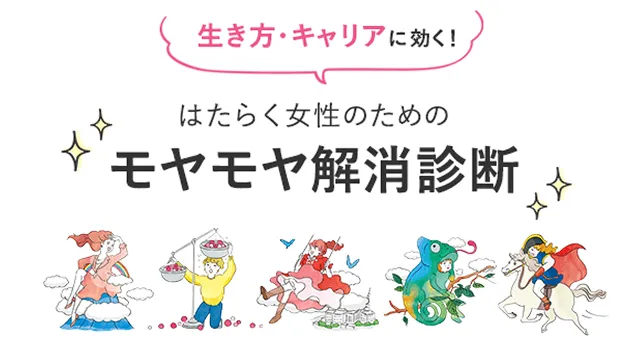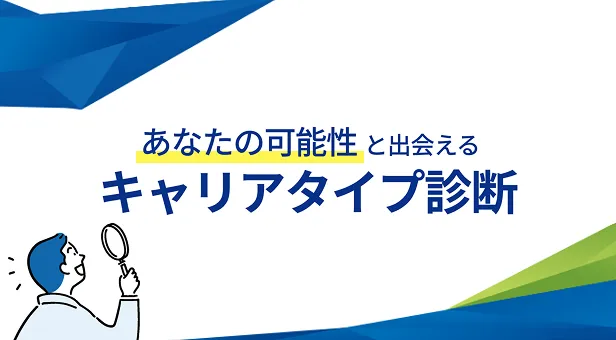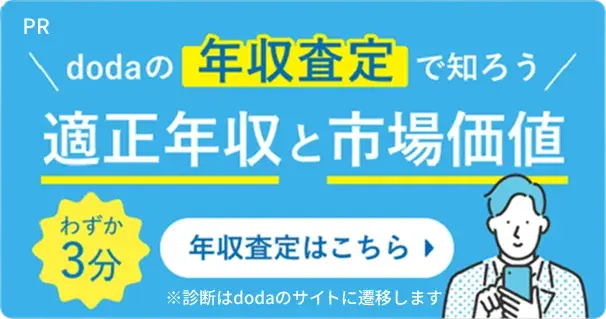【解雇後の手続き】11日以内にやらなければいけないことって?
皆さん、解雇後の手続きについて詳しくご存知でしょうか。この記事では、従業員解雇後の手続きの流れや、解雇に関する基本的な考え方などご紹介致します。また、解雇予告や、従業員を辞めさせる方法についても解説致しますので是非参考にしてみてはいかがでしょうか。
従業員の解雇について
人事の方は自社の従業員には長期的に就労して欲しいと思うものです。
その一方で成果を出さない、また他の従業員に悪影響を与える従業員に対しては会社を辞めて欲しいと思うことでしょう。
しかし、従業員を辞めさせることは簡単ではありません。
では、そういった社員にどのように辞めてもらうのか、解雇できるのか本編では説明いたします。
従業員の解雇について
まずは従業員の解雇に関して基本的なことを説明いたします。
解雇に関する基本的な考え方について
大前提として労働者を簡単には解雇することはできません。
解雇するためには相応の理由が必要であり、合理的な理由なく解雇することは法律上認められません。
実際労働契約法には解雇に関して以下のように記されています。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。(労働契約法16条)
従業員の解雇にはかなり高いハードルが設定されているということをまずは理解しましょう。
解雇規制について
また、労働契約法以外においても男女雇用機会均等法などで以下のような理由での解雇は認められていません。
- 労働者の国籍、宗教または社会的身分を理由とした解雇
- 労働者が業務上での負傷し、または疾病を理由とした解雇
- 女性労働者の結婚出産に関わる解雇
- 性別による解雇
- 正当な労働組合活動を理由とする解雇
- 労働基準監督署等への申告を理由とする解雇
あらゆる法律で労働者の立場は守られているのです。
解雇の種類について
一口で解雇と言っても解雇には色んな種類があります。
具体的には以下のとおりです。
- 普通解雇
普通解雇は、後続で説明する整理解雇および懲戒解雇以外の解雇のことを指します。
普通解雇が認められる場合は著しく悪い勤務成績、健康上の理由、著しく協調性を欠くふるまいが見られるなどという状況が挙げられます。
- 整理解雇
整理解雇は、会社の経営悪化などにより人員整理を目的にした解雇のことを指します。
整理解雇には、整理解雇することの妥当性、整理解雇の回避に最大限の努力、解雇対象者が合理的な選定、および労使間の十分な協議が揃ってはじめて認められます。
- 懲戒解雇
懲戒解雇は、従業員が極めて悪質な規律違反や犯罪行為などを行った際に行う懲戒処分です。
懲戒解雇を行うためには、就業規則や労働契約書にその解雇要件を明記することが求められます。
従業員解雇後の手続きについて
従業員を解雇した場合、ただ辞めさせたら良いというものではありません。
本章では解雇後の手続きについて説明をいたします。
従業員解雇後の手続きの流れについて
従業員を解雇した場合やらなければならないことは、以下の通りです。
- 雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書をハローワークに提出
- ハローワークから送られてきた離職票を解雇した従業員に渡す
この一連の対応を遅滞なく行います。
解雇後のハローワークでの手続きについて
会社を解雇された労働者は失業保険を受けられるようにするため、会社は解雇してから11日以内に雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書をハローワークへの提出することが必要となります。
雇用保険被保険者資格喪失届は雇用保険の加入者、すなわち失業保険の支給対象者だということハローワークに届け出るための文書です。
これがないと、ハローワーク側が失業保険の支給対象者だと認識することができないため、失業者が困ってしまいます。
会社を退職したことを早急に証明したいとき、例えば国民健康保険への切り替えや、転職先の会社に提出する時に使います。
また、失業保険の支給金額やタイミングを決めるため、離職証明書についても提出することになります。
そして、受理されたらハローワークより、離職票が発行されるということになるのです。
解雇後の社会保険の手続きについて
解雇する際は、失業保険関連の手続きだけではありません。社会保険関連の対応もまた必要となります。
では、どのようなことをしなければならないかというと、以下2点となります。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を年金事務所へ提出する。
- 資格喪失証明書を従業員に渡す
すなわち、会社加入の厚生年金保険や健康保険から国民年金保険に加入するための一連の対応が必要になるということなのです。
解雇予告について
解雇をする際は、原則解雇予告を行います。
では、解雇予告に関してお話をいたします。
労働基準監督署による解雇予告除外認定について
上述の通り、従業員を解雇をする際は解雇予告が必要となります。
ただし、労働基準監督署長から解雇予告除外認定を受けることができれば、その限りではありません。
犯罪、風紀違反、無断欠勤、など従業員の責に帰すべき理由があった場合解雇予告除外認定なしでも解雇できる場合もあります。
解雇予告を行う場合は?
従業員の解雇を行うときには、解雇予定の従業員に対し、30日前までに解雇予告をし、次の仕事を探すまでの猶予を与えることが必要です。
辞めさせたいからすぐ辞めさせるは原則不可能です。
解雇予告を行わない場合は?
もし、解雇の予告を行わずに解雇する場合には、解雇予告手当として30日分の賃金を支払う必要があります。
また、解雇予告までに30日に満たない時は、その不足日数分の賃金が解雇予告手当として必要です。
解雇予告には猶予か相応の手当が必要なのです。
従業員を辞めさせる方法について
会社を解雇させるのはハードルが高いので、自らが辞めさせるというのも、1つの手です。
では、どうすればそのような段取りを作ることができるのかを最後に説明いたします。
従業員にノルマをつくることについて
従業員を辞めさせるためにはノルマを与え、ノルマの達成状況に対してモニタリングし、達成できない状況にあれ口頭注意を行っていきましょう。
このようにすることにより、辞めさせたい社員にプレッシャーをかけることができ、退職理由を作るきっかけもできます。
目標やノルマを設定するというのは社員を辞めさせるためのきっかけ作りになりますし、それでその従業員が変わるきっかけになればいうことはありません。
目標設定は色々な意味で重要です。辞めさせたい従業員には厳しく目標設定をしましょう。
従業員に指導書を渡すことについて
もし、設定した目標に対して、達成できていないのならば、指導書を発行します。
そうすることにより、退職させるためにちゃんと段取りを踏んで、いきなりクビにしたことではないと分かるように、また普通解雇要件に該当させるようにするというのが大事です。
また、指導書を会社からもらうことで、従業員はさらなるプレッシャーを感じることになります。
なかには、そのプレッシャーに耐えかねて退職するきっかけにもなり得ます。
目標を設定するだけではなく、モニタリングし、だめだったらダメでしたという形を残しておくことが重要だと言えるのです。
従業員の減給または配置転換をすることについて
成果が出せないのたなら、雇用は守るけど給与は下げる、また配置転換をしていくということを行うのも手です。
給与を下げられるというのは、労働者にとってダイレクトな問題です。
そのため、退職の意思決定の促進に進みます。
ただし、いきなり行ってはいけません。あくまでも指導をし、それを形にしたうえで行うという手順を踏むことが大事だと言えます。
まとめ
解雇は簡単にはできません。それ相応の理由が必要になります。また、手順も踏まなければなりません。
そのため、解雇をするより、時間をかけて退職してもらうほうが良いです。
従業員に辞めてもらうことは精神的にも厳しいですし、恨みも買います。
それよりも自らの意思で辞めてもらうようサポートし、新しい場所で輝いてもらうほうが重要であると言えるのです。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。