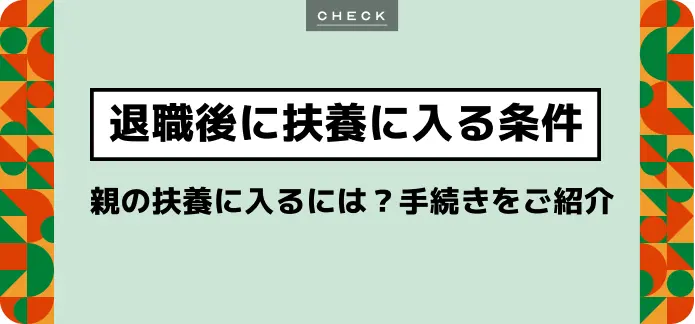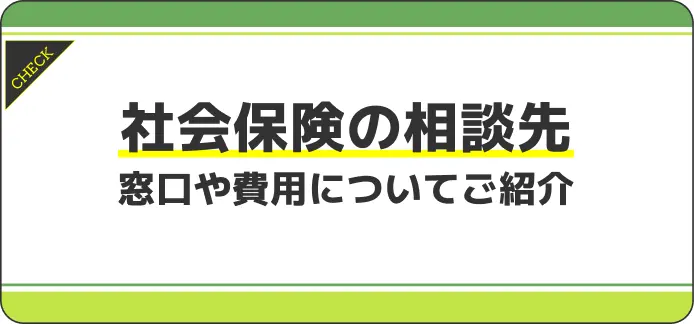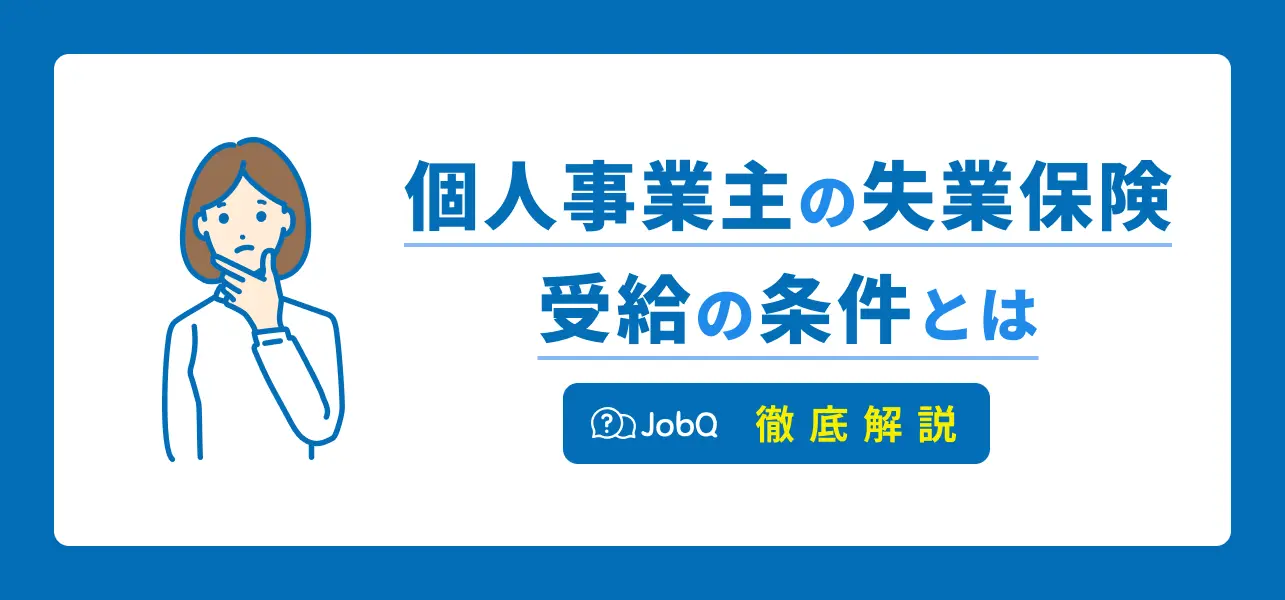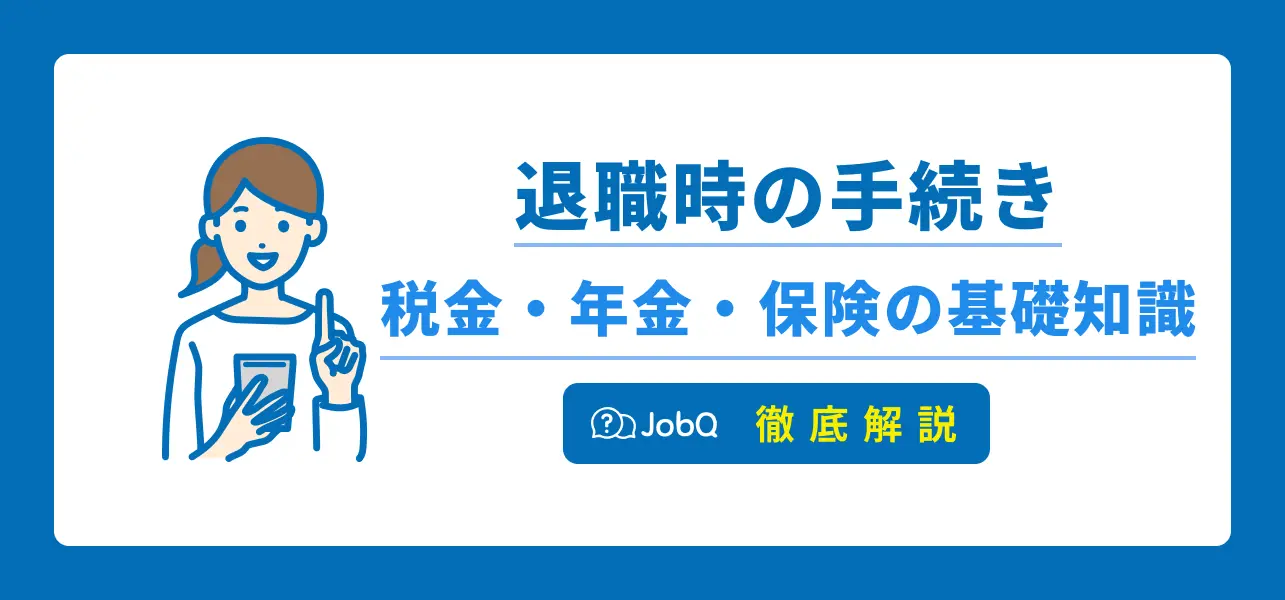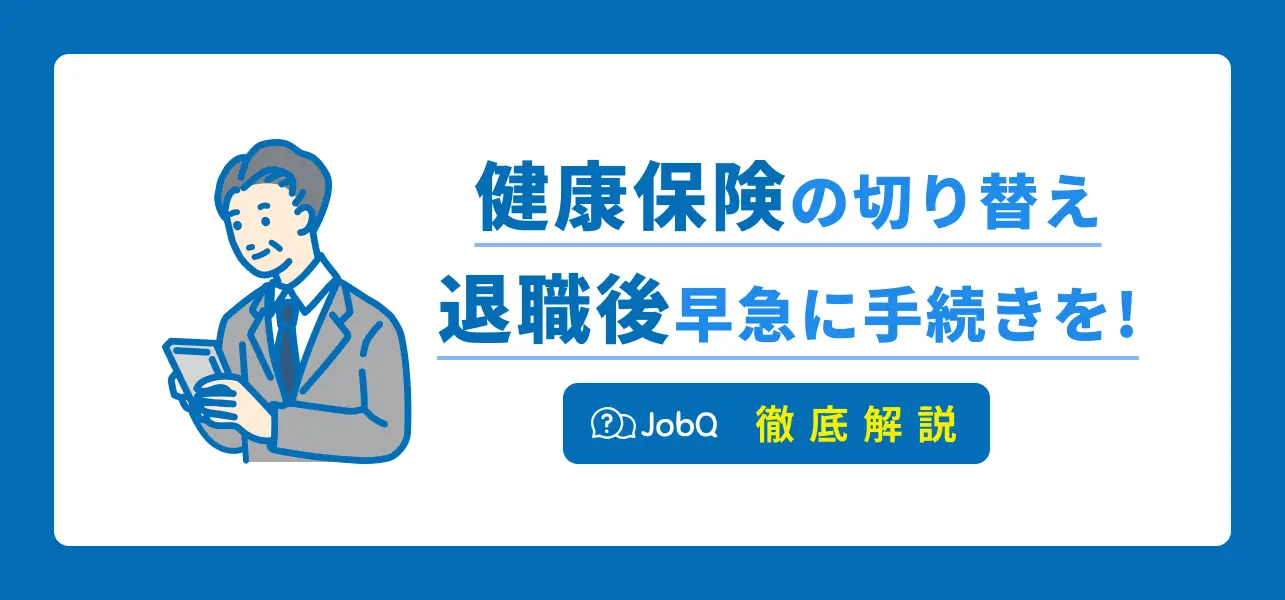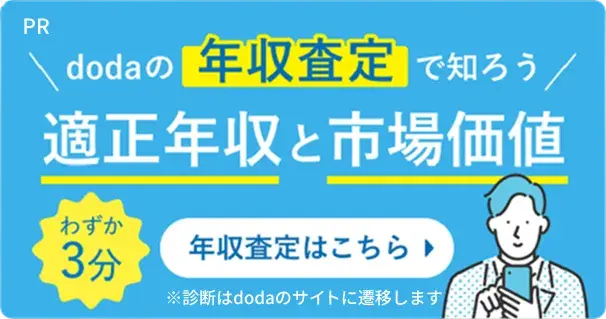【海外の年金制度について】日本との比較や代表例についてご紹介
老後の生活を考える上で、最もポイントになるのが「お金」の問題です。そして、老後のお金の重要な柱となるのが、「年金」といえるでしょう。今回は、日本の「年金制度」と海外の「年金制度」を比較して、どのような違いがあるのかご紹介していきます。まずは、日本の現状について確認してみましょう。
日本と海外の年金制度を比較すると
高齢化が進む現代、そして「人生100年」ともいわれるようになり、定年といわれる年齢からその先、どのように生計を立てていくか、つまり「老後のライフプラン」への意識は社会全体としても高まりをみせています。
老後の生活を考える上で、最もポイントになるのが「お金」の問題です。
そして、老後のお金の重要な柱となるのが、「年金」といえるでしょう。
今回は、日本の「年金制度」と海外の「年金制度」を比較して、どのような違いがあるのかご紹介していきます。
まずは、日本の現状について確認してみましょう。
世界の年金指数ランキングの上位10位は?
日本のように、世界各国でも年金制度と同等のものがあり、国民の生活が守られています。
そこで、年金の持続性や十分性、そして健全性を指数として数値化し、世界における年金制度を評価しランキングすることが可能です。
世界ランキング上位に日本は入っているのでしょうか。次が、その世界の年金指数ランキングです。
第1位 デンマーク
第2位 オランダ
第3位 オーストリア
第4位 フィンランド
第5位 スウェーデン
第6位 スイス
第7位 シンガポール
第8位 カナダ
第9位 チリ
第10位 アイルランド
指数としては、トップのデンマークで80、10位のアイルランドで62、その比較として、日本は43.2とトップのほぼ半数で、ランキングは27カ国中26位と持続可能かどうかが困難とされる域と評価されているのです。
日本と他のG7国の違いはどこにある?
日本の年金制度と他の先進国であるG7国(アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、日本)と比較すると、どのような違いがあるのでしょうか。
最大の違いは、年金支給条件となる支払い義務期間にあり、日本は7カ国の間で最も長い支払い期間である25年と設定されていました。フランスでは支払い義務期間はなく、ドイツは5年、アメリカ・イギリス・カナダで10年、イタリアで20年です。
また、日本では年金は全国民が強制加入となっていますが、他6カ国では被雇用者もしくは自営業者、つまり働いている人のみが強制されています。
先の見通しが暗い現在の日本の状況
少子高齢化が進み、かつ平均寿命が延びていることから、年金受給開始年齢の引き上げが検討されているだけではなく、現状でも若年層の貧困化が深刻化しており、年金の未納率が上がっていることから、年金制度そのものが破綻することも想定されています。
政府としても、個人ベースで老後へ向けての貯蓄などを推奨するなど、日本という国が提供する年金制度は見通しがくらいといわざるを得ません。
日本の年金制度と海外

ここでは、日本の年金制度に対する海外の反応と、海外移住した場合の年金受給について確認してみましょう。
日本が年金の運用で出した大損失に対する海外の反応
2015年の公的年金積立金の運用成績が5兆円を超える損失と発表され、国民年金と厚生年金の運用方法を疑問視する声が一気に加熱しました。
この巨額の運用損失に対しては、海外から、日本政府の政権を問題視する声や、投資というギャンブルまがいの運用法を指摘する声、さらには、もはや日本の年金制度に頼ることをやめ、個人での貯蓄や資金運用を考えるべきだという声が上がっています。
海外移住をしても日本の年金をもらうには?
海外移住をした場合でも、必要手続きをとれば日本の年金を受給することが可能です。
まず「海外転出届」を提出した後、現住所管轄の年金事務所で海外転居の旨を伝え、「年金の支払いを受ける者に関する事項」の用紙を受け取り、必要事項を記入し、必要書類と併せて提出すると手続きが完了します。
年金受給開始年齢に達した後は、自動的に支給されないので、自分で必要書類を年金事務所へ提出するという手続きが必要になります。
海外各国の年金制度その1

ここからは、海外各国の年金制度について確認していきましょう。
まずは、デンマーク・スウェーデン・ノルウェーについてご紹介します。
デンマークの年金制度について
デンマークの年金制度は、基本的に3層に分かれており、基礎年金となる税金でまかなわれる「国民年金」と就労者が義務としてかけている「労働市場付加年金」で、年金受給者にとってベースとなるものです。
それに加えて、「労働市場年金」と「個人年金」があり、「労働市場年金」は職種によって基準掛け率が定められ、給与から差し引かれて負担するもので、「個人年金」は年金金融機関などで個人的に掛けるタイプで、掛け捨てゼロという点がポイントです。
高い税金を負担することで、社会全体の福祉レベルが高くなる一例です。
スウェーデンの年金制度について
スウェーデンでは、年金は保険料を財源とする「所得比例年金」と税金を財源とする「最低保証年金」から成り立っています。
デンマークと同じく、税金を財源とする年金が存在することで、低所得者や所得がない場合でも最低限の生活が保証されるような年金制度があるということがわかります。
ノルウェーの年金制度について
ノルウェーの年金は大きく分けて3種類あります。
まず、公的年金としてのインカム年金および最低保障年金、そして企業年金、最後に個人年金です。最低保障年金は、税金を財源とし所得などに関係なく支給されるもので、それ以外が所得や職業によって掛け率の異なるもの、そして個人年金は個人で積み立てる形式のものです。
海外各国の年金制度その2

ここでは、フィンランド・オランダ・イタリアの年金制度について確認してみましょう。
フィンランドの年金制度について
フィンランドでは、基礎年金と厚生年金にあたる企業年金があり、基礎年金は税金が財源となっており、所得などに関係なく誰でも受給することが可能です。また、住宅手当も支給されるため、低所得者であっても、老後の生活は保障されます。
また、企業年金が一定額を超えると、基礎年金受給額が減額になるという仕組みです。
オランダの年金制度について
オランダの年金制度は、デンマークの制度と似ており、基礎年金・職域年金・個人年金の3層で積み立てられており、基礎年金と職域年金からの支給額で平均所得の8割程度となることからも、その水準の高さがわかります。
同時に、高齢化が進む中で、日本と同じく受給開始年齢の引き上げなどが実施されています。
イタリアの年金制度について
イタリアの年金制度は日本のものと酷似しており、基礎年金にあたるものはなく、就業している人は強制的に加入する必要があります。無職の場合は、加入する必要はありませんが、その代わり年金の受給資格を失うということになります。
無職や専業主婦の場合などは、条件を満たせば任意加入も可能で、加入すれば年金受給資格を得ることが可能です。
海外各国の年金制度その3

ここでは、オーストリア・アメリカ・韓国の年金制度について確認してみましょう。
オーストリアの年金制度について
オーストリアでは、職種や所得に関係なく、州によって定められた年金額が男性は65歳、女性は60歳から支給されます。
年金をもらいながら仕事を続けることも可能ですが、その場合は支給された年金も所得として換算され、課税されるという点を考えると、仕事を続けると、かなり年金受給額が少なくなるということになります。
アメリカの年金制度について
アメリカでは、就業している人(自営業を含む)のみが、社会保障制度となる年金への加入が強制されています。
10年以上の年金加入期間があれば、受給資格があり、受給開始年齢は、生まれた年によってそれぞれ異なるという特徴があります。
韓国の年金制度はどういうもの?
韓国では、年金は「国民年金」と「特殊職域年金」とがあります。「特殊職域年金」とは、公務員や軍人、国立学校職員など特定の職種の人が加入するもので、それ以外は「国民年金」に加入するというものです。
財源は双方とも、所得の一部から掛けられるもので、年金加入期間は10年以上の場合にのみ受給資格が与えられます。
まとめ
各国の年金制度を知ることで、日本での現状を改めて理解することができます。
これから先、日本人として日本で生活する上で、年金が生活を保障するものになるとは言い難い状態だということを理解することが、まず重要な第一歩であり、ここから個々がどのように対策し準備していくかを早い段階で考える必要があるのです。
まずは、自分自身の現状を確認し、そしてマネープランを長期的に考えることから始めましょう。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。