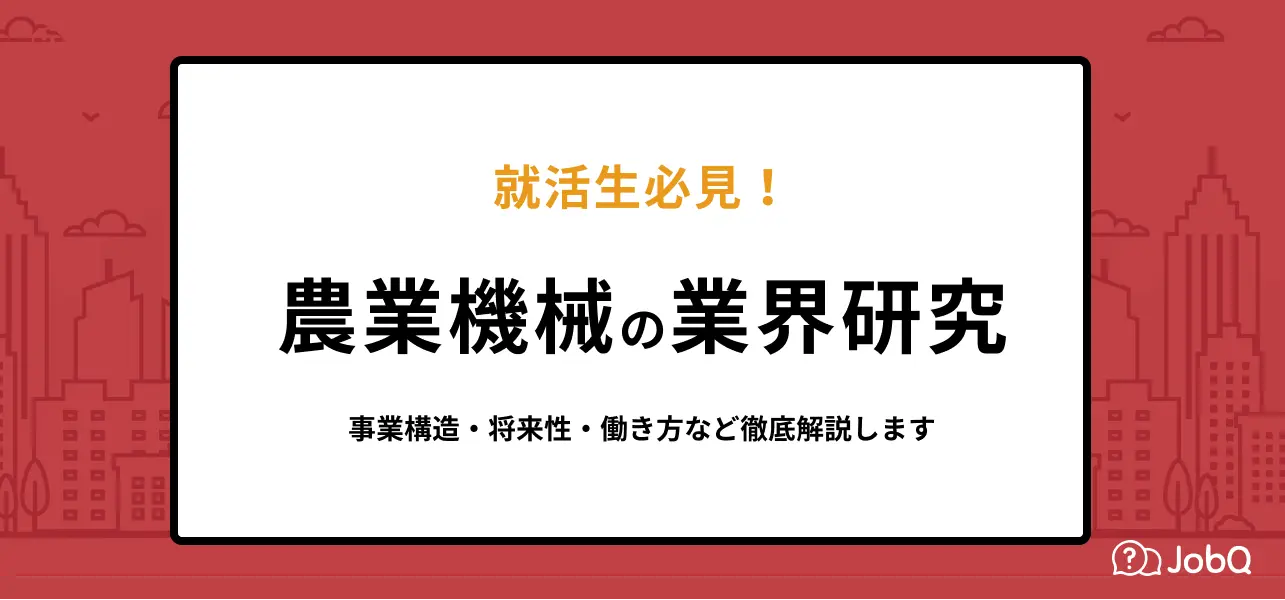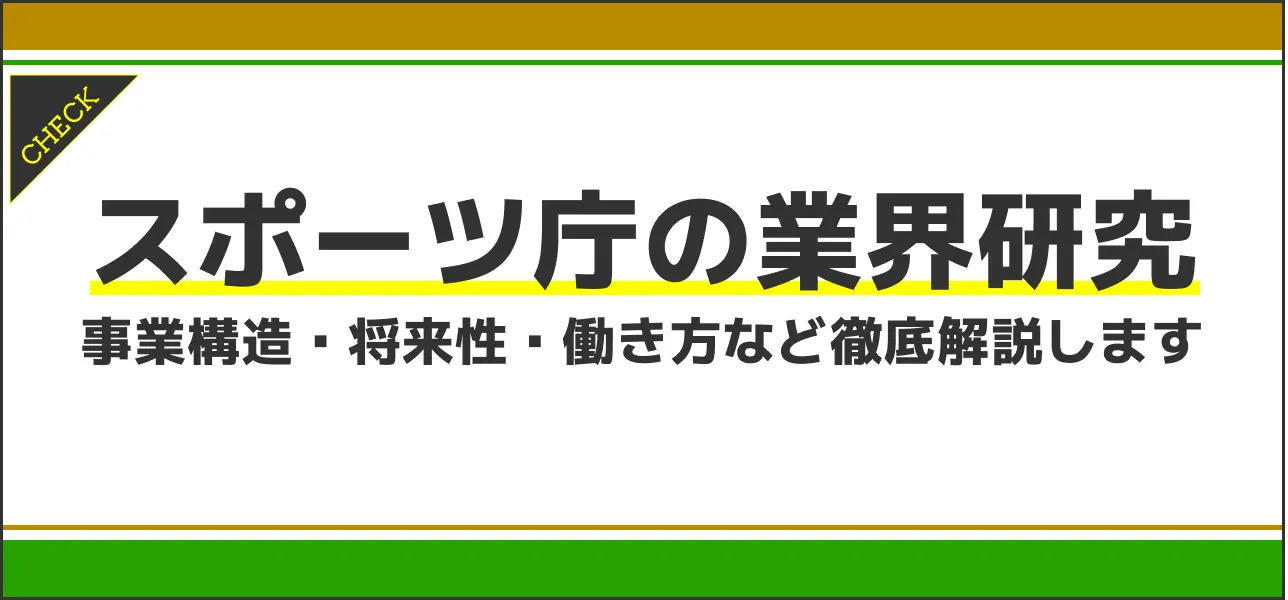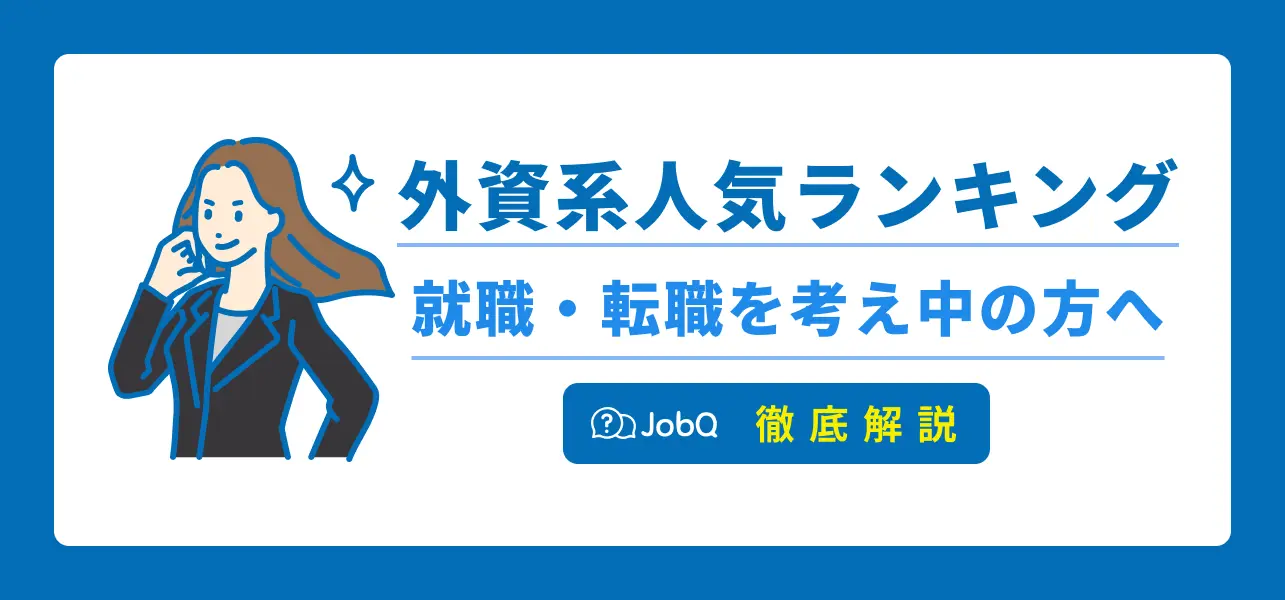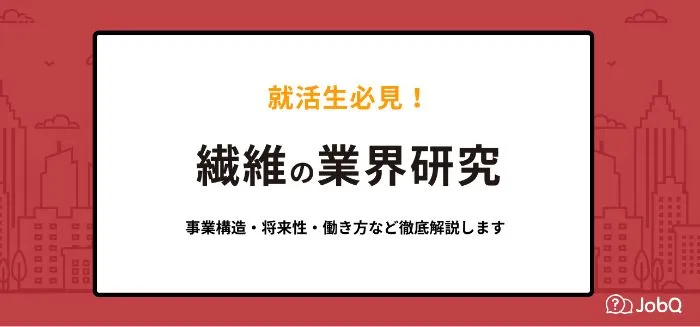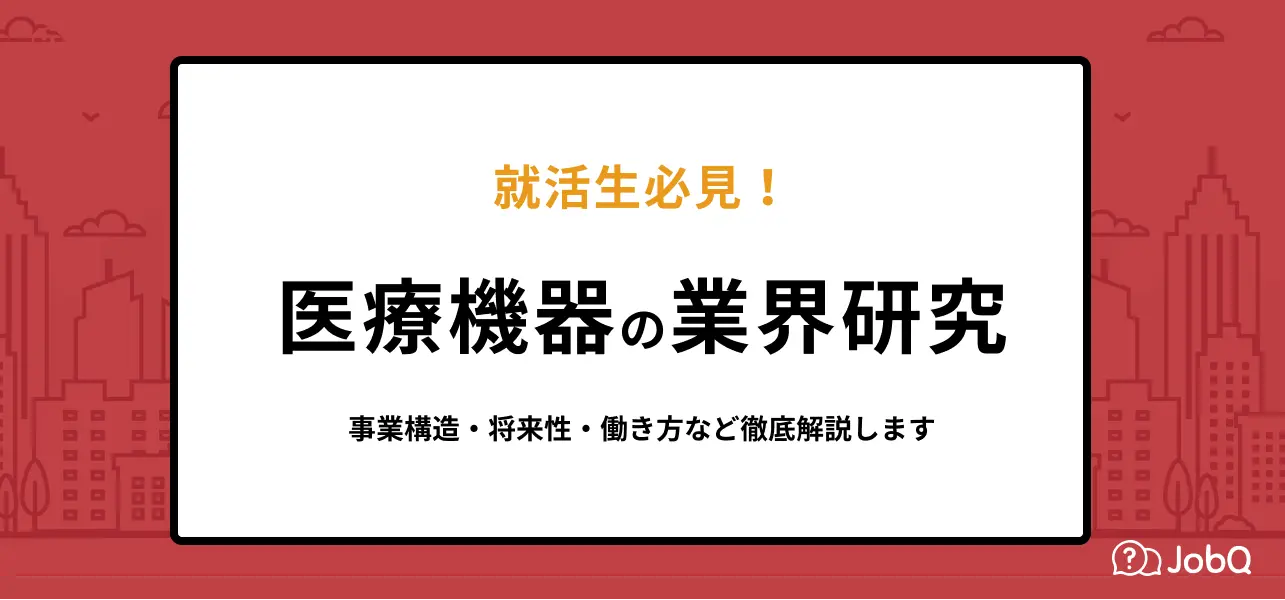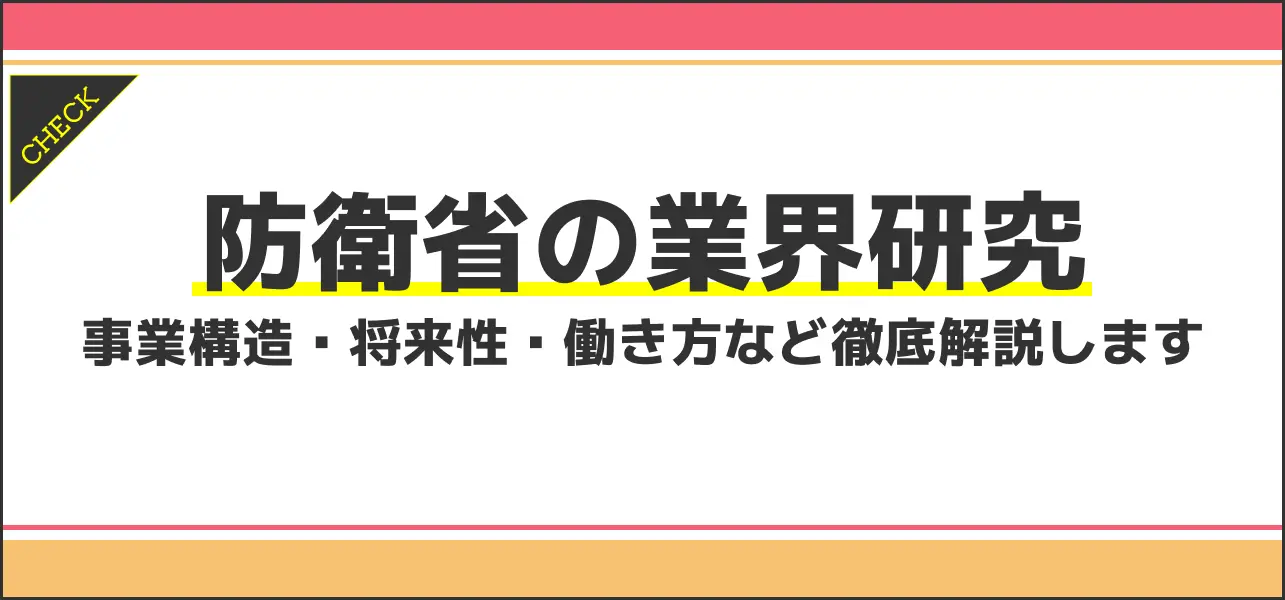
防衛省の業界研究|就活に役立つ事業構造・将来性・働き方など徹底解説します
防衛省は国政の根幹である国家安全保障を担当しています。日本を取り巻く安全保障環境が激変する中で防衛省の重要性が増しています。国防の最前線で活躍する防衛官僚を志望する学生は増えており、内定獲得の難易度も高まっています。この記事では防衛官僚を目指す学生に向けて防衛白書や防衛省の採用ホームページ、所管法令を参考にして、防衛省の業務や取り扱う政策について解説しています。
防衛省とは
防衛省は自衛隊の管理、運営、日米安全保障条約に係る事務など「安全保障」という国家存立の根幹を担う中央省庁です。
第二次世界大戦に旧日本軍は解体されましたが、その後の安全保障環境の変化に伴い、アメリカ主導の下で警察予備隊という形で軍事組織が復活しました。
1954年には内閣府の外局として防衛庁が創設され、2007年には防衛省へ移行しました。
戦争放棄及び"戦力"の不保持を定めた日本国憲法第9条のもと日本の国防を所管する行政機関であり、国家行政組織法3条および防衛省設置法2条に基づき内閣の統轄の下に設置されています。
防衛省設置法第三条に防衛省の任務について規定があります。
防衛省は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第二項から第四項までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同じ。)を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うことを任務とする。
現在、日本を取り巻く安全保障環境は様々な安全保障上の課題や不安定要因がより顕在化・先鋭化してきており、一層厳しさを増しています。
こうした安全保障上の課題や不安定要因は、多様かつ広範であり、一国のみでは対応が困難なため、安全保障上の課題等への対応に利益を共有する各国と地域・国際社会の安定のために協調しつつ積極的に対応する必要があります。
世界各国との安全保障協力、国際平和協力活動、大災害への対応、陸・海・空だけではなく、宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域においても求められる安全保障の取り組みなど防衛省が必要とされるフィールドは多岐にわたります。
防衛省職員は自衛隊の飛行場・港湾・駐屯地といった「防衛施設」の整備や戦車・護衛艦・戦闘機等といった「防衛装備品」の取得、関連する政策立案を任務とし、自衛隊の活動を支えています。
防衛省には様々な部局があり、安全保障環境を踏まえ、先進的な防衛政策を立案し、それを部隊編成、基盤整備、人事、地元自治体からの協力確保、諸外国との連携などに反映させています。
これらが機能的に結び付き、相互に緊密に連携を取りながら役割を果たすことで、防衛省は安全保障という大きな責任を果たしています。
防衛省の役割
安全保障政策の立案
国家間のパワーバランスが複雑に変化し、自らに有利な国際秩序を目指した国家間の競争が顕在化しています。
また、宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域の利用が急速に拡大し、これまでの安全保障のあり方は大きく様変わりしつつあります。
このような変化の激しい時代の中でも、日本の平和と安全を守るために防衛省では、日々必要な防衛政策を検討しています。
いわば日本の平和と安全を確保するためのグランドデザインを描き、 それを具体化する仕事です。
安全保障協力
日本や地域、さらには国際社会全体の平和や繁栄に寄与するめ、“FOIP”というビジ ョンを踏まえて、様々な国との防衛相会談、共同訓練、能力構築支援など二国間・多国間の防衛協力を戦略的に実施し、各国との関係強化に努めています。
加えて、海洋安全保障や宇宙・サイバー領域の利用に関する関係国との協力、国際平和協力活動などのグローバルな安全保障上の課題等に取り組むことで日本に望ましい安全保障環境を創出していきます。
多国間協力の中でも日米同盟は日本の安全保障の基軸の一つです。
また、地域や国際社会の平和と安定や繁栄にとっても重要な役割を果たしています。
変化の激しい時代の中で、日米同盟の重要性はますます増加しています。
防衛大臣と国防長官との会談のセッティングや、自衛隊と米軍の部隊の運用、装備・技術面での協力、宇宙やサイバー空間など新たな領域での防衛協力など、様々なレベルでの協力を推進しています。
アイデアと調整力・交渉力で一層同盟関係を一層強化します。
日本周辺の各種事態への対応
日本周辺では日常的に周辺国が情報収集や訓練等の軍事活動を活発化させており、防衛省は様々なレベルで日夜、これに対応しています。
平素から日本周辺で異常がないかなどを確認する警戒監視活動はもとより、北朝鮮による弾道ミサイル発射への対応、北朝鮮籍船舶による国連安保理決議で禁止されている洋上での物資の積替え(いわゆる「瀬取り」)への対応、中国機やロシア機などに対する緊急発進といった複雑化・多様化する脅威への対処など次々に生じる事態に迅速に対応しています。
防衛省の仕事内容
防衛装備調達
防衛省の外局である防衛装備庁では燃料や糧食、被服といった需品の管理を担当しています。
需品は自衛隊の運用や隊員の生活を支える重要な分野であり、整備の進捗状況や必要量の確実な確保などに常に気を配る必要があります。
日々の業務では、担当案件の背景や経緯を深く理解し、現状や課題を見極めることが求められます。
地に足のついた政策の企画・立案には正確な情報の把握が不可欠なため、時には基地等の現場に赴くなど、積極的に取り組むことが重要です。
防衛省のの調達事業部では、装備品の価格算定や契約などの調達業務を行っており、係員・係長での業務を通じて得た経験を踏まえ、決定が将来に与えるインパクトを考慮しつつ、俯瞰的な視点を持って仕事に臨んでいます。
武器調達官では、装備品のうち戦車や迫撃砲などを扱っています。
運用者である自衛官や製造者である企業から詳細を聞き取りつつ、 他国の動向やトレンドについて情報収集することで、担当する装備品について深く理解することができます。
防衛政策立案
防衛省防衛政策局は各課において「プロジェクトマネージャー」として政策を推進する存在です。
防衛省では情報本部や陸海空の各自衛隊が電波情報、画像情報などを収集するアセットを駆使して、日々情報収集に励んでいますが、 それぞれがバラバラに運用されては実効的な情報収集はできません。
したがって、情報の収集・ 分析と政策の立案・決定を橋渡しする防衛政策局調査課はインテリジェンス部局全体を見渡し、「不足している能力は何なのか」についてアンテナを張り巡らせ、新たな課題に対応するべく業務を行っています。
インテリジェンス部局の生み出すプロダクトは日本政府の意思決定や自衛隊のオペ レーションにおいて重要な役割を果たしており、防衛省でしか経験できない世界も広がっています。
安全保障環境がドラスティックに変化する中でインテリジェンス部局も常に進化し続けなければなりません。
自衛隊基地勤務
防衛省の総合職は3年目で様々な研修を受けます。
例えば、 同期が全国の陸海空自衛隊の司令部に散って、現場感覚を養います。
最前線部隊でも中央でもない場所だからこそ、見えるものがあります。
各司令部では防災業務で部隊運用を学びつつ、実任務や訓練、基地業務の現場にも赴きます。
指揮官から作業員に至るまで、自衛官の物の見方を全身で感じる貴重な時間です。
また、同期が防衛研究所に集まって、安全保障理論などを学ぶ機会もあります。
座学に近いものですが、2年間実務を経験した身で理論を学ぶことは安全保障感覚の形成に大きなインパクトがあります。
防衛省の組織図
防衛装備庁
防衛装備品の適切な開発、生産、維持整備は日本の安全保障上、極めて重要です。
特に、諸外国との防衛装備・技術協力の強化、厳しさを増す安全保障環境を踏まえた技術的優位の確保、防衛生産・技術基盤の維持・強化、防衛装備品のハイテク化・複雑化等を踏まえた調達改革などが重要な課題となっています。
このような課題に対処するため、また装備品等の開発及び生産のための基盤の強化を図り、研究開発・調達・補給・管理の適正かつ効率的な遂行並びに国際協力の推進を図ることを任務とする防衛装備庁が防衛省の外局として2015年に創設されました。
防衛装備品には迷彩服、食糧、燃料まで、様々なものが含まれます。
それら防衛装備品は自衛隊の運用にとって必要不可欠なものといえます。
その装備品にかかる行政を担っているのが防衛装備庁です。
防衛装備品の産業基盤の強靭化や諸外国との防衛装備・技術協力の推進といった装備行政、プロジェクト管理、先進技術を取り込んだ研究開発、 適正かつ効率的な調達などその内容は幅広く、防衛装備庁には実に様々な仕事があります。
日本を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、 役割が拡大する防衛省・自衛隊にとってそれらの仕事はどれをとっても不可欠なものであり、 防衛装備庁では多様なバックグラウンドを持った事務官や技官が自衛官とともに国内外を問わず、日々職務に当たっています。
地方防衛局
地方防衛局は防衛省の地方支分部局として全国の主要都市に所在し、主に事務官(事務職)と技官(技術職)で構成された組織です。
2007年に防衛施設庁の地方支分部局である防衛施設局と防衛省装備本部の地方支部・事務所を統合して創設された機関です。
また、地方防衛局の下には防衛支局、防衛事務所、出張所があります。
比較的規模の大きい基地・駐屯地等が所在する近隣に防衛事務所があり、地元との連絡調整を行っています。
地方防衛局は、自衛隊及び在日米軍の活動基盤となる防衛施設の安定的使用を目指し、防衛施設の整備や自衛隊及び在日米軍の活動が円滑かつ効果的に実施されるよう地域住民と在日米軍との交流行事の実施等など幅広い業務を行い、国民と自衛隊及び在日米軍との架け橋となっています。
地方防衛局の主な業務は、①防衛政策についての理解を得るための情報提供や説明の実施、②自衛隊や在日米軍が使用する防衛施設の建設、③防衛施設用地の取得・管理、訓練に伴う障害の軽減や損失に対する補償等、その業務は多岐にわたります。
最新のトレンド
膨張を続ける中国軍
日本の安全保障環境が大きく変化している要因の一つに中国軍の拡大路線があります。
中国は過去30年以上にわたり、透明性を欠いたまま、継続的に高い水準で国防費を増加させ、 核・ミサイル戦力や海上・航空戦力を中心に、軍事力の質・量を広範かつ急速に強化しています。
また、作戦遂行能力の強化に加え、中国は既存の国際秩序とは相容れない独自の主張に基づき、東シナ海をはじめとする海空域において、力を背景とした一方的な現状変更を試みるとともに軍事活動を拡大・活発化させています。
特に海洋における利害が対立する問題をめぐっては、高圧的とも言える対応を継続させており、その中には不測の事態を招きかねない危険な行為もみられます。
例えば、 中国軍指導部が日本固有の領土である尖閣諸島に対する「闘争」の実施、「東シナ海防空識別 区」の設定や、海・空軍による「常態的な巡航」 などを軍の活動の成果として誇示し、今後とも軍の作戦遂行能力の向上に努める旨強調していることや近年実際に中国軍が東シナ海や太平洋、日本海といった日本周辺などでの活動を急速に拡大・活発化させてきたことを踏まえれば、これまでの活動の定例化を企図していることは明らかです。
さらに中国軍は質・ 量ともにさらなる活動の拡大・活発化を推進する可能性が高いです。
中国軍のこのような拡大路線は日本のみならずアメリカなど諸外国に大きな懸念を抱かせており、2021 年3月に行われた日米安全保障協議委員会(日米「2+2」)においては東シナ海及び南シナ海を含め、 現状変更を試みるいかなる一方的な行動にも反対するとともに、中国軍の活動に関する深刻な懸念を表明しました。
米中対立
近年、米中両国の政治・経済・軍事にわたる競争が一層顕在化し、相互にけん制する動きが活発化しています。
特に技術分野における競争は今後一層激しさを増す可能性が高いです。
中国が急速に軍事力を強化する中、米中の軍事的なパワーバランスの変化がインド太平洋地域の平和と安定に影響を与える可能性もあり、南シナ海や台湾などの地域の米中の軍事的な動向について一層注視していくことが必要です。
中国が領有権を主張する南シナ海において中国は弾道ミサイルの発射や空母による軍事訓練などの軍事活動などを活発化している一方、米国は2020年 7月に中国の海洋権益に関する主張は不法だと非難するとともに航行の自由作戦や空母も含めた軍事演習を実施するなど一層厳しい姿勢を示しています。
米議会公聴会においてインド太平洋軍司令官はインド太平洋地域での軍事バランスは米国と同盟国にとって好ましくない状況、中国による現状変更のリスクが高まっていると指摘しており特に台湾に対する野心が今後6年以内に明らかになる旨証言しています。
激変する安全保障環境
現在の安全保障環境の特徴として、第一に国家間の相互依存関係が一層拡大・深化する一方、 中国などのさらなる国力の伸長などによるパワー バランスの変化が加速化・複雑化し、既存の秩序 をめぐる不確実性が増しています。
こうした中、自らに有利な国際秩序・地域秩序の形成や影響力の拡大を目指した、政治・経済・軍事にわたる国家間の競争が顕在化しています。
このような国家間の競争は軍や法執行機関を用いて他国の主権を脅かすことやソーシャル・ ネットワークなどを用いて他国の世論を操作することなど多様な手段により、平素から恒常的に行われているのが特徴です。
こうした競争においてはいわゆる「ハイブリッド戦」が採られることがあり、相手方に軍事面に止まらない複雑な対応を強いています。
また、いわゆるグレーゾーンの事態が国家間の競争の一環として長期にわたり継続する傾向にあり、今後さらに増加・拡大していく可能性があります。
第二に、テクノロジーの進化が安全保障のあり方を根本的に変えようとしています。
情報通信などの分野における急速な技術革新に伴う軍事技術の進展を背景に、現在の戦闘様相は陸・海・空のみならず、宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域を組み合わせたものとなっています。
各国は、 全般的な軍事能力の向上のため、また、非対称的な軍事能力の獲得のため、新たな領域における能力を裏付ける技術の優位を追求しています。
さらに、各国は人工知能(A Artificial Intelligence I)技術、極超音速技術、高出力エネルギー技術など将来の戦闘様相を一変させる、いわゆるゲーム・チェンジャーとなり得る最先端技術を活用した兵器の開発に注力しています。
防衛省の年収
防衛省単体での職員の年収は非公表ですが、人事局が公表している「国家公務員の業務状況等の報告」を基にすると、国家総合職採用の職員は1年目で300~400万円程度、30代で600~700万円程度、40代から50代で1000万円を超えてくるイメージです。
また、国家一般職については国家公務員25万3132人のうち、一般職にあたる行政職は14万2236人であり、給与は全職員の平均給与は41万6203円で、行政職に限ると40万8868円となっています。
防衛省で求められる人物像・スキル
防衛省はどのような人物を求めているのでしょうか?
詳しく解説していきます。
採用実績大学
防衛省が説明会参加者向けに配布している「内定者の声」によれば、採用された学生のうち、大半が東京大学出身者で占められています。
中央省庁は東京大学出身者が多い傾向にありますが、防衛省は特にその傾向が強く、インターンシップや本選考の過程で東京大学出身者が優遇される傾向にあるようです。
また、東京大学以外の大学出身者もいますが、大半が女性となっており、男性の場合は東京大学、女性の場合は旧帝大や難関私大出身者が多いようです。
志向性やスキル
防衛省の採用ホームページによれば、「幅広い視野を持ちつつ、様々な業務に関心を持ち、自分から積極的に学んでいける人材」が求められているようです。
ただし、防衛省の社員クチコミサイトなどでは防衛省の事務官、技術官の仕事は激務であり、退職率が多いことから実際には精神的かつ身体的にタフであることが求められているようです。
防衛省のES・面接対策
最後に防衛省の就活対策を解説していきます。
ここが最も重要なところなので、ぜひ参考にしてみてください。
ES対策
志望動機
内定者の志望動機を見てみましょう。
幼少期は地元の警察官に憧れていましたが、学生時代に諸外国の学生と交流していく中で国際関係に興味を持ち、地域の治安ではなく国を守る仕事に携わりたいと思うようになり、防衛省・自衛隊を志望しました。
学生時代に国際政治を専攻し、日米同盟等の安全保障分野の研究をしていました。
国防に関わる仕事に就くことは自身の憧れだったため、入省を決めました。
趣味の読書をつうじて日本の歴史を知り、安全保障の分野に興味を持ちました。
大学では機械工学を専攻しており、機械に関する知識と培った調整能力で国防に貢献できると考え、防衛省を志望しました。
防衛省の志望動機としては学生時代の専攻や趣味などを通じて、国際関係や安全保障に関心を持った人が多いようです。
ポイントとしては「なぜ自衛隊ではなく防衛省職員なのか」「なぜ防衛省に関心を持ったのか」について明確にしましょう。
学生時代に頑張ったこと
内定者の記載例について見てみましょう。
ラクロスに打ち込んでいました。
防衛省はチームで動く組織であり、省内外の方々との信頼関係が重要な組織ですが、人を動かすにはまず自分が汗をかくことが不可欠であること、自分の行動や態度は様々な形で自分に返ってくることなど、組織人としての基本をここで学びました。
防衛省の業務は激務であると言われています。
社員クチコミサイトからも離職率が高いことがわかるため、精神的かつ身体的にタフであることが求められます。
したがって、上記のように部活やスポーツに打ち込んだ経験を述べる学生が多いようです。
面接対策
グループディスカッション
内定者によれば、防衛省では東京大学出身者とそれ以外の大学出身者で選考プロセスが異なります。
東京大学出身者は人事面談と原課面談と呼ばれる職員面接で内定を獲得できますが、それ以外の大学出身者はグループディスカッションを受ける必要があります。
グループディスカッションでは防衛省所管の政策や安全保障関連の問題に関して、グループで議論を行い、個々人が結論を出します。
選考の過程では論理的な思考能力や頭の回転の速さ、防衛省の政策に対する従順さなどが評価されます。
出身大学
内定者や退職した職員によれば、防衛省は東京大学出身者が選考に有利になりやすいという特徴があります。
東京大学出身者であれば、選考に比較的簡単に通りますが、それ以外の大学の学生は少ない枠を奪い合う必要があります。
したがって、最大の面接対策は東京大学に入学することかもしれません。
よくある質問
東大生が優遇されやすいですか?
防衛省は総合職及び一般職に内定した学生の出身大学を公表していません。
しかし、Facebookなどで内定者に対するインタビューを実施しています。
すべての内定者のインタビューが掲載されているわけではありませんが、東京大学出身者が大半を占めているようです。
採用説明会や採用パンフレットでは「学歴に関係ない採用を行っている」と記載がありますが、実際には東大出身者が優先して採用される傾向にあるのは事実のようです。
総合職と一般職の業務内容に違いはありますか?
一般的に国家総合職は「政策の企画立案等の高度の知識、技術または経験等を必要とする業務に従事する職員」と定義され、政策の企画立案を行います。防衛省本省の幹部候補(官僚)として、省内での異動を繰り返しながら政策立案、法案作成、予算編成などに携わり、国家のデザインともいえるダイナミックな仕事を行います。
一方で国家一般職(大卒)は「主として事務処理等の定型的な業務に従事する職員」と定義され、政策の実行を行い、企画立案を支える立場になります。
ただし、現実には一般職は総合職の雑用を行ったり、激務の割には総合職と比べて待遇が悪いというデメリットがあります。
採用人数について教えて下さい
総合職事務系の採用人数は以下のとおりです。
| 試験 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| 総合職院卒者 | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 総合職大卒程度 | 11 | 11 | 14 | 13 | 15 |
| 合計 | 11 | 12 | 14 | 14 | 18 |
総合職技術系の採用人数は以下のとおりです。
| 試験 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| 総合職院卒者 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 総合職大卒程度 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 合計 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 |
まとめ
日本の安全保障環境が激変する中で防衛省の重要性は増しており、防衛官僚を志す学生も増えています。
それにしたがって、防衛省の採用難易度も高まっており、徹底した就活対策が必要になっています。
この記事を読んで、就活対策を仕上げましょう。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。