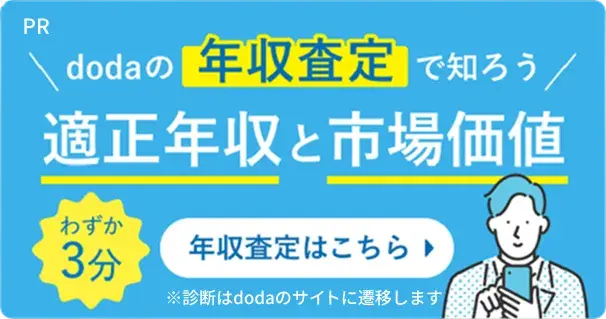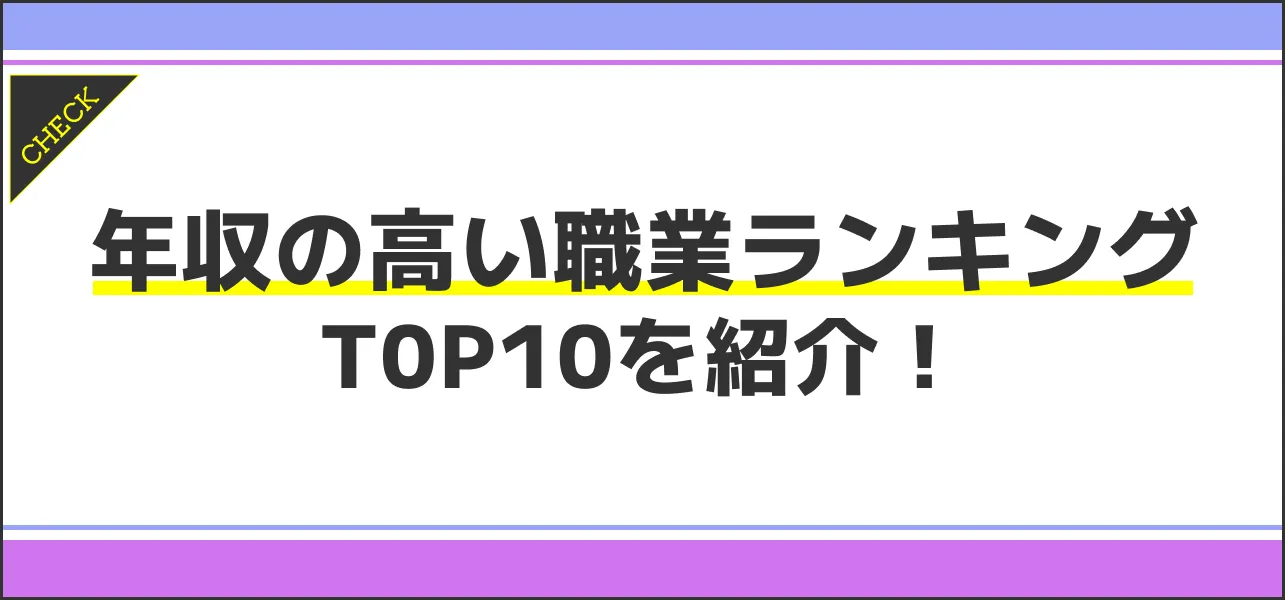
【男女共通】年収が高い職業ランキング!なり方や必要な資格まで徹底解説
「収入が高い仕事に就きたい」と考える人は多いでしょう。しかし、どの職業が実際に高収入なのかを知る機会は意外と少ないものです。本記事では、最新(2025年2月時点)のデータをもとに、年収が高い職業をランキング形式で紹介します。就活や転職を成功させるために、ぜひ参考にしてください。
年収が高い職業TOP10を詳しく紹介
給料が高い職業にはどのような仕事があるのでしょうか?
「令和5年賃金構造基本統計調査」によれば、年収の高い職業は以下の通りです。
※令和5年賃金構造基本統計調査より以下の方法で算出
職種(小分類)、性別、きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)10人以上男女計
平均年収の計算方法:「所定内給与額」×12カ月+「年間賞与その他特別給与額」
専門性が高く技術習得に時間のかかる職業ほど上位になる傾向が見受けられます。
以下では、さらにこの中から特に年収が高いTOP10の職業について、それぞれの仕事内容や必要なスキル、どうすればその職業に就けるのかを詳しく解説していきます。高収入を目指す上での参考にしてください。
【1位】航空機操縦士(パイロット)(1732万円)
航空機操縦士は、航空機を操縦して乗客や貨物を安全に目的地まで輸送する職業です。
機長と副操縦士が協力して操縦を行い、機長は飛行の全責任を負います。航空機の操縦だけでなく、地上の航空管制官との通信や、飛行計器類の監視も行います。
また、出発前には気象データなどを考慮して、運航管理者とともに飛行計画を立てることも仕事です。飛行中は、常に安全運航に気を配り、不測の事態にも冷静に対処することが求められます。
航空機操縦士になるには、定期運送用操縦士の資格が必要です。資格を取得する方法はいくつかあり、航空会社に入社して養成訓練を受ける方法や、航空大学校に入学する方法、一部の大学や専門学校の養成コースで学ぶ方法などがあります。
航空会社への入社後は一定期間の地上勤務を経て、副操縦士として経験を積み、30代後半から40代前半にかけて機長へと昇格するのが一般的です。
パイロットによくある質問
関連記事
▶︎パイロットになるには?条件や難易度・学生や社会人から目指すルートも紹介
【2位】医師(1267万円)
医師とは、患者の健康と生命を守る責任を担い、診療活動だけでなく医療の革新にも貢献する、極めて重要な専門職です。高度な知識と技術が要求されるため、どの分野においても報酬が高い傾向にあります。
医師への道は、まず医学部に入学し、6年間にわたる専門教育を受けることから始まります。そこでの学びを終えた後、国家試験に合格することで医師免許が授与され、医療現場に一歩踏み出す資格を得ます。
しかし、独り立ちするためにはその後の実地研修が欠かせません。
卒業直後の2年間は「初期臨床研修」と呼ばれ、内科・外科・小児科・救急医療など複数の診療科において現場経験を積みながら、基礎となる診察や治療のスキルを養います。
初期研修を経た後は、さらなる専門性を身につけるため、3年から5年に及ぶ専門研修を受けるのが一般的です。
また、研究分野に興味を持つ者は大学院に進む道もあり、医学の発展に貢献する研究者としてのキャリアを築くことが可能です。
加えて、公衆衛生や医療政策に関わる公務員として、国や自治体の医療運営に参加する選択肢も存在します。
どの進路を選ぶにしても、日々新たな知識の習得と技術の向上を目指し、患者のために最善の医療を提供する使命は変わることがありません。
医師によくある質問
関連記事
▶︎医師の年収│勤務先や年齢別に収入事情を解説
【3位】法務従事者(1117万円)
法務従事者は、法の知識を駆使して社会の秩序維持と正義の実現に貢献する職業群です。弁護士・裁判官・検察官といった職種があり、それぞれ異なる任務を担いながらも、法制度の運営に欠かせない役割を果たしています。
弁護士は、民事や刑事の問題に取り組み、依頼者の権利保護に努める存在です。依頼者との相談や契約書の作成、訴訟代理、和解の仲介などを通して、個人や企業が抱える法的課題を解決に導きます。
弁護士になるには、法科大学院の課程を修了するか、予備試験に合格し、司法試験に合格した後、実務研修を経て正式に登録される必要があります。
裁判官は、法に基づいた判断を下し、民事や刑事事件において争いを解決する役割を持ちます。離婚や相続、少年事件などを扱う家庭裁判所から、上級審における審査に至るまで、その判断は幅広い場面で求められます。
裁判官となるためには、司法試験合格後に研修を重ね、補助的な判事職として経験を積む必要があります。
一方、検察官は、犯罪の捜査と起訴の決定に関与し、公共の安全を守る使命を担っています。事件の詳細を調査し、起訴すべきか否かの判断を行い、裁判では証拠の提示により有罪を立証します。
検察官もまた、司法試験の合格とその後の実務研修を経て任官されるのが一般的です。
これらの職種はいずれも高度な専門性が要求されるため、仕事に就くためには膨大な学習が必要です。
関連記事
▶︎弁護士の年収は低い?四大法律事務所の年収は?
【4位】大学教授(1070万円)
大学教授とは、自らの専門領域において最先端の研究を推進しながら、学生に対して知識や技術を伝授する職務を担う存在です。担当する業務は大きく分けると研究と教育に分かれ、どちらも極めて重要な意味を持ちます。
研究面では、専門知識を背景に独自のテーマを設定し、実験や調査、解析を通じて新たな知見を得ながら論文を作成し、その成果を国内外の学会で発表していきます。
これに対し、教育面ではシラバスの作成や講義の実施、さらにはゼミ形式の指導を通して、学生が卒業論文や大学院での研究に取り組む際のサポートを行います。
また、就職活動に関するアドバイスを提供することも、仕事に含まれている場合もあります。大学教授になるためには、小学校や中学校、高校の教員免許は不要ですが、極めて高度な専門知識が求められます。
一般的なルートとしては、学部卒業後に大学院へ進学し、修士課程で2年間学んだ後、博士課程に進み3年間程度の研究を経て博士号を取得するのが通例です。
博士号取得後は、助教や講師としてキャリアをスタートし、実績に応じて准教授、そして教授へと昇進していきます。
大学職員によくある質問
関連記事
▶︎大学教授の年収(私立・国立)はいくら?ランキングも紹介!
【5位】歯科医師(894万円)
歯科医師は、口腔内の健康維持を目的として、虫歯や歯周病の治療はもちろん、予防策の指導も行う専門家です。
治療では虫歯の除去や充填、抜歯、さらには義歯の作製といった施術を行い、近年ではインプラント治療や審美歯科への関心も高まっています。
また、患者が健全な歯を保てるよう、定期的な歯石除去や口腔衛生に関するアドバイスも欠かせない業務です。
特に高齢化が進む現代では、来院が困難な方々へ自宅や介護施設での治療を行う訪問診療の重要性が増しており、医科との連携によるがん患者の術後ケアなど、専門的な支援も求められています。
歯科医師になるためには、まず歯学部で6年間の教育を受け、歯科医師国家試験に合格しなければなりません。
試験合格後は、1年以上の臨床研修を通じて実践的な技能を磨き、基礎を固めます。その後は、病院や歯科医院で勤務医としてのキャリアを積むか、自ら開業するか、または大学病院で専門的な治療や研究に従事する道が選べます。
歯科医師の約2割が女性であり(2020年時点)、ライフスタイルに応じた柔軟な働き方が可能とされていますが、一方で都市部では供給過多となり競争が激化しています。
そのため、将来のキャリアプランを明確にし、自分に合った道を選ぶことが重要です。
関連記事
▶︎歯科医師の将来性は?今後の需要やキャリアパスなどをご紹介
【6位】大学准教授(858万円)
大学准教授とは、大学において自らの専門分野を深める研究と、学生への教育・指導を担う職種です。
学術雑誌に論文を発表し、国内外の学会で成果を共有するなど、研究活動を通じて知見の拡大に努める一方、授業内容の企画や講義、ゼミナールの運営を通じて学生の学びをサポートします。
また、卒業論文や修士・博士論文の指導、さらに学内委員会や学部・学科の運営にも関与し、大学全体の機能向上に寄与することも仕事です。
准教授として活躍するためには、まず大学院で博士号を取得し、その後、助教や講師として教育や研究の経験を重ねる必要があります。
数々の学術的実績を積み上げる中で、将来的に教授へ昇進することを目指すのが一般的ですが、その過程は非常に競争が激しく、評価基準も厳格です。
なお、かつては「助教授」と呼ばれていたこの職位は、2007年の法改正を受け、国際的な誤解を避けるために「准教授」と改称され、より自立した役割が明確に示されるようになりました。
【7位】研究者(708万円)
研究者とは多岐にわたる分野で新たな知見を追求し、その成果を実社会に応用する役割を担う専門家です。
大学や各種研究機関で基礎的な調査を進めるほか、企業の研究部門や行政の研究所、博物館など、さまざまな現場で活躍しています。
研究領域は非常に広く、医学、宇宙開発、工業や農業技術などの理系のみならず、経済学・歴史・文学など文系の領域も対象となります。
研究者になるためには、まず大学で専門知識を習得し、その後、大学院に進み修士課程や博士課程でさらに研究を深めるのが一般的な進路です。
学会での発表や論文の執筆を通じて実績を積み重ね、博士号取得後は大学の助手、講師、助教などのポジションを経由して、最終的には准教授や教授として昇進する道が開かれます。
しかし、大学教員のポストは定員制であり、欠員補充が基本となるため、採用競争は非常に激しいのが現状です。
そのため、企業や行政の研究機関で経験を積み、後に大学教員へ転身するケースも見受けられます。いずれにしても、専門分野に対する深い理解と絶え間ない探究心が、研究者として成功を収めるための不可欠な要素となります。
関連記事
▶︎【研究者になるには】なり方と必要な学歴・スキルを徹底解説
▶︎研究職の年収は低い?大手企業は1000万円もらえるのかご紹介
【8位】公認会計士,税理士(700万円)
税理士と公認会計士は、会計および税務の知識を活かして、企業や個人の経済活動を支える専門家です。
税理士は、主に納税者の代理人として税額の算定や申告書の作成、さらに税務調査への同席や各種税務相談に応じることで、適正な税務処理を実現します。
また、財務や会計に関する助言を行い、企業の経営管理や資産運用のサポートにも努めています。
一方、公認会計士は、企業の財務諸表の正確性を保証するための監査業務を主な任務とし、経営戦略や会計処理に関するコンサルティングなども手掛けるなど、企業の経営全般に対して幅広い支援を行っています。
資格の取得過程においては、税理士は税理士試験に合格するか、あるいは弁護士や公認会計士の資格を持つ者が対象となり、2年間の実務経験を積んだ上で日本税理士会連合会への登録が必要です。
独立して業務を行う道も開かれており、企業の財務部門や税理士法人での就職も可能になります。
対して、公認会計士は難関とされる公認会計士試験に合格した後、3年以上の実務経験と実務補習、修了考査を経なければならず、資格取得までのハードルは高めです。
いずれの資格も、長期的なキャリア形成や将来的な独立を視野に入れた魅力的な職業の選択肢と言えるでしょう。
関連記事
▶︎公認会計士の年収│女性の収入や初任給について詳しく解説
▶︎税理士の年収の現実│給料は低い?女性や開業税理士の場合は?
【9位】高等学校教員(691万円)
高校教員も比較的高収入な職業です。その理由としては、業務範囲が小中学校と比べて多岐にわたることや授業の専門性、私立の割合が上がることが挙げられるでしょう。
中学校までの義務教育を終えた生徒に対して、受験に使う教科以外にも、高校の性質によって農業や工業、商業、水産などの専門教科まで、より高度で専門的な学びを提供する役割を担っています。
加えて、ホームルームや部活動、学校行事など学校全体の活動にも関与し、個々の生徒に対する指導や進路相談、生活指導を通じて、学習面だけでなく精神面の支援も行います。
就業するためには大学で所定の単位を取得し高等学校教諭免許状を取得する必要があり、さらに教育実習を経て、都道府県や私立高校が実施する教員採用試験に合格することが必須です。
関連記事
▶︎高校教師の年収!都道府県ランキング・年収1000万円は可能?
【10位】大学講師・助教(665万円)
大学講師と助教は共に大学で教育と研究に従事する職ですが、その業務内容には明確な差異があります。大学講師は、主に授業やゼミ、演習を通じた教育活動が業務の中心です。
対照的に、助教は研究活動を主体とし、教授や准教授を補佐する立場で、研究室に所属して実験の補助や論文作成の指導、研究プロジェクトへの参加を通じて自身の研究成果を高めることに努めます。
つまり、大学講師は教育に重きを置くのに対し、助教は研究を前面に出した活動が特徴です。
大学講師になるためには、まず博士号を取得し、教育や研究に関する実績を積む必要があります。
専任講師のポストは限られているため、非常勤講師として経験を積みながら、大学の公募に応募して選考を通過することが一般的です。
助教については、博士号取得後に十分な研究業績を示しながら、助教の募集に応募するのが通例であり、一定期間研究に従事した後に助教として採用されるケースも多いです。
どちらの職も高度な専門知識と実績が求められ、厳しい競争の中で早期から研究成果や教育経験を重ね、自身の強みを明確にすることが将来的なキャリアの成功につながります。
ここで、JobQ Townに、女性が高収入の企業に就職するために何をするべきか質問が来ていたので見ていきましょう。
女性で高年収の企業に就職するためにやるべきことは何ですか?
現在高校2年生の者です。
女性で高収入の一般企業に就職する為に、行くべき大学や、そこでやっておくべきこと等を教えていただきたいです。
また、就職活動においてどのようなことが重要になるかも知りたいです。
宜しくお願い致します。
女性については結婚や出産というライフイベントをどの様に…続きを見る