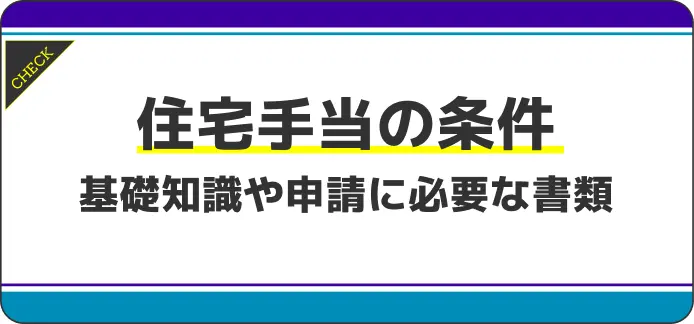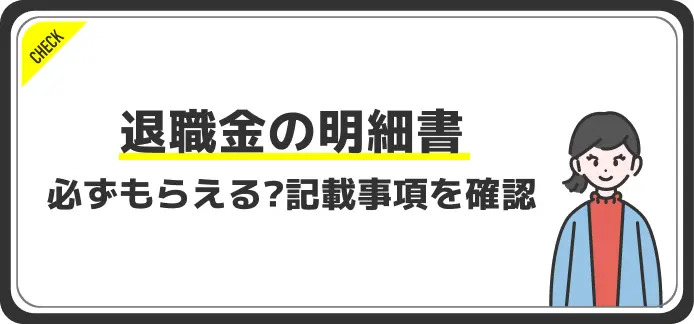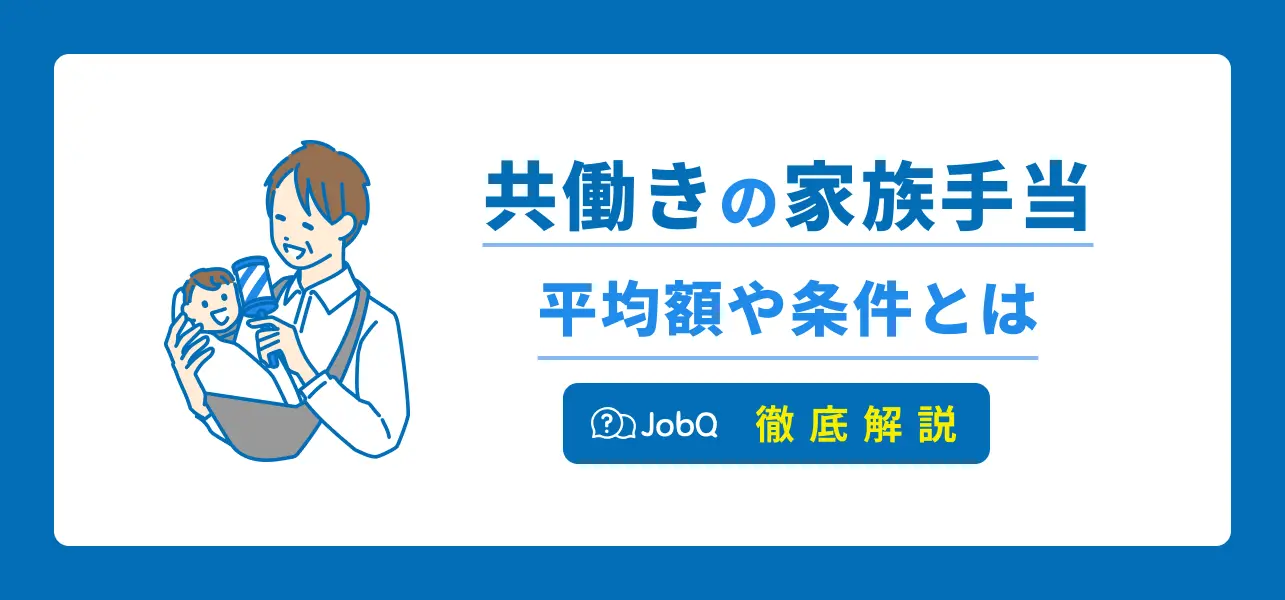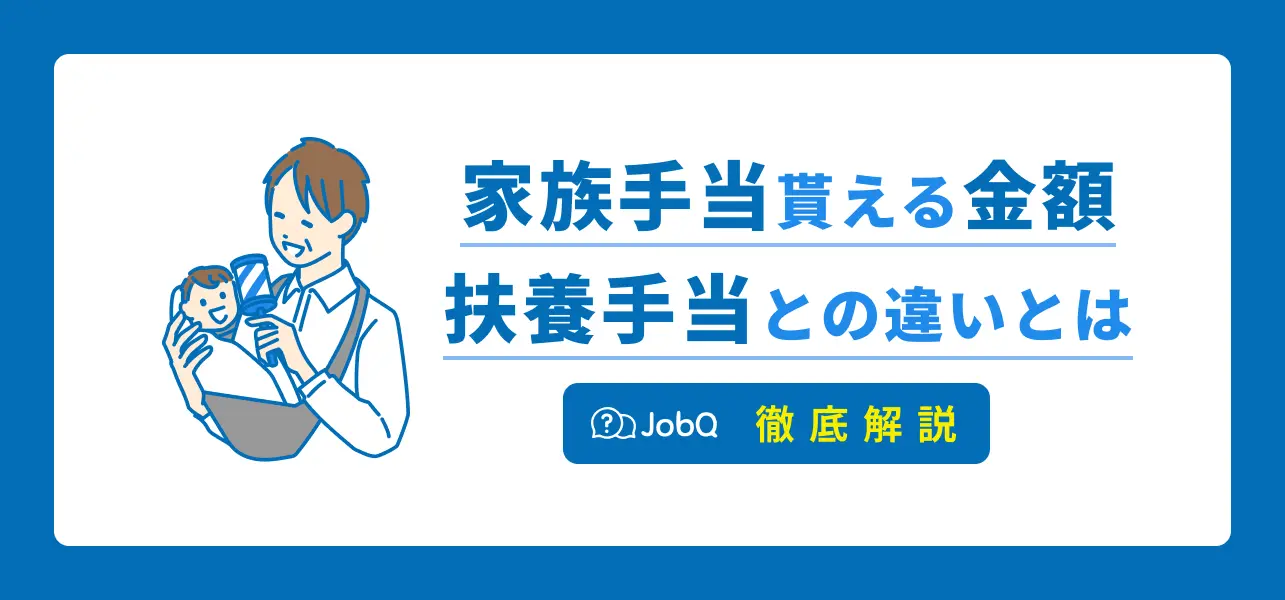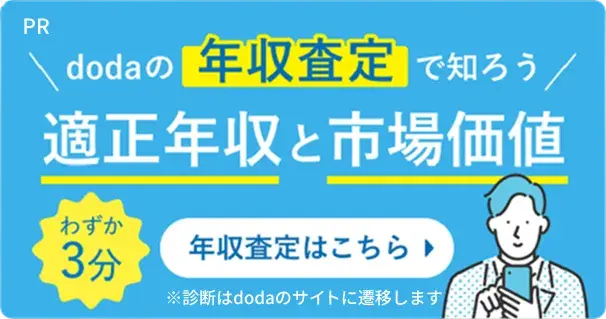【福利厚生費】従業員なら知っておきたいシステム!具体例などご紹介
皆さん、「福利厚生費」についてご存知でしょうか?福利厚生費とは、企業に勤める従業員の生活の向上及び、労働環境の改善などのために支出される基本給とは別の費用の事を指します。今回は、法定福利費との違いや福利厚生費の範囲についてなど、詳しくご紹介します。是非、ご参考にしてみてはいかがでしょうか?
そもそも福利厚生費とは
企業に就職する際に気になる要素の一つとして、福利厚生費が思い浮かぶ人も多いかと思います。一方で、そもそも福利厚生費とは、具体的にどのようなシステムなのかあまり知らない人も少なくありません。
今回は福利厚生費について、詳しく解説していきますので就活や知人との情報交換に役立てて頂けたら幸いです。
従業員のモチベーションを上げるもの
福利厚生費とは、企業に勤める従業員の生活の向上及び、労働環境の改善などのために支出される基本給とは別の費用の事を指します。
企業側としても福利厚生費を充実させる事で、良い人材を得る事もできます。
福利厚生費が充実しているかどうかでも、その企業の質が現れるといっても過言ではなく、働く従業員のモチベーションを上げるものとして機能しなければならないのです。
福利厚生費の具体例
典型的な福利厚生費の具体例としては以下が挙げられます。
- 社員食堂:社内に食堂が整備され、外食よりも低価格で栄養バランスの良いメニューがあります。
- 住宅手当:賃貸や持ち家に対しての住居費が補助されます。
- 財型貯蓄制度:退職金の上乗せの為、毎月の給料から一部の額が控除され積み立てます。
- 優待施設割引制度:様々なレジャー施設などでを割引価格で利用できる制度です。
他にも社宅、社員旅行や慶弔見舞金、忘年会や新年会の費用や歓迎会や送迎会の費用が出る場合もあります。
また企業のよっては独特の福利厚生を設けいているところもあります。あるアプリ会社では「エンタメ休暇制度」といって、新しいゲームの発売日に社員がゲームを買いに行くための休暇です。日本最大級のファッションサイトを運営する企業では、「1日6時間労働制度」が導入され、社員のプライベート時間を充実させることでおしゃれやファッションに関してのサービスの知識を向上させる事を目的としています。
法定福利費との違い
福利厚生費と似た名前の法定福利費というものもあります。
法定福利費とは福利厚生の内、法的に費用負担が義務付けられている費用の事です。
- 健康保険:従業員やその家族が病気やけがをした際に医療費が給付されます。(労使折半)
- 厚生年金保険:従業員の老後のために老齢、障害、死亡に対して給付されます。(労使折半)
- 介護保険:介護が必要な高齢者の治療費や介護費を支援します。(労使折半)
- 雇用保険:従業員が離職した場合に必要な給付を行います。(一定額)
- 労災保険:従業員が業務中や通勤中などに負傷した場合に支給されます。(全額負担)
福利厚生費の範囲
福利厚生費には利用できる範囲があります。
平等であることが大事
福利厚生費を利用する際、全ての従業員に対し平等に支出され、社会通念上適度な出費である、日金銭的な支出である事が条件でもあります。例えば社員旅行の例でいうと、一部の社員のみが旅行に行ったとなれば平等に支出されることにはならないので、福利厚生費とは認められません。
社宅の場合、物件の適正家賃の50%未満を会社で負担しているのなら、そこまでが福利厚生費の範囲といわれます。また、常識を逸脱するような高額な金額ではなく、あくまで妥当な金額であることも利用する上での条件といわれます。
個人事業主も福利厚生費を利用できる
個人事業主が一人で仕事をしている場合は福利厚生費を利用する事はできません。これは事業主のみに福利厚生費を認めてしまうと、業務に必要な支出なのか個人的な支出なのかを判断するのが難しくなるためだといわれます。
一方で従業員がいる場合は利用する事ができます。しかし、事業主だからといって従業員と差があるのは認められません。
例えばレジャー施設を利用する際に、事業主だけが費用を負担する事はできないので従業員全員分の費用として出されなくてはならないのです。
課税対象になる福利厚生費3選
給与として課税対象となる福利厚生費について解説していきます。非課税として認められるものも場合によっては課税対象になります。
限度額を超えた通勤手当
通勤手当や通勤定期券に関しては、ある一定の金額までは所得税も課税されませんが、この一定限度額を超える事で課税対象となってしまう場合があるので、注意が必要です。
社宅制度で従業員の負担が50%未満の場合
社宅の場合、従業員の家賃を支払う負担が通常の50%未満の場合は、その差額を従業員に対する経済的な利益として課税対象になってしまいます。
ちなみに借上げ社宅が複数ある場合には、50%以上徴収していれば問題は生じません。
研修旅行の費用
研修旅行では、従業員の50%以上が参加する場合、4泊5日以内の期間であれば非課税となりますが、研修や旅行に参加できなかった従業員に対して旅行代や金銭を支給するなどの措置を摂る場合は課税対象になります。
カフェテリアプランについて
最後に福利厚生の中でもユニークなカフェテリアプランについて説明していきます。
カフェテリアプランという名前は、好きな食事、飲み物を自由に選べるカフェテリアにちなんでつけられました。
サービスを自分で選べる
カフェテリアプランとは、企業が設定してある福利厚生制度の中から、自分に必要なサービスを選択できるというものです。
一般的には、企業側が従業員に対して有効期限付きの複利厚生ポイントを毎年付与し、従業員はそのポイントの範囲内で補助を受けるという仕組みとなっています。
カフェテリアプランのメリット
企業側にもカフェテリアプランを導入するメリットがあります。
- 自社の状況や環境に合わせた福利厚生サービスを構築できる。
- 従業員の好みに合わせた多種多様なニーズに答える事ができる。
- ポイント制のためサービスの利用状況の確認や管理が簡単にできる。
- 自社のアピールポイントとして採用力を上げれる可能性がある。
- ポイントの有効期限があるため従業員が活用する率が高い。
- 従業員に福利厚生を意識させることができる。
カフェテリアプランのデメリット
一方で少なからずデメリットも考えられます。
- ポイント付与やシステム構築といった導入に時間がかかる。
- 従業員の満足度に合わせてプランを見直したり変更する場合がある。
- コスト計算をして支出を増やさないように気を付けなくてはならない。
まとめ
福利厚生費に明確な定義がないのが事実であり、議論が分かれる事もあります。
基本的には、従業員の福祉を目的としているので、企業に従業員が存在しその人たちが平等に利用できる妥当な金額であれば福利厚生費として認められます。そしてこれまで説明してきた福利厚生費は「法定外福利費」と呼ばれることもあります。
正確に言うと、福利厚生費とは先で述べた「法定福利費」と「法定外福利費」の二つで構成されています。忙しいとこういった福利厚生の事に関しても、意識が向かない事もありますが今一度自社の制度について確認しておくことも大事かもしれません。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。