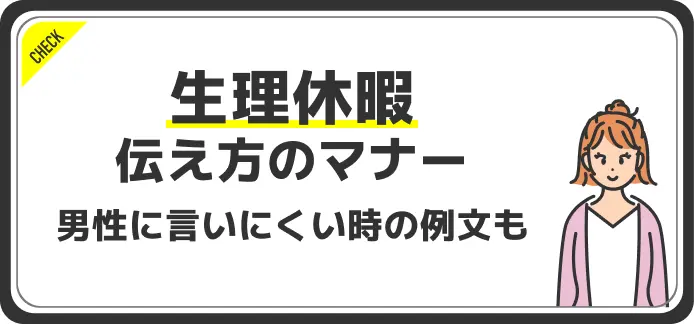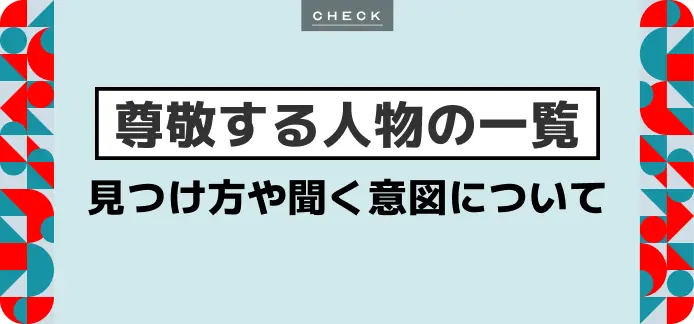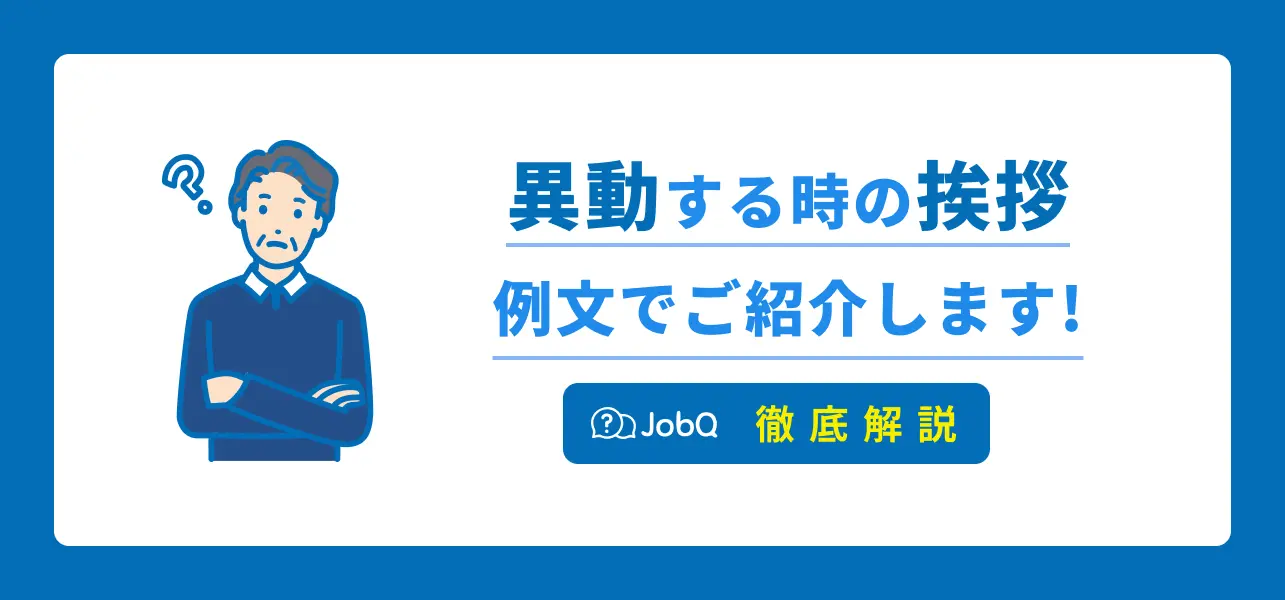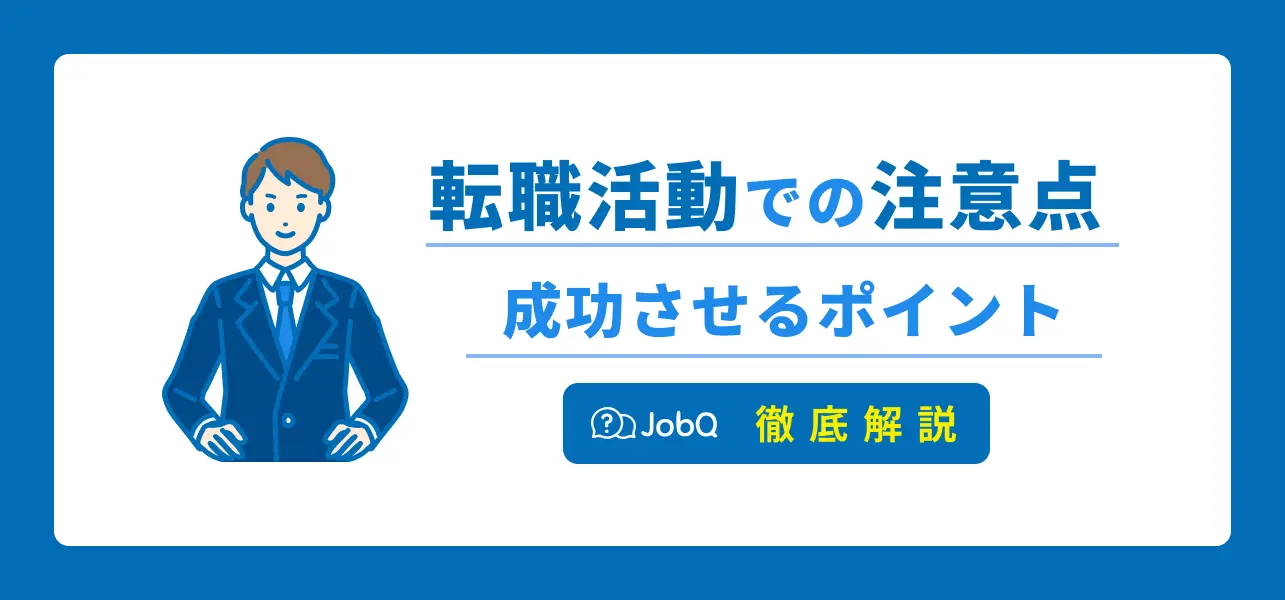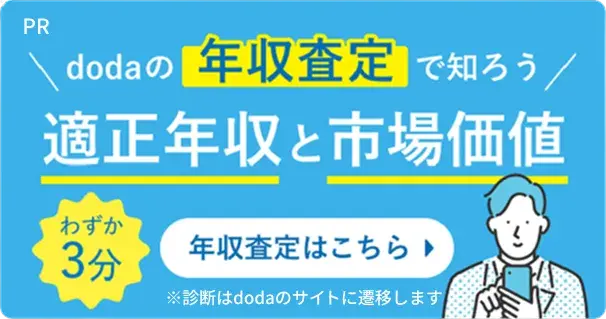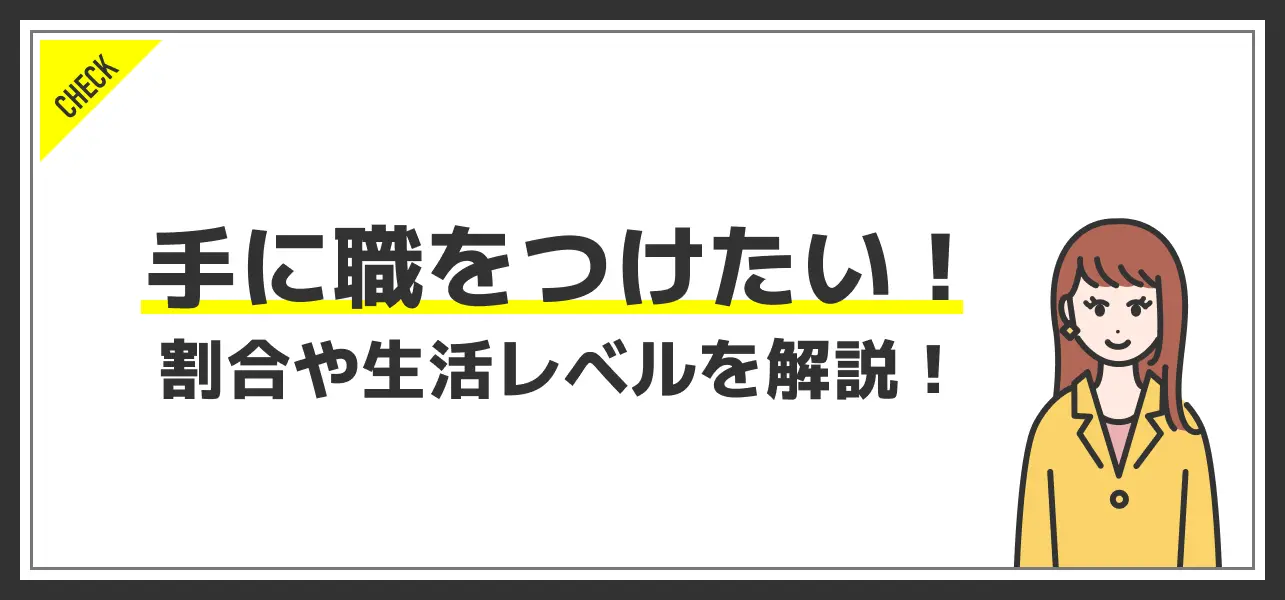
手に職を付けたい女性必見|おすすめの職業と選び方のポイントを解説
育児や介護などのライフイベントでの離職を経験し、これからは手に職をつけて働きたいという方も多いのではないでしょうか。しかし、仕事によっては「習得まで時間がかかる」「単価がそもそも低い」など、いろんな事情を抱えていることが多く、そもそもうまく仕事とマッチングできないと大きなストレスがかかってしまいます。今回は、そんな手に職をつけたいあなたに向け、おすすめの職業と選び方のポイントを解説していきます。
女性に手に職をつけることをおすすめする理由
女性の私たちが手に職をつけることで、多くのメリットを感じることができます。
そのため、以下の理由から、手に職をつけることをおすすめします。
- 安定的に収入を得られる
- ライフイベントから復帰しやすい
- 学歴に左右されづらい
安定的に収入を得られる
手に職があるということは、会社に依存せずとも収入を得られるということになります。
勤めている会社が業績不振あるいは倒産してしまっても、同業種で転職することができるため、安定した収入をもらうことができます。
ライフイベントから復帰しやすい
転職しやすいのと同様に、社会復帰しやすいというのも、手に職を持つメリットです。
仮に結婚や出産などライフイベントでブランクがあったとしても、実務経験や資格によって再就職しやすくなる特徴があります。
学歴や年齢に左右されづらい
手に職をつけ、個人で稼ぐスキルがあれば、そのスキルの実務経験などが評価対象とされ、学歴や年齢はあまり重要視されないことが多いです。
故に、個人のスキルで大手企業と取引ができたり、長期的に働くことができるため、比較的安定しやすくなります。
関連記事
▶︎女性の仕事でよくある悩みをランキングから解説!おすすめの解決方法もご紹介
▶︎女性は正社員で何歳まで働くのが理想?データから割合や働きたい理由などを解説
▶︎仕事ができる女性の特徴を解説|出来る人に共通している習慣や性格とは?
女性が手に職を付けられる職業と資格
ここからは多くの女性が手に職を付けられる職業と資格を解説します。
手に職を付けられる具体例として、大きくはこの5つに分類されています。
- 在宅ワーク系
- 医療・介護系
- 美容・サービス系
- 士業・専門職系
それぞれの仕事を職種別に解説していきます。
在宅ワーク系
在宅ワーク系というのは名前の通り、自宅で業務ができる仕事です。
自宅でなくても、好きな場所で勤務できるため、無理なく続けられるのが特徴の一つです。
在宅ワーク系には具体的に以下の職種があります。
- Webライター
- Webデザイナー
- プログラマー
- ハンドメイド販売
Webライター
Webライターでは、日常生活で用いられる文章を作っていく仕事です。
例えば、HPで掲載される記事、商品の口コミ、販売広告など文章を作って集客をしたり、ものをPRしていく執筆を作り上げていきます。
Webライターは無資格から始められるため、初心者でも始めやすい仕事です。
まずは簡単なものから文章にする癖を付けていくことが、Webライターになるための近道です。
- 美味しい料理を食べたら、どこが美味しいと感じたのか
- 面白いと感じた本は、どの場面がどう感じて面白かったのか
こういった感情を文章にしていくところから始めていきましょう。
Webデザイナー
Webデザイナーは、WebサイトやLPなどのレイアウトを作成する仕事です。
消費者の心に届きやすいメッセージを作るために、HPの色合いや広告の全体図を構成していくなど、Web集客において重要な業務です。
無資格で始められますが、基本的にはサイトやシステムを使ってサイト制作を進めていくので、独学で始めるよりも誰かに習ったり、チームに所属してメンバーとともに活動をした方が、売上を上げるうえでは効率がよいです。
プログラマー
プログラマーはHPやゲームの根源となるコードを書いて、実際にサイトを立ち上げたり・動かしたりする仕事になります。
これも無資格でできますが、言語(コードの種類)を覚えていく必要があるので、ある程度知識を付けた上で始めるのがおすすめです。
ハンドメイド
ハンドメイドとはその名の通り、手作りでアクセサリーや日用品を作り、販売する仕事です。
ネット上のショッピングサイトや自分自身でサイトを立ち上げたりすることで、店舗を持たなくても自分の商品を販売することが可能です。
ハンドメイドは、趣味の延長線上で始める人も多く、好きなことや趣味を仕事にできることから初心者の方でも始めやすく続きやすいビジネスの一つです。
医療・介護系
医療・介護の仕事も一般的に「手に職」といわれている職業の一つです。
医療・介護系のほとんどは有資格業務であることから、資格さえ取ってしまえば長期的にキャリアを積むことが可能です。
医療・介護系の主な職種には以下が挙げられます。
- 看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 栄養士
- 医療事務
看護師
看護師は医師と連携して医療行為を行い、患者の健康を守っていく仕事です。
全体的にも看護師は人材不足であるため、資格さえ持っていれば、派遣のような流動的な働き方だとしても重宝されるため、さまざまな働き方ができます。
まずは資格を取る必要があるので、3年制の専門学校や短大、4年制の大学での看護過程を履修する必要があります。
介護福祉士
介護福祉士は介護老人保健施設や障碍者支援施設、特別養護老人ホームなどで利用者の生活に関する補助や手助けをする仕事です。
介護福祉士の資格は特別で、実務経験が必要になります。
- 福祉系の大学であれば1~2ヶ月程度の研修実績
- 実際に勤務しながらであれば、6ヶ月程度勤務し試験を受ける
いずれの方法もある程度の時間がかかりますので、資格取得に進むかどうかは、まずは無資格で施設で働くところから雰囲気を掴んでいきましょう。
保育士
保育士は、0~6歳までの子供を預かり、日常生活のお世話をする仕事です。
勤務先は保育園や児童厚生施設、児童養護施設などが挙げられ、国家試験に合格することで保育士になることができます。
昨今は保育士不足の影響もあり、ニーズのある職業の一つです。
栄養士
栄養士は、病院や学校、介護施設などに籍を置き、そこの従業員やサービス利用者の健康を気遣った食事メニューを考える仕事です。
厚生労働省が定めた教育機関を卒業し、国家試験を通過することで栄養士として働くことができます。
栄養士の上位互換として管理栄養士という資格もあり、この資格をとると資格手当がもらえたり、昇進につながる可能性が高いので、今後のキャリア構築の上では狙っていくべき資格といえるでしょう。
医療事務
医療事務は、各医療機関で受付や会計、その他事務回りの仕事をこなす為の資格です。
資格は必要ないですが、ある程度の医療知識や実務経験、民間の資格をとることで有利に仕事を選ぶことができるのです。
都会でも地方でも医療機関の数は一定数存在するため、一度働ければ仕事の幅も広がっていくでしょう。
美容・サービス系
美容・サービス系も資格が必要だったり、講習会を受ける必要がある仕事が多いです。
ただ、自分の好きなことや普段から意識していることを仕事にできるので、一生涯続く職業にすることができます。
美容・サービスの具体的な仕事には以下があります。
- 美容師
- 調理師
- ヨガインストラクター
- セラピスト
- エステティシャン
美容師
美容師は、全国にある美容室でヘアカットやパーマ、ヘアカラーなどの対応をする仕事です。
美容師として働いていくには、美容専門学校を卒業し国家資格を取得する必要があります。
美容師の国家資格を取るためには、通信制や夜間制の教育カリキュラムを組んでいる学校もあるため、育児の合間に資格取得を目指せるのが、人気のひとつです。
調理師
料理が好きな方には、調理師免許がオススメです。
レストランやホテル、学校の給食室で勤務できる調理師は、調理師養成学校を卒業するか、調理師試験を通過することで、資格を得ることができます。
飲食店は、全国に存在することから、仕事がなくなるリスクも少ないです。
ヨガインストラクター
ヨガインストラクターはスタジオやジムでヨガの指導をする仕事です。
無資格でも生徒を持つことはできますが、指導スキルや生徒からの信頼の意味では、資格があった方がよいでしょう。
近年では、オフラインでの教室だけでなくオンラインでも生徒と繋がることができるため、生徒を持つことができれば場所を問わず働くことができるメリットがあります。
セラピスト
セラピストは人の心身を癒す仕事です。
アロマセラピストや心理カウンセラーとして働くため、精神科クリニックや学校で働くことが多いです。
専門学校に通ったり、国家資格か民間資格を得ることでセラピストを名乗って働けるため、まずはどの方法でセラピストになるかを検討していく必要があります。
エステティシャン
エステティシャンは施術を通して人の皮膚を美化したり、体型を整えたりする仕事です。
カウンセリングを経て、最適なプランやサービスを施術していく必要があるため、資格が必要かと思われやすいですが、実は無資格でも可能です。
しかし、専門知識はしっかり身につけなければならないので、スクールで学んで自分の価値を高めるところから始めていくのがオススメです。
士業・専門職系
士業・専門職系の職業は、組織に所属して働くこともできれば、独立して自分の事務所を構えて売上を上げることもできる、働き方を選びやすい仕事の一つです。
士業・専門職系の具体的な仕事には以下が挙げられます。
- 司法書士
- 行政書士
- 社会保険労務士
- ファイナンシャルプランナー
- 宅地建物取引士
司法書士
司法書士は、法務局や検察庁、裁判所などに提出する書類作成を行う仕事です。
基本的には司法書士試験に合格して、国家資格を取ることで司法書士を名乗ることができるようになります。
几帳面で細かいことにも気づく真面目な一面を持つ方であれば、お客様からも信頼される素晴らしい司法書士になること間違いありません。
行政書士
行政書士は、司法書士で対応していない官公庁に関する書類作成を手掛ける仕事です。
例えば、飲食店を経営する際に必要となる営業許可証や、会社設立の登記書の作成などが挙げられます。
国家試験を通過する必要はありますが、それまでの教育機関のプロセスは無いため、受験資格は誰にでもあります。
社会保険労務士
社労士とも呼ばれる社会保険労務士は働く上での雇用関連や社会保険の労務管理・処理のエキスパートとなる仕事です。
社会保険労務士試験の国家試験に合格する必要があるのですが、その受験資格には行政書士の資格を保有しなければならないなど、ハードルは高い資格となっています。
女性の合格率も30~40%程度と、少数派であることは事実ですが、だからこそ資格取得が叶えば優位性をもってお客様を獲得することができるでしょう。
ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナーは、依頼主の収支報告や負債管理、資産状況を整理した上で、今後の資産構築のアドバイスやプラン決めをする仕事です。
金融業界や保険業界でも顔が利くので、資格を取得すれば一生涯で活躍できる職業となるでしょう。
ファイナンシャルプランナーは年金制度や保険関連での知見が増えるので、自分自身の生活にも活かすことができます。
宅地建物取引士
宅建士とも呼ばれる宅地建物取引士は、不動産業界においては必要不可欠な資格となります。
不動産をお客様にご契約いただく際には、お客様の損になることの無いよう、トラブル防止を目的とした説明義務が求められます。
その説明そのものを、宅地建物取引士が実行しなければなりません。
国家試験を受けるにあたっての条件は無いため、しっかり勉強して資格取得を目指しましょう。
関連記事
▶︎なぜ女性はキャリアで悩むのか?誰も教えてくれない結婚や出産との両立を叶えるポイント
▶︎キャリアウーマンは結婚できない?結婚できない理由と結婚しやすい男性の特徴は?
手に職を付けたい女性の職種の選び方
ここまでは場所や状況に囚われない、一生涯続けることができる仕事をご紹介してきました。
多種多様な仕事がある中で、どういった基準で仕事を選ぶべきなのかは、以下の3つの軸を中心に選択するといいでしょう。
- 向いている・興味のある職業から選ぶ
- 今までの経験が活かせる職業から選ぶ
- 理想の働き方ができる職業から選ぶ
興味のある職業から選ぶ
まずは、自分自身が興味を持てるかどうかで選ぶ方法です。
一生涯続く仕事であっても、そもそも「続けてやりたい」と感じられなければ意味がありません。
この観点で言えば、趣味の延長でできる仕事や、自分自身の性格に基づいた上で最適な仕事だと言い切れるものを選択していくことで、あなたにピッタリな職を手にすることができます。
今までの経験が活かせる職業から選ぶ
次は、ここまでのご自身のキャリアをもとに職を選んでいく方法です。
原点に戻り高校や大学で学んできた分野に精通する仕事に踏み込んでみたり、前職の経験から既に受験資格を持っている場合もあるため、そこから国家試験にチャレンジできるのであれば、手っ取り早く手に職をつけることができます。
ただ、前職での経験ともなると、そこでの退職理由が気になります。
あくまでも仕事内容は好きで、会社の人間関係に悩んでの退職であれば、その道に進んでも問題ないでしょうが、業界が変わるわけではないので、かかわりを持つ人は前職と似たような人柄の方が多いのは頭に入れておくべきです。
理想の働き方ができる職業から選ぶ
最後は理想の働き方ができる職を選ぶということです。
育児もあるためできるだけ在宅で仕事をしたい方や、全国どこでも働く口に困らない仕事にしたいというニーズは人それぞれでしょう。
その中で、理想の働き方がもしあるのであれば、それが実現できる職を手にすることで、無理なく働き続けることが可能です。
関連記事
▶︎キャリアウーマンが向いている人の特徴とは?なり方やキャリアウーマンの結婚事情も紹介!
▶︎独身のキャリアウーマンが抱える悩みとは?結婚のメリット・デメリットも解説
女性が手に職をつけるための選択肢は多い
今回は、手に職をつけたいあなたに向け、おすすめの職業と選び方のポイントを解説してきました。
この記事の中でも19種類の仕事があるように、調べるだけでも仕事はさまさまなものが存在します。
今の環境の中で、仕事や今後の働き方に悩んでいるのであれば、本記事を参考に新たなスキルを身につけながら、手に職をつけることを検討してみてはいかがでしょうか。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。