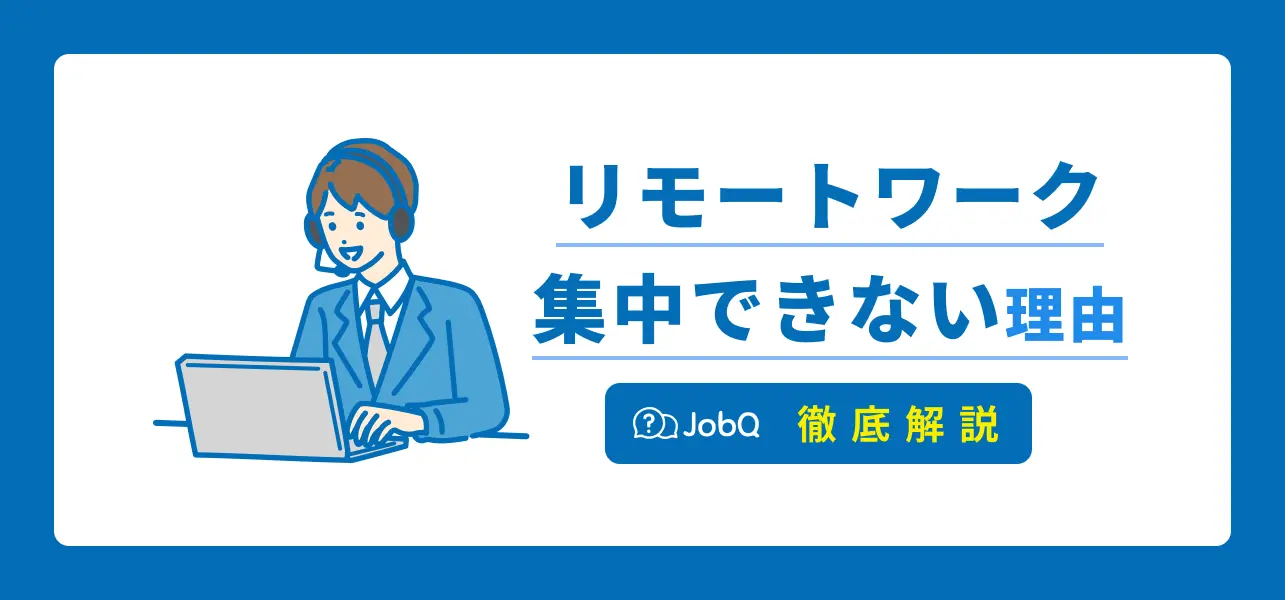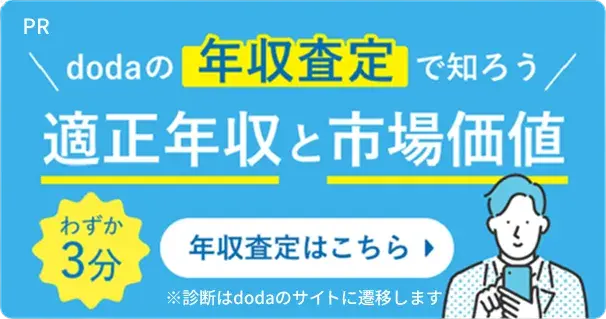在宅勤務にはどんな職種があるの?新しい働き方を解説します
近年、在宅勤務としての働き方が増えてきていますが、在宅勤務にはそんなスキルが必要なのでしょうか?そもそも今の在宅勤務はどんな仕事が主流なのでしょうか?この記事ではそんな在宅勤務の職種について徹底的に書いていきますので、ぜひ参考にしてみてください。
在宅勤務に資格やスキルは必要なのか
近年、アメリカなどでは一般的だった在宅勤務が,日本でも注目を集めています。
場所や時間にとらわれない働き方のできる在宅勤務は、育児や介護で外に働きに出ることが困難な人に適した働き方です。
では、そんな在宅勤務をはじめるにはどうすれば良いのかについて紹介したいと思います。
最低限欲しいスキルはこれ!
在宅勤務のほとんどは、自宅のパソコンと勤務先のサーバーとインターネット回線を通じてつなぎ、情報のやり取りをして行います。
つまり、インターネット環境とパソコンがあれば、簡単に始めることができます。
しかし、言い方を変えると、パソコンが全く使えなければ在宅勤務を始めるのは難しいです。
最低限、メールや文字入力の程度のパソコンスキルは必須になります。
また、在宅勤務であっても仕事には変わりありません。
どんな職種においても、社会人としての最低限のビジネス上のマナーやスキルは必要です。
パソコンのレベルはどれくらい必要?
在宅勤務をするにあたり、必要なパソコンのスキルは職種によって変わってきます。
例えば、データ入力の仕事であれば、文字や数字が入力できる最低限のレベルでも可能です。
案件によっては、WordやExcelを使う場合があるので、基本操作は出来るレベルだと良いでしょう。
しかし、Webデザイナーやエンジニアとなると話は別です。
より専門的なパソコンのスキルが求められます。
在宅勤務で働いている人ってどのくらいいる?

では、実際のところ在宅勤務はどのくらい浸透しているのでしょうか。
在宅勤務をしている人の人数や導入している企業について具体的に紹介します。
日本国内で在宅勤務をしている人は〇万人
厚生労働省の調査によると、日本国内で在宅勤務をしている人は2015年度で220万人でした。
これは通常の勤務者の約4%にあたり、まだまだ少数派です。
しかし、2016年に厚生労働省が発表した『働き方改革』で副業・在宅勤務を奨励したことから、在宅勤務者の数は上昇する傾向にあります。
現在ではおよそ300万人が在宅勤務で働くようになるなど、多くの職種の人が在宅勤務をするようになって来ています。
厚生労働省の目標は2020年には週一日以上終日在宅で就業する雇用型在宅勤務者数を10%に上げることです。
これが実現すれば、フリーランスの在宅勤務者数も含めるとかなりの人数が在宅勤務で働くことになります。
在宅勤務を取り入れている企業は〇社ほど
IT専門調査機関の調べによると、在宅勤務を取り入れている企業は2017年で14万社です。
企業の導入率は4.7%です。
特に大企業で在宅勤務の導入が加速しており、従業員が500人以上の大企業では23.6%と全体と比べて非常に高い割合になっています。
4社に1社が何らかの在宅勤務制度を導入していることになります。
情報通信業、金融業、製造業など多くの業種、多くの職種で在宅勤務が導入されています。
政府の奨励の後押しもあり、今後は中小企業でも在宅勤務を導入する企業が増加していくでしょう。
在宅勤務可能な職種は主にWEB専門職種

在宅勤務を導入する企業は広まりを見せていますが、早くから在宅勤務を導入しているのが情報通信業です。
特にWEB制作の仕事はインターネット環境とパソコンがあればどこでも仕事ができます。
また仕事も個人の裁量によるところが大きいので、在宅勤務に大変適した業種です。
WEB専門職種の種類を説明
WEB業界の中でも、特にWEBサイトを制作するスペシャリストは在宅勤務が多いです。
具体的には『WEBエンジニア』、『コーダー』、『WEBデザイナー』があげられます。
『WEBエンジニア』は、WEBサイトやモバイルサイトで利用するアプリケーションの開発や、WEBサイトを設計や運営・保守を行う職種です。
次に『コーダー』というと耳慣れない職種かもしれませんが、WEBサイトやプログラムを実際に作る人です。エンジニアの作成した設計図を元に、ソースコードを書き出していく仕事をしています。
そして『WEBデザイナー』はWEBサイトのデザインを作る職種です。
WEB専門職種以外の種類を説明
先に挙げたWEB専門職種以外でももちろん在宅勤務は可能です。
そこで、WEB専門職種以外の、在宅勤務の仕事について紹介します。
まず事務系の仕事で多いのが『データ入力』です。
求人サイトで目にする機会も多い仕事です。
コツコツと正確にデータを入力さえすればよいので、事務の経験がなくても大丈夫です。
そのため未経験者には最もハードルの低い仕事の一つといえるでしょう。
また『ライター』の仕事も、特別な知識やスキルがいらないため、誰でも気軽に挑戦しやすい仕事です。
他には、シール貼りやアクセサリーのパーツ組立といった作業系の職種もあります。
WEB専門職種になるには、いつから何をすべきか

在宅勤務の仕事は様々ですが、求人の件数も多く収入も安定している職種は、WEB専門職種です。
そこで、未経験からWEB専門職種を目指す方法について紹介します。
未経験ではじめるなら〇歳までが限度?!
WEB専門の職種は、スキルと経験があれば年齢に関係なく仕事がある世界です。
しかし、企業が求める条件から考えると30代になってからでは未経験でWEB専門職の職を得るのは非常に困難です。
もちろん30代の未経験者には、全く仕事がないわけではありません。
20代に比べてハードルは高くなりますが、アルバイトや契約社員であれば求人はあるので、小さな仕事をコツコツと重ねて経験を積むことが大切です。
在宅で習えるWEB技術者系の学校を紹介
WEB専門職に就くためには、WEBの専門スキルを身につける必要があります。
専門学校に数年間通う必要はなく、今は在宅で学べるスクールも多数あります。
在宅で学べるオンラインスクールだと、学習の期間も短く、費用も安く抑えられるメリットがあります。
また、夜遅い時間までサポートの対応をしており、仕事後に自宅で学ぶことも可能です。
例えば、『TechAcademy』 のWebデザインコースは、最短で4週間のコースからあります。
スクールの費用を抑えたいのであれば『WebCamp』のWebデザインコースは、1か月の受講で99,800円と10万円以下で学ぶことができます。
また、『ヒューマンアカデミー』には、在宅ワークの実践的セミナーや就職の手厚いサポートのある、在宅WORKスタートパックもあります。
WEB系職種の為のオンラインスクールはたくさんあるので、費用や学習の期間や内容をよく調べて自分に合ったスクールを見つけましょう。
在宅勤務をはじめる前にやっておきたいこと

最後に、これから在宅勤務をはじめようとする前に、しておいた方が良いことを何点か紹介します。
パソコン環境を整えて、興味のある職種について調べてみる
在宅勤務を始める際には、パソコンとインターネット環境がなければ話になりません。
まずはパソコン環境を整えましょう。
次に、どんな職種の在宅勤務の求人があるかをチェックしましょう。
その中で興味のある職種があれば、詳しく調べてみると良いでしょう。
必要なスキルがあれば、在宅勤務をはじめる前に身につけておくと、スムーズに在宅勤務の仕事を得ることができます。
副業可であれば、クラウドソーシングなどを利用してみる
本格的な在宅勤務を始める前に、まずはクラウドソーシングを利用して在宅勤務の雰囲気に慣れておくのも良いでしょう。
クラウドソーシングの市場は拡大しており、WEB専門職種だけでなく、未経験者でもできるデータ入力やライティング、作業系など、たくさんの職種の仕事があります。
仕事の後や、週末だけで簡単に出来るような、単発の仕事も多数あります。
ただし、会社によっては副業規定に抵触する場合がありますので、事前に副業が可能であるかを確認しておきましょう。
まとめ
厚生労働省の働き方改革により、在宅勤務をする人も導入する企業も増えています。
在宅勤務の仕事は、WEB専門職種の他、特別な資格やスキルが不要の未経験でもできる事務系や作業系の職種があります。
なかでもWEB専門職種は求人も多く、収入も安定しています。
この先、在宅勤務を視野に入れているのであれば、今のうちにWEBの知識とスキルを身につけておくと良いでしょう。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。