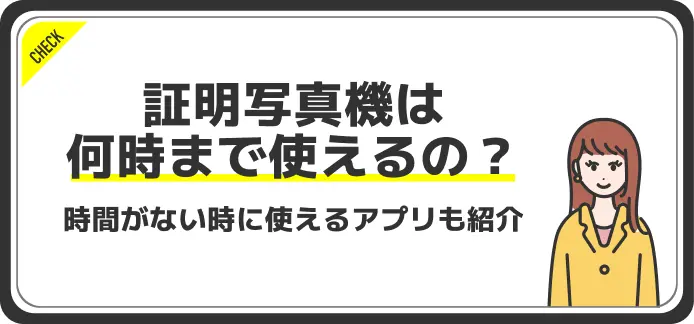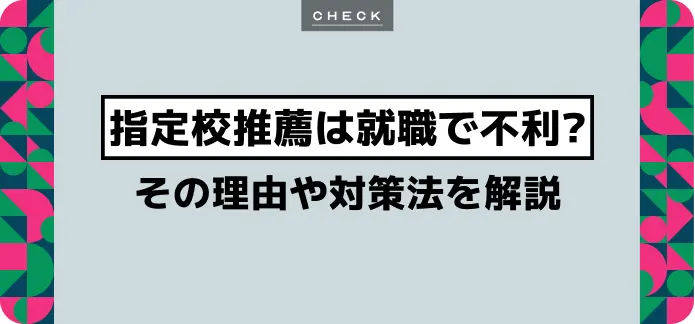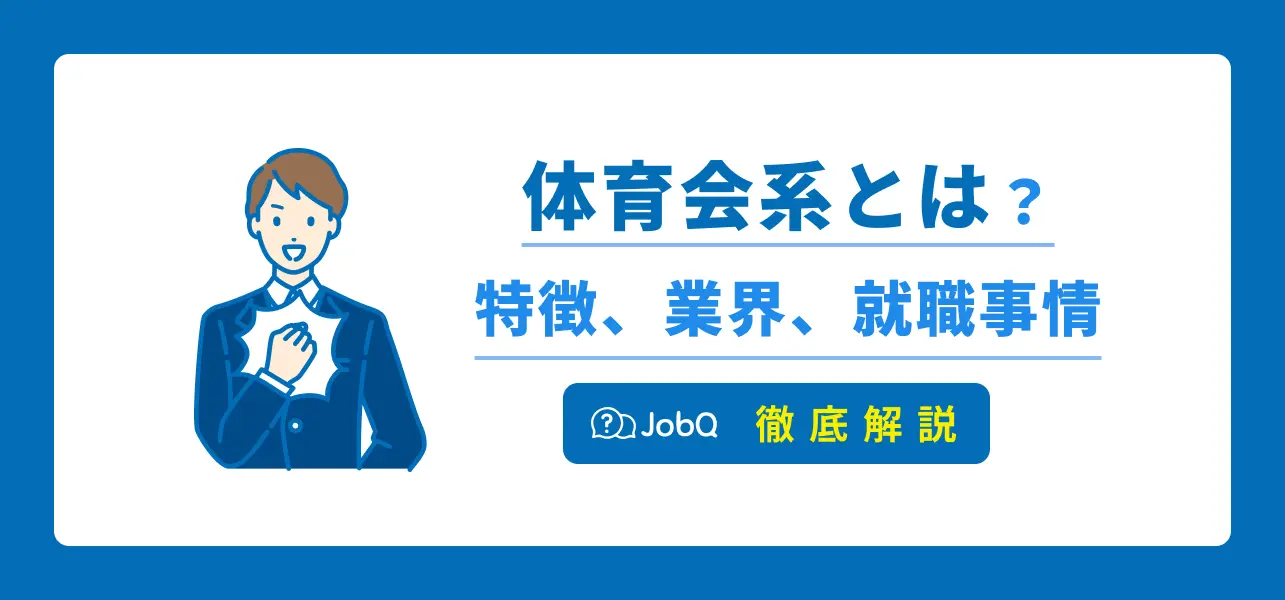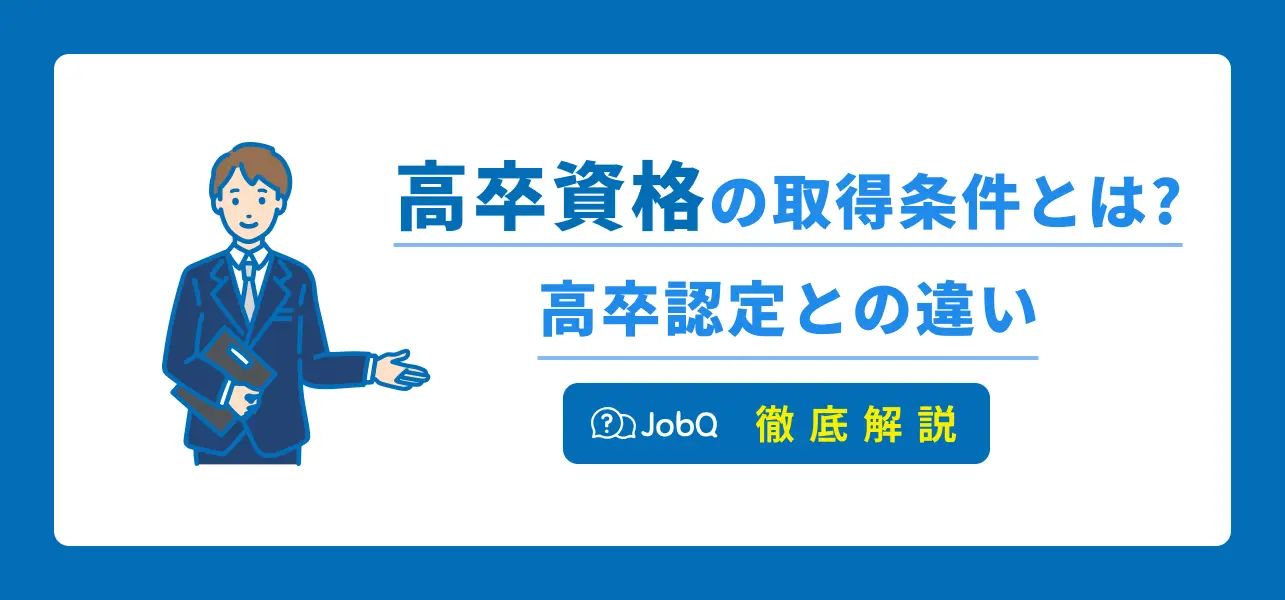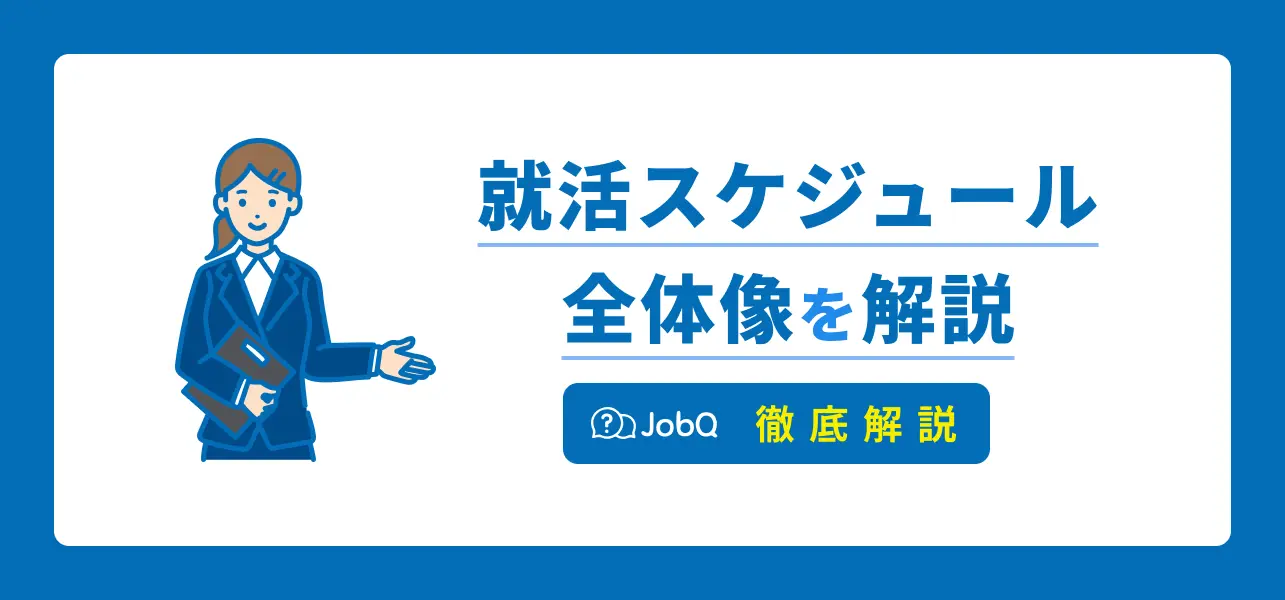
就活スケジュール【全体像を解説】
就活を始めよう!と思っても、何からすればいいのかわからない。就活を成功させるためには全体像を理解することが重要です。早期化・オンライン化する就活のスケジュールをいち早く押さえ、スタートダッシュを決めましょう!
全体スケジュール
【就活スケジュール】
一般的に、本選考の前にインターンの参加を目指す就活生が多いです。
インターンに参加するためにはインターン選考を突破する必要があり、難易度は高いです。
ES、テスト、GD、面接の突破確率を上げ、インターン参加→早期内定を目指す人が多いです。
早期内定できなくても、「実力アップ+慣れ」が本選考で生きます。
インターンシップ
1day〜5day まで日数で大別されます。
形態は9割以上が完全オンラインです。
時間帯は9〜17時ぐらいです。
1dayインターンシップ
1dayは会社説明に近いです。
業界や仕事内容の説明を受ける→グループワーク(2hほど) の流れが多いです。
5dayインターンシップ
5dayはグループワークがメインです。
本選考につながる選抜も兼ねます。
毎日グループワークに取り組み社員からのFBを受け、修正し最終日に発表、という形が一般的です。
ワーク内容の例
会社データが与えられ、将来の売上予測や利益拡大の方策を議論するワークや、利益を出すサービスのアイデアを出し、細部まで設計するワークがあります。
エントリーシート(ES)
就活を始めた就活生が最初に困るのがエントリーシート(ES)でしょう。
小論文や感想文とは性質が異なり、最初は苦戦することでしょう。
ここでは、エントリーシート(ES)についての基本情報を押さえ、書き方のコツを紹介します!
エントリーシート(ES)とは
エントリーシート(ES)は採用選考で参考にするため企業が質問を問い、就活生が文章で答えます。
志望動機や自己PR、学生時代に頑張ったことなど、選考に当たり知りたい項目、フォーマットや文字数を企業ごとに設定しているケースが多いでしょう。
現在はPCで書くエントリーシート(ES)が主流になり、書く手間が少なくなり応募できる数が増えました。
エントリーシート(ES)は選考の最初の関門
ESは就活の選考において、最初の関門です。
企業に応募しマイページを作った後、ESの提出を求められます。
ESの出来で、次のテストや面接の選考に進めるかが決まります。
エントリーシート(ES)の上手な書き方
・結論を最初に、話の流れを明確に書く
一番伝えたい結論を最初に書くと良いです。
結論とそれを支える根拠、具体例と話を広げられるのがベストです。
話の流れがわかりやすいことも重要です。
・読みやすいかチェックしてもらう
家族や友人に読みやすいかチェックしてもらう機会があると良いでしょう。
自分が書いたエントリーシート(ES)を評価するのは難しくミスに気づきにくいため第三者の目線が必要です。
文章推敲ソフトでチェックするのも良いです。
WEBテスト(SPI/ENG/玉手箱/GAB/TG-WEB)
テストの種類は5種類に分けられます。
SPI、ENG、玉手箱、GAB、TG-WEBの5種類です。
それぞれの特徴を押さえ、対策することが重要です。
SPI
最も一般的なテストで、内容は算数、国語に近いです。
比較的易しく、高い正答率が求められます。
関連記事
▶︎SPIってなに?Webテスト対策ができるサイトも詳しく解説
ENG
英語版SPIです。
全体として採用している企業は少ないです。
商社など英語力を測りたい企業で課されます。
玉手箱
問題は、文章内容の正誤判定とグラフを用いた計算の二本立てです。
時間の制約が厳しいためたくさん練習しましょう。
GAB
SPIと比べ問題数が多く、時間が足りないです。
内容はそこまで難しくないため十分に対策し時間内に解けるようになれば、突破確率を格段に上げられます。
TG-WEB
問題内容は玉手箱と類似しますが、難易度は極めて高いです。
問題数は少ない一方、時間内に終えるのは至難の技です。
適性検査
個人の性格を検査します。
テストと異なり明確な答えはなく、自分の性格に近いものを選択肢から選びます。
自分の本心で正直に答えることが重要です。
関連記事
▶︎「インターンで行われる適性検査」
グループディスカッション(GD)
インターンシップの選考で多く課されるグループディスカッション(GD)について説明します。
面接などと異なり、練習することが難しいため早期の対策が必須です。
ここでは、グループディスカッション(GD)についての知識をお伝えします。
グループディスカッション(GD)とは
就活生数人が1グループとなり与えられたテーマについて話し合います。
論理的思考力に加え、協調性などの面接では測れない能力が判定されます。
グループディスカッション(GD)の進め方
一般的に、定義確認→アイデア出し→検討→発表 の流れです。
ディスカッションの最初に進め方を確認し、時間配分をあらかじめ決める場合が多いです。
グループディスカッション(GD)のお題の例
定量分析型と抽象型の二つに大別されます。
定量分析型は「スタバ一店舗の月間売上を求めよ」「2年後に利益を10%上げる方法」など、数字で判断できるものについて議論します。
抽象型は「初対面の人をよく知る質問は?」「効率よく勉強する方法は?」など、一見つかみどころのないテーマについて議論し、思考力が試されます。
グループディスカッション(GD)内の役割
ファシリテーター:チームの議論を引っ張るリーダー的存在。
タイムキーパー :時間設定を守るため、「残り何分」と伝える
書記 :議論の内容を記録する。発表原稿作成に繋がる。
アイデアマン :議論を進めるため、アイデアを出す。
関連記事
▶︎「グループディスカッションですべきこと」
面接
面接で大事なこと
面接で大切なことは「一緒に働きたい人」と感じさせることです。
就活の選考と身構えずにリラックスして臨むことが重要だと言えるでしょう。
「面接官と友達になろう!」と意識して臨むとリラックスし上手に自分を表現できます。
面接で聞かれること
一般的にはESの内容を詳しく聞く質問が多いです。
志望動機や入社してやりたいこと等は事前に考えておきましょう。
面接官が気分で聞く突発的な質問には焦らず落ち着いて対処しましょう。
関連記事
▶︎「面接の質問例・マナー対策総集編」
面接のマナー
オンライン面接かどうかでも変わりますが、基本は同じです。
清潔感のある身だしなみ、約束時間を守る、ハキハキと挨拶するなどをしっかりしていれば社会人として最低限のマナーが守れていると感じてもらえるでしょう。
関連記事
▶︎「集団面接でのマナー」
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。