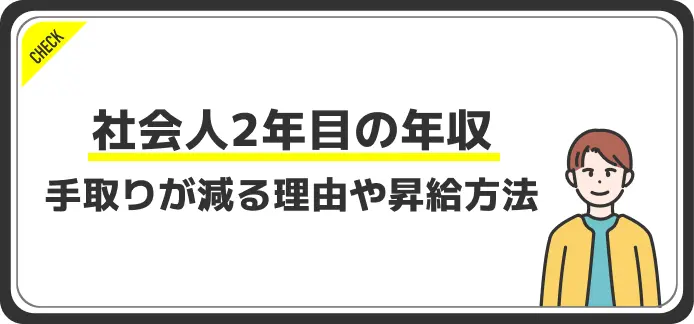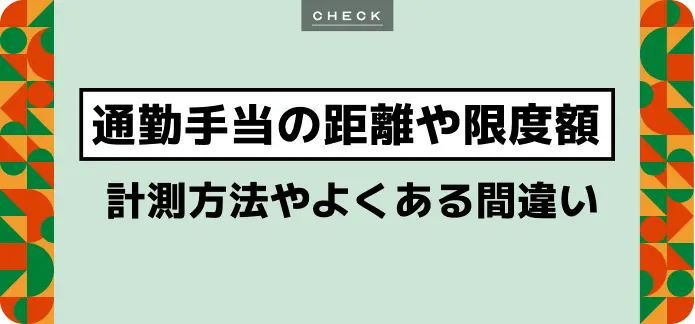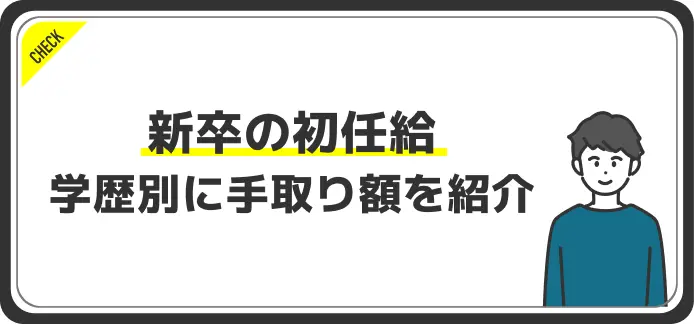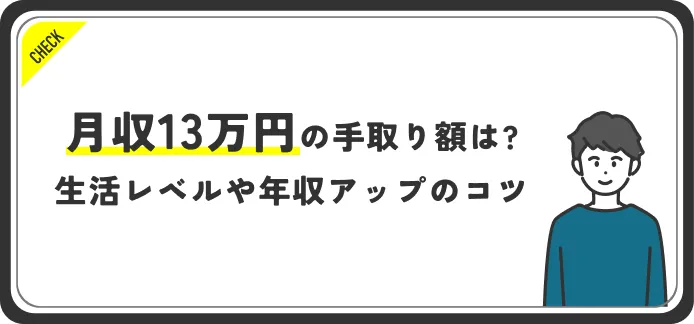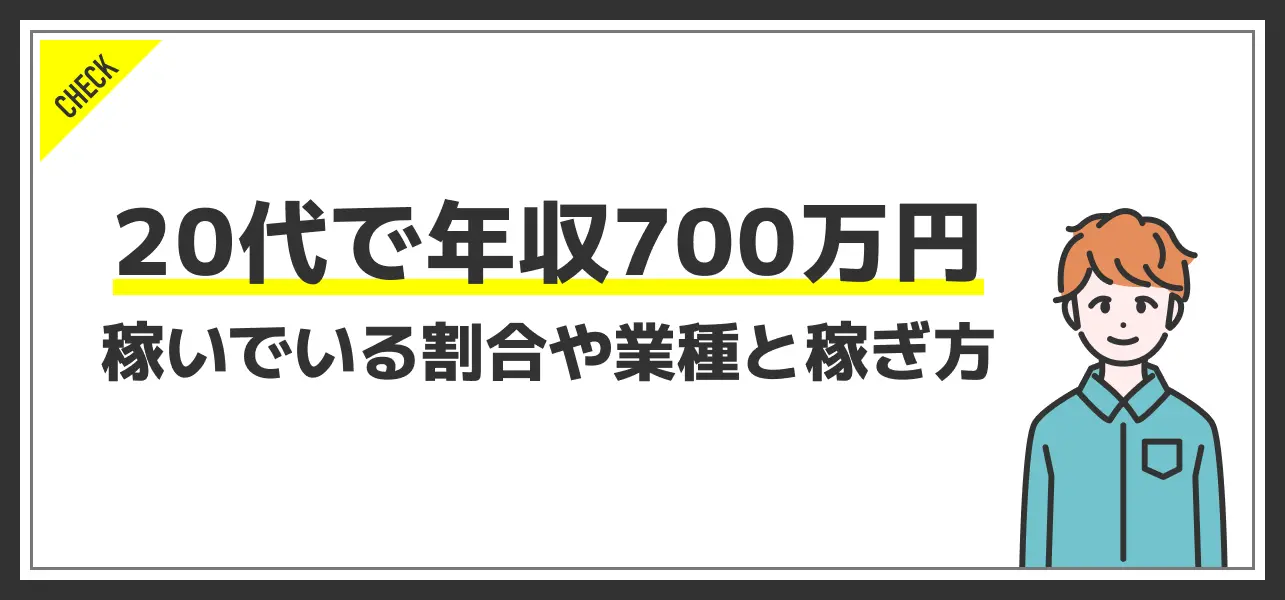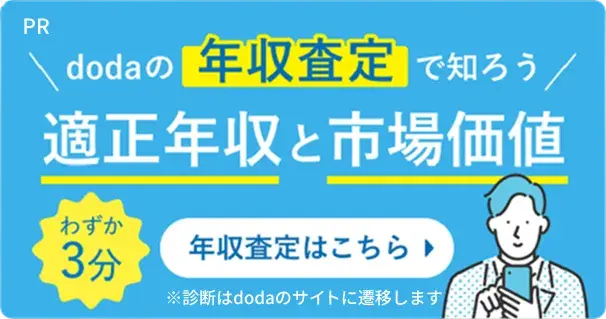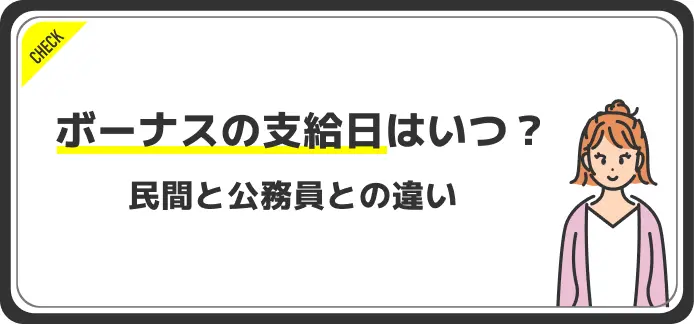
ボーナスの支給日はいつ?民間と公務員との違いや引かれるお金も解説
この記事では、気になるボーナスの支給日について、民間と公務員それぞれのケースを詳しく解説しています。一般的な支給額や差し引かれるお金など、ボーナスにまつわる知っておきたい情報を網羅しているので、ぜひ参考にしてください。
ボーナスの基礎知識
ボーナスは、月給とは別に支給される大切な収入です。まずは、ボーナスにまつわる基本的な情報から整理していきましょう。
そもそもボーナスとは?
国税庁は、ボーナス(賞与)を次のように定義しています。
賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。
引用元:No.2523 賞与に対する源泉徴収|国税庁
つまり、通常の月給とは別に支給される特別な給与がボーナスです。通常、社員の働きぶりや会社の業績を評価して支給額が決定されます。
ボーナスから差し引かれるお金は?
ボーナスからは、所得税(源泉徴収)と社会保険料が差し引かれます。差し引かれる金額は、支給額の20〜30%程度が一般的なため、手取り額は支給額の70~80%程度です。
たとえば50万円のボーナスが支給される場合、手取り額は35~40万円程度となります。控除額は、個人の給与水準や扶養家族の有無などによって変動します。
夏・冬のボーナスはいつ支給される?
年2回のボーナスは、多くの社会人にとって大きな楽しみの一つ。支給時期は企業や業界によって異なりますが、民間企業と公務員とでそれぞれのパターンがあります。ここでは、民間企業と公務員それぞれの支給時期について詳しく解説します。
夏・冬のボーナス支給日|一般企業の場合
民間企業の場合、夏のボーナスは6月下旬から7月下旬・冬のボーナスは12月に支給されるのが一般的です。査定期間は、通常、夏のボーナスが前年10月~3月・冬のボーナスが4月~9月です。
ただし、「決算賞与」としてボーナスを支給する企業の場合、支給額は企業の会計年度全体(多くは4月から翌年3月)の業績に基づいて決定されます。そのため、3月決算の企業であれば3月下旬~4月に支給されるのが一般的です。
関連記事
▶︎夏のボーナスの平均はいくら?企業規模・年代別の平均額もチェック
▶︎冬ボーナスの平均額はいくら?産業別・大手企業の支給額を紹介!
夏・冬のボーナス支給日|公務員の場合
公務員のボーナスは、民間企業のボーナスの相場を参考に決定されます。国家公務員のボーナス支給日は、国家公務員法にもとづく人事院規則によって夏が6月30日・冬が12月10日と定められています。
地方公務員の場合、自治体によって多少の違いはありますが、基本的に国家公務員に準じた日程となっています。当日が休日の場合、直前の平日が支給日です。
民間企業とは異なり、支給日が明確なのが特徴です。
夏・冬のボーナス支給日|新卒の場合
新卒社員の場合、基本的には入社年の夏から支給が始まります。ただし、最初の夏のボーナスは、寸志程度の金額になるケースが珍しくありません。というのも夏のボーナスは、基本的に前年度の査定が反映されたものだからです。
産労総合研究所の2023年の調査によると、新入社員への夏季賞与支給実施企業は86.1%で、そのうち64.5%が「一定額(寸志等)」を支給しています。平均支給額は、大学卒が9万6,732円・高校卒が7万9,909円となっています。
参照:2023年度 決定初任給調査 | 決定初任給調査 | 賃金制度・春闘 | 産労総合研究所
関連記事
▶︎【社会人1年目】新卒のボーナスはいつ・いくら(冬・夏)?使い方のポイントも解説!
▶【1年目はボーナスなし?】新入社員のボーナス事情を解説します
夏・冬のボーナス支給額と手取り額
ボーナスの具体的な金額は、企業規模や業績、個人の評価によって大きく異なります。ここでは、一般企業、公務員、20代それぞれの平均的な支給額を見ていきましょう。
夏・冬のボーナス平均支給額は?|一般企業の場合
厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和5年9月分結果速報等」によると、2023年夏のボーナスの平均支給額は397,129円でした。また、「毎月勤労統計調査 令和6年2月分結果速報等」によると、2023年の冬のボーナス(年末賞与)の平均支給額は395,647円となっています。
手取り額は支給額の約70~80%程度となるため、おおよそ28~32万円です。
ただし、これはあくまでも平均値から求めた参考程度の数字です。実際の金額は企業規模や業績によって大きく異なることを心に留めておきましょう。
参照:厚生労働省|毎月勤労統計調査
関連記事
▶︎中小企業のボーナスの平均額はいくら?ボーナスなしもある?
▶︎ボーナスの平均額は大企業だといくら?中小企業との差は?
夏・冬のボーナス平均支給額は?|公務員の場合
人事院が公開している「令和5年 給与勧告の骨子」によると、令和6年に国家公務員の冬のボーナスに支給される額は、給料の2.25ヶ月分でした。内訳は「期末手当」が1.225ヶ月・「勤勉手当」が1.025ヶ月です。
令和4年度12月期(冬)の支給額額は約65万円、令和5年度6月期(夏)の支給額は約63万円だったことから、年間の平均支給額は約128万円が目安となります。手取り額の目安は約90〜102万円です。
参照:
人事院「令和5年 給与勧告の骨子」
令和5年6月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給
令和4年12月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給
関連記事
▶︎2024年|冬・夏の公務員ボーナスはいつ?何ヶ月分?支給額も解説
夏・冬のボーナス平均支給額は?|20代の場合
厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、勤続年数1~2年(大学卒)の20~24歳の年間賞与支給額は平均で617,500円でした。
夏冬2回で考えると、1回あたり約31万円となります。手取り額が支給額の70〜80%程度となることを考えると、手取り額は約22~25万円程度と予想できます。
参照:賃金構造基本統計調査|令和5年|学歴、年齢階級、勤続年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額|産業計
関連記事
▶20代のボーナスの平均額は?大卒・高卒の違いもチェック
▶︎30代のボーナス平均額は?男女別や企業規模別の平均をチェック
▶︎40代のボーナス平均額・手取り額はいくら?学歴・企業規模別に解説
20代のボーナスの賢い使い方
初めてのボーナスをどう使うか、頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。ここでは、将来を見据えた効果的な使い方をご紹介します。
貯蓄で未来に備える
将来の大きな出費に備え、ボーナスの一部を貯蓄に回しておきましょう。
具体的な目標(結婚資金・住宅購入など)を設定し、計画的に貯金することで、将来の選択肢が広がります。「ボーナスの3割を貯蓄に回す」など決めておくと、無理なく実行できるのでおすすめです。
貯蓄方法としては、普通預金だけでなく、金利が上乗せされる定期預金や住宅購入を見据えた住宅財形貯蓄なども検討しましょう。また、緊急時への備えとして、生活費の3~6カ月分程度を普通預金で持っておくことも大切です。
将来の目標に応じて複数の貯蓄口座を作り、目的別に管理するのも効果的です。
投資で攻めの資産形成を
20代から投資を始めることで、長期的な資産形成が期待できます。特に20代は時間という大きな味方があります。投資信託やNISAなど、初心者でも始めやすい投資手段から検討してみましょう。
たとえば「つみたてNISA」なら、月々の少額から始められ、20年間非課税で運用できます。また、確定拠出年金(iDeCo)も、将来の資産形成に効果的です。
ただし、投資には少なからずリスクもあります。資産が減る可能性もあるため、十分な理解と慎重な判断が必要です。
自己啓発でスキルアップ
資格取得や専門スキルの習得など、自己投資もボーナスの有効な使い道です。特に20代は学ぶ意欲も高く、新しい知識やスキルを吸収しやすいため、新たな学びに挑戦するにはピッタリのタイミングです。
IT系の資格(基本情報技術者試験やAWS認定など)・会計系の資格(簿記検定など)、語学力向上(TOEIC対策や英会話スクール)などへの投資は、将来のキャリアアップに直結します。
資格取得やスキルアップにかかる費用は、将来の収入増加につながります。投資の一つとして捉え、一定額を設定するのがおすすめです。
ボーナスアップを目指すならどうする?
中には、自社のボーナスについて「思ったよりも少ない」と不満を感じる人がいるかもしれません。より高いボーナスを目指すためには、計画的なアプローチが必要です。ここでは、社内でのキャリアアップと転職という2つの観点から、ボーナスアップの方法を提案します。
社内でボーナスを上げる
社内でボーナスを増やすためには、業務に直結する資格の取得や、専門スキルの向上が効果的です。たとえば、業界特有の資格(金融であればFP資格など)を取得することで、専門性をアピールできます。
また、社内の評価制度をよく理解し、評価項目に沿った業務改善や提案を行うことも大切です。
多くの企業では、業績評価・能力評価・行動評価など、複数の要素を組み合わせて総合的な評価を行っています。自分の得意分野を理解して実績を作り、上司など評価する立場の人へ十分にアピールしましょう。
転職でボーナスを上げる
より高いボーナスを求めるのなら、転職も選択肢の一つです。ボーナスの水準が高い企業への転職は、大幅なボーナスアップをかなえるもっとも効率的な方法といえます。
なお、実際に転職を検討する際は、総合的な待遇や将来性も考慮に入れる必要があります。中には、若い世代の給与やボーナスの水準こそ低くても、将来的な伸び率が高い企業もあります。企業ごとの給与形態はもちろん、転職市場の動向や業界別の報酬水準もよく調査して、キャリアプランに沿った選択をしましょう。
ボーナスにまつわるよくある質問
ここでは、ボーナスにまつわるよくある質問をピックアップして紹介します。ついそのままにしていた疑問点をここで解消しておきましょう。
ボーナスの有無や支給日はどう調べればいい?
ボーナスの有無や支給日などの詳細は、求人票・就業規則・賃金規程・労働契約書(雇用契約書)などで確認できます。
不明な点がある場合は、人事部や総務部に直接問い合わせることも可能です。また、労働組合がある場合は、労働協約(労使協定)にも記載されているケースもあります。
ボーナスの支給日に退職していたらどうなる?
多くの企業では、ボーナスの支給日に在籍していることがボーナス支給の条件となっています。つまり、査定期間中に働いていても、支給日前に退職した場合、ボーナスを受け取れない可能性が高くなります。
JobQにも、退職後のボーナスの支給について疑問を持つ人から次のような質問が寄せられています。
Q.退職後に給料とボーナスがもらえるタイミングを教えてください
仕事をやめようと思ってます
次の仕事の予定は大体たってます。毎月15日締め、25日払いです。ボーナスは7月と12月です。11月15日に退職届を出して12月15日にやめたら給料とボーナスは貰えますか?新しい年には新しい仕事を始めたいと思ってます。
A.会社の給与規則を確認してください。賞与の支給について…続きを読む
退職を考える際は、ボーナスの支給時期も考慮して計画を立てましょう。
ボーナスから住民税は引かれる?
ボーナスから住民税は引かれません。
住民税は前年の収入に基づいて計算され、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から天引きされます。対象になるのはあくまでも毎月の給与で、ボーナスが天引きの対象になることはありません。
ただし、支給されたボーナスの額は、翌年の住民税額の計算に含まれることは心に留めておきましょう。
ボーナスの支給日を正しく把握しよう
ボーナスの支給日は、一般的な民間企業で夏季(6〜7月)と冬季(12月)・公務員は6月30日と12月10日です。新入社員の場合、最初の夏のボーナスは少額になることが多いものの、年々増加していく傾向にあります。
支給されたボーナスは、将来を見据えた計画的な使い方を心がけましょう。貯蓄・投資・自己投資をバランスよく行い、理想のキャリアはもちろんのこと、プライベートも充実した理想の未来を実現させてくださいね。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。