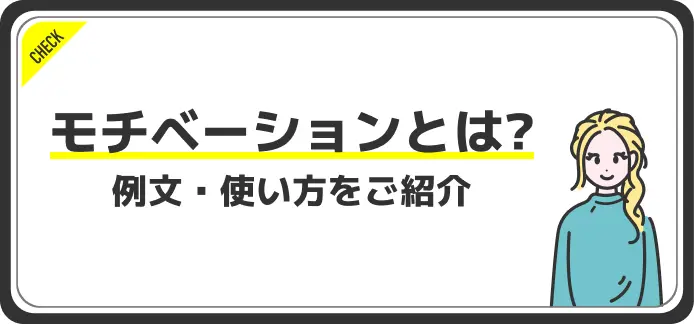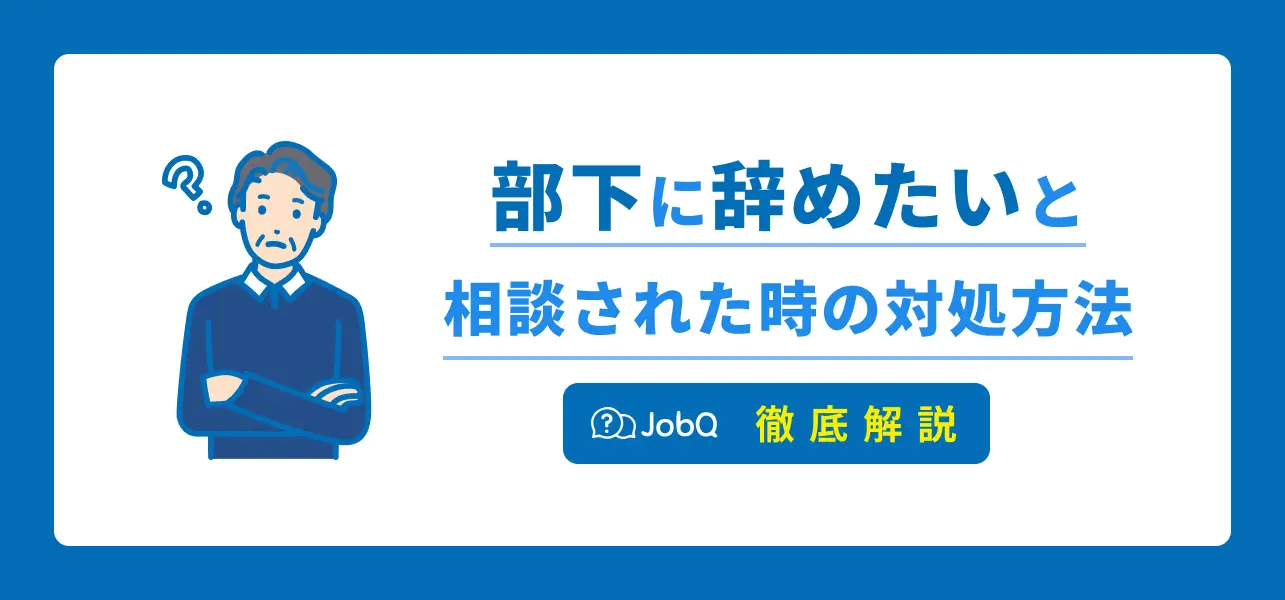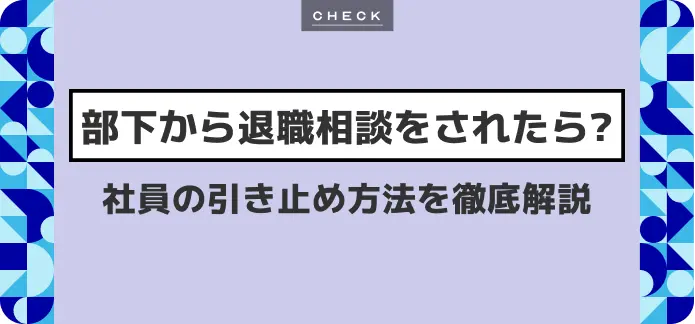【アンガーマネジメントの方法】実践的な現場の例を用いてご紹介
アンガーマネジメントという言葉を聞いたことがあるでしょうか。アンガーマネジメントは怒りと向き合う心理療法です。仕事や日常生活の中で怒りを感じることは多いことと思います。今回はどのようにアンガーマネジメントをするかを様々な場で用いられている実践的な方法をお伝えします。
アンガーマネジメントの方法の基本の考えとは?
アンガーマネジメントの方法の基本の考えとは、「自分で自分の怒りをコントロールする」というものです。
アンガーマネジメントの基本の考えを身に付けることができれば「衝動的な怒り」に駆られることなく、怒りを感じている状況でも冷静に判断することができ、対人トラブルやミスなどを避けることができます。
アンガーマネジメントの基本の考えを身に付けたら、収入が上がる、寿命が伸びる、というようなことを主張する人もいるくらいです。
実際アンガ―マネジメントが収入や寿命にどれくらい関係しているのかは定かではありませんが、対人トラブルを避ける、冷静な判断力を維持する、ミスを減らすなどという事に対しては十分な効果があるそうです。
ぜひ、案が―マネジメントの基本の考えを身に付けて、仕事やプライベートにおけるリスクの排除を進めましょう。
怒りと上手に付き合うことができるようになる
アンガーマネジメントができるようになると、怒りと上手に付き合うことができるようになります。
残念ながら、人間は、かならず「怒り」を感じる生き物です。
だからこそ、怒りを排除するのではなく、上手に付き合うことが大切です。
アンガーマネジメントでは、そのスキルを活かす前に自分が怒りを感じる要因を深く掘り下げていきます。
どういった時に怒りを感じるのか?どれくらいの怒りを感じるのか?その怒りは本当に必要なのか?
このように自分自身の「怒り」に対する理解を深めた上で、その怒りとどうやって上手にき合うのか、考察していきます。
怒りと上手に付き合えるようになれば、余計なトラブルを回避できたり、自分自身の能力を高く維持できたりします。
怒りの6秒ルールを理解する
怒りには、「6秒ルール」と呼ばれるものがあります。
6秒ルールとは「怒りのピークは6秒間である」というものです。
この6秒ルールに従って、ピークの6秒間に怒りを発散しなければ、アンガーマネジメントが上手にできていると言えます。
6秒ルールの後、怒りは徐々に小さくなっていき、最終的になくなります。
この6秒ルールをどれだけ理解し、実践できるかが、アンガーマネジメントの一つのポイントです。
アンガーマネジメントの方法を実践するテクニックとは?

アンガーマネジメントと一口に言っても、さまざまなテクニックが存在します。
そういったテクニックを一つ一つ組み合わせて実践することによって、アンガーマネジメントは本来の効果を発揮します。
アンガーマネジメントのテクニックは、テクニックというほど複雑なものではありません。
心の中での考え方にエッセンスを加えるようなイメージです。
また、テクニックには多少の合う合わないがあります。
自分に適したテクニックを見つけてアンガーマネジメントを進めましょう。
自分のなかの固定概念をリセットし~するべきを捨てる
アンガーマネジメントの代表的なテクニックとして、「自分の中の固定概念をリセットする」というものがあります。
分かりやすく言い換えると「~するべき」であると思っている部分を一度リセットするということです。
人間は沢山の固定概念=~するべきを持っています。
その固定概念が覆された時に、人は怒りを感じます。
例えば「朝食はパン食を用意するべき」という固定概念を持っていたとして、そこに和食の朝食が運ばれてきた時に、怒りを感じるという現象が起こります。
特にこの「~するべき」が誰かが自分に対して「~するべきである」と考えている人は、怒りを感じやすいです。
何故なら、他人がどういう行動をするか、自分ではコントロールしづらいからです。
こういった固定概念が多ければ多いほど怒りを感じやすいのです。
まずアンガーマネジメントの一歩として、固定概念=~するべきをリセットし、
本当に必要な概念だけを残し、不要は固定概念を捨て去る必要があります。
怒りを整理するために記録を付ける
アンガーマネジメントにおいて、自分自身の怒りについて理解を深めることは重要です。
そのための代表的手法として、「怒りの記録を付ける」というものがあります。
なぜ自分は怒りを感じるのか?
何に対して怒りを感じているのか?
そしてその怒りの度合はどれくらいのものなのか?
こういった形で、怒りを整理するために記録を付けるのです。
自分が怒りを感じるパターンの記録を付けることにより、そのパターンに入ってしまったことに気が付くことができたり、またその怒りのパターンに入ることを事前に察知して避けることも可能です。
このようにして、怒りの記録を付けることで、怒りそのものに大して冷静かつ柔軟に対応することができます。
まずは、自分の怒りのパターンの記録を付けることから実践してみましょう。
アンガーマネジメントの方法のひとつである診断とは?

アンガーマネジメントを進める上の方法の一つに診断を受けるというものがあります。
これは、診断を受けることにより自分の怒りの「類型」を理解して、アンガーマネジメントに役立てるというものです。
人の怒りの感じ方にはある種のパターンがあります。
診断を受けて、自分がどのパターンなのかを理解することでアンガーマネジメントをより効率的に進めることができます。
診断と一口に言っても、様々な形での診断が存在します。ここでは、その診断方法をご紹介します。
誰でもすぐにできる診断方法について
アンガーマネジメントの診断は、とても手軽に受けることが可能です。
インターネットで「アンガーマネジメント 診断」と検索すれば、無料で簡単に出来るアンガーマネジメント診断のサイトがいくつか出てきます。
これだけの診察でも、アンガーマネジメントにおいていくつかのヒントを得ることができます。
また、一種類のアンガーマネジメント診断のみならず、複数の診断を受けることもおすすめです。
なぜなら、複数のアンガーマネジメント診断を受けることにより、各診断結果から共通点を見出して、より信憑性の高いデータを取ることができるからです。
診断後に分類されるの怒りタイプとは
アンガーマネジメントの診断を受けると、その後、怒りタイプというものが提示されます。
これは、先述した「パターン」に当たる部分です。
人間には様々な気質や考え方、性格、傾向があり、それによって怒りタイプも様々です。
均一なアンガーマネジメントの方法というものはなく、その人その人の怒りタイプに対応したアンガーマネジメントを行うことがあります。
アンガーマネジメント自体、まだまだ発展途上の技術ですので、「これさえやっておけば大丈夫だろう」と過信せず、自分の怒りタイプを把握した上で創意工夫の伴ったアンガーマネジメントを行うことが大切です。
怒りタイプを把握しておけば、より効率的かつ効果的なアンガーマネジメントを実施することができます。
怒りタイプの詳細とは?
アンガーマネジメントの診断を受けると、怒りタイプを知る事が出来ます。
ここでは、アンガーマネジメントにおいて代表的な怒りタイプをご紹介します。
-
公明正大の怒りタイプ
素晴らしい正義感や信念を強く持っており、それに従って行動するタイプです。
倫理観や、モラル意識が強く、それに反する状況に陥ると怒りを感じます。
このタイプの怒りタイプを持っている人は「自分の正義や信念が絶対ではない」という考えを改めて、多様な考え方を受け入れるようなアンガーマネジメントが適しています。
-
威風堂々タイプ
自分自信に自身を持っており、自他ともにリーダーとして認められているタイプです。
どちらかというと勝気で、周りを引っ張っていくことができます。
逆に、プライドを傷つけられたり、他者が思った通りに動いてくれないと強く怒りを感じます。
このタイプの場合、自分を客観視したり、他者が自分の思い通りには必ずしも動かない(その義務が無い場合がある】ことを学ぶことがアンガーマネジメントになります。
-
用人堅固タイプ
慎重に物事を考えて、仕事や人間関係を構築できるタイプです。
気が利く方で、周りに安心感を与えます。
反面、臆病さや脆さを抱えており、人との信頼関係を築きにくかったり劣等感を感じやすく、そういった感情と共に怒りを覚えます。
アンガーマネジメントとしては、他者との相互理解を深めて、懐疑心や劣等感を取り除く方法が適しています。
アンガーマネジメントの方法を子育てに実践すると?

アンガーマネジメントは、職場やプライベートのみならず、子育てのシーンでも実践することができます。
子育ては、自分の子供を育てる喜びを感じることができる反面、怒りを感じてしまう場面も多いものです。
幸せもありながら大変なことも多い子育てですが、アンガーマネジメントを実践することにより、子育てにとても良い効果を与えることができます。
特に昨今は身体的・心理的虐待がメディアで取り上げられており、胸を痛めている人もいるかと思います。
そういったリスクを回避するためにも、アンガーマネジメントを子育てにおいて実践することはとても良いことです。
自分の子育てに自信が持てず、悩む親は大勢います。
アンガーマネジメントを導入することで、ストレスを軽減し、自分自身の子育てにおいて確かな自信と精神的余裕を持って臨むことができます。
ぜひ、家庭内の関わり合いでもアンガーマネジメントを取り入れていきましょう。
寝かしつけてから1時間も経つのになかなか寝ない
絵本を読み聞かせたり、子守歌を歌ったり、どんなに親が工夫して寝かしつけても寝ない子供が寝付けないということはよくあることです。
寝かしつけている自分の方が眠いのに寝てくれない……本当に親として大変な一場面です。
しかし、親として、子供を寝かしつけないわけには行きません。
こんな時、アンガーマネジメントを使って、子供を寝かしつけるという親の役割をどうやって全うするから考えてみましょう。
アンガーマネジメントの見地から、まずこの状況を客観的に観察して見ましょう。
普通に見れば「親が一時間寝かしつけても子供が寝ない」という状況です。
しかしこれは、アンガーマネジメントの考え方では子供は、親が一時間寝かしつけたら寝る「べき」である、という考えを持っているということになります。
先述したように「~するべきである」という考え方はアンガーマネジメントでは好まれません。
「親が1時間寝かしつけても、寝ない時は寝ないものである」という考え方を持つだけで、少しは怒りが収まると考えられます。
また、先述したアンガーマネジメントの「6秒ルール」に従い、大きな怒りを感じたら一旦その場を離れて、時間を置いてからもう一度寝かしつけてみるというのも効果的と考えられます。
こうやってアンガーマネジメントを行うことができれば、子供にも自分にも余計なストレスを与えずに子育てを進めることができるでしょう。
お店で駄々をこねて話を聞いていない
「あれがほしい!」の一点張りで親が何を言っても聞いてくれない……こういった事も子育てではよくありますね。
親と同じく、子供も一種の怒りを感じ、駄々をこねるという形で怒りを表現しているのです。
まして子供なので、アンガーマネジメントのような高等な技術を使うはずありません。
しかし、親はアンガーマネジメントを用いて、この状況の捉え方を変えることができます。
まず、親としてのあなたが「子供は駄々をこねないべきである」という風に考えているのであれば、まずはこの考えをアンガーマネジメントする必要があります。
つまりアンガーマネジメントを経て「子供は、時として駄々をこねる時もある」という考え方に切り替えて行きます。
他にも「今では親の自分でも、かつては同じように自分の親に駄々をこねたことがあったな」という風に考えることもできます。
そうしてアンガーマネジメントを利用し、冷静になって、根気よく子供をなだめましょう。
ここでも6秒ルールは有用です。手を上げたりしそうになったら、6秒、6秒だけ時間を取りましょう。
その6秒を乗り越えれば、そこからは怒りの感情は徐々に沈んでいきます。
アンガーマネジメントの方法を看護で活かすと?

アンガーマネジメントは、看護の場面でも有用な効果を示すとされています。
そもそも「仕事」というものは、ストレスが溜まるものです。
その中でも看護の仕事はストレス量が多い部類に入るものだと言われています。
ストレスの要因が多い現場でこそ、アンガーマネジメントは必要とされています。
看護のストレス要因としては、わがままな患者、不規則なシフト、命を預かるというプレッシャー、人間関係、ドクターとの折衝などが挙げられます。
どれも大きなストレス要因になると考えられます。
そのあたりにおいては看護業界も理解している様子で、看護師に対してアンガーマネジメントの研修を行ったりしているようです。
また、看護師向けに特化したアンガーマネジメントの書籍が出版されているなど、看護業界にはストレスの対策としてアンガーマネジメントが普及しつつあります。
看護の現場でのストレスに対してどのようにアンガーマネジメントが活かされるのか見ていきましょう。
現場に多い「人格否定の暴言」に耐性ができる
実際に看護の現場で、アンガーマネジメントはどのように活用できるでしょうか?
看護の現場では、時として「人格否定の暴言」が発されることがあります。
これはかなり大きなストレス要因になるのではないかと考えられます。
医師や看護師長からそのような言葉が発されることは、パワハラ問題にもなりかねません。
なので、これらがストレス要因になることは比較的少ないのではないかと考えられます。
しかしながら、患者からの人格否定の暴言は、その限りではありません。
患者が看護師に対して人格否定の暴言を吐いたとしても、現実的にペナルティが発生することはないでしょう。
そこにかこつけて、看護師に暴言を吐き、ストレスを与える患者がいるのが現状です。
では、アンガーマネジメントを用いて、この人格否定の暴言にどのように向き合うか考えてみましょう。
まず、「人格否定の暴言を吐かれない【べきである】」という考えを改めることが、アンガーマネジメントの第一歩です。
患者も、病気に対する不安、恐怖、焦りからストレスを抱えています。
中には精神を患い、必要以上に怒りを感じやすくなり(アンガーマネジメントどころではなくなり)、人格否定の言葉を吐く患者もいることでしょう。
つまり、患者とはある程度、人格否定の暴言を吐きやすい存在なのです。
そしてその人格否定の暴言を吐いている原因は「あなたが実際にそういった人格であるから」ではなく、人格否定の暴言を吐きやすい人がたまたま選んだ言葉がそれであっただけで、あなたの人格とは何の関係もないのです。
このように、「人格否定の暴言」を吐く原因を冷静に見つめれば、「あなたへの人格否定は全くの的外れ」であるということが分かります。
このようにアンガーマネジメントすることができれば、人格否定の暴言に耐性を持つことができます。
人格否定の某気にに対し、一切の動揺が無くなるとは考えづらいですが、少しでも受け止め方が変わって、ストレスを感じにくくなることが期待できます。
スタッフ内や医師に合わない人がいるときに対処ができる
看護の現場において、患者とのコミュニケーション以外にも、一緒に働く人との間における問題にも、アンガーマネジメントは役に立ちます。
看護の現場は激務かつ、重い責任を伴っています。
きれいごとだけでは上手く行かず、軋轢が生まれたり、意見の衝突なども多いかと思います。
看護は「感情労働」とも言われ、どのような精神状態で業務に当たるかが非常に重要です。
こういった高負荷下のシーンでこそ、アンガーマネジメントは役に立ちます。
やはり、スタッフ同士の相性が合わないという問題は、どうしても出てくるでしょう。
例えば医師と性格が合わない問題についてアンガーマネジメントを行うことを考えてみましょう。
医師が言っていることに対して怒りを感じてしまう・・・こんな事が起こったら、「コントロール可能ではないものに対しては怒らない」ということを思い出してください。
たったこれだけでもアンガーマネジメントが成り立ちます。
医師と看護師では担当している業務が明確に違いますので、相互に干渉のしようがないことがほとんどです。
だから、コントロールしようのない医師の言動に対して怒っても意味はないし、またそうする必要もありません。
それであれば、きちんとアンガーマネジメントを行い、しっかりと看護業務に向き合うことの方が重要なのです。
このように、どこまでが自分のコントロールできる範囲なのかをはっきりと理解することで、不要な怒りを感じなくて済むようになります。
患者からのひどい暴言に対応ができるようになる
看護師にとって、患者の暴言は残念ながらつきものです。
看護の現場にいる以上、切っても切れないものでもあります。
では、患者からの暴言をいかにアンガーマネジメントで対応するか考えてみましょう。
先述した部分と重なる部分もありますが、やはりまず「~べきである」という考えを捨てるアンガーマネジメントが基本中の基本になってきます。
「患者は暴言を吐かないべきである」という考えは、真っ当にも思えますが、果たして本当にそうでしょうか?
患者というのは、何かしらの傷病を患ってその場所にいます。
つまり、患者も患者で他者を思いやる余裕がなかったり、病への不安などが高じて、暴言を言ってしまうようになるのです。
あなたがひどい暴言通りの人間なのではなく、患者を取り巻く環境がそうさせてしまっているだけなのです。
アンガーマネジメントの見地から言えば、あなたは患者からのひどい暴言を真正面から受け止める必要はありません。
患者からの暴言は、要するにストレスを感じることからの八つ当たり程度の意味しかないということを、しっかりと理解しておきましょう。
何かひどい暴言を吐かれて強い怒りを感じたら「6秒ルール」の出番です。
6秒を耐え抜くためには、「病室にあるものを心の中で順番に読み上げる」「単純に心の中で6秒」を数えるなどのアンガーマネジメントテクニックがあります。
患者が暴言を吐こうとも、看護師は患者を守らないといけないというのが現実です。
アンガーマネジメントを使って、怒りに振り回されず、看護師としての業務に集中できるよう努めましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
アンガーマネジメントの方法についてご紹介しました。
アンガーマネジメントをする方法として
・固定概念=~するべきをリセット
・怒りを整理するために記録を付ける
・6秒ルール
などがございました。
ぜひこれらの方法を用いてうまく怒りと付き合っていきましょう。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。